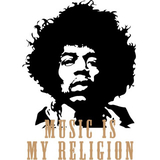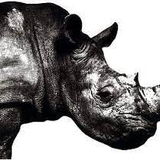レヴェナント 蘇えりし者のレビュー・感想・評価
全516件中、61~80件目を表示
見続けるモチベーションが上がらない
まず最初のシーンでいきなりの戦闘シーン長すぎる。戦闘シーン、アクションシーンというのは主人公たちがなぜ戦うのかということはしっかり描けてからでないと見ていても退屈である。しかもそのシーンが広角カメラによる近接手持ち撮影によって撮影されている。臨場感溢れる撮影ではあるがファーストシーンでこういうことをしてしまうと監督が酔ってるようにしか見えなくて、見るものは逆に冷める。次に敵役の名前がいけない。なんとなく雰囲気が「アギーレ神の怒り」に似てるなと思って見ていたらヘルツォークのもうひとつの傑作のタイトル=主人公の名前が出てきてガクッときた。こういうところも監督が一人で酔ってるからこんなことしてしまうのだよ。次に熊が出てくる。この熊は全く噛みつかないし爪で攻撃もしていない。その様子が分かるような撮り方をしてしまっている。こういうところに監督の無能さが出てしまう。熊は噛み付くものなので人形とか用意して噛み付くところを撮らなきゃいけないし、 噛みついていないところがバレないように上手に処理しなきゃいけない。さらに物語が進んでいくと敵役がはっきりしてくるのだが、この敵役があまりにも雑魚キャラすぎる。敵役というものはもう少し大物であって人間的にも深みが無いと敵役としての面白さが出ない。この適役を倒すために物語が進んでいくのかなと思うと絶望的な気分になる。トータル的に見てレベルの低い作品だと言わざるを得ないだろうと思う。
壮大な復讐劇、それを超える自然の壮大さ
タイトルなし
クマやインディアンとの戦闘シーンは迫力あり、グロテスクであり。息子を殺したトムハーディーに復讐するため、厳寒で瀕死の中、不屈の執念で追いかけ回すが長い。ラスト、なぜトムハーディーを二人だけで追うのか疑問。またそもそもなぜレオナルド・ディカプリオはインディアンの妻がいるのか、ラスト、その妻が幻想の中でも消えてしまい、結局復讐を果たしても息子は戻ってこない虚しさが残る。
迫り来る自然の脅威
レオ様が見事アカデミー賞を受賞した話題作。
監督も有名な方でバベルや21グラムのイニャリトゥ監督でこちらも監督賞受賞。
また撮影もイニャリトゥ監督のバードメンに続きルベツキさん。こちらも撮影賞受賞。
実在した西部開拓時代の罠猟師ヒュー・グラスの伝記映画です。
圧倒的な映像美と鬼気迫る演技で約2時間半もの長編映画を押し切ります。
というのも台詞は少なく、レオ様が這いずり回り自然の脅威と美しさを見せるシーンが長いのです。
ただし、これが凄い!
素晴らしい映像とそれに決して負けない演技で映画に飽きない。
もちろんストーリーも素晴らしいもので冬の山の厳しさもしっかりと描かれていますが、レオ様の生への執着、その力を生む息子への愛情から憎しみの狂気まで描かれていると思います。
見どころばかりの作品です!
タイトルなし(ネタバレ)
長いー
クマに襲われるシーンは迫力あってすごかった。
けどさすがに切り裂かれすぎてて死ぬでしょこれは。
なんで先住民と暮らしてたのかとか意味ありげな雰囲気出しといてそこには全く触れないんだ…
どんな背景があったとしても大事な息子を殺されたら仇を打ちたいと思うのは当然でそれは理解できるけど、フィッツジェラルドの行動も決して間違ってるわけではないからいざ復讐を遂げてもスッキリ感はあまりない。
グラスもそう思ってるからこそのラストカットのあの表情かなぁと深読みしてみる。
ディカプリオさん、本当に受賞おめでとうございます!
ただただ本能で好きな映画
ストーリーは至ってシンプルでわかりやすい
音楽と映像美と先住民族たちの独特な存在感や表情に引き込まれ…
初めて映画館で観た日は上映終わってもその場から動くことが出来ず呆然としていたのを思い出す
それから無になりたいとき、あの景色をまた観たいと無性に思ったときにすぐ観えるよう購入するほど魅せられていた
自然が地球に蔓延っていて空気が美味しくて水が綺麗で…ヒトが人間よりも猿に近かった時代
色々な想像力を掻き立てられる
ディカプリオもトム・ハーディも好きだから致し方なく⭐︎5つとなるが…
この映画を想い出す度眼に映るのは決して華やかなハリウッドスターの姿ではなく、静かで壮大でモノトーンに近い雪景色…そして先住民族たちのクリアで警戒心の強い野性的な目
心奪われる映画
自分の中のNo.1.
ディカプリオの演技と大自然の迫力
西部開拓の時代。グリズリーに襲われ仲間に置き去りにされた男のサバイバル。
映画のストーリー云々より、ディカプリオの演技と、アメリカの大自然に驚きました。
私はCS鑑賞でしたが、映画館で鑑賞していれば、もっと評価を高くしたかもしれません。
ストーリーは、実話をベースにしているそうです。正直、日本人の私には時代設定等は分かり難い部分もあり、全部を汲み取っていないかもしれません。それでも、裏切り者との対決シーン等は緊迫感があり手に汗を握るものでした。
「復讐するは我にあり、我これに報いん」
19世紀のアメリカ北西部を舞台に、実在の猟師ヒュー・グラスのサバイバルと復讐を描いたウェスタン・アドベンチャー。
監督は『バベル』『バードマン』の最高に名前が覚えづらいオスカー監督のメキシコ人、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ。
主人公ヒュー・グラスを演じるのは『タイタニック』『インセプション』のレオナルド・ディカプリオ。
グラスの仇敵フィッツジェラルドには『インセプション』でもディカプリオと共演しているトム・ハーディ。
部隊の隊長アンドリューには『ハリー・ポッターと死の秘宝』『アバウト・タイム』のドーナル・グリーソンがキャスティングされている。
👑受賞歴👑
第88回 アカデミー賞…撮影賞、監督賞、主演男優賞(ディカプリオ)の三冠を達成‼️ディカプリオは自身初のオスカーを手にした。
第73回 ゴールデングローブ賞…監督賞、作品賞(ドラマ部門)、主演男優賞(ドラマ部門)の三冠を達成‼️
第69回 英国アカデミー賞…作品賞、音響賞、主演男優賞の三冠を達成‼️
第21回 放送映画批評家協会賞…主演男優賞!
あのレオナルド・ディカプリオが、グリズリーと戦ったり動物のレバーを生で食べたり魚を『ロード・オブ・ザ・リング』のゴラムの様に貪り食ったり滝に落ちたり馬の死体の中で眠ったりする映画。たまに喋る。
こだわりにこだわり抜いた撮影によって映し出される西部開拓時代の世界は非常に美しく、また残酷。
画面越しにも寒さが伝わってくるような世界で、必死に生きようともがくグラスの姿を見るだけでとてつもなく疲れます。
160分近く上映時間があり、その時間の大半はグラスが呻きながら地面を這っているという地味な絵面。
しかし、レオナルド・ディカプリオの圧倒的な演技(過酷な撮影により本当に苦しんでいるだけな気もするが…)により、画面に引き込まれるので退屈はしなかった。
いくら実話を元にしているとはいえ、さすがにちょっと盛り過ぎではないでしょうかね。
あんだけボロボロにやられておいて、しかも応急手当てしかされていないのにも拘らず、どんどん元気になるグラスの超人さは一体なんなのだろう…
滝に落ちても、崖から落ちても死なず、瀕死の重傷でありながら複数のインディアンや白人とも渡り合う。
80年代のアクション映画の主人公よりも多分強い。
シナリオは昔ながらの仇討ち物。いろいろと哲学的な展開もありますが、基本はわかりやすい単純な映画。
かなりキリスト教的な思想が重要なポイントとなっているので、キリスト教徒であったり、特別な知識があった方が作品に入り込めるかも。
クライマックスの一騎討ちは往年の西部劇のようで非常に燃える!本当にシナリオは徹頭徹尾王道。
とにかく、ディカプリオの頑張りを見る為の映画といってもいいほどのディカプリオ祭り。
しかし、ただのディカプリオ・ファン・ムービーではない。
ディカプリオとトム・ハーディ、ディカプリオとグリズリー、白人とインディアンといった対立の構図を複数登場させて、その中でのやったりやられたりの無常感が映画を支配しています。
それぞれが生きていく為に命を奪い合わなくてはならない。大自然の中にあるのはただそれだけの、単純な自然の掟である。
その中で復讐心を持つことのなんと無意味なことか。映画のラストはまるで視聴者にそう投げかけているようです。
全体的に暗くて静かな映画ですが、個人的にこういった作品が好きなので割と評価が高めです😊
19世紀アメリカ西部の厳しい自然を壮大で美しく描く圧倒的な映像美。ディカプリオ演じるヒュー・グラスのサバイバルテクにも驚嘆する。
迫力
これは多分DVDで見たらつまらないと思う。
私は公開当時に映画館で見た。
自然の恐ろしさや自然の動き流れを感じれた。
レビューではつまらないやクソだと言われているけど
そんな風に言うならレビュー書かなければいいのに。
レオナルド・ディカプリオが初のオスカーを手にした作品。ベジタリアンなのに肉を食べるシーン。民族への思い。こういったことが現実にあるかもしれないのに、、
私はこの作品から得られるものがあると思います。
重ためで見ごたえ十分
自然の畏怖と人間の生きる力
1823年、毛皮ハンター一団がアメリカ西部の未開拓地を進んでいる最中に先住民に襲撃されるところから始まる話。ディカプリオ演じる、ヒュー・グラスは実在の人物で、実話を基にした映画。
「愛する息子を奪われた父の復讐」などと書かれた作品紹介を見ましたが、私自身は父子の愛など、そういった点にはほとんど感情移入できませんでした。大自然のスケールというか、自然の畏怖に圧倒されっぱなしで、自然の中の一部である人間が、ここまで生きようとした姿(生命力)をただ唖然と見つめるばかりでした。過酷な自然の中で、いかに人間が死なずに生き抜いたかということに感動を覚えるものであって、ストーリーで人を惹きつけるものではないと思います。監督の映像、撮影、演出、出演者やスタッフの根性なども半端じゃないと思います。
違和感があるとすれば、グラスの回復が早すぎるということかもしれません。映画の中では、どれだけ日にちが経ったかというのは明確にしておりませんが、特にラスト、瀕死の状態で戻ってきたのに、すぐに敵討ちに向かうというのは、ちょっとなあ……。
あと、ディカプリオが童顔であるせいか、息子と一緒にいても父親らしく見えなかったですし、トム・ハーディの方が年下のはずなのに、トムの方がおっさんぽく見えました。
もう一度、観賞したい気持ちはあるものの、やはり、これだけの映画なので、鑑賞後、ドッと疲れが出ました。自宅で52インチのTV画面で見ましたが、本物のスクリーンで観ていたら、感動が大きかったものの、圧倒されて疲労感がもっと凄かったかもしれません。
余談ですが、
スケールもストーリーも時代背景も違いますが、厳寒の中、極限状態を生き抜いたという『マイナス21℃』という映画も思い出しました。こちらも実話がベースです。
.
自宅にて鑑賞。五度目のノミネートで初のオスカーを手にしたL.ディカプリオを始め、'15~'16年における内外の各賞を総なめにした一作。自然光に拘って撮影された濁った無彩色の寒々しい原風景に重厚乍ら主張し過ぎないBGM。科白も少なめな上、夢うつつが度々混在する未整理で説明不足な構成もあり、1823年アメリカ北西部と云う時代背景や物語のバックグラウンドを知らないとなかなか読み解けない。ストイックな作り乍ら、情け容赦無く心揺さぶられる描写もあり、喩えるなら薄味乍らコッテリ濃厚で、お腹一杯になる一本。60/100点。
・実話ベースとの触れ込みだが、“ヒュー・グラス”、“ジョン・フィッツジェラルド”、“ジム・ブリジャー”や“アンドリュー・ヘンリー”隊長等、各人の設定や末路は史実と異なる箇所があり、あくまでM.パンクが'02年に発表した原作『レヴェナント 蘇えりし者』を元にしている。亦“ヒュー・グラス”の逸話は、R.C.サラフィアン監督が『荒野に生きる('71)』として映画化している。'10年、J.ヒルコート監督がC.ベールを“ヒュー・グラス”にした企画が進行していたらしい。
・一見、不屈の精神による復讐劇だが、或る意味で唯心論的な境地に至るラストでカタルシスを得られるかは観る者を選ぶ。本篇では殆ど説明が無いが、M.ナケコ演じる“アリカラ”族の探す“ポワカ”と思われる女性の顔を憶えておくと理解が深まる。
・リアルに拘り、劇中の時系列通りにカナダから始まった撮影は暖冬で融雪した為、アルゼンチン南部の高地に移り、約九箇月間に亘り続けられた。これにより撮影スケジュールは大幅に遅れ、予算も当初の6,000万ドルから9,000万ドルと徐々に膨らみ、最終的に1億3,500万ドルとなった。
・極力CGIに頼らない作りを目指したが、熊との格闘シーンや谷底に落下するシーン、馬を射殺するシーン等はこの限りでは無い。亦、『スター・ウォーズ/帝国の逆襲('80)』にシンスパイアされたとされる馬を切り裂いた後被り、吹雪を凌ぐシーンでは、馬を始めその内臓もフェイクである。
・ひたすら喘ぎ、苦しむ“ヒュー・グラス”のL.ディカプリオは本来菜食主義者だが、A.レッドクラウド演じる“ヒクク”と知り合うシーンでバイソンの肝臓を生で食した。この“ヒュー・グラス”と対照的な心持でいかにもアクが強い存在感を示すT.ハーディの“ジョン・フィッツジェラルド”だが、当初はS.ペンが演じる予定だった(スケジュールの都合がつかなかった為実現しなかったらしい)。
・鑑賞日:2017年3月6日(月)
まぁ凄い。
アカデミー賞うんぬん以前に、予告編を観てこれは絶対に観たいと思っていた作品。
結論から申しますと、まぁいろんな意味でとにかく凄まじい作品だ。
全編通して、寒そうで、冷たそうで、痛そうで、襲ってくる原住民とか熊とか、もう凄いのなんの。
まさに体当たりの演技なわけで、ここまで演るかといった感じ。
レオ様ファンの女子は観ない方が賢明かな?
いや、悲惨過ぎて観ていられないかも。
ま、信じられないくらいに主人公が超不死身だったり、ものすごい回復力だったりというのはあるが、こんなにも過酷な撮影を頑張ったのだから、アカデミー賞ぐらいあげないとダメでしょう。
映像は素晴らしかった。
カメラワークも迫力満点。
あまりに凄過ぎて、冒頭からずーっと気分が悪いまま観ていて、人には勧めにくい作品ではあるが、一度ぐらいは観ておいて損はないかも。
興味のある方はどうぞ。
アポカリプトのアメリカ大陸編
全516件中、61~80件目を表示