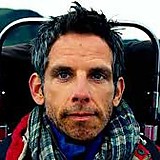この世界の片隅にのレビュー・感想・評価
全158件中、1~20件目を表示
どこまでも、丸く、柔らかく、そして優しく
大変な時代、厳しい社会、壮絶な戦時中であるということを、隅々まで丸く、柔らかく、そして優しく包み込んでいく不思議なドラマ。何がどうなるのか、ある程度は想像がつくだけに、判っているだけに切なかった。笑えなかった。ただ、見守るしか無かった。その裏に隠された激しい想いが、判りやすく見え隠れする。それでも、あくまでも柔らかく、丸く、そして切なくて。
玉音放送を聴いて地に伏せてむせび泣く姿。これまで良く観た映像だけど、その本当の意味をやっと知った気がして恥ずかしかった。ああそうか、それまで戦争の煽りを喰らい、大変な生活をしてきたことが、全て無駄になったということだ。何も日本が負けたことが悔しいとか、陛下への忠誠とかそんなんじゃなく、今までの苦労を返せと。少し考えれば判りそうなことだったのに。貧しくとも家庭を守り、大変な思いをしてきたのに負けやがって、こん畜生、と。ただ、無心に平和を唱えることは、それは正しいのかも知れないけれど、そんな単純な物差しでは測れない想い。
そして、最後の最後に凄い話をぶっ込んできたな、と思った。親を失い、拾われたあの子の話。これまでにない、無残な映像にビックリしただけかも知れないけれど。そして、最後の最後の最後に沢山の絵を書いて視聴者に手を振るのは、失われたすずの右手。失われた・・・。
どこまでも、まるく、柔らかく、優しく、そして、切ない――。
アニメ耐性がついたおっさんが出会った幸せ。被ばく2世のおっさんは本作をこう見た
「傷物語II」「君の名は。」「聲の形」と今年アニメ映画にチャレンジする、という目標を掲げ、最初のとてつもないハードルをなんとかクリア?し、ここまで来たおっさんにとって、本作を鑑賞することに「アニメ映画」というハードルを全く気にせずに鑑賞しようと思ったことは自然な流れ。
ましてや、広島市、呉市が舞台の映画。被ばく2世のオレにとって、「観なければいけない映画」である。
「この世界の片隅に」
・
・
・
私的なことだが、主人公すずは、オレのおばあちゃんにあたる世代である。
祖母はまさしく「そのような生き方」をしてきたお人である。いきなり終盤の話をするが、広島で原爆を受け、孤児を受け入れ、孤児院を立てた立派なお人である。
だが、それ以上に、「かわいい」人だった。笑顔がくしゃっとなる。祖母と暮らした日々は中学生までだったが、「当時」の話は一切しなかった。今も資料館にその書記を残す祖母がなぜ「当時」の話をしなかったのか。
それはたぶん、「精一杯生きることに、周りがどうだろうと、やるべきことをする。子供たちにこれ以上悲しい思いをさせない」
本当に、ただそれだけだったのだと思う。
ただ日々を、その日を、その次の日を、その次の年を、「生きてきた」だけなのだろう。それは大変な日々だっただろう。だが、人は笑っていきていたい。
いや、「笑っていきなければいけない」。
祖母のように、すずのように、どんなに世界の片隅にいる人間でも、何があろうと、そうなのだ。
大事なものが奪われる。だが、今は生きている。ならば。
その「ならば。」をどう過ごしたか、この映画の登場人物のさまざまな「ならば。」を「さりげなく」描いていることに、オレはうれしく、悲しく、その「上手さ」に激しく感動しているのである。
この映画には、その日々がある。そしてそこからの、未来がある。
この映画は、戦時中、戦後と、主人公すずが日々を生きる姿を描くと同時に、彼女の中にある「相反する思い」が日々常に交錯し、それが「笑い」「怒り」「悲しみ」「諦観」を重ね、織り交ぜ、小さなエピソードをいくつも見せてくれる。
広島を故郷に、呉を田舎に持つオレにとっては、特に瀬戸内海の景色、小丘の松の木、その土の質感に涙する。
周作の、すずへの気配りと照れの所作に微笑み、性の生々しさを感じる。
哲くんの、すずの「普通の姿」をみて、カットごとに、「はははは」と笑う姿に爆笑し、そして涙する。
ラッキーストライクの空き箱の入った残飯に、怒りと笑いがこみ上げる。
一番ボロ泣きしたのは、ラストの橋の上で、バケモノのかごから出てきたアレ。最高に優しい新たなる出発である。
そして、孤児を連れて帰るすずに涙する。その子供は、うちの母とほぼほぼ同い年にあたる。オレはおばあちゃんのおかげで、ここにいるのだ。
追記
エンドロールも泣かせる。「受け継ぐ」、とはこういうことなのだ。
生きていく人の怒り
こうの史代の作品は、悲哀よりもずっと印象的に「怒り」が描かれていると思う。素直で純粋なキャラクターのまっすぐな怒りは、受けとめざるを得ないのに直視できない厳しさがある。
敵国でも原爆でもなく、すずさんは幸せな世界をこんな風にしたすべてを憎み、詰り、泣き、絶望し、それでも生きていくためにまた立ち上がる。真っ当な怒りは生き続けるためのエネルギーだと分かるから、私は彼女の作品にこんなにも惹かれるんだろう。
人さらいを撃退する星空、爆撃される空に走る光の表現は妙にファンタジーチック。恐ろしい現実を受け入れるための脳のまやかしにも思える。
涙が………
このシーンでとか台詞でとかではなく終わってから止まらなくて次の映画観るのに気持ちの整理もつかなくて困りました。
ネットやTVでもやっていたしロングバージョンも保存していたんですけどまだ観ていなかったのでせっかくなんだからスクリーンでと思い鑑賞しました。
昔親にどうだったの?戦時中は?と聞いた事がありました。
親父は元々口下手であまり語る事もなく母親が言うには「食べるものが無かったからいつもお腹空いていたわ」とのこと。
田舎の方に住んでいたこともありやれ爆撃機だとか焼夷弾だとかは無かったみたいです。
そして今日は2025年8月15日。終戦の日を迎えました。
今住んでいる街は正午にはサイレンが鳴りません。
出身地は毎年、前に住んでいた街もキチンと鳴っていたのですが………。
別に近い身内が戦地へとか被害がとかはありませんですけど、毎年サイレンが響くと平和をそして戦没者に向けて願いを込めて黙祷をしてました。
この作品を通して今一度戦争や平和の事を改めて考え思い起こしてほしいです。
辛い悲劇や苦痛や苦悩を乗り越えていく強かさ
ずっと観たかった映画です。
中々の名作だと思いました。
派手さはないけれど、アニメーションとしてのクオリティも高かったし、のんさんの声の演技も良かった。
お話しも、途中までは淡々としていながら、色々なエピソードに良い意味でのインパクトがあって飽きません。
戦争中の生活を描いているから、大変辛い悲劇や苦痛や苦悩は沢山有るのだけれど、それを乗り越えていく強かさもあると感じました。
とても面白かったです。
何よりも、この時期にのんを起用した上で、きっちりと名作にした製作陣の慧眼は凄いと思った。
世の中に逆らわず、厳しい時も工夫して小さな幸せを見つけながら生きて来たのに、 気が付くと、突然、大事なものをいくつも奪われてしまう恐怖
主人公すずさんを通した、これまで描かれる機会が少なかった、第二次大戦当時の「普通の人たちの普通の日常」。
ちょっとぼーっとしているすずさんのキャラクターと、それにぴったりな声を演じるのんさんがとってもいい。
さらに加えてアニメであることで、生々しさが少し薄まっているのも観やすくなっています。
「ひとさらい」「ざしきわらし」や「おにいちゃんのワニのお嫁さん」の話、波を撥ねる「白いうさぎ」など、すずさんの空想も、映画全体に優しくて楽しい空気感を作ってます。
そのおっとりしていたすずさんが終戦を迎えたときの「心情」や、そのあと描かれる戦後の人生がさらに心に残ります。
反戦を声高に描かないスタンスが素晴らしいです。
…というのが2016年公開時の感想でした。
その後、2018年年末公開のロングバージョン「この世界の(さらにいくつもの)片隅に」を鑑賞。
そしてこの度、すずさん100歳、終戦80年上映を改めて鑑賞して、少し感想が変わりました。
不自由で貧しい生活の中でも、つましい小さな幸せを見つけて生きていけるようになることは、実は褒められるようなことでも何でもない。本当は恐ろしいことなのだと。
そして、あらゆる状況でも受け入れて逞しく生きていく。
少しずつ周りの状況が悪くなっていき、絵を自由に描くことすらできなくなっていき、気付いたときは、いくつもの近くの大事な人の命が、一瞬で失われてしまう。
個人では逆らえない、どうしようもない大きな波にさらわれてしまう。
身近な大事な人も、日常も奪われて、ただの普通の人間が、例え最後の1人になっても竹やりでも戦う覚悟でいたのに、1つのラジオ放送だけで、突然無かったことにされる悔しさ。行き場のない怒り。
ぼーっとしたすずさんのままで死にたかったのに。
それでも、拾った子とともに歩き出す姿には救われる。
ここでまた、どんな状況でも生きていける、人の強いところを良き方向に生かせる時代が来る。
失った右手が、生き生きとして明るいエンディングのイラストを描いている。
すずさんの日常における戦前戦後
のんが演じるすずさんの何と魅力的なことか。
ぼーっとしている、という表現を自ら何度もするすずさんだが、
そこがすごくカワイイのだ。
すずさんの生活が実にリアルというか現実的であり、
当時の生活が生々しく描かれているのも好感が持てる。
嫁に行くとはどういうことか等、よくわかるつくりなのである。
戦時中、市井の人々はどう受け止め、どう生きていたのかも
痛いほど伝わってくる。
このドラマならではなのは、すずさんの姪が亡くなり
自らも右手を失くしてしまうこと。
そこからのすずさんの絶望、そして前を向いて生きようとする姿勢に
元気をもらえる。
戦争を中心に描いている映画ではないと感じるが、
日常の中に戦争という要素が入ることで、
より戦争の恐ろしさや悲惨さを痛感できる作品になっているのみならず
重厚な中にも、すずさんのゆるやかさに元気をもらえる作品なのだ。
猛烈に心に刺さったし、劇場で観ることができて本当にうれしい。
今後も毎年夏に公開してほしいと思った。
多くの特に若い方に観てもらえるとうれしい。
タイトルなし(ネタバレ)
原作は未読のまま、クラウドファンディングの話を知ったりして気になっていたので、公開されたら必ず観ようと思ってました。
まず、主役ののんさんの好演が印象的でした。おっとりとしつつも力強く生きた主人公にぴったりで、他の人は考えられないほどの適役。
数年分の出来事を二時間で描くために、話はかなりのスピードで進んでいくのだけど、観ていると、とてもゆったりとした気持ちでいられるのはこの好演によるものだと思う。
今までの戦争映画にありがちな、悲惨さを強調するのではなく、あの時代を生きた人々の日常を淡々と語っていく。そこには笑いがあり、物資が欠乏する中で工夫するたくましい姿もある。
それでも、歴史を知っているだけに日付が進むごとに胸が締め付けられる思いになる。
戦争はそういう何でもない日常を否応なく壊してしまう。家族を奪い、楽しい時も辛い時もすずさんの心の支えとなった絵を描く右手も奪った。
エンドロールも素晴らしかった。すずさん家族のその後や、絵を描くすずさんの右手が描かれていて、戦争を生き残った人々の未来と、戦争で奪われていなかったらあったはずの未来の可能性を表してるのかなと感じた。
声高に戦争反対と言っている映画ではないけど、改めて、二度と起こしてはいけないという思いを強くした。
いろんな世代、たくさんの人に観て欲しい。自分も、一回では捉えきれなかった部分があると思うので、もう一度観たいと思う。原作や関連本を読んでみたいし、広島にも行かなくてはと思った。
最後に余談だけど、鑑賞したシネマシティの袋と本作品のパンフレットが絶妙のマッチで、戦災から復興した現代の町並みに思えた。あの当時も今も、この世界の片隅に生きている、すずさんたちと自分たちがより身近に感じられた。
何か良い映画
................................................................................................
戦時中に広島育ちのド天然主人公は、結婚をして呉へ。
軍事拠点のため空襲は日常茶飯事の中、強く生きていた。
気の強い義姉が出戻りで同居していたが、それなりにうまくやってた。
しかし空襲の時に義姉の一人娘を連れた状態で爆撃を受ける。
これにより娘は死亡、主人公も右手首から先を失う。
そして義姉に辛く当たられ、広島に帰ることを決断、旦那に告げる。
しかし義姉は主人公に辛く当たった事を悪く思っていて、詫びる。
そして変な気を遣ったりせず身の振り方を決めるよう告げる。
こうして呉に残る主人公、そしてまもなく広島に原爆が落ちる。
やがて終戦し、主人公夫婦は広島を訪れ、孤児を連れ帰る。
こうして新しい生活が始まるのだった。
................................................................................................
劇場で見た。何を訴えたいのかが難しくてよく分からなかった。
でも戦争の悲惨さや恐ろしさ、人々の強い生きざまはよく分かった。
戦争をしてはいけないこと、現代人は恵まれていることが伝わる良い映画。
主人公は鈍くさくて、義姉の妹の死因にもそれは絡んでいる。
だから主人公も辛かっただろうし義姉の腹立ちもよく分かる。
でもそこが訴えたいことではなかったっぽい。
旦那も嫁を束縛せずに理解してくれるいい人で、主人公は救われている。
タイトルは「この世界の片隅に自分を見出してくれてありがとう」の意味で、
やはり旦那との愛情部分がメインテーマとなるのかな。
しかし能年の声が主人公のキャラとピッタリで顔が浮かんだ。
やっぱり表現力あるのかな、適役だったと思う。
名作映画
戦争前から戦後までの時代をすずさん(そぼくな能年玲奈さんの声が実によくマッチしている)の目線で描くアニメ映画
まるで岡本喜八の映画の登場人物のように辛い境遇でも明るく楽しく生きる姿もよかったけれど、後半、目の前で姪が死に自分も腕を失ってからは暗いながらも必死に生きる姿もまた良かった。
住んでいる世界が違うんだ。と別れてしまう娼婦
病に体を蝕まれてしまった妹
実はすずさんに思いを寄せていた巡洋艦の水兵
時代にほんろうされる登場人物たちの心境を考えると重い気持ちになるが、孤児を拾い家で育てる家族になるラストからは明るいものを感じた。
そして驚かされたのが砲撃や飛行機のエンジン音
おそらく当時の呉で戦時中を知る人の証言かもしれないけれど、本当に大きくて恐ろしく感じた。
叔父の影響で戦争映画は結構見るけれど、こういう音響で驚かされたのは初めてだった。
海にずらりと浮かぶ戦艦大和のような艦艇
迎撃に向かう紫電を見て馬力がいいんだ。と語るおっちゃん
戦争は良くないことだけれどこういう兵器がカッコいいんだよね。
「機動戦士ガンダム ポケットの中の戦争」や「太陽の帝国」のような要素を感じた。
冒頭とラストに出てくる謎の存在「ばけもの」
アレは地獄の黙示録のクラシックを鳴らし飛ぶヘリコプター部隊、
戦争のはらわたのOPとラストに流れる童謡ちょうちょ
炎628の発砲していくと若かった時代~赤ちゃんになるヒトラーの写真
激動の昭和史 沖縄決戦の戦場をさまよう女の子
それらのような超現実的な演出なのかと思う。
リアルな戦争映画だからああいうファンタジーのような演出がはえるのだろうか。
今までみた戦争映画の中で上位に来る作品だなと思った。
どんな状況でも人は生きていかなければならないのだと
事前の情報を一切知らないで映画.comの評価だけで見てみた。
前半を見てすずの平凡な一生を描くのかな?と思ったら。。。
戦時下で、ともあれ人々は貧しくとも生活をしていかなければならないわけで、
そんな中でも舞台である呉市は戦況が悪くなるまでは、ごく平凡な当時の日本人の
生活を送っていたわけだ。
作品全体の雰囲気や絵のタッチ、音楽など
全てがほのぼのとした表現がなされているが、物語は後半終戦間近の広島を描いているため
雰囲気とはかなりギャップのある展開になる。
この作風と戦争の残虐さと生活。悲惨で悲しくてやるせない気持ちを表現し
他に類を見ない世界観を作っていると思う。
すずが腕をなくしても、径子が晴美を、夫を、家を、息子を失っても、
(径子が一番悲惨だけど。。)
そんな気持ちをしながらも次の日からは世界は回っている。
この世界の片隅にというタイトルは非常にぴったりだと思う。
生きるというか生活するという言葉が合うと思う。
どんな時でも人は前を向いて生きていかなければならないのだと
思わされた物語だった。
能年玲奈の声を久々に聞いたが非常にすずにあっていた。
穏やかだけど実は強烈な反戦映画
お婆ちゃん世代の戦前から戦後の激動の日本。割と最初の方で、ああこのままだと・・と知っているだけにヒヤヒヤした。今世界はコロナと戦っていて、その前に自分の国の政府との考えのズレにイライラしているけれども、この映画の時代は無理矢理戦争に駆り出され、日本に残っていても空襲が命を奪っていく。まあどちらも政府によるところだ。どんな政治家を選ぶかで人生が延びたり縮んだりする。選挙は大切だし、教育も大切。この当時を生き延びて今の日本を築いてくれたお年寄りがコロナで再び苦しめられている。政治家さんは自分だけでなく国民の命も大切にして欲しい。
***主人公すずは人の心を明るく変えられる実は凄い強い人。私なら結婚してすぐに義姉の態度に腹が立って広島へ戻るかも?彼女は若いけど心が広いし鈍感力と包容力がある。次第に義姉も素直な彼女の事が好きに。広島から爆風によって飛んできた障子戸に「あんたも広島から来たんね」と言って広島への想いを巡らせていた。昔の女性は周りが縁談を持ってくるケースが多かった様なので、義姉の様に恋愛結婚は珍しいだろう。すずを見て、私の祖母達の苦労や貧乏生活の中でも僅かな楽しみ方を垣間見た様な気がする。一緒に観て色々当時の話を聞いてみたかったなぁ…
※焼夷弾が自宅に落ちた時、一時悩んだのは家が燃えれば広島へ堂々と帰られると考えていたのかな。あの時は呉で生きていく事を選んだけど片腕は無くなるし、晴美ちゃんは死んでしまうし呉での経験は辛かったのだろう。
映画の構成では、画面の入れ替わりが所々早すぎたりして分かりにくいシーンがあったり、原爆投下のシーンは2回あったりまとめるのが難しかったのかなと思いました。リンさんは少ししか出ていないのにすずはリンさんの事を何かと心配していたり変だなと思ったら、原作ではリンさんはもっと重要人物のようですね。
※良かった、良かったのシーンで「4月にはテルさんの紅を握りしめた右手」のすずのセリフがあって随分何度も見返して探したけれどテルさんすら出てこない。ネット検索してようやく分かりました。リンさんのお友達のようです。この台詞は省けなかったのかな?
※ところで玉音放送の直後のシーンで家々が映りその先に韓国の国旗の様なものが見えます。巻き戻し一時停止して見ました。一瞬です。これは一体どう言う事なのでしょう?呉に韓国人が住んでいたのでしょうか?
この世界の片隅に
当時の人々の生活がよく分かる。
配給の停止、防空壕の設置、空襲、原爆…。戦争の足音が日を経つごとに強く聞こえてくるのがリアル。
死ぬ事が意外にあっけなく描かれてた。誰もがいつ死ぬか分からない世の中。
コロナできつい日々なんてこの時代に比べると本当に大したことない。
そんな中で右腕を失い、絵を描くことも奪われる。
それを彼女は今までの思い出全てが奪われたように感じてしまっていた。
この作品は突如として絵画チックになるが、それが意味するものはなんなのだろう?
すずの物語はまさしくこの世界の片隅でおこっていることで、この時代では他の人々にもそれぞれに物語がある。
すずの『この世界の片隅で私を見つけてくれてありがとう』というセリフが印象的。無理やり連れてこられたみたいに言われるシーンが何度かあるが、このセリフがすずの気持ちの全てを表してる。
いつの時代も、世界の片隅にいる誰かに出会い、共に生きていくことは変わらない。
75
「絵」の使われ方が見事だった。
すずの心情を表す水彩画のようなタッチ、暗闇の中で線香花火が弾けるような映像、失った右手、左手で描いたような歪さという表現、「絵」というキーワードを織り交ぜるだけでここまで深みを出せるのがすごい。
何でも使うて暮らし続けるのが、うちらの戦いですけぇ
原作、連続ドラマ共に軽く触れてはいたので、ストーリーは把握済みでした。
我らがすずさん。
圧倒的ヒロイン。
どこにでも居そうなちょっとボケーっとした癒し系ヒロイン。
彼女の声を当てたのはのんさん。
彼女の優しくてゆったりとした声がぴったりで、声で言ったら彼女以上の人はいないと思うほどしっくりきます。
舞台は広島、そして呉。
前半は普段の平和な日常に、少しずつ戦争の影が近づいてくる感じが良かった。
物語が進むにつれて戦況は悪化し、毎日のように空襲警報が鳴り響く。
後半は次々と事件が起きていき、終戦からは涙が止まりませんでした。
普通、戦時中の人の死などに色々と考えさせられますが、終戦してからも戦争が簡単には終わらないことが分かります。
戦争映画ですが、戦闘としての残酷な真実を伝えるような作品ではなくて、あくまでも昭和初期の人々の暮らしが描かれていて、戦場へ向かわない者たちの戦いの記録のような作品です。
すずさんは確かにボーッとしていてマイペースだけど、その分戦時中は色々な出来事が目まぐるしく起こっていくということが分かりました。
映画だから一つ一つのシーンが短めだったのかもしれません。
特に印象的だったのが、人の死の描き方。
お兄ちゃんや晴美の死、そして原爆。
本来もっと尺が長いはずですが、この映画ではすぐに次のシーンに変わります。
確かに心に深い傷を負っていますが、それくらいすぐに切り替えないと、当時はやっていけなかったのではないかと思うと、当時の人たちの心がいかに強かったかが分かります。
それでも、経子さんが娘の死に対して隠れて泣いているシーンには、胸を打たれました。
コトリンゴさんの優しく切ないような、歌も素晴らしかったです。
また、広島弁が何ともいい味を出しています。
本当に美しい映画だと思いました。
必ず観ておきたい名作ですし、何度も観ればその分良さが倍増するのではないでしょうか。
「普通を保つこと」が「特別格別」
どうしても映画館に見に行く勇気が出ず、ドラマだけで留めていた作品。
コロナ禍で終戦後の平和維持を高めるドラマなどが少なく、しかし戦争の惨禍を経験した世代は年々減っていて危機感を覚えていたタイミングで鑑賞。
冒頭の海苔を売りに行く場所が、まさに原爆を積んだ飛行機が落下地点としていた場所で、最初からぞわぞわが止まらない。冒頭で、来たれ友よが流れると、これから出るとわかっている犠牲者に捧げる物として、作品がより一層重たく感じられる。
ほわほわとしていて、何かあらば命を守る機転が働くのか心配なすずだが、人攫いの望遠鏡に海苔を被せるファインプレーと命拾い。
嫁入り後、義姉も出戻って肩身の狭い思いをするが、その義姉ケイコも喪失の連続を乗り越え、娘の晴美だけは守っていく覚悟と緊張感に満ちてなのだろう。
そして、本当は器用で男気ある性格ゆえ、足の悪い母に充分に甘えられず育ったのかもしれない。それゆえ、すずを生易しく感じ、キツい言葉をかけてしまうのかもしれない。オシャレに溌剌と人生を切り開いていたケイコも、身体は被災をしていないが、強がっているだけで本当は心がズタズタで、見ていて苦しい。
でも、ケイコが、すずの人生は「自分で選択した末の果てではない」かのように言ったが、それは違う。
実際その直後、すずは微妙な関係の義姉に泣きついて、ここに居させてくれと頼み、被曝を逃れることができた。
思えば、幼なじみの水原が迎えに来てくれた時も、夫を想いすずの意思で思いとどまれたからこその、高台で過ごせて守れた命。
晴美と畑にいた時は、義父が守ってくれ、白鷺を追いかけた時は、夫が守ってくれ、沢山の命がすずを守ろうとしてくれている。
次々と爆弾の種類が変わり、無関係な大勢の一般市民が恐怖と不安と戦禍で人生を狂わされ、でもその中でも人と人が助け合って守り合ってそれぞれ少しの心の拠り所を保っているのが、より戦争の無意味さを露呈させる。
なかでもすずは、戦争を通して、最初はハゲができるほどストレスがかかっていた環境下の中で、義家属との心の通い合いが深まり、かえって居場所を見つけていく。
嫁入り前には気付いたり、慮ることの難しかった人間の感情にも、しなくても良い経験を沢山させられてしまう中で、否応なしに大人になり、わかるようになっていく。
それでも過酷な環境で我慢をし義家族のために尽くし、実家も兄を失い被爆し、腕も失い、絵も描けなくなり、なにも「良かった」ではないのだけれど、世界の片隅にすら思える1人の人生の中に、人間の存続に不可欠な、思いやりや優しさを生み出す、命あってこその経験や感情の積み重ねが詰まっていて、「尊い」命が繋ぎ止められた安堵がある。
だからこそ、晴美という小さな尊い命の犠牲が悲しくてたまらない。原爆さえなければ、陸軍の将校さんとのキラキラした青春が成就していたかもしれない、姉のすみの被曝の描写も見ていられない。家業の海苔も、被曝した事だろう。一方、すずの夫、周作が戦地に出兵せずに済んだ事は大きな希望である。
誰しもが心の余裕をなくして当然な中でも、少し鈍感なお陰でやさしさを保てたり、時を経て、誰かに攻撃的になるのではなく、少しだけ図太くなれる、すずのような淡々と「普通」を守れる女性が実は1番生命力があり、特別、格別に強いのかもしれない。
そうした想像を絶する忍耐力、咄嗟の判断力の持ち主達が繋いできてくれた、現代の日本人の命を、私は無駄にしていないか、平和維持のために使えているかと、省みる作品。
子供にも平和への意識を強く持っていて欲しいとか、あれこれできるようにならねばと年々求めてしまうが、まず生きているだけで大感謝なことを思い出させられる。
タイムリミットを知っているだけに「ごくありふれているけどキラキラした日常」が次々と奪われていく悲しさがあると聞いていたが、見てみるとどんな環境変化の中でも工夫し、例え原爆まで落とされたあとも、助け合い暮らす人々の逞しさ優しさの方が印象に残ったし、それらを残したまま終戦を迎えられた日本は、むしろ軍事力で負けても人間力では勝ったとさえも感じる。戦勝国がいまだ核の正当性を主張していると、余計に。
想像することすらできない、感情の経験値が浅い優しさでは、世界平和など程遠いだろう。
世界平和に向けて、今後の日本の立ち位置に期待する。
軍港の呉、海猿の呉、呉には既に印象がたくさんあったが、九嶺でくれなことは初めて知った。
戦争がメインの映画ではない
戦争にフォーカスした映画ではなく、一番被害にあった広島市の近くの呉市の話。
他の戦争がメインの映画とは違って他の地域の物語。
タイトルとマッチしているのと、違うところからフォーカスされているのが面白いと思った。
沖縄出身なので戦争について小さい時から勉強させられていましたがこういう映画もまた勉強になるなと感じました。
確かに残酷な描写とかはあまりないが、本当にこういうマイルドな感じで過ごされたのかなぁと。
今コロナで死と近い状況下の中どうでしょうか?
出来ることはして、その中で普通に暮らす。
そんな感じ。
すずの天然な優しさや、前向きな思考、行動、知恵と私に必要な事が沢山詰まった映画だと思いました。
ここからネタバレを含みます
妹さんはピカドンで腕にあざができて、結果亡くなるのか?
最後の今までにない残酷に表現された死体は戦争の悲惨さを描写したのかなと感じました。
後清水さんは、どういうポジションだったのか、、、。
そこがちょっとわからなかったです。
生きてきた中で最初にすずが自分で選んだ道という意味でしょうか、、、。
また、日本が負けたときにとても悲しくなりました。
日本が勝つに決まっていると思って死んだら勇者!
日本の勝利のための犠牲にありがとう。
って思って生きてきた人の気持ちになったらあれだけでは立ち直れないと思うのです。
それをこのほのぼのした表現であの短いシーンで感じさせれるのが凄い。
後、防空壕の中で耳と目をつぶって口を開かないと目が飛び出すという事を知ったのが衝撃でした。
観て良かったです。
全158件中、1~20件目を表示