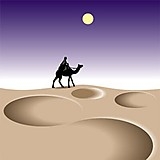ふたつの名前を持つ少年のレビュー・感想・評価
全36件中、21~36件目を表示
都合の悪い過去を生き延びろ!
ポーランドのユダヤ人少年が、ナチスの迫害から逃れ、たったひとりで戦禍を生き抜いた、という実話を基にしたお話です。
少年の名はスルリック。お父さんは街のパン屋さんでした。しかし、平和な暮らしも、ナチスドイツがポーランドに侵攻してきたことによって一変します。ナチはユダヤ人狩りをすすめてゆきます。住み慣れた家を追われ、ナチから逃げる一家。どうしても息子だけは生き残らせたいお父さんは、スルリックに、教え諭します。
「今日から名前を変えろ、何がいい?」
スルリックは、強い、いじめっ子の名前を言いました。それが「ユレク」でした。
「そうだ、お前は今日からユレクだ、いいな」
そしてお父さんはユレク少年に語り諭します。
「いいか? 父さんの名前も、母さんの名前も忘れていい。だけど、これだけは忘れるな、ユダヤ人であることは絶対に忘れるんじゃないぞ!」
この言葉はユレク少年が聞いた、お父さんの最後の言葉となります。
8歳の少年はたったひとり、森へ逃げ込みます。
もうすぐ冬がやってくる。幼い少年の命は、厳しい自然の中で耐えていけるのか? 食べ物もない、やがて吹雪が襲ってくる。寒さの中、彼は一軒の農家にたどり着きます。少年を救ってくれたのは、その家にひとりで住むヤンチック夫人。彼女は暖かいスープと寝床を与えてくれました。それだけではなく、彼女は8歳のユレクが、これからひとりで生きていけるよう、さまざまな知恵を授けてくれました。
やがてユレクは、ヤンチック夫人のもとを離れ、少しづつ森の中で生活する術を、体で覚えてゆきます。
時には近所の農家の前で「物乞い」をし、あるいはその農家で働いて食事をもらいます。
ユレク少年が学んだことは「一つの農家で長居をするな」ということでした。一つ所で暮らすよりも、放浪し続けることの方が、ユダヤ人だとバレない、ナチに見つかりにくい、のです。こういったことをわずか8歳の少年が体得してゆく、徐々に成長して行く姿を淡々と監督は描いてゆきます。
ユレク少年は、生き延びるためには嘘もつく、機転を効かせる、危険を察知する、そして働く。
どんどんたくましく、賢くなって行くユレク少年。
彼はやがて、大きな地主の家で、農作業の手伝いとして、住み込みで働き始めます。しかし、ある日、牛をつないだ歯車に手を挟まれる大怪我を負います。
街の病院へ担ぎ込まれるユレク。しかし、担当の外科医は、少年をユダヤ人だと見破ってしまいました。
「ユダヤ人に手術はしない」と外科医は冷たく言い放ちます。少年は治療も受けられぬまま、病院の廊下に放置されてしまうのですが……
本作で強く印象に残ったのは、ユレクとお父さんの別れ際のシーンでした。
お父さんがユレク少年に求めたことがあります。それはユダヤ人であること、ユダヤ教徒である「誇りと尊厳」をわすれないことです。
それほどまでに、ユダヤ人であることのアイデンティティは、強烈なものなのだ、と思い知らされるのです。
我々日本人は、よく無神論者であると言われます。ハロウィンやクリスマスを大騒ぎして楽しむかと思えば、大安吉日、友引、仏滅を意識します。また、占星術やタロットカードなど、あらゆる種類の占いは、もはやファッションの一部であり、人が亡くなると、お葬式には数珠を持ち、僧侶が読経を唱えます。
まるで都合の良い時に、都合の良い宗教行事をとっかえひっかえ利用している、実に無節操極まりない民族のようですが……
本作においては、(すくなくとも舞台となるポーランドにおいては)人間と神との関係を、改めて認識し直す必要があると感じさせられます。
人間などは、神の前では、実に取るに足らない存在であり、神は絶対的、全宇宙的なスケールでこの世を支配している。
だからユレク少年は、見ず知らずの農家で、物乞いをする時に「神を祝福する」言葉を唱えます。
物乞いをされた家の家主としても「神様を祝福する少年」を邪険に扱うわけにはいかなくなるのですね。
この辺り、自分の「ちっぽけな命」を生き延びさせるために、ユレク少年が神様を実にうまく「方便」として使う、そのしたたかさ。少年がひとりで生きてゆく、生き延びることの過酷さと「リアル」を感じます。
さて、このユレク少年。映画のHPを見ると、驚くべきことに、ペペ・ダンカート監督は、双子の子役を使って「ひとりの」ユレクという少年像を描きあげております。
オーディションには一年以上かけ、候補者700人から選び抜いた、という逸材の二人です。
また、ユレク少年の運命を左右するドイツ親衛隊(SS)将校。どこかでみたなぁ~、と思っていたら、ブラッド・ピット主演の「イングロリアス・バスターズ」やスピルバーグ監督の「戦火の馬」にも出演していた、ライナー・ボックというドイツ人俳優さんでした。
日本では戦後70年の節目、とされますが、ヨーロッパ、特にドイツやユダヤ民族にとっては、アウシュビッツに代表される「絶滅収容所解放70周年」の記念イヤーに当たるわけです。そういう年にこの作品が、日本でも公開されたことは、意義深いことだと思います。
本作はドイツ・フランスの合作映画。ドイツは徹底してナチズムの「忌まわしい過去」と向き合い続ける姿勢をとります。
日本では過去の戦争に関して「将来に渡って謝罪し続けること」を避けようという空気があります。一つ間違えばそれは、美しいとされる未来のために、臭い過去には蓋をしておこう、さらには、都合の悪い醜い過去は、いっそのこと書き換えてしまおう、という姿勢につながってゆくかもしれません。
ナチスによって都合の良いスケープゴートにされてしまったユダヤ民族。
本作は、そのなかで、奇跡的に生き延びた小さな命の記録です。
わずか8歳の少年が、戦争という極限状況のなか、機転を利かせながら、たくましく、したたかに生き延びた、というのは、神様がユレク少年に歴史の語り部という役割を背負わせた、のかもしれません。
人間って醜いなぁ
生き延びるためには、何でも出来なきゃいけない。私みたいな軟弱者には、無理ですね。精神崩壊するしかないし、死んだ方が幸せだ。少年らしく、やさしい人にのこのこ付いていくところは、賢くないと思うが、この年齢では無理ないか。世界が平和になりますよう祈らずにはいられない。就職氷河期ではあるが、この時代日本はまだまだ幸せだ。
最後の決断は民族の誇りか父の遺言か
2015/09/01、109シネマズ川崎で鑑賞。
冒頭で父が主人公の少年に託した名前も父も母のことも忘れてもいいから、ユダヤ人であることを忘れるな、という言葉、まだ右も左も分からない子供に民族の誇りや宗教を押し付けるのは親のエゴではないかと感じた。
その後親と別れて一人キリスト教徒になりすまし、ナチス親衛隊から逃れながら、いろんな大人に助けられたり裏切られたりしながら生きていく。
悪い大人にも会ったがたくさんの良い大人にも助けられた。
束の間の幸せを手に入れたりもしたが、それはユダヤ人であることを隠せたから。ユダヤ人として生まれたことを相当恨んだだろうに、最後に少年に迫られた決断を選んだのは民族の誇りからだったのだろうか、それとも父への思いからだったのか。
このような経験を二度としたくない思いでイスラエルという国家を作り上げたシオニストたち。しかし今度は同じような苦しみをパレスチナ人たちにさせている。映画の最後にそんなやるせなさを感じた。
走れ!走れ!
双子の笑顔の愛らしさたるや。
ヒューマントラスト有楽町で初鑑賞。これまで何作か(「縞模様のパジャマの少年」「悪童日記」「愛を読むひと」など。)”あの頃”が描かれた映画を観てきたけど、特に「ゲシュタポ」や「ソ連軍」「ユダヤ人」「傍観者」の描かれ方が今までで一番鮮明だと思った。そして、すごく詳細まで描かれている。例えばユダヤ人の見分け方を「割礼しているか否か」で判別していたり。
鑑賞後にパンフレットをぱらぱらめくっていたらキャストのところに二人の名前が書いてあって、双子が演じ分けているのだと知って驚いた。確かに、犬が銃で打たれてしまって泣いている時、みんなが離散してしまって泣いている時に見る”優しさ”、嘘方便(これには隣で観ていたひとも笑っていた。笑)、ゲットーから逃げ出す時、右手を失くした事実を受け止められない時に見る”勇気・反抗”。それぞれ表情豊かに演じ分けているから、すごいなこの子は!って思っていたけれど、二人だったなんて。笑
氷山の一角
実話ということだが、生き延びたユダヤ人の内の氷山の一角なんだろう。それぞれにドラマがあり…。
ユダヤ人だからと言って理不尽な扱いを受けた事実と、一方で、それを快く思わず手をさしのべる人達がいたことも事実なんだろう。
それって、日本の太平洋戦争の時も同じではないだろうか?
驚くべきは、この映画はドイツとフランスの製作で、さすがに直接的なナチスの残虐行為は描いていなかったけど、明らかにナチス(ドイツ)に分がない状況を説明しているところではないか?
例えは良くないかも知れないが、日本で従軍慰安婦の映画を作るようなもので、それだけ客観視している(ある意味で他人事?)ことが、日本との大きな違いなのではなかろうか?と、映画とは関係ない感想を持った。
よい作品なんだけど・・・
ユダヤ人とポーランド人との違いは、男の場合あれの皮で分かるのだという。ポーランド人だと偽っていても、ユダヤ人である証拠をつかむためにズボンを脱がされることを強要されるシーンが所々あり、女性にとってこの映画を見るには複雑であろう。事実なのだろうけど、男の私でもちょっと興ざめする映画であった。いい作品なのに評価がもうひとつ上がらないのは、これのためであろうか。そういうところを全部でなくても、もう少し省いてくれたらな、と思った。
他人に手を差し伸べるられる強さ。
レビューの通り、抑制感が程よい
生き延びろ、ユダヤ人であることを忘れずに
キネコ国際映画祭(旧・キンダーフィルム・フェスティバル)にて、吹替ライブシネマで鑑賞しました。上映の場で声優たち(声優科で勉強中の学生たち)が台本片手に吹替えるというもので、その迫力は一入(ひとしお)でした。
戦時下のサバイバル譚であるが、スルリック=ユレクを演じる少年の名演もあって、凄まじい迫力である。
(少年を演じていたのが、双子の兄弟と知ってビックリしたが、そういえば、ところどころで若干顔つきが違うなぁとは思ったのですが)
生き延びるためにキリスト教徒を装っていた少年が、いつしかキリストや聖母マリアに心を傾けていくさまなど、少年の心情の揺らぎも感じられて興味深い。
(手に入れたロザリオを手放そうとするが、もういちど手に取るシーンなどで、それが感じられます)
このような描写があるので、ラストシーンが活きてきます。
すなわち、終戦後、ユダヤ人孤児の救済センターの職員が来て、ふたつの道を示すシーンである。
左は、最後の最後まで少年の面倒をみて助けてくれたポーランド人一家へと続く道。
右は、ユダヤ人孤児救済センターへと続く道(この道は、遠くイスラエルまで続いていることが仄めかされている)。
この左右ふたつの道は父親が遺した言葉「生き延びろ」「ユダヤ人であることを決して忘れるな」のふたつでもある。
揺れる少年の心であるが、少年はユダヤ人であることを選ぶ。
静かであるが、力強い決断でもある。
その後のエピローグが描かれ、ここでビックリした。
年老い、イスラエルで暮らす少年の姿が写し出される。
老人は、あの少年の本物の姿であり、この物語は実話であったのだ。
(チラシの裏などには書いてあったんだけれど、読んでいませんでした)
それにしても、壮絶な生き様だったのですね。
「戦争は残酷、悲惨」は、いわずものがな。
RUN BOY RUN
日本語のタイトルが悪すぎると思う。決して名前がキーになっているお話じゃないのに、なんでこんな笑えない邦題をつけるのか、コモンマンの自分には理解できません。
まさにラン・ボーイ・ランと言うにふさわしいストーリーだったと思う。あてどなく生き抜いていく中に展開される、人間の優しさと醜悪さ、そして出会いと別れ・・・戦争という枠を越えて、エンターテインメントとしても楽しめる要素もたくさんあったように思う。それ故に若干の物足りなさも感じてしまうかも─。
時を自在に飛び越えるような構成は上手くはまっていたように思う。
映し出される絵は非常に美しく、まさにヨーロッパにおける伝統絵画を全て継承しているような映画であった。
中盤までは食い入るように見て、所々涙する場面もあったが、後半になるにつれて演技も絵も中途半端な印象を持った。
非常良い部分とあまり感心しない部分とを併せ持った映画のように、自分の目には映った。
ミクロの視点で描かれる、戦争の悲惨な真実。
【賛否両論チェック】
賛:“迫害”という凄惨な日々の中でも、手をさしのべてくれる人々の温かさが身に染みる。戦争の持つ負の部分について、深く考えさせられる。
否:歴史の予備知識がないと、退屈してしまうかも。最後の主人公の決断は、日本人の感覚からすると、やや理解しにくい部分もありそう。
戦争が生み出す“迫害”という悲劇の現実が、これでもかと描かれます。“ユダヤ人”というだけで暴力を受け、家を追われ、重傷を負っているのに手当てさえしてもらえない。そんな人間の悲しい一面がこれでもかと描かれ、思わずやりきれない気持ちになってしまいます。
一方で、そんな大勢に流されることなく、困っている者に温かい手をさしのべてくれる一部の人々の素晴らしさにも、思わず感動を覚えます。手術をしてもらえず、病院の廊下に放っておかれていた主人公を、年配の医師が見つけて激怒し、彼を手術室に運び込ませるシーンなんかが、特に印象的です。
歴史の知識があった方が、より感情移入出来る作品かとは思いますが、戦争の愚かさや悲惨さを痛感させられる、非常に社会派の作品です。
必死に生き延びようとする少年に引き込まれる。
救いの手
全36件中、21~36件目を表示