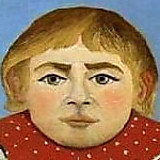アクトレス 女たちの舞台のレビュー・感想・評価
全6件を表示
過去の自分と若き自分からの解放
原題の「Clouds of Sils Maria」(シリス・マリアの雲)は作中に登場する劇中劇のタイトル「マローヤのヘビ」と重なっている。同様に、映画本編と劇中劇とが重なり合って物語は進む。
劇中劇「マローヤのヘビ」は若い女シグリッドが年上の女ヘレナを翻弄し自殺に追い込む話だという。かつて女優マリアはシグリッドを演じ、成功のキャリアを手に入れた実績がある。そのリメイクを上演するに際し、今度はヘレナを演じてほしいと言われることから物語は動き出す。
一方の本編でも、若い女と年上の女が登場する。ジュリエット・ビノシュ演じる女優マリアとクリステン・スチュワート演じる若きアシスタント。アシスタントのヴァレンティンは片時もマリアの元を離れず、彼女の仕事も私生活もサポートしている。2人の関係は女優とアシスタントというよりも、まるで親友同士のような親密さを感じさせる。親子ほど年の離れた女同士とは思えない対等な立場でものを言い合い、信頼関係があるのがよく分かる。後にセリフで出てくる「シグリッドとヘレナはある種、同一人物だ」という文句はそのまま、マリアとヴァレンティンのことかもしれないと思う。
マリアの前に立ちはだかるのは20年という月日と、若さへの羨望、そして時間との対峙だ。20年前に演じたシグリッドに固執し、そこから得たもの失ったもの流れ去った時間というものに囚われ、マリアは思うように演技ができない。その様子を、舞台の「本読み」を通じて描いていくのが、この映画の特徴的な部分だ。
映画の中で、ヘレナのセリフをマリアが吐き、ヘレナとマリアが徐々に一体化するのは理解できる。一方、シグリッドのセリフを吐くのがアシスタントのヴァレンティンであるところがユニークだ。ヴァレンティンとシグリッドとを重ねながら、マリアと向き合わせる。実際に舞台に立つ新人女優ではないところがミソ。常に行動を共にするアシスタントだからこそ、直面させられる過去と現実とが如実に浮き彫りになる。これはうまいやり方だった。
マリアとヴァレンティンが、舞台のセリフを発し合うだけのシーンも少なくない。しかしそのセリフの端々に、マリアが浮かんだりヘレナが強く出たり、ヴァレンティンがシグリッドとしてマリアを脅かしたり・・・という2人の女優だけで4人分のパワーバランスを魅せる。これは演じる女優2人の力量に見ごたえを感じる。
本読みとマローヤのヘビを見に行く旅を通じて、マリアは過去と若さと時の流れとを受け入れ、手放し、達観するまでの心の旅をする。
しかし、そんな長い旅も無意味なほど簡単なきっかけでマリアは腹を括る。エンディングで、クロエ・グレース・モレッツ演じる新人女優から平手打ちのような言葉をかけられるのだ。そしてビノシュが見せる、目が覚めたような揺るぎない決断の目が印象的だった。
正直なところ、抽象的な暗喩表現が多くて読み解きが難しい。またモレッツを通じて描くハリウッド業界を揶揄するエピソードは、映画のタッチを崩すだけで余分な贅肉だったように思う。
三層
ジュリエット・ビノシュ主演。
ビノシュが「女優」を演じた『コード・アンノウン』と『マリー もうひとりのマリア』は、有無を言わせぬ神演技でホント凄かったなあと個人的には思う。それらほどの迫力はないものの、本作でも女優を演じるビノシュを堪能。大変楽しかった。
--
中年女優がある舞台にキャスティングされるが、主役は別の若い女優だった、というストーリー。
舞台戯曲の登場人物「ヘレナ」と、それを演じる中年女優「マリア」と、マリアを演じる「ビノシュ」。
この三層構造が、面白い。ヘレナとマリアの境目が溶けていく感じがいい。
そして、文芸からブロックバスターまでオファーが来る女優マリアと、同じく単館系からゴジラまで幅広いビノシュ自身。なにやら重なる部分も多い。
共演の若手女優、『キックアス』クロエ・モレッツと『トワイライト』クリステン・スチュワート。超エンタメ映画で名を売った彼女らが、アサイヤス監督のカンヌ出品作に出る。これも、劇中のアクション映画で鳴らした若手女優が地味な舞台に挑戦という設定と重なる部分がある。
あえて重ねた設定・キャスティングであるが、違う点も。
劇中の中年女優は、若手に主役を奪われてキーッ、くやしい!となる訳だが。
現実のビノシュは、新進気鋭のクロエ、クリステンを従えて、まごうことなき主役を張っている。
現実の中年女はしぶとい。(というか、ビノシュがしぶとい。)
若手に攻めの演技をさせて、それを受けて立つ余裕。
クリステンがもの凄く良かった(素晴らしかった!)が、まだまだビノシュまでの道は遠い。
観終った感想としては、中年の悲哀というよりは、若手頑張れ!というエールの方が個人的には強く残った。
重鎮演出家や先輩女優のエピソードなど、死の匂いが所々漂う映画だったが、死に足をかけた中年女優のしぶとさが漂う映画でもあった。
—
追記1:クロエも良かった。クロエは、ベタな役ドコロをわかりやすく熱演。自分が求められているものを賢く把握出来る女優さんなんだなあと思った。あっぱれ。
追記2:女優だけでなく、雲(風景)も良かった。この映画、主役は雲だろう。
追記3:上記のような事を知人に言ったら、アサイヤスだからビノシュだから日本で公開が決まった訳ではなく、クロエだからクリステンだから公開出来たんでしょと、シビアな反応だった。そうか、世間はBBAに冷たいなあ。
ちりばめられたメタファー
ジュリエット・ビノシュがベテラン女優役という、等身大の役を演じた作品。
ストーリーにたくみに隠されたいくつかのメタファーが、見ごたえと余韻を残す魅力を生み出していた。
映画中の舞台のタイトルの「マローヤの蛇」とは、映画中に出てくるスイスの地、シルス・マリアの自然現象のことらしい。
イタリア側から谷間を這うように流れてくる雲が蛇のように見えることからついた名前だとか。
この現象は天候が崩れる兆候らしいが、「マローヤの蛇」が暗示するものは、忍び寄る不安か、それとも嵐の前兆か。
シルス・マリアという地名と、ビノシュ演じるマリアという女優の名前も無関係ではないだろう。
ちなみに、マリアと個人秘書バレンティンのやり取りを見ている限り、「マローヤの蛇」という舞台は「冷酷で現代的なシグリットに利用され、捨てられる哀れで平凡な中年女性ヘレナの悲劇」という
単純なメロドラマで終わるものではないと感じた。
(そもそも女社長になれる人物が平凡なわけはないと思うが…)
マリア、あるいはヘレナは世間から取り残される不安から心を閉ざしてかたくなになり、バレンティン、あるいはシグリットは狭い関係性に閉塞感を感じはじめ、たびたび相手の目線を外に向けようと忠告する。
マローヤの蛇のように忍び寄った不安や警告を見逃し、結局嵐から逃れられなかったヘレナに対し、マリアは無事遭難せずにすんだのか。
結局答えは明らかにされないまま、映画は終わる。
最後にちょっとだけ登場した若い映画監督の言葉がヒントになるか。
若者の勢いが時代を創っていくものだけれど、年月を経ても変わらぬ雄大なシルス・マリアの地のように、時代を超えてあり続ける存在になることこそ真のスターである条件なのかもしれない、と思った。
世界で活躍する女優の華やかな表舞台と、彼女が時代に取り残されるのを恐れる裏の顔。
世界で活躍する女優の華やかな表舞台と、彼女が時代に取り残されるのを恐れる裏の顔。
ジュリエット・ビノシェが全編ノーメイクて揺れ動く感情を演じれば、クリステン・スチュワートがなだめすかしながら、自身の本心をこの大女優に浴びせて行く。この二人の確執・演技合戦が最大の魅力と言える。
自分を表舞台へと誘ってくれた恩人の死。その人の代表作であり、自分が昔に演じた当たり役。それを相手役の立場に変えて再度演じる。この最大の賭けに臨む事となった大女優。
彼女にとっての当たり役は、あくまでも若い役の方。
その相手役を演じる事は寧ろ本意では無い。しかし時代がそれを許さなくなってしまった事実。
彼女が全てを受け入れるしかなかったのは必然だった。
意を決して本読みを始めるのだが、その相手役をするのは有能な秘書のクリステン・スチュワート。
この大女優にとって今の彼女は、当時の自分を度々投影してしまう存在と言える。
そうなのだこの映画は、当時の当たり役である役こそがクリステン・スチュワートが演じている役所であり。今自分が演じようとしている役所は、その後事故死してしまった女優さんが演じた役所の多重構造で構成されているのである。
若いとゆう最大の武器によって抹殺されてしまう老いて行く事の悲哀。
これを今自分が演じても良いのだろうか?と悩み抜く。
更にこの映画の主題には【若さへの嫉妬】が大きなテーマとして内包されている。
若さを謳歌し、自由に恋愛をするスチュワート。
この戯曲には【若さへの嫉妬】と共に、二人のレズビアン的な要素も作品の台詞の中で説明されており。度々スチュワートの行動を監視するかの様なビノシェの行動には、問題となっている戯曲そのものを反映する多重構造の要素すら、見え隠れしている様にも見受けられる。何しろ彼女が居ないと、この大女優は自分自身のアイデンティティーを維持できないかの様にも描かれているほどなのだ。
彼女は若者の代表としての意見をビノシェにぶつけて来るのだが、この大女優にとって若い意見に屈する事は、それまで培って来た自分を全て否定してしまう事になるのではないか、と考えている様な気がする。
それだけに彼女の助言を素直には受け入れられない、
その昔ハリウッドの大作映画に出演した事を恥じている様なのだが、若いスチュワートにとっては、寧ろその様な題材を演じる事こそ必要なんだ!と激しく対立する。
いよいよ舞台公演が近付いて来るのだが、若き日に自分が演じた役には、今のハリウッドを代表する若さ溢れる女優クロエ・グレース・モレッツ。
彼女の発言や行動そのもの自体が、自分とは真逆な事に不安を募らせてしまい、この若い女優の行動や発言をチェックする。
世界が若い才能を欲している事は、かって自分がのし上がって来た事実からして、身に染みて感じているのが分かる。
それだけに、戯曲自体に自分の存在が薄まる要素がある内容を知るこの大女優は、彼女にある意見を薦める。しかし、この若い女優はその意見にはっきりとした意見を唱える。
それこそが、この戯曲に描かれた若い主人公そのものであり。この大女優は、もう自分の時代が去ってしまったのかも知れない…と悟るのだ。
しかし彼女はまだまだ老いに対して、世間から忘れ去られる不安感に対し、まだまだ闘志を燃やし続けてる。
この戯曲でその昔、自分が演じた役の女優さんは、自分を引き立ててくれる役でもあった。
彼女はその後直ぐに事故死してしまったのだが、この大女優はだから言ってやすやすと第一線から退く意識等無い。
だからこそ戯曲の最後と違い、最後に消え行くのは若い日に自分が演じた役を多重構造により演じていた、クリステン・スチュワートだったのだろう。
今彼女は女優魂を賭けての闘いを続けている。
その為には、それまで助言をくれていたクリステン・スチュワートの薦めに対して馬鹿にしていたハリウッドのSF大作にだって出演する覚悟すら厭わない。
“立場が変われば結果も変わる“のだ!
スイス山岳映画の巨匠アーノルド・ファンクの美しいモノクロ映像と、現在の技術力を駆使したカラー映像を対比させ。美しいアルプスの山々をうねる様に進んで行く神秘的な霧の映像を折り込みながら、女優とゆう立場と秘書としての立場。それぞれの胸の内に去来する揺れ動きを反映させ、作品の内容と同様の多重性を持たせている。
ジュリエット・ビノシェとクリステン・スチュワートの火花が飛び散る。刺激に満ちた2時間を堪能させて貰いました。
(2015年10月28月日/ヒューマントラストシネマ有楽町/シアター1)
中年のおかしみとかなしみ
主人公の女優はキャリアの頂点を極めている。
この人にとっては、若い人たちの間で話題となっているものは関心の外にある。それどころか、同業であるはずの若手女優に関する情報にも疎いときている。
人は、自分の歩んできた道にある程度の満足や誇りを覚えると、自分以外のことへの関心を失っていくものだ。
これは、ある意味の自己防衛であり、自分の歩んできた道を否定する価値観や能力との出会いを避けているとも言える。
自らのキャリアを新しい観点から見つめ直すことになる女優という職業の女性をジュリエット・ビノシュが演じる。スクリーン上の彼女の存在から目を離せなくなるのは、彼女を初めて観た「トリコロール 青の愛」以来である。
年を重ねると言うことは、かつて自分が嫌悪した存在に自分自身が近づいていく側面を持つ。これは不安であり、腹立たしくもあり、悲しくもある。こうした複雑な感情を、ビノシュは大げさには演じずに観客に伝えている。
そして、映画の演出も素晴らしい。冒頭の列車の中で四六時中携帯電話でどこかと連絡を取っているシークエンス。携帯電話という、時空の感覚を極小化してしまう映画の敵のようなアイテムを、ここでは逆手にとって、手短に二人の女性の置かれた状況を提示することに活用している。
「マローヤの蛇」をこの二人が見ることは結局ないことも象徴的である。あの幻想的な、東洋人ならばきっと龍と呼びたくなるような、谷を流れる雲。これを見ることがなかったばかりか、クリステン・スチュワート演じる秘書とそのリメイクされた「マローヤの蛇」公演初日を迎えることもないのだ。
新進女優のクロエ・グレース・モレッツが、ビノシュの演じる役を「観客はどうだっていいと思っている」と冷たく賢そうな表情で言い放つ瞬間は、言われた当人ばかりか観客席も凍り付いてしまう。このこともなげなに口から出た一言によって、ビノシュの腹が決まるところが残酷でユーモラスである。
久しぶりに好いフランス映画を見せてもらった。オリビエ・アサイヤス、わが愛しのマギー・チャンをフランスへ連れ去った罪はそろそろ時効にしてやるとするか。
女優って、めんどくさい
フランス映画祭@関西にて鑑賞。今回は会員800円なので先に見てきました。
終演後にティーチインという解説トークがあり、なるへそーと思うこともありました。
ジュリエットビノシュ演じる高名な女優が、出世作の再演で、昔演じた主演の役に翻弄されて自殺する中年女役をオファーされて、そんなのやりたくねーよとごねまくるが結局やることにして、でもやりたくないから秘書に当たり散らしながら役作りし、秘書に消えられつつもなんとか上演にこぎつける、という話です。
説明がないのでわからないことだらけのままですが、なんとかついていけます。
ギョーカイ人たちもゴシップに興味があって、GoogleつかってYouTubeつかって共演者の噂とか見たりするんですなぁと、ゲーノー界の舞台裏を垣間見られるところは面白かったです。
ジュリエットビノシュ演じるマリアが、めんどくさい人で、秘書に同情です。
個人秘書との演技論、映画論、女優論も興味深い感じがしましたが、字幕だけでは噛み砕けず残念でした。
個人秘書をクリステンスチュワートが、共演する若い女優をクロエグレースモレッツが演じています。豪華共演です。
フランス映画ですがほぼ英語です。
なんか難しい哲学的な比喩が含まれた脚本らしいです(ティーチインで聞く限り)が、あまりわからなかったです。
なぜか第2部とエピローグだけ表示がありました。第1部とプロローグはないんかいと思いました。
全国公開は2015年の秋だそうです。
スイスの風景も美しいです。
蛇の雲も迫力ありです。
全6件を表示