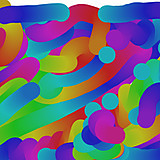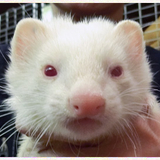バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)のレビュー・感想・評価
全430件中、321~340件目を表示
痺れ上がる
みんな バードマン
過去の名声にとらわれ 舞台で成功を再び夢見る「バードマン」
しかし 色んなトラブルに巻き込まれ・・・
人間 誰でもバードマンだ あの時は良かった 何であの時みたいにならない 主人公の彼のように名声ではなくとも あーだ こーだと 過去にとらわれ 今を考えない
主人公の彼を観ていて 何だか苦しかった
とても彼が幸せには見えなかった とにかく昔の栄光が
欲しくて 必死にあがく 彼の姿が描かれている
しかし 主人公が 昔の作品「バットマン」のマイケル・キートン
とは 驚いた。確かに彼だが やはり歳もとり 顔も心なしか
丸くなったような(笑)
この作品は若者よりも年配者の方が より 面白く
観ることができるのではないだろうか
私は年配者なので そう感じたが
しかし あの長回しの カメラワークには恐れ入りました
そして あのラスト?わからない・・・
いったい 彼はどうなったのか?
「真の成功とは、何か?」を問いかけます。
先週04/10に公開した当該作品を遅くなりましたが、やっとで観てきました。
当該作品は、ご存知の通り、2014年映画界の最高峰である米国アカデミー賞で
最優秀作品賞を受賞した作品です。
しかしながら、公開直後の先週末・映画ランキングでは、なんと6位と低調です。
私の率直な感想は、
「この作品が、American Sniperを負かしてNo.1になった事に驚き!」
「ハリウッドの人々に受ける様に作っただけ」
「真摯で誠実に創り上げたクリント・イーストウッドが可哀想。。。」
でした。
お薦め出来ません。。。
無理やりポジティブに評論すると、次の通りです。
「過去の栄光」とか「過去の成功体験」という表現がある様に、
新たな進歩・成長の最大の妨げとなる事があります。
その典型が、「ソニー」の繁栄と衰退です。
過去の成功は、運や環境ではなく、自分の実力だったと人間は信じたいからです。
真に認められ・褒めらたんだと信じたいからです。
自分が一番かわいいから。
周りの人や家族を犠牲にしていたなんて考えもしていないから。
「真の成功とは、何か?」
当該作品は、これを、聴衆に問いかけています。
「無知がもたらす予期せぬ奇跡」の意味が、ここに隠れています。。。
Michi
評価は高いが。
関係者
「よくわからなかった」という方へ、中年のおっさんとして補助線を引いてみました。
レビュー欄では賛否両論が盛り上がっていますが、僕なりに補助線を引いてみたいと思います。(ちょっとネタバレ含みます。)
人には誰しも多少なりとも「理想像」というのを持っていて、若いうちはそれを「目標」にして追いかけることができますよね。でも、人生の折り返し点を過ぎた中年になると、その「理想像」はいつの間にか「べき論」に変身して、自分を追っかけてくるのです。
親としてどうあるべきだったか。夫や妻としてどうあるべきだったか。仕事キャリアはどうあるべきだったか。それらをひっくるめて自己実現はどうあるべきだったか。
理想像を実現してなきゃいけない年齢になったとき、「まだ届いてない」とか「もう手放してしまった」とかの現実があるわけです。そのギャップと折り合いをつけて、それでも生きていくのが大人になるってことなんだなぁと最近思うようになったんですけど、それが「諦め」のように思えて辛くなることもありますよね。かと言って、なんとか自分を奮い立たせてあがいたとしても、ハタから見たらパンツ一丁で大通りを駆け回るような滑稽な姿を晒すようで恥ずかしい。
映画の中で可視化されるバードマンを「置き去りにした理想像」とか「主人公のホンネ」として考えるとちょっと無理がありますけど、「やっぱり前の会社辞めるべきじゃなかったのか?」とか「やっぱり元カレ(元カノ)とヨリを戻したほうが幸せになれたんじゃないか?」とかいう「迷いが実体化したもの」として捉えるとしっくり来るような気がします。
その迷いを断ち切るのではなくて、“自分の一部”として受入れて、取り込む。観客は一瞬、主人公がバードマンに戻ってしまったのかと思わされるんですけど、主人公は最後にその仮面をちゃんと脱ぐんですね。
そして、ラストシーン。これを「シニカルなバッドエンド」として笑い飛ばすこともできるし、「ファンタジックなハッピーエンド」として感動することもできる、ハイブリッドなエンディングだったと思います。
(決して悪い意味ではなく)消化試合を戦ってる人は前者を採ればいいし、
(無謀と言われても)敗者復活戦に挑む人は後者を採って励みにすればいいのです(僕のように)。
副題に(無知がもたらす予期せぬ奇跡)とありますが、これまた年を取ると世の中の色々が見えてきて、いまさら「無知」になるのは難しい。でも「無知なフリしてエイヤっと飛んだら、今まで知らなかった奇跡が起きるかもよ。」というメッセージだと考えると、ややハッピーエンド寄りで解釈してもいいじゃないかなと思ったりもします。
生きる可笑しみ、生きる悲哀
上映が始まって、最初の3分、もう映画に引き込まれた。
キャメラは最初から長廻しを続けている。
5分経った。
「えっ、まだ廻してるよ!?」
10分経った。
「マジで!!」
「これ、どうやって撮ってるの?」
むしろ、この延々と続く長廻しの「妙」もあって、ストーリーそっちのけで、いったいいつまで、この長廻しの限界に挑戦し続けるのか? そちらに注意がいってしまうのである。
20分経ってもまだ続く長廻しに、ようやくこちらも「驚き」から解放され、物語の中に入っていけるようになった。
「こうなりゃ、映画の最後までやっちゃってくれ!!」というのが僕の本音だった。
主人公は、かつて「バードマン」という映画で、スーパーヒーローを演じた舞台俳優マイケル・キートンである。
彼にはこだわりがある。
舞台が好きなのだ。
舞台作品の持つ芸術性、ライブの緊張感、それらを観客に伝えたい。
はっきりいって、映画で着ぐるみを着て、スーパーヒーローを演じたのは、金のため、生活のため、自分の地位を確保するための、まあ、いわば「方便」にしか過ぎない、と自分自身では思っている。
しかし、演劇に情熱を注げば注ぐほど、彼の熱意は空回り。おまけにプロデューサーや、役者仲間たちと衝突を繰り返す。
なにより、彼にとって一番「ムカつく」のは、したり顔で、舞台芸術のレビューを新聞に書く「演劇評論家」たちだ。
あいつらに言わせると、自分はもう過去の栄光にすがっているだけの、落ちぶれた俳優のカテゴリーに入るらしい。
そんな厳しい批評ばかりが彼の耳に入ってくる。
彼はイライラする。
かつて結婚もし、一人娘もいるが、奥さんとは別れてしまった。年頃の娘は、そんな父親をハスに構えてみている。彼女はマリファナなんかを吸ったりして、ちょっとヤサグレている。
マイケルは、もうじき次の舞台公演がある。今はそのリハーサル中だ。
演目はレイモンド・カーバーの「愛について語るときに我々の語る事」
この作品はマイケル自身が脚色、演出し、登場人物を演じている。
この作品の解釈をめぐって、新しくメンバーに入った役者と彼は対立する。
この作品はどう演じるべきなのか? 彼は悩みだす。本当にこれで正解と言えるのか? 自分にもわからなくなってくる。
そんなとき、彼には、ある声が聞こえてくるのだ。それはかつて自分が演じた、もう一人の自分。そう、「バードマン」の声だ。
「ダメなら、またバードマン・スーツを着て、羽ばたいて見せればいいのさ」
「映画の客はアホなアクションが大好きだぞ」
「ミサイルを撃ち落とせ! ヘリコプターをぶちのめせ!」
「お前はバードマンだ! さあ、飛んで見せろ!」
彼はこの、もう一人の自分の声に頭を抱え、悶え苦しむのである……。
本作は冒頭触れたように、長廻しのショットが印象的だ。まさに、上質の演劇を鑑賞しているかのようである。
俳優たちの動きに連動して、キャメラは動くが、決して「手ブレ」をしない。ここら辺りが、監督のうまいところなのだ。
今時の風潮だが、アホな監督は、すぐブレブレの「手持ちカメラ」とか、中途半端なワンシーン・ワンカットの長廻しを使う。なぜ、それを使う必然性があるのか? と観客の一人である僕はいつも疑問に思う。
僕は専門家ではないが、おそらく本作での撮影機材は、ただの「ハンディ・キャメラ」ではなく「ステディカム」を使っているはずだ。
「ステディカム」はキャメラマンの体に固定され、手持ちカメラのように自由自在に動ける。しかし、その安定した機構によって、手ブレが起きないように制御されている。
また、本作でバックに流れている音楽。特にジャズ・ドラムの演奏がいい。スクリーンに映る映像に、絶妙の緊張感とライブ感を与えていて「次は何が起きるんだ?」と観客を映画に引き込ませてしまう。
本作の主人公は、紛れもなく舞台を愛している人だ。
自分が輝ける場所はいったいどこなのか? 自分は何者なのか?
難しい言葉で言えば「アイデンティティ」というやつである。
彼はそれを必死で掴もうとしている。まさに雲をつかむように、彼は必死に自分を探している。その必死さが、第三者である僕たち観客から見れば、「ユーモラス」に、そしてある種「滑稽」にさえ見えてしまうのである。
ところで僕は落語という芸術が好きだ。
かつて桂枝雀師匠は「笑い」とは「緊張と緩和」が生み出すものだ、と言った。また、立川談志師匠は「落語とは人間の”業”の肯定である」と言った。まさに名言だ。
本作「バードマン」には、この二つの名言がピッタリ当てはまるのである。
本作の主人公マイケルは、演劇、舞台という「ナマモノ」そういう緊張感の中で日々を暮らす。そして「緊張」が極限に達すると、それを「緩和」するために、時折、暴走したり、感情を爆発させたりする。
その生き様がなぜか、第三者である僕たち観客には、生きている事自体の「可笑しみ」と「悲哀」を感じさせる。
彼は、どんなにもがこうとも、演劇の呪縛から逃れられない。また、それは自分が望んだことでもある。まさに”業”としか言いようのないものを背負ってしまった人物だ。
どんなジャンルでもそうだが「芸術」に真摯に取り組もうとする人たちは、なにか”業”と言えるものを背負わざるを得ないのである。
その覚悟がなければ、「芸術」をやる資格はないと僕は思う。
ジェットコースターのような作品
濃密な映像の連続にとにかく圧倒され、2時間が永遠のように長く感じられたが、画面に引き込まれているうちに気が付けば映画は終わっており、まるでジェットコースターにでも乗っているかのような気分だった。登場人物がそれぞれ心の葛藤を抱えエゴをむき出しにする有様に、観ていて人間関係のストレスを感じて自分は胃が痛くなりっぱなしだった。落ち目の映画俳優リーガンが孤軍奮闘するさまは、暗中模索で先行きが見えず何が正しい道なのか分からない中でも、とにかく己の信じる道を歩んでいかねばならないのだというリアルでシビアな人生像を我々に示しているように感じた。
理屈で考えるよりは感覚で楽しむ映画なのではないかと思う。意味がわからないといえばわからないし、映画の既成概念をブチ壊して、観客を驚かせたり困惑させたいというような作り手の意図があるように感じた。若干ハリウッドのパロディ的というか内輪的な雰囲気があるので、その点が受け付けない人もいるかも知れない。でも総合的に言えば、本当にレベルの高い映画だったなとつくづく思う。
文句無しに面白い!!!
脚本の妙(人はみな、ビギナーズ)
長回しがー、俳優の演技がー、音楽がー、ハリウッド&観客への批評性がーなどは、もうすでに皆さんお書きになっているので、その他感じたことを書きたいと思います。
以下、ネタバレ含みます。未見の方は、ご注意を。
落ち目の俳優が、レイモンド・カーヴァーの『ビギナーズ(通称:愛について語るときに我々の語ること)』を舞台化する、というのがこの映画のストーリー。
単に劇中劇というだけではなく、この映画全体が『ビギナーズ』そのものだったんだなと思う。『ビギナーズ』の、自殺をしくじり3日後に死ぬ男、妊娠をあきらめる女など、様々なエピソードが、映画の地のストーリーに反映されている。
その男は、狂人にしか見えないけれども、本物の愛があった、それが『ビギナーズ』の筋書き。と同時に、愛について語れば語るほど、何かがすり抜けていき、何が本物か分からなくなる、揺らぎも描いている。
揺らいで傷ついているけれども、この世に「本物」があると信じたい…そんな希望と絶望の物語。
「我々は愛についていったい何を知っているだろうか。僕らはみんな初心者みたいだ。
僕らはみんな恥じ入ってしかるべきなんだ。こういう風に我々が愛について語っているときに、自分が何を語っているか承知しているというような、偉そうな顔をして我々が語っていることについてね。」
そんな、一文が『ビギナーズ』にはあるけれども。
バードマンは、「愛」を「映画」に置き換えたものなんだろうなあと思う。
--
バードマンの主人公は常に自問自答する。俺は本物の俳優なのかと。
娯楽映画に出てるときは、ただの人気稼ぎじゃないかと悩み、
アート系舞台の時は、こんなの単たる自己満足じゃないかと悩む。
何が本物かなんて、誰にも分からない。
人気や成功や、批評家やTwitterからの注目は、一時の狂騒と安心を与えてくれるかもしれないが、揺らぎの根本は変えられない。
俳優として親として生きることにおいて、ビギナーズで、揺らぎ続ける愚かな存在だけれども。
それでも彼は本物の俳優で父親だったよ。そう信じる、本作ラストの娘の表情が清々しい。
—
淡々と怖くて悲しくて愛おしい『ビギナーズ』を、力強い喜劇に書き換えた脚本・構成の妙が光る映画だったなあと思う。
よかった
マイケル・キートンの超能力が一体なんだったのか、意味が分からないけど、でも面白い。超能力ができても実生活では何の役にも立たない。
『ファイトクラブ』でヘナチョコだったエドワード・ノートンが偉そうにしていて、しかしそんな彼もインポだったりと人生の悲哀をにじませていてた。
予告ではブリーフ一丁でブロードウェイを歩き回る場面でかっこいいソウルミュージックが流れていたけど、どこにもその音楽が使われておらず残念だった。
劇中劇が面白そうだった。初日で主演が大怪我してその後の公演は払い戻しなのではないだろうか。お金が無さそうだったけど大丈夫なのだろうか。伝説的な話題になったから、その後は安泰なのだろうか。
頭を狙って実弾を発射して血が出ていたのに鼻の怪我で済むのは、超能力のお陰なのだろうか。
いろいろ気になった。
ほぼマイケル・キートンの目線の範囲を描いていて、エマ・ストーンとエドワード・ノートンの屋上の場面だけマイケル・キートンがいなかったように思う。
昨日見た『シェフ』もネット炎上がテーマの一つだったが、この映画でも炎上していた。ハリウッド俳優は動画の再生回数に過敏なようであった。落ちても上がっても、どっちにしてもみんな発狂気味でテンション高かった。元気でよかった。悲惨な事やままならない事もいろいろあるけど元気を出して頑張ろう!という気持ちになった。
ユナイテッドの一番スクリーンで見れて大満足。名画座での併映なら『その男、ヴァンダム』がいいな。
再起をかけてあがいた先は
期待しすぎた
遅ればせながら観に行ったのだが、、
演出に凝り過ぎた映画。
ゴダールの映画のように点滅するアルファベットの羅列で始まります。
この映画は一言で言えば、演技に取り憑かれた一人の男についてのひとつの考察、ということになります。始まってから、20分ほどで、ああ、この手の映画なのだな、ということが判ります。現実の世界の映像と心象風景の映像とが境い目なく続いてゆくのですが、(この境界線を如何にぼかすか、ということが、この手の映画の生命線なのです)如何せん、演出に凝り過ぎています。騒々しい映像がこれでもか、これでもか、とばかりに次から次に迫ってきて、視神経を刺激します。そう、確かに視覚に訴える場面はあるのですが、全てを観終わった後、心の残るものが余り、ないのもまた事実です。結末もやっぱり、こういう終わらせ方しかなかったのだな、という大体、予想がつくものです。☆が三つなのはそういう事情があったからです。映像をぎゅうぎゅう詰めにするのではなく、観客の想像力を働かせる余白を残しておいて欲しかったですね。この映画をこけおどしだけの空疎な作品だ、と酷評する人がいても何の不思議もありません。この監督は映画に新機軸を打ち出そうとしたのでしょうが、今の時代、映画に限らず芸術の大体の分野において、あらゆることはもう、やり尽くした、という閉塞感が強くなっています。音楽、美術、文学、みんなそうです。この映画の演出によって、イニャリトゥ監督にアカデミー監督賞が贈られたのは納得できますが、果たしてこの作品がアカデミー作品賞に値するのか否か・・・、うーん、私には疑問です。
皮肉なことですが、この映画を観終わった後、私は黒澤明の時代劇やジョン・フォードの西部劇を観たくなりました。2000年くらい前にユダヤ人が書き綴った聖書が未だに世界中で読まれています。どうやら、残念なことではありますが、小手先だけの思いつきでは新しい地平を切り開くことはできないようなのです。
全430件中、321~340件目を表示