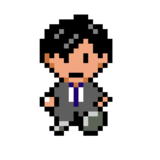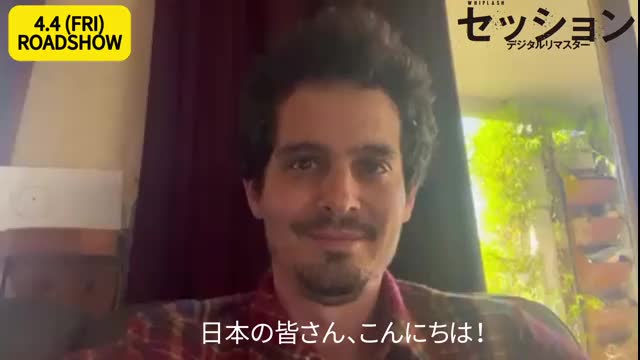セッションのレビュー・感想・評価
全191件中、1~20件目を表示
原題だと「フォックスキャッチャー」と間違えるから「セッション」にしたのだろうか
いや、すまん。
期待した人はいないだろうが、さすがにあっち方面のネタに飽きてきた。というか。
「セッション」
ギターソロより、ドラムソロに憧れた青年。
とはオレのことだが、女にもてたいくせに、ドラムを選ぶという、しょぼいガキだったオレは、さんざんストイックに、「叩け、叩け、叩け」のモノを聞いてきた、観てきただけあって、演奏シーンに特に深い思いはない。ドラムソロはストイックな絵になり易いし。
そう、観るべきは、下の尊敬するレビュアーさんにあるように、ハゲとガキのエゴとエゴの「鞭の打ち合い」。
ハゲはチームのことなんざ、考えちゃいねえ。「オレの音」「オレのリズム」そこからの唯一無比のミュージシャンを生むことしかない。
チャーリー・パーカー出さずとも、世に言うトップ・ミュージシャンは少なからずそのように生まれたことも多かろう。
だが、その思いすら本当かどうか分からない。教え子が自殺した、という知らせに涙するする姿も、「オレの音を忠実に再現できるやつが死んだ」と悲しんだだけかもしれない。
でも音楽ファンからすると、その悲しみ方って実は間違いではないんだよね。
だから、このハゲのやっていることは、それでも「分からなくはないエゴ」なのだ。
ガキのほうは青いだけに、プライベートのバランスが取れなくなるが、つまるは、「悔しい」と「オレはトップになる」の「若さゆえの正しいエゴ」でそれに反発する。
また途中のキレ芸があったのが、大きいよね。あれもまたある意味「『正しい』もう一方の青臭いエゴ」。楽譜の件は言うに及ばず。
追記
ハゲがクライマックス、コロッと表情を変えるのだが、それも虚か実か、結局分からない。
分からないからこそ、キュン、とくるのである。
追記2
うおっ、こう書くとまたあっち方面になるじゃないか。今年はこの路線でレビューするのか。
ラストはなぜ「キャラバン」なのか?
いまさらネタバレでもないのですが、ラストの演奏シーンに絞って書いたので、ネタバレ投稿とします。
冒頭のシーン。主人公の部屋にジャズドラマーのレジェンド、バディリッチのポスターが貼ってあったので、ラストシーンでキャラバンの演奏が始まった時は、あのドラムのイントロから、これからバディリッチやるんだー!となってむちゃくちゃ興奮しました。
バディリッチといえばキャラバンのソロというくらいの代表的なパフォーマンスなので。
ジャズ演奏の知識としては、ジャズのドラムソロは、演奏する曲のテーマ(メロディ)にそって、テーマの小節数✖️何回、というのがルールなので、だからバックバンドも最後のジャーンとか合わせるとこもドンピシャでまとまるというカラクリがあります。
普通のジャズライブでもバックバンドの人も涼しい顔して真剣に拍数を数えてます😛
余談ですが、映画ではそこをごまかすためにスローモーションにしたりしてましたが、わかるーとなりました。(バディリッチのガチコピーは流石にムリだし、映画的にはあの描写のほうがいいと思ったので悪い意味ではありません)
バディリッチのキャラバンだからこそ、あの人数のメンバーがリハーサルなしでバッチリ最高の演奏ができてしまう、というのも映画的に説得力があるんですよね。
ちなみに主人公がコピーしたバディリッチのソロもよく聞くとドラムのタムの音の高低でテーマ(メロディ)を再現しており、上記カラクリを知って聴くとより楽しめます。
狂気と狂気のぶつかり合い
己の欲求と憎悪を燃料にして生きる狂気の指揮者と狂気のドラマーの物語。
彼らが音楽が好きなのはわかる。しかし、その「好き」が「純粋な好き」ではないと感じられるところが、この映画の捻くれたところであり、傑作と言われる所以だろう。
フレッチャーは、世界的な名プレイヤーを育てた教育者になりたい、完璧なテンポと音階のセッションを披露したいという強烈な欲望のために、常軌を逸したパワハラ指導を行う。相手の面前で大声で罵倒し、椅子を投げ、ドラムを蹴り飛ばす。
20代の1年間、同じような言動をするパワハラ上司に仕えたことを思い出し不快感が湧き上がる・・・。
ニーマンは、名プレイヤーになって周りから認められたい、自分の地位を確立したい。そのために邪魔になるもの(寝る時間や恋人)は捨てる。血を流してでもドラムを叩く・・・。
最後のセッションでのフレッチャーの陰湿な仕打ちに一度は折れそうになったニーマンが、踵を返して舞台に戻り、指揮者であるフレッチャーを差し置いてソロ演奏を続け、圧巻のプレイでバンドをリードする。
そしてその熱量の中で最後の刹那、2人が「純粋な好き」を見せる。このシーンがあってこその作品だと思った。
いい映画だと思うのですが・・・。自分の過去の経験が思い起こされてあまりいい印象が持てなかったのが残念。
狂気
鬼才デイミアン・チャゼル監督が描く『セッション』は、音楽教育という枠を超えて、狂気すら帯びた師弟関係と「一流とは何か」という問いを突き付ける作品だ。音大教授フレッチャーの指導は、常軌を逸している。人格否定や家族の侮辱、さらにはイスが飛ぶほどの暴力的な言動――現代社会では到底許容されないであろうそのやり方に、観ている側も身構えずにはいられない。
一方で、そんなフレッチャーに認められたい一心で、血反吐を吐くまでドラムに打ち込むニーマンの姿は、執念を超え、もはや狂気に近い。交通事故で全身血だらけになってもステージに立とうとする場面は、人間の限界を超えた執念と自己破壊の表象であり、観る者に畏怖の感情すら抱かせる。
この作品の恐ろしさは、フレッチャーのやり方が「完全に間違い」とも言い切れない点にある。平凡な指導では突出した才能は生まれにくい――その信念には一理あり、私たちもまた「限界を超えるためには何が必要か」という不穏な問いを突き付けられる。『セッション』は、努力・狂気・信念が渾然一体となった、人間の極限を描いた衝撃のドラマである。
動悸が止まらない
個人的にはシビル・ウォーに並ぶかそれ以上か。
見終わった後、今もしばらく続く、何かに追われるような焦燥感、ぐったりした疲労はどうだ。
ポシェットを胸前でギュッと抱えながら、イーッと引きつった顔でスクリーンを見続けていた。
初めてだった阿佐ヶ谷のミニシアターで鑑賞。背もたれが小さい、音の迫力がいまいちと、予告編のときに湧いた小さな不満は、あっという間にどこかに消えた。そんなことも感じたと、今やっと思い出した。
血だらけで舞台に立つまで追い詰められた狂気、そんなこと経験ないから分からんが、この作品上は分かる。そこまで矛盾のない展開。
再起の舞台に上げて密告の復讐を遂げる狂気、クソだクソだクソだ。ああ、自分は絶望した息子を抱きしめてやれる父親にならないと…と本気で思った。そこから始まる9分19秒(とプロモーションに書いてあった時間はこのことなのだろう)。
このメンタル、なに!?
でも一度は狂気のレッスンをやり遂げ、血だらけで登壇した男なのだから、こうするのは当然だった。これを引き出すためのフレッチャーのプレッシャーだったか?いや、クソだ、狂ってる。
パワハラはいかん。見てて、部下の顔が何人か思い浮かんだ。いいところを見ないと。見えてる才能にクローズアップしないと。部下は自分の手駒じゃない。この映画を思い出そう。いいものを見た。
もう一回みたい。ニコルはかわいかった。昔の彼女の前でカッコつけたくなる幼稚さ。わかる。ずっこけフラレたのが最後の狂気へのアクセント。この演出もすごい。
もう二、三回は見たい。
ラストで感動。
パワハラ教師と性格に問題のある若いドラマーの話だが、リアリティーが凄かった。出演者は皆音楽の専門家に見えた。ドラムのこんなに長いソロを聴く機会は滅多にないが、(誰が叩いているにせよ)感動した。この邦題は素晴らしいと思う。作品を見た後で知ったが、この監督は製作当時20代とのこと、びっくりした。
実力でねじ伏せる!
アンドリュー vs フレッチャー なのだろうと理解した。
フレッチャーのパワハラし放題の育成方法はどうかしていると思うが、
彼なりに最大限に演奏者の能力を引き上げようとするアプローチが、
罵詈雑言を浴びせまくり&物を投げまくる ということ。
そして執拗なイビリ。
まともな人だったら、絶対関わりたくない、こんなやつ。
だが、
アンドリューは、偉大なドラマーになりたいというビジョンがあるから
絶対に負けないという不屈の精神、もはや闘魂と言っても過言でないほどの
ドラムへの執着で、家族にもあたりちらし、恋人も捨て(追ってアンドリューが捨てられるのが笑える)、
運転している車がトラックと衝突しても、演奏の舞台に立つほどだ。
他、いろいろなキャラクターが出てくるものの、基本はこの二人の構図。
そして、ラストで
まずはフレッチャーの恨み節&陰湿な嫌がらせリベンジ。
これは高潔な音楽家ではもはやない。私はここでフレッチャーの底を見た気がする。
実に残念だった。今までのパワハラの極みここにありだが、目的が復讐になっているので
この時点でフレッチャーは音楽家ではなくなったと思う。
この嫌がらせに、アンドリューが実力でねじ伏せる終わり方は実に素晴らしかった。
ねじ伏せるというか、フレッチャーに音楽の楽しさを思い出させるようなドラムソロであり、
ここからまたセッションが始まっていくという、秀逸なエンディング。
感服した。
実に観ていて疲れる作品ではあるが、このラストを観ることができて、とても満足。
10年前の公開当時に観たかったが、あらためて4Kで劇場で観ることができてうれしかった。
新しいチャーリー・パーカーはこの世界に誕生するか
スゴく面白い映画だった。
猛烈なパワハラによるスラングが300回くらい出てくる酷いお話しなんだけれど、物語に引き込まれて目が離せません。
主人公に感情移入し過ぎてしまって、一心不乱に練習する主人公のスティックの動きに合わせ、どうしても身体が小刻みに動いてしまった。夜遅くの上映なので観客が少なくて、両脇に誰も居なかったから良かったけれど。
エンディングまで、色々と衝撃の場面が多く、ホッとさせておいて、何度もほとんど暴力のパワハラが容赦なく襲って来るから、油断がならない。
とっても怖い映画なんだけれど、終わって直ぐにまた観たくなる感覚になるから不思議です。
ラスト、主人公は救われたのだろうか。
新しいチャーリー・パーカーはこの世界に誕生するのだろうか。
謎は尽きないと思いました。
狂気VS狂気
序盤から狂気による緊張感が凄いんです。
って、言うとホラー映画みたいですが。
ある意味で、ホラー映画より怖くて緊張感が有るかも。
何故なら、狂気と狂気がぶつかり合うから。
そして、それはクライマックスの演奏シーンまで続くんです。
最後の最後だけ、狂気と狂気が融合した様には見えるけど。
狂気の中からしか誕生しない物って有ると思うの。芸術の分野は特に。
だからと言って、それを全面的には肯定できないんですけどね。
それでですね、今回の上映ありがたい事にパンフレットを売っていたんです。
パンフレットを読んだら、監督自身がドラマーの経験が有って、恐怖を感じる様な厳しい環境で音楽をやっていたみたいなんですね。
なので、この作品は当然その経験がもとになっているのでしょうが、これ以外の作品にも根底にこのような狂気が流れているのかもしれません。
そうやって考えると、今『ラ・ラ・ランド』を観たら、印象が変わりそうな気がします。
叩け、叩け、叩け! 血が騒ぐ!
4月9日(水)
またしても、極私的公開時見逃して再公開劇場初見シリーズ?「セッション 4Kデジタルリマスター版」をTOHOシネマズ日比谷の4KDolby-Atmosで。
いつも言ってる事だけど、映画は映画館で観るのを基本としているので、殆ど配信では観ない。円盤持っているのも基本は映画館で観た作品である。
と言う訳で、もはや伝説にもなっているJKシモンズの鬼教師フレッチャーの怪演をやっと映画館で観る事が出来た。
今なら絶対ハラスメントで駄目なやり方でフレッチャー(J・K・シモンズ)は罵詈雑言を浴びせ、追い込んで行く。
本作を観た日に、趣味でオーケストラやっている娘が家に帰って来たので聞いてみた(彼女は公開時にセッションを観ている)。
「101小節目頭から、なんてあんな風に練習するの?」「コンサート前の練習なんてあんなもんだよ。先生も必死で(フレッチャーと)変わらないよ」
へぇ〜そうなんだ。趣味でやっててもそうなら、プロを目指すプレイヤーは必死だろう。
フレッチャーは色々な手を使ってニーマン(マイルズ・テラー)にプレッシャーをかける。ニーマンの友人のドラマーを主奏者に呼んでライバル心をあおったりもする。
あの指導の仕方で天才や伝説のプレイヤーが生まれるとは思わないけれど、ニーマンはフレッチャーに必死に食らいついて行く。しかし、演奏会への途上のアクシデントでスティックを忘れて取りに戻り事故る。それでも血だらけでプレイするがアウト、ニーマンはドラムを辞めるのだが…。
ラストの約9分にわたるプレイは圧巻だった。そこに至るまでの二人の駆け引き、教師の座を追われたフレッチャーの怒りの報復、復帰したニーマンの意地、全てが混ざりあった"セッション"の中でニーマンは叩く。
叩け、叩け、叩け!プレイ中に緩んだシンバルを締めなおして継続させるフレッチャー。
ニーマンは叩き抜く。
不満は、恋人ニコルの扱い(よりを戻そうするのを含めて)と復帰する時に仕舞ってあったドラムセットを引っ張り出すだけで練習するシーンが無かった事。
助演男優賞、録音賞、編集賞(音楽(音)とシンクロする編集が見事)3部門のアカデミー賞受賞も納得だった。
見終わった時に心地よい映画ではないが、凄い映画だった。
「WHIPLASH」と並ぶ演目が「キャラバン」だった。知っている曲で良かった。
まぁ、私が聞いていたのはベンチャーズだけどね。
おまけ
ニコルがバイトしている映画館へ父親と映画を観に行って知り合うが、上映しているのがジュールス・ダッシンの「男の争い」。ここは名画座か?
Not my fxxxin’ tempo!!
何度か観ている作品ですが、スクリーンで観たことがなかった事と4K&Dolby atmosで再上映ということで鑑賞しました。
スパイシーなフレッチャーの指導がニーマンを追い詰め、彼の焦りと苛立ちがヒシヒシと伝わる前半。フレッチャーも丸くなったか…と思わせてそんなことある訳なかった後半。教え子だった時はもちろんフレッチャーのペースだったのが、最後はニーマンがフレッチャーを飲み込んでいく…!
何よりも好きなシーンはラストでドラムソロを叩く息子を隙間から見つめる父。あの表情が本当に堪らんのです。
自分にとっては実にリズムもテンポも良い作品です。
再上映に感謝🙌✨
ありがとう再上映
今回初めて鑑賞。DOLBY ATMOSで音よろし。
ジャズはフリーに楽しむものという印象があったが、
このような軍隊みたいな世界もあるのかと恐れ慄く。
フレッチャーは終始鬼だが、最後の最後にアンドリューと音で魂通わせるシーンは言葉では表せないほど最高だった。
アンドリュー、おとなしそうで対人関係も苦手、フレッチャーに何度も痛めつけられるのに最後これでもかと実力見せつけてくれた。最高のカタルシス!
作品を観ている間、ずっと心がたかぶっていたが
ラストは音楽の力で感情を最高の最高レベルまで高め上げてくれた。
エンドロール後、あーっと叫びたくなるほど余韻が素晴らしい映画だった。
Jack the JAM
ずっと気になっていた作品を、リバイバルにて。
オープニングからもう音が格好いい。
そして初登場時からハッキリと分かるパワハラモラハラ教師フレッチャーのヤバさ。笑
彼が本当に曲者で、最後まで一筋縄ではいかない。
ショーンの死に涙を流しながらも死因を偽り、丸くなったかと思えば強かに復讐を仕掛ける。
対するニーマンは、最初はナヨナヨした雰囲気。
しかしフレッチャーの熱気と狂気にあてられてどんどんと“そちら側”へ踏み込んでゆく。
中盤以降、特に演奏中は輪郭すらシャープに見えるほど。
普通なら終盤にフレッチャーの真意が明かされて感動的な共闘関係になりそうなものだ。
いや、実際言葉に偽りはないだろうし共闘もする。
しかしそれは殴り合いながらの共闘だ。
「本当は良い人でした」なんて優しい真相は用意されておらず、それでも音楽やプレイヤーへの愛は本物。
最後のセッションで否応なく熱くなるあの姿から、それは疑いようもない。
彼におもねることなく挑みかかるニーマンも、もう同じ所まで行ってしまったのだろう。
睨み合いながらも楽しそうな2人が印象的。
口元の演技が魅力的だったニコルをあの扱いにするのは勿体ないが、本作には必要な措置だった。
その分、本番直前に復縁を狙おうとしたのは余計かも。
半年以上のブランクから最後の演奏の説得力を出すには、「実は練習続けてました」くらいは欲しかった。
あの後の2人の関係を描かないのは賛否が割れそう。
個人的にはフレッチャーの年齢になったニーマンの様子とかで何かしら臭わせて締めてほしかったかな。
とはいえ、ジャズにはまったく詳しくない自分が前のめりになるくらいには、素晴らしい作品でした。
天才アーティストの心理
評価が高いので、その理由が知りたくて観ました。
完璧を求める指揮者ってこんな人なんだなー。ドラムのタイミングで速いか遅いかが素人には全くわからない。しかし、作品として完成をイメージしてる人には、僅かな違いが許せないんだろう。
変人、奇人と言われる所以はこんな部分に表れるんだろうな。
ラストシーンまでモヤモヤ感が抜けず、こんな大舞台でも引きずり落とそうとする変人に付き合ってられるかー。はめやがってー。って主人公の気持ちになって観てました。しかし、与えられる側だと、相手の思うつぼになることを逆手に取って、主導権を握る辺りからの大逆転劇。
ドラム主導で、周りはプロの演奏家。観客のために合わせざるをえず、痛快な10分間。きっと、指揮者もこの大どんでん返しに驚きながらも、こんなやり方で仕返してくる主人公に嬉しさが出てきたんだろう。
しかし、この指揮者の怪演を演じることのできる演技力は圧巻。名作と言われるのが分かりますね。
殺意を熱に、熱を音に。 ぶつけ合い奏でろ
人と人がでっかい思いをぶつけ合うと、それがどんな思いであれお互いを動かすし変える。
その思いは愛や信頼みたいな綺麗なものじゃなくてもいい。
嫉妬や憎しみ、怒りや殺意なんでもいい。とにかく大きく相手にぶつける。すると動く。もちろんどうやって動くかは予想できない。事故や自殺のような身を滅ぼす方へ相手が動く場合もあるし、別れや孤立させてしまうこともある。一方で、絶対に自然的には起こり得ない何かを生み出す場合もある。主人公の最後の演奏はまさにそれだった。
セッションとは、人と人が思いをぶつけ合った時に起こる現象のことなのだと思った。
僕は至極当たり前の事を言っているつもりなのだが
もしサッカー映画で、スパルタ顧問の先生が、天才プレーヤー(キーパー)を生む為にスパルタ指導で才能ある主人公を締め上げる。それに付いて行けず先生に暴力をふるい退学になる。主人公の告発で先生も退職させられる。でもその先生がW杯の監督になり、その大舞台でキーパーだった主人公をダマし出場を要請するが復讐の為、突然フォワードで使う。その為、負けそうになるが、突然、主人公が勝手にキーパーになり神憑り的ファインセーブで勝つ。観客は大盛り上がり、鬼監督もまんざらでもないって話だったらどうだろう?
何じゃその話?って思わない?
映画「セッション」を見た。
ホントに何が言いたいのかわからないヘンテコなストーリーだった。
たかだか3億円の製作費でアカデミー賞3部門を取り、評価も異常に高い。
こりゃあ見なきゃ!と意気込んで見たが、上記の話の音楽バージョンの映画である。
主演の鬼教官が自分の輝かしいキャリアを捨ててしまう様な、カーネギーホールの大舞台で主人公に突然、別の曲を与え復讐する。でも主人公の即興の酷い演奏は直接、指揮者である自分(鬼教官)の評価につながるはずである。つまり鬼教官の復讐行為は、自身が二度とJAZZの世界に戻る事は出来なくなると言う意味である。復讐のはずなのに、ただ常軌を逸した自分の評価を下げる(JAZZの世界から抹殺される)だけの理解できない事をする。
僕にはかなり違和感がある。
スポーツに比べ、音楽(奏者)は評価されない事を、この作品を通して訴えていたが、でも一番音楽を馬鹿にしているのは 作者に思えてならない。
僕の見方がおかしいのか?何か見落としているのか?
ネットでは絶賛で、そこに引っ掛かっている人がいないのも不思議である。僕は至極当たり前の事を言っているつもりなのだが、
子供の頃、友達と西部警察を見ていて、犯人が他人に殺人現場を見られてしまって、その目撃者を殺そうと狙う。西部警察も、その目撃者(証人)を守ろうとするが、最後には、犯人とお決まりの銃撃戦になる。なのに、この期に及んで犯人はまだ目撃者を、警察の銃弾を かわして殺そうとする。僕は「もう こうなったら目撃者とかの問題じゃないんじゃないの?」と言うと友達は「そんな屁理屈言わんと、純粋に楽しまれへんか?」とたしなめられた。
セッションを見て西部警察を思い出した。
でも、「ノーカントリー」の殺し屋は、目的を失った殺人依頼の執行が、異様な不気味さを醸し出していた。
音楽モノ映画として観てはイケない、スポ根作品
自分が詳しい分野を題材にした映画やドラマは、知識がバイアスになって素直に観られないというのはあるにしても、その分野への最低限のリスペクトがあるかどうかは、その作品の評価に影響して当然だと思う
音楽を扱う作品において、作品全体のこの音表現はあまりに粗雑で、楽器奏法についてのアプローチも誤解を生みかねない表現が多すぎる
血豆の上に血豆ができたり、長い練習時間が上達として成果に返ってくるという、個人の努力のプロセスが存在すること自体は共感できるが、それはこの作品のような筋トレ的な見え方にはならないはず
チャゼル監督の高校時代の実体験がベースになっているとのことだが、あまり幸福な音楽教育体験を得られなかったとしか思えず、ビッグバンドだとしても著しく一般性を欠く経験に基づいていると感じ、共感が持てない
ラストのドラムソロについても、「好演で見返した」大団円の扱いで描いているのだと思うが、演奏がぜんぜん好演になっておらず、ジャズにおいては古くてダサいドラムソロの部類で、ちっとも見返せてない
時代設定とかジャンルとかの問題ではなく、である
演奏は音声で被せられるので、ラストシーンをこの演奏で締めたのは監督の意思に他ならない
つまりおそらくこの作品は、専門家による考証や介入の不足により、題材に対する深堀りに失敗したのだと思う
周囲の興行関係者はチャゼルの実体験を信じたが、観る人が観ればその音楽知識と音楽愛は浅いものでしかなかった、ということだと思う
ちなみに、邦題の「セッション」についても、ビッグバンドジャズとコンボジャズの区別もついてない日本の配給担当に買われた不幸を物語っていて、残念でならない
例えば『THE FIRST SLAM DUNK』を観たバスケット経験者で、ここまでの違和感を感じる人がいるかどうか
他の分野の作品と比較してみると興味深い意見が得られるかもしれない
タイトルなし(ネタバレ)
常に重苦しいピリピリとした緊張感が続く映画。教鞭を取る鬼教員が明らかにイライラしている授業というのは日本人全員が履修済みだと思われるが、その時間が延々と続く。その中で希望と落胆が交互に訪れる。最後のセッションは素晴らしく、ドラム一本でここまで魅せることが出来るのかと感動した。
他の批評で行き過ぎた指導が不快などという的外れな感想が散見されるが、この映画のテーマは芸術への狂気なのだと思う。音楽程ではないが僕もある程度芸術的要素が求められる仕事だ。経験則として、やはり良いと感じられるモノを作り上げるのは狂気的な人間なのだ。この映画は狂人が一人の狂人を練り上げる映画と言っても差し支えない。それ以外の人間は道を外れていく。フレッチャーの影に隠れているが主人公も最初からある程度狂っている。
僕は間違いなく凡人なので狂人が作り上げる世界観を一般に伝えられたらと思う。こんな風には生きられない。映画中でこそだなぁ。
狂気のぶつけ合いバトル
指揮者のフレッチャー、ジャズドラマーのニーマンが互いの追い求める芸術と狂気で殴り合うシーンがメインのストーリー。
この世界にコンプラは存在しない。しかし純度100%の剥き出しの魂のぶつかり合い・互いを食い殺さんとする情熱がある。
最後の10分の為だけに苦痛を延々積み上げていくような映画だが、最後の10分にはそれだけ苦しむ価値がある。
一緒に演奏している筈の奏者たちも、聴いている観客すらもどうでもいいと言わんばかりの一曲に人生の全てを賭けた二人だけのセッション、演奏がただ美しい映画。
最終的に指揮者もドラマーもどっちもヤバい奴なので一方的な暴力でないのも良い(二人の周囲は狂人に巻き込まれて可哀想だが、二人にとってはそれすらどうでもいいというのがこの映画の味だと思う)。
フレッチャー(J・K・シモンズ)の鬼指導が怖くて緊張感ある
フレッチャー(J・K・シモンズ)の鬼指導が怖くて緊張感あった。怒涛の精神攻撃はもはやパワハラ。自分だったら絶対ソッコーで挫折してる。
鬼指導に耐え続けたニーマン(マイルズ・テラー)も凄い。
何となく生きてるニコル(メリッサ・ブノワ)と、明確な夢を持ってるニーマンとの対比が良い。
ニコルを振る時の台詞がリアル。自分も同じ立場だったら同じ台詞言うだろうなぁ。夢に恋愛は邪魔だしね。終盤ニコルに電話するシーン、彼氏居ることが判明した時のニーマンの表情が切ないけど、下手にヨリ戻して恋愛要素入れないでくれて良かった。
最後の演奏シーンは爽快。ニーマンが吹っ切れてドラム叩きまくるの気持ちい。
自分はどちらかと言うとニコル寄りなので、ニーマンのように好きなことを何か見つけて、とことん打ち込んでみたいと思える映画だった。
全191件中、1~20件目を表示