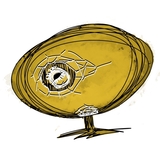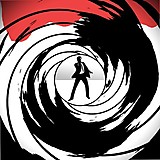野火のレビュー・感想・評価
全160件中、61~80件目を表示
もう観たくない
この映画を低評価する理由はひとつです。 「血糊がわざとらしかった」...
ふむふむ
やりすぎてギャグになっている
塚本晋也の作品は好きなので前々から本作を観ようと思い、ついに観た。
とはいえ今まで観たことがあるのは『鉄男』『双生児』『六月の蛇』『悪夢探偵』の4作品しかないので、本作が5作目になる。
最近では俳優として『沈黙 サイレンス』で波に打たれる苦しそうな磔姿が印象に残っている。
ただなぜ今更大岡昇平なのかは疑問が残る。
筆者はこの手の戦争の悲惨さを伝える映画は既に時代に即していないと感じている。
戦時中南方の日本兵の多くが食糧難のために餓死や病死していたのは有名な話であり、ドキュメンタリー作品である原一男監督の『ゆきゆきて、神軍』でも食人の話は出ている。
そもそも極限状態での食人は洋の東西を問わず枚挙にいとまがなく、緊急性を考慮されて裁判でもめったに裁かれない。
『野火』の作者である大岡昇平は、食料不足にあえいだ敗残兵の憂き目を身を持って知っているわけであり、刊行当時は日本全体が戦争のつらさややむにやまれない行動に及んだ兵士への同情もあった時代だと思われる。
実際原作の『野火』では主役の田村はキリスト教徒であり、その葛藤に苛まれている設定である。また刊行時は戦後6年しか経っておらず食料も日本全国に十分に行き渡っていたとは思えない。
しかし、今や東京がミシュランガイドで世界一星を獲得するぐらい飽食の時代である。
本作を観た時、現代の日本人は食人をした兵士に何を思うのだろうか?
食に何不自由のない現代の我々が彼らを人道的に責めるのはたやすい。
よく戦争の悲惨さや残虐さを後世に伝えなければいけないという人がいるが、ならば戦争の正当性や悲惨さに至る情状酌量の余地、戦地での美談もあわせて伝えるべきではないだろうか。
片方しか伝えないのは、筆者には公正とは思えない。
本作でもフィリピンの原住民が騒いだために錯乱した田村が銃で撃ち殺してしまうシーンがあるが、一方では現地の人々に規律と慈愛を持って接していた日本兵の話もある。
パラオで現地のパラオ人が日本兵とともに敵軍と戦おうとした時、日本兵が「お前ら蛮人が日本人と対等になれると思うな!」とわざと憎まれ口をきいて彼らを戦争に参加させなかった話があるなど、誇り高い日本兵は数多くいる。
しかし筆者は生まれてこの方そういう戦争時の日本兵の高潔さを謳った映画を観たためしがない。
これからは戦争時の日本兵に肯定的な映画も制作されるべきだと思う。
その意味において『野火』が刊行されて66年、この作品は既に使命を全うしているのではないだろうか。
なお前述したフィリピン人女性を殺すシーンだが、多分女性は一般人なのだろうか?キャーキャー騒ぐ声があまりにもうるさ過ぎる上に不自然過ぎてかえって笑えてしまう。
また日本兵が銃撃を浴びて死ぬシーンは塚本の過去の作品を彷彿とさせるようなおどろおどろしい残酷さに満ちている。
塚本自身は真剣なのだろうが、あまりに過激な残酷さはかえって異化効果を生み出し、こちらもなんだか笑えてしまう。
本作を出品したヴェネチア映画祭で残虐シーンはやり過ぎだと言われたらしいが、筆者も意味は違うが同感で、笑わせない程度にやり過ぎを抑えてほしかった。
主演の塚本はもちろん、安田役のリリー・フランキーも、伍長役の中村達也、永松役の森勇作など全員がそれぞれにいやらしい男でなかなか真に迫る演技を披露している。
ジャングルでの撮影も大変な苦労があっただろうと推察される。
塚本は脚本の参考にするため2005年11月にフィリピンでの日本兵の遺骨収集事業に参加したというから見上げたものである。
またその際の経験が本作に活かされているのだと言う。
塚本は、悪いのは相手で自分は正しかったと考えているうちは戦争はなくならないという旨の発言をしているが、悲しいかなこちらが戦争を望まなくても相手が仕掛けて来る場合もある。
そのようなパワーゲームの中で自国の自主独立を勝ち取るのは相当な覚悟が必要である。
だからこそ今重要なのは戦争の感傷に浸ることではなく、戦争を未然に防ぐために何が必要かを論理的に判断していくことだろう。
飢えの苦しさ…、生きることの辛さ。
人生における戦争映画の最高傑作
まず第一にこの映画を反日映画だと安易に批判する輩がいるがそのような内容ではない。戦争には様々な側面があり、その中の戦争の悲惨さという側面を切り取った映画である。そのため、観た後は二度と見たくないが、傑作であることは間違いない。(普通、傑作は何度も鑑賞したくなるものだが、余りの悲惨さにもう一度観る勇気がなくなる、
つまりトラウマになる)
映画全体を通して主人公の視点から描かれており、生きるか死ぬかの緊張感が張り詰めていて、何度も途中で声が出てしまいそうになった。
風景となった死体の山、一方的に殺される日本兵、小さな芋の奪い合い
挙げ句の果てに食人行為
これほどまでに悲惨な戦争があったのかと言わんばかりの飾り気の全くない「リアル」、是非一度は映画館でみていただきたい。
ちなみに監督自身は「映画は一定の思想を押しつけるものではありません。感じ方は自由です。」と発言しており、私は「兵站、補給は大切だなぁ~」そして、「このような悲惨な戦争を戦った英霊に感謝、脱帽するしかない。」と感じました。(マヌケですみません。)
誰も悪くない
2015年の初公開から2年経った2017年の終戦記念日にユーロスペースで鑑賞しました。当日は塚本晋也監督のトークショー付きで会場は満員。
公開当初より噂は散々耳にしていましたが、マッドマックス祭の最中だった私は見に行く機会を失っていました。
毎年毎年、8月15日に改めて観るべき作品だと感じました。
言葉にできないほどの凄惨な戦争体験を生々しく描いた本作。監督自ら扮する田村一等兵は弱々しく、身長も低く、まさに当時の日本兵そのままといった風貌。
数多くあるヒーロイズム的な映画にはしないとは監督の言葉で、まさに戦争の負の面だけが次々に田村を襲います。
飛行機からの掃射によって頭部が破裂した医師から始まり、
小さな小さな芋を分け合うガリガリの日本兵
ジャングルのその辺で死んだようにならんで眠る日本兵。
ウジが湧いても息はある者。
風景に溶け込む日本兵の死体。そこら中に死体が転がり、もはや当たり前となっている。
そして、人肉食問題。
監督は実際にフィリピンに行かれ、戦争体験者から言葉を聞かれたようで、映画に出てくる目を覆いたくなる悲惨な状況は当たり前だったという。
その上に立ち、人肉を食べたとか食べてないとかの議論の余地はないのだと。
人肉を食べるのは当たり前。
問題は「誰を」食べたかだと。
言葉でいくら語っても陳腐なものになってしまうので、百聞は一見に如かずだと思います。
トークの時にも監督がおっしゃられていましたが、この作品が、「はだしのゲン」のようにいい意味で子供の心にトラウマを残せればという言葉ほど、この作品の価値を言い表している言葉はないでしょう。
すでに成人し良いトラウマ経験とはいえませんでしたが、これを良いトラウマとして体験できる未来の子どもが羨ましくて仕方ありません。
その情熱が伝わったのか、映倫もPG12指定。
ぜひ子どもとみてトラウマを作ってほしい作品です。
この作品が後世まで伝わるよう応援していきます。
陳腐な言葉ですが、やっぱり戦争は良くないんだなと感じた雨降る8月15日でした。
ただただ衝撃を受けた
美しいわけがない
肉片が散乱し、ウジが大量にわき、唇を真っ赤にして人肉を貪る。想像以上のおぞましさにしばらくの間、スクリーンを直視することが出来ずにいました。
この作品はあくまで田村一等兵ひとりの体験がベースです。100人の兵隊がいれば100通りのおぞましい体験が各々にあったのではないでしょうか。もちろん、田村一等兵以上の体験もあったかと、容易に想像がつきます。
昨今、戦争を美化する様な作品もありますが、私は「野火」の様なおぞましさ以外に戦争の真実はないと思います。
というのは、10年程前にひめゆりの塔を訪れた際に、ひめゆり学徒隊だった語り部のおばあから「映画ひめゆりの塔(1953)で、キャベツをボールにして遊んだり、笑ったりするシーンがあったけど、あんなことは微塵もなかった。楽しいことや美しいことは、ひとつもなかった。あれは映画だから。」と聞いたからです。
塚本監督は、映画だからという理由ではなく、戦場の真実をフィルムにしました。それは、人の身体は簡単にバラバラになり、腐敗しウジがわくこと。そして、異常な環境にもやがて慣れ、人を殺せる様になるということ。
そして、この戦場に敵は不在です。何の為にこの場所にいるのか、もはや誰も分かりません。日本の為なのかどうかも、誰も分かりません。分かることは、日本という国家が想像を絶するほどに「狂っていた」というたったひとつの事だけです。
全160件中、61~80件目を表示