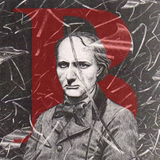リアリティのダンスのレビュー・感想・評価
全27件中、1~20件目を表示
嫌いではないトリッキーさではあるが、いくらなんでもさすがに濃すぎるか…
映像的には舞台であるチリの田舎町はカラフルでそして山海ともにとても映えていたし、独特な登場人物達の破天荒な振る舞いもインパクト抜群で最後まで目が離せない。
ただし、思想色強めの芸術的映画として観ればなかなかいいね!と思う反面、いくらなんでも奇抜でやり過ぎでは?と思ってしまうと、こちらの方が個人的には断然上回るかも知れない。はっきり言って相当なぶっ飛び映画だ。
観終えた満足感はじゅうぶん味わえるものの、他人にお勧めするには少々躊躇してしまう作品かな。評価は相当分かれるでしょ。
好き!
チリの恐山
一度観ただけではわからない、過激だけど、本質 まるで夢
夢の見方はひとそれぞれらしいので、ワタシの思いは伝わらないかもしれないけど、
ワタシは、色付きで、空間があり、いろんな変な人も登場して、唐突な行動したりして、ぞっとしたり、汗をかいたり、いわゆる、「夢見の悪い」をよく経験をしています。
この映画は、そういう、あり得ない変な、夢にでてくる情景を、「実写」している映画。
初めて観ると、その登場人物や過激な描写に、まず違和感、そこに目がいってしまい、 うっ っていう嫌悪感を持つと思います。
魚の大群や、バイオレンスや、不具の人たちや、大きな胸、変な人たち、生き埋め? 裸ほか、あれこれ、 妙な演技の下手さや、演出のあいまいさとかも・・・
でも、そういう思い切ったキャラクターや展開や、ビジュアルには、・・・実は、夢で観たみたやつ、と思えば、そんな感じ、と思える。
そして、大事なのは、退屈な「事実」より、本質を言い当ててる!! ってこと。
まさに、リアリティ、って何よ!? と問いかけてる
これは、一度目では、わからない。 まず、違和感たちに慣れないと。ww
まとめてしまえば、「息子にとっての、父母、の物語」 実際はいろいろあるんだけど、結局こういう感じでしょ、っていう。。
それに、人種差別、ペストや、難民や、弱者、宗教、金持ちと貧者、施しと強奪、救う人、拷問・・・
最近まで、日本では実感が持てにくかったけど、ここ数年、じわじわわかるようになってきた話もあるよね~、って感じ。
だから、これは、まだ未解決、かつ、現在まだ膨張し続けている問題にもなるんですよ、ここが、すごいところ。 まだまだ、次世代にも、問われますよ、これ
そういう時代のあれこれの中で、 自分のアイディンティティって、なんなのよ! って
にしても、70年代のアングラ芝居にさも似たり、っていう www
映画ですもの、この規模で、これだけやられると、たまらんですな~ って思う映画です
ダンスを踊っていると
毒親を人間化するということ
エンドレスポエトリーを観てからすっかりホドロフスキーファンになってしまったので、前日譚である本作を鑑賞。こういうタイミングでホドロフスキー特集を組んでくれるアップリンクには感謝しかありません。
さて、本作は幼年期のアレハンドロの話かと思いきや、父親ハイメがメインの話でした。
ハイメの暴君ぶりはエンドレス〜でも強い印象を与えてきますが、本作はアレハンドロが子どもなので、虐待描写がかなり強烈です。トラウマある人にはキツいかもしれない。また、アレハンドロも子どもだから反抗もできず基本ただ耐えるだけなので、なかなかにシンドいです。前半部はそんな感じの息苦しい父子関係の話なので、正直ちょいと退屈しました。
しかし、ハイメの話になっていく後半からドライブ感が加速し、グイグイと引き込まれました。
暗殺を試みていざイバニェスと直面したときに衝撃を受けるハイメの姿に、こちらも衝撃を受けました。鏡のように、ハイメはイバニェスに自分の姿を見たのです。エンドレス〜を観たときに、「イバニェスとハイメは同じキャストなのでは?」なんてこちらも思っていたので、そうか、意図的に似せていたのかと直観できました。
馬係になり、馬に語りかけることで、ハイメは自らの思いを語れ、はじめて悲しげで人間的な表情を浮かべることができる。そしてついにこの時、虐待の常習者である独裁者ハイメの、そう生きざるを得なかった彼の背景にはじめて思いを馳せられるのです。そしてハイメも、政敵イバニェスが馬と戯れ、喜び悲しむ姿に、同じ人間であることを体験的に理解していく。
ここて、ハッと気付きました。これは、ホドロフスキーが憎き毒親ハイメを人間化しているんだな、と。
ホドロフスキーにとってハイメは加害者。悪魔のような存在だったと思われます。しかし、ハイメも人間。その時はそう生きるしかなかった。
おそらく、これまでホドロフスキーは父親に対して100%の悪のイメージを抱いていたのでは、と想像します。しかし、それではホドロフスキー自身も救われない。本作はサイコマジック、心理療法なのです。父と向かい合い、父を理解する。父は悪魔ではなく、弱い、それでもなんとか必死に生きたひとりの人間なんだ、とホドロフスキーは本作を撮りながら身体で理解していったのでしょう。
無神論者ハイメは聖者ホセと出会い、神の存在を知覚します。これは特定の神の存在ではなく、神的な、個を超えたものへの信仰心の目覚めが描かれているようで、じわりと沁みました。生きるには生かされるという面もあるのだ、と気づけたハイメは、愛する妻子が待つ家に帰り、自分の影と対決し、独裁者のペルソナを見事に焼き捨てたのです。
そして、この作業があったからこそ、エンドレス〜のあのredemptionなエンディングを迎えることができたのだ、と断言できます。
過去を変えることはできる、とホドロフスキーは言います。これは、過去の捉え方を変えると、本当に変わったように実感するのだと思います。捉え方を変えるには、徹底的に向かい合い、理解すること。
現実世界を生きたハイメ・ホドロフスキーがこのように救われたかどうかは窺い知れません。しかし、本作によって、アレハンドロ・ホドロフスキーの中に生きるハイメの魂は解放されたと思います。仮に霊魂があるのであれば、怒りと恨みに縛られてこの世を彷徨っていたハイメの霊は成仏できたと思います。
ちなみに、映画の面白さはエンドレス>リアリティ。
やっぱり、父の話よりも本人の話の方がテンション上がりますからね。
ホドロフスキーのサイコマジック5部作、だいたい3年インターバルで作られているので、最終作のときホドロフスキーは97歳くらい。イケる!新藤兼人は98まで撮っていたぞ!
ホドロフスキー映画好きな人向け
自身の幼少時の自伝的映画、とはいってもこの監督のことなのでこういう内容になる。
聖と俗、美と醜、リアリズムと幻想。
ごった煮的な構成はいつものことだが、今作は(これでも)ややすっきりまとめた感じ。
自身のルーツであるユダヤ人であるとかロシアとの繋がり、父や母との関係などおそらく正直な吐露が見られてファンには嬉しいかな。
本作だけ観てもつまらない。デューン/砂の惑星→ホドロフスキーのDUNE→リアリティのダンスと観てください!
「狂気がなければ芸術作品は生み出せない」
byアレハンドロ・ホドロフスキー
『デューン/砂の惑星(1984年)』
『ホドロフスキーのDUNE(2013年)』
『リアリティのダンス(2013年)』
1980年 エレファントマン
1984年 デューン/砂の惑星
1986年 ブルーベルベット
これはデビッド・リンチ監督の1980年度の監督作品です。
この後1990年に、私の大好きな"ワイルド・アット・ハート"を撮りますが……。
さて、みなさん。一作、一作、内容を思い出すと、かなり酸っぱい顔になる作品がありますよね?
そう!「デューン/砂の惑星」です。
※実は昨夜30年振りに観ましたが、諸々と酸っぱかったです。
いやいや、大好きですよ!
顔にできたおできを、執拗に気持ち悪く映し出す困ったコダワリとか。
仄暗い、こんがらがったサーガとか。
ナウシカをはじめ、色んな作品に影響を与えた(何故か側面の部分的なアップばかりの)サンドワームとか。
厨二の大好物である"力が覚醒する"とことか。
人気者のシンガーだと?スティングだと?知ったことか!と、これでもか!と格好悪く死なすとことか。
まだまだ可愛いショーン・ヤングとか。
大好きですよ!
でも、ブッツ、ブッツに話が切れて、なかなか世界に迎え入れてくれない部分もあり。
きっと、もっと長い作品だったんでしょうね。
だってある監督は「絶対に12時間で撮る!」と言ってきかなかったんですから。
それだけの時間をかけてこそ、描ける世界観なのでしょうね。
1975年「デューン/砂の惑星」を、12時間で撮ると言ってきかなかった監督がいます。
スタッフ&キャストと言わず「魂の戦士」と呼んで探し求め、変態的な交渉術で天才達を口説き落とし、完璧な企画ができあがっていたのに。
ある理由でダメになったんです。
その過程を、ドキュメンタリーにしたのが"ホドロフスキーのDUNE"です。
ホドロフスキーと言ったら、"エル・トポ"でパンツ一丁で泥まみれで蠢いていたイメージが強いです(笑)すみません、他の作品は未見です。
ハリウッドのメジャーな映画会社に売り込みにいった際に、実は"企画は最高!だけど監督を変えろ"と言われた理由は、この"エル・トポ"のせいでした。
「あんな変人に、むっちゃお金のかかる12時間の映画を撮らせられっか」だったんです。
最近"オンリー・ゴット"をレフン監督から捧げられていた、鬼才、変態、アレハンドロ・ホドロフスキー監督。
ホドロフスキー監督が撮ろうと思った「デューン/砂の惑星」が、どれだけ凄いか「魂の戦士」一覧を見るだけでお分かりになるかと思います。
◎スタッフは下記の通り。
ミシェル・セドゥー
メビウス
クリス・フォス
H・R・ギーガー
ダン・オバノン
ピンク・フロイド
◎キャストは下記の通り。
デヴィッド・キャラダイン
ミック・ジャガー
オーソン・ウエルズ
サルバドール・ダリ(と、ダリのミューズ:アマンダ・リア)
ブロンティス・ホドロフスキー
このメンツで、12時間の映画を撮るって凄くないですか?
ホドロフスキー監督が、目をキラキラさせて当時の様子を語ります。なんだ、こんなに可愛い人なんだー。と思っていたら、むっちゃ笑顔で「私は原作をレイプしてやったんだよ!レイプしてやった!」と繰り返していて、びっくりしました(笑)
いや、80歳過ぎてこのテンション!素晴らしい(でも、息子さんで俳優のブロンディス、疲れそう……)。
当初は、特撮に「2001年宇宙の旅」のダグラス・トランブルを予定していました。
でも打ち合わせ段階で、ホドロフスキー監督そっちのけで電話に40回も出るその不遜な態度で「あいつは魂の戦士ではない」と断るとことに。
爽快!
ホドロフスキー監督は"映画は自分にとって芸術なんだ"と繰り返し言いますが、それがよく分かるエピソードです。
さて、ここまでできあがっていた企画が、監督へのダメ出しでなくなってしまいます。
が、満を持してリンチ監督が映画化するんです。※ホドロフスキーの企画は映画化してません。
ホドロフスキー監督は泣いたそうですよ。でも、勇気を振り絞って映画を観にいったそうです。
「リンチだぞ、あの天才リンチが撮った映画。とても敵うわけない!けど……」
この後、ホドロフスキー監督は満面の笑みで続けます。
「けど、大失敗やん!酷いやん!」
リンチ監督の「デューン/砂の惑星」を観て、すっごくハッピーになった!って。
あ、決してリンチ批判をしているわけではないんです。
ホドロフスキー監督は確信したんですよ、自分の企画が間違ってなかったって。自信を取り戻した満面の笑みだったんです。可愛い人。
ホドロフスキーのDUNEは幻の作品となってしまいましたが、その企画の片鱗はSWにも、フラッシュゴードンにも、エイリアン(ホドロフスキーのお陰で出会った2人が作ったんだもの)にも、最近ならプロメテウス等にも見つけられます。
未完なのに、多くのSF作品に影響を与えるとは。凄いです。
ギーガーや、レフン監督の貴重なインタビューや、クリス・フォスの宇宙船のイラスト(凄く良いんですよこれ!)が見られるだけでも素晴らしいです。また、もし本当に映画化されていたら、SWはどうなっていたんだろう?と思いを馳せるのも楽しい。
「狂気がなければ芸術作品は生み出せない」と"ホドロフスキーのDUNE"で繰り返し言っていた監督と、プロデューサーのミシェル・セドゥーがそれから35年後に再びタッグを組んで制作したのが、"リアリティのダンス"です。
本作は、ホドロフスキー監督半生の映画化です。勿論、ご本人も出演されてますよ。
あ、半生というか、子供の時に体験したエピソードの数々と言った方が良いかもしれません。寺山修司の「田園に死す」に確かに似ています(あ、VHS持ってます)ね。
色々と、妙なんです(笑)
父親(ブロンティス・ホドロフスキー)は厳格というか、息子のアレハンドロを強く育てたいと思うあまり、麻酔ナシで歯科治療をさせたりします。
巨乳の母親は(オペラ歌手志望だったみたいで) 普段の喋る口調が、全てオペラです。暗闇を怖がるアレハンドロを靴墨で真っ黒に塗って克服させたり、夫の伝染病を放尿で治したりします。なんでしょう、何かを超越した女性です。
そんな幼少期のアレハンドロを、優しい目で見つめて励ますホドロフスキー監督。
妙なエピソードから垣間見られる、チリ政権下の抑圧された恐怖と奇々怪々な貧困生活。
ホドロフスキー監督は、現在86歳です。
本作を観ていて、創作の源になっていた狂気と、漸く折り合いをつけたのかも知れないと思いました。凄く、解りやすい作品です。
独裁的な父と、その父に抗えない母と、あの時代を赦す。
ホドロフスキー監督の悟りと、優しさを感じる作品です。
そして同時に、ホドロフスキー監督とのサヨナラが近付いていることを、強く感じる作品でした。
いつまでもお元気で!そう願わずにはいられません。
原題が「LA DANZA DE LA REALIDAD(英:THE DANCE OF REALITY)」です。
真実のダンス。現実を思いっきり踊らせる。現実を好き勝手にダンスさせて、滅茶苦茶にして、そうすれば何かが再生されるのかも知れない。
私もリアリティのダンスをしようか。
できれば3作品、纏めてどうぞ!
頭おかしい
幻想は救い
子どもは、自分が両親を満足させる対象でありたいと望みながら、アイデンティティーを形成しようとする。
誰もが、そんな子どもの自分を抱きしめたくなる。
両親にとって自分がどのような対象であるのか分からないまま成長し、ふと気づく。
その答えは、幻想の中にあると。
自分が作る幻想の中でこそ、他人の願望だけでなく、自分の願望も、はっきりと浮き彫りになる。両方を一度に抱きしめればいい。
抑圧的な父が「英雄」で、母が「奇跡の女」であったことは、おそらく幻想だろう。
父を、愛情を込めて許したいという願望が成就し、小さいホドロフスキーは、幻想の世界で救われる。
すると、リアルな世界が、優しく彼に寄り添ってくるのを感じた。
初ホロドフスキーの方にこそ、是非!
ホドロフスキーおじちゃんの不思議な不思議な回顧録。
ホドロフスキーって、
ぶっちゃけあまりにも悟りすぎて結局テーマ意味わかったのかって
言われれば本当は良く分かりませんでしたすみません
ってなるのがほどんどだけど、
これはエンターテイメントとして楽しめる!
初めてホドロフスキー見る人には、
とてもわかりやすいし、かなりの衝撃を受けると思われ。
見終わったあとは、テーマを頭で理解するとかじゃなくて、
生きるエネルギーみたいなものを授かる!!
幼少期のアレハンドロを演じている、
イェレミアス・ハースコビッツ君の美しさにクギつげ☆
実孫らしいけど、どうやったらこんな宝石みたいなお子が
生まれるんよ。
あと母ちゃんのオペラうるさいけど癖になる。
映画という愛の形
はじめてのポドロフスキー
女の子かと思ったポドロフスキー少年役の少年がやっぱり女の子に見えてしかたがなかった。いつも困ったような、ちょっとまぶしそうにしている表情がまたいいのです。
それにしてもポドロフスキーの語りはいい声でした。
物語の展開の息もつかせぬ感じ、幻想的な映像表現、音楽、どれをとってもすばらしいのでした。
当初は絶対的権威であった父が受難者となって放浪の旅に出てゆき、ぼろぼろになって帰ってくる。最後には年老いて髪も白くなった父が柔和な表情でうつります。旅を通して武装がほどけ、やさしさも弱さもにじみでる人間らしい人物になったのでした。ポドロフスキー少年の父親像の変遷が見て取れると同時に彼自身の成長が感じられる壮大な物語でした。
お母さんもとっても魅力的でした。台詞ぜんぶオペラなの、とやや違和感がありましたが、中盤からむしろ安心感を感じるようになるのでふしぎです。
前半で、ポドロフスキー少年とその父のせいで「(わたしは)みなしごになってしまった!」にはあっけにとられてしまいましたが、あとからしみじみ感じられるものがありました。娘から母になる心理的葛藤が描かれているように思えたのです。
そんな母が誰よりもたくましく、息子と夫をささえてゆくのです。
神はいないと言う夫に神は(ここ=心に)いるわと言うシーンは感動的です。映像的には過激な描写もありますが…。
そういえばR15だったな…と。なるほど。でも他の作品よりか刺激は少ないほうなのかなと思ったり。
両手の不具が罪の印や聖なる木工職人の口にした詩篇5、母のまじないが土着信仰のなにかと関連しているのか、鉱山労働者、感染症の患者の隔離(傘をかぶった黒い一団)の存在など、いくつも強く印象に残り、チリについてもっと勉強したいと思いました。
冒頭のかもめとさかなのエピソードが印象的です。喜びと苦しみは一続きにつながっている。浜に打ち上げられ苦しんでいる魚とそれを喜ぶかもめ。そこで喜んでいるのがかもめにかたよっていることに心を痛めた、といった言葉の断片が、映像とともにふと思い出されるのでした。
映画みたな、と感じられる力強い作品でした。
時の流れの中で全く風化することのないイマジネーションの輝き
オッサン!なにすんねん!ヾ(*T▽T*)
宣伝ポスターを見て
「この娘、萩尾望都さんが描く美少女みたい♪(//∇//)」と思ったのは私だけ?
(因みにこの子の表情の作り方がイイ!素人くさいんだけど何故か惹かれる)
出だしは『父と息子の根性焼き物語』?で、キャラが立ってるのはママさん位か?とか思って観ていたら……
オッサン!
あかん事しまくりや、ないですか?
(´д`|||)
『しも』の方は案外、大丈夫だとして『キャタピラ』の方は色んな団体とかいいんスか?
まあ、でも全部、撮りたかったんですよね?
そして見せたかったんですね?
自分の中に沸いた画を……
「あんたそーゆ人だもんね……」
などと小さなカウンターバーの
ママさんみたいに言ってみる。
監督の隣ではフランク・パヴィッチが延々三時間!
温和な笑顔を崩さずに彼の話を忍耐強く聞いています。
この若者、いまだホドロフスキーに
相槌しか許されておりません。( ̄▽ ̄;)
全27件中、1~20件目を表示