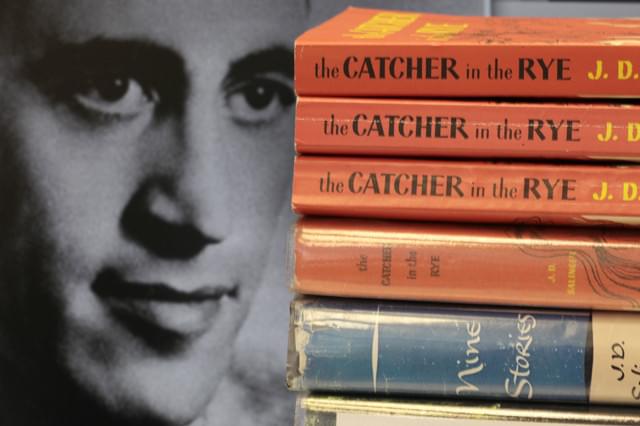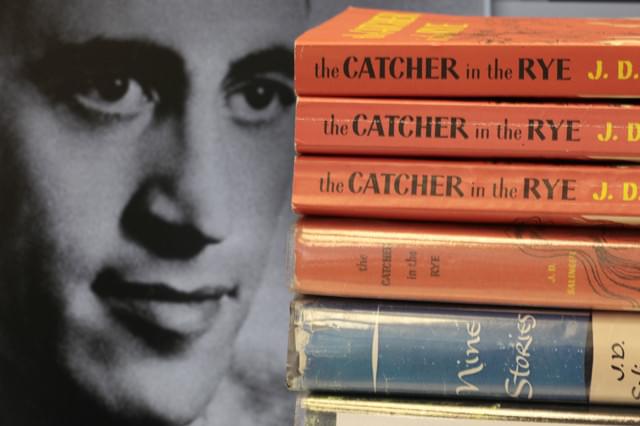野蛮なやつら SAVAGES : 映画評論・批評
2013年2月19日更新
2013年3月8日よりTOHOシネマズみゆき座ほかにてロードショー
グローバリゼーションの時代の「ナチュラル・ボーン・キラーズ」

作家のノーマン・メイラーは、順応主義や全体主義がはびこる1950年代に、国家による集団的な暴力と極端な非順応主義者=ヒップスターが行使する個人の暴力の間に一線を引き、後者を援護した。
オリバー・ストーン監督は間違いなくそんな精神を引き継いでいる。これは本人も認めていることだが、「ナチュラル・ボーン・キラーズ」では、全体主義的な暴力と個人の暴力の間に一線が引かれている。視聴率や売名にとらわれたキャスターや刑事、サディストの刑務所長は、いわば全体主義的な暴力装置に組み込まれた歯車だ。これに対して、個人として暴力を行使する主人公の男女は、かつてのヒップスターに重なる存在になっていく。
それを踏まえるなら、ストーンの新作は、グローバリゼーションの時代の「ナチュラル・ボーン・キラーズ」といえる。この映画で暴力装置となるのは、メキシコの巨大麻薬組織だ。そのバハ・カルテルから強引に提携を迫られた主人公のベン(アーロン・ジョンソン)とチョン(テイラー・キッチュ)は、危険を察知し、事業を丸ごと渡す決断を下すが、それではすまない。カルテルは、ふたりの彼女を拉致し、彼らそのものを支配しようとする。
そうなるとふたりはもはや手段を選ばない。仏教を信奉していたベンも、葛藤の果てにその手を血に染めていく。しかし、最愛の女を取り戻すために野蛮になるだけなら、おそらく物足りなく思えただろう。
同じ野蛮でもカルテルと主人公たちでは目的地が違うが、メイラーは「どんな代価を払っても個人の暴力で本来の自己を取り戻そうするヒップスターは、野蛮人を肯定する」と主張している。この映画のラストには、そんな解放された野蛮人の姿を垣間見ることができる。
(大場正明)