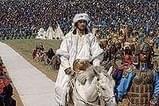真昼の惨劇
劇場公開日:1958年8月24日
解説
先頃世間を賑わした、娘の父親殺しを素材としたもので、水上伸郎・峰竜太(2)の共同脚本を、新人の野村企鋒が監督、荒牧正が撮影した。出演者は、「つづり方兄妹」の望月優子をはじめ、福原秀雄・青柳寿恵・島田典子・左卜全・中村是好など。
1958年製作/80分/日本
配給:松竹
劇場公開日:1958年8月24日
あらすじ
--東京のほとりのバタヤ村落。平井親子はバタヤの親方吉田をたよってきた。彼の温情でやっと職にありつき、平井は真面目にバタヤ暮しを始めた。が、彼は酒には目のない男だった。吉田をたよってきたのも、元はと言えば、酒のために身を持ちくずしたからだった。小銭が入り始めると、いつか彼はまた酒びたりの生活に戻って行く。彼の妻・あきは嘆じたのである、--酒さえ飲まねば良い夫なのに。長女の君子はもう十六歳になっていた。彼女には母の嘆きがよく判った。妹の芳江や幼い弟・常夫までが父をおそれた、--働きに出ずに寝ころがって酒に溺れる父を。じじつ、平井は酒が入ると狂暴になる。あきが暗いうちから家を出て働いてきた金が、たちまち彼の手で酒に代った。米を買う金もなくなる。母子を飢えが攻めたてた。近所の惣菜屋が見かねて君子を雇ってくれた。やっと急場はしのげたが、平井の行状は改まらない。吉田も怒り出し、追い出すと言った。母子は泣いてすがった--。平井は、それでも、友人が強盗を誘ったとき、きっぱり断るくらいの良心は持っていた。君子がいくばくの食物を持って帰宅し、弟妹に与えていると、平井は悪態をついた。俺に内証で。彼は狂暴になり、わが子に乱暴を働き、あきがとめると、彼女を半殺しの目にあわせたのだ。あきはそのまま家出した。どこで死のう。彼女が子供のために残した、その日のわずかばかりの働貨は、平井がたちまち酒にかえた。酔って寝ころがった父を子どもらは憎悪の目でみつめた。父さえいなければ母子四人で仲良く暮せるのに。--君子の頬から血の気が引いていった。あきは子どもたちを思うと、死にきれなかった。鉄道でも、川でも。道で拾った新聞が「父を殺した娘」を報じていた。わが家のことではないか! あきは警察へ駈けつけ、わが子をひしと抱いた。