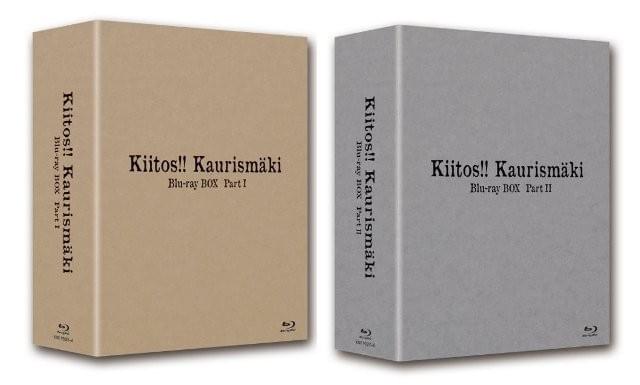ル・アーヴルの靴みがき : 映画評論・批評
2012年4月17日更新
2012年4月28日よりユーロスペースほかにてロードショー
筋金入りの善人を集めて幸せな結末に漕ぎつける荒技

字幕が足りない。笑えないじゃないか。
映画の冒頭で、私はちょっと首をかしげた。主人公マルセル(アンドレ・ウィルム)に靴をみがかせたやくざが画面から姿を消し、銃声が聞こえたあとのやりとりを見たときだ。
靴みがきの助手が「可哀相に」とつぶやくのに対して、マルセルは「でも、金を払う時間はあった」と答えている。ところが字幕では「金は払った」としか出ない。
因縁をつけているのではない。練達の翻訳者をもってしても、カウリスマキのおかしみはときおりこぼれ落ちてしまうことに驚いているのだ。「ル・アーヴルの靴みがき」は美しいおとぎ話だ。美しくて幸せで、嬉し涙が滲みそうになる佳作、といっても過言ではない。
が、美談だけで感動するのはただの馬鹿者だ。幸福感の背後には人を食ったユーモアがある。無愛想の陰にはデリカシーあふれる構図や色彩設計がある。だからこそ、この映画は分厚くなった。そもそも、20年前のパリで売れない芸術家だったマルセル(佳作「ラヴィ・ド・ボエーム」を思い出そう)が、ブルーカラーの港町ル・アーブル(「商船テナシチー」や「霧の波止場」の舞台だ)で靴みがきをしているという設定が不敵ではないか。
しかも彼のまわりでは、山中貞雄やマルセル・カルネの映画に出てきそうな人々が、こまめにほほえんだり胸を痛めたりしている。たとえば、酒場の女主人。死んだ亭主へのお悔やみを警視が述べると、彼女は「なぜ? 彼は宿命論者だったのよ」と返す。こういう台詞が映画の情感を稠密にしていく。
凝ったなカウリスマキ、と私は思った。世知辛い娑婆に身を置きながら、同情と親切と献身だけで奇跡を起こすには、どうすればよいか。カウリスマキは、この難問に知恵を絞った。「ル・アーヴルの靴みがき」をナイーブな映画と思うのは初歩的な誤解だ。「筋金入りの善人」を集めてなにがなんでも幸せな結末に漕ぎつける手法は、ほとんど荒技に近い。
(芝山幹郎)