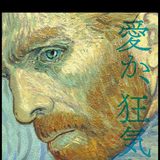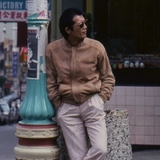最強のふたりのレビュー・感想・評価
全375件中、41~60件目を表示
ブラックジョークがかなり攻めてる
正直期待値上げすぎてた。それでもやっぱりちゃんと面白かった。
人種の描き方がかなりステレオタイプだけど、あえてそうしてるのかな?
意図してなかったとしてもちょっと前の作品だし仕方ないのかな。
こっちがギョッとするくらい踏み込んだブラックジョークがちょくちょく出てくる。そういうの引いちゃう人は引いちゃうかも。自分は笑った。
志村けんの影響力
本作もそうですが素晴らしい映画はオープニングとエンディング〜エンドロールが素晴らしいんですよね。エリーズ最高です。見てるだけですべてが素晴らしいです。
またヤン、ロイック、アンリの男性陣3名が素晴らしいアクセントとなっています。愛すべきフランスの男たちですね。人間性が素晴らしくどこか笑えるいい奴ヤン。恵まれない幼少期を過ごしながらメッチャクチャ美味しそうな料理を作り精力旺盛なロイック。ロイックのバレリーナの白いチュチュを笑うくだりは、日本でも昭和の昔からあるお笑いパターンで変なおじさんが股間から白鳥の首を出した白いチュチュ姿が日本におけるバレエの基本的な認識を作ってしまったのか?同じフランス映画で「最強のふたり」の中で上流階級のフィリップが介護士に雇った貧困層の黒人ドリスとオペラを鑑賞した時、出だしでドリスが仮装したオペラ歌手に爆笑した場面を思い出しました。父親のアンリとは父娘の関係性の難しさを切実に感じます。少し不器用でシャイな日本の父親のようなアンリ。とても良い作品でした。
君といれば僕は笑える。
パラグライダーの事故で首から下が麻痺してしまった
大富豪のフィリップ。
彼の新しい介護人募集の面接にやってきたのは、
スラム街の黒人青年のドリス。
失業手当を貰うために不採用の証明が欲しいという太々しさ。
面接結果は、
「私の事を哀れんでいない」とフィリップは採用してしまう。
障がい者の介護を描いているのにユーモアたっぷり。
金持ちだからと媚びず、障がい者だからといって、
同情しない。
腫れ物にさわるような同情にうんざりしていたフィリップが
ほしかったのは介護人ではなく友達だったのかもしれません。
残りの人生を楽しく豊かに過ごして行くためには、ドリスが必要
だったのです。
障がい者の下ネタまでギャグにして笑い飛ばしてしまう陽気さ。
お互いを羨むことなく妥協することもなく、
繋がりが強くなって行く過程が新鮮でした。
ドリスといる時のフィリップの本当に嬉しそうな顔。
それが幸せに生きること。
エードロールで実物のフィリップ本人が登場すると、
奇跡の友情は俄然と真実味を帯びました。
心の持ち方ひとつで人生は明るくなると実感しました。
秀作
フランス版も面白い!
たまたまフランス版最強のふたりをテレビだが、観る機会があった。
アメリカのリメイク版は観たが、本家フランス版も面白い。
介助士と資産家のつながり、カギを握る女性秘書とのやりとりもまた
面白かった。しかし、フランス版とアメリカ版はやはり国の社会事情も
また違う。
リメイク版の楽しさを知った。
シンプルにウケる、障害があっても笑うこと
これが障害者?
好きなシーンのひとつは主人公の黒人が面接を受けるところ。
観て欲しい。日本人に
こんな人いたら、普通面接は不採用
障害者は刺激が欲しかったのか。
自分は障害者の気持ちはわからない。可哀想っていうのはエゴだろう。
あくまでも雇い主と労働者であるが、まるで親友のようにストーリーが進んでいくのが爽快だ
あと、言いたいことを言わずにいられない黒人が周りの人(従業員)と少しずつ仲良くなっていく過程もいい。
けっこうふたりに焦点当てがちだけど、そういった細かいところも好きになった。
従業員同士の恋愛応援しちゃうところとか。
どんな人に観て欲しいか?と聞かれたら
冗談が通じなくて、頭が堅い人って答えると思う。
あなたの会社の周りに冗談通じない人がいたら、是非勧めてほしい。
障害者って言葉はいったい誰が始めに定義したのだろう。
そこまで歴史は調べないので誰がコメントで教えて。
「障害があっても」笑おうとかタイトルに付ける時点で、自分が障害者を特別に思ってるんだなって気が付いた。
もう一回みたいかなって思う映画です。
苦しむ二人が互いの優しさに癒され新たな1歩を踏み出す物語
ずっと観ていたくなるふたり
のっけからカーチェイスをおっぱじめるドリス、そしてフィリップの障がいを知るやいなや仮病にあっさり騙される警察、パトカーに先導されながら勝利のSeptemberを歌いかっ飛ばす二人!
このオープニングのシークエンスが何度でも観たくなる気持ちよさ。
フィリップは首下の麻痺、それよりもさらに辛い、最愛の妻を失った自分の人生をドリスに語る。そんなフィリップにドリスは「俺なら自殺してる」と返す。
一瞬ドキッとしたけど、フィリップの悲しみと強さに対して、どこまでも素直に反応出来るドリスだからこその台詞なんだろなあ。
(障がい者だから弱い立場)(雇用者だから強い立場)
フィリップにそんな立場というレッテルを貼らずに無遠慮に接するドリスが、フィリップに呼応するかのようにどんどん魅力的にみえてくる。
大きな事件が起きるわけでもなく、全く境遇も違う二人が友情を育くむ様子をただ眺める映画なのだけど、ずっと観ていたくなる。
私も気の合う若者と出会いたい
初めてフランス映画を見たので、彼らの息を吸う音や感嘆に込められた意味をいまいち掴めなかったのが少し残念でした。
物語序盤、フィリップは自分の障害をドリスにいじられる事を気にしていなかったから、フィリップは懐が深い人物なのかと思っていた。そうじゃない。彼が許したのはドリスが彼を一切の同情を持たず、素直な部分を見せていたからだ。
ドリスの描いた絵に1万1000ユーロの価値がついたシーン。人は何に対しても意味や教訓を求める。だから音楽や絵画などの芸術に価値がつく。いつしか本意は声に出すよりもキャンバスに描けば儲かるようになった。
そのスキームそのものに憧れてしまう人間は少なく無くて、目の前の絵に込められているかも分からない意味や教訓を分かった振りをして格好つける所が滑稽でかつ最も人間らしい。
ラストのシーン。伝えたい事も素直な気持ちも着飾った言葉で綴れば聞こえは良いけど、伝えたい相手に1ミリのズレもなく伝えるには手紙でも電話でもなくて直接会えって事なんだと解釈した。
あるある
なんか見覚えあるなと思ったら、観るの二回目だった。けど内容全部忘れてたからよかった。でも最近グリーンブック見たばっかりだから、ああこういうやつねって、なんだか新鮮味なかった…。。。
「これから食事を始めます。」って食事介助するのとか「障がい者が好きなんです!」とか、自分を障害者らしく扱うとか、健常者とは違う人間だと扱われるのが苦手だったのかな。甲斐甲斐しく介助されるあの感じ。
面接時点で他の候補者よりもドリスを選んだのは何故だったのか、よく分からなかった。
違うバックグラウンドを持つもの同士、お互いの文化や嗜好を嫌々ながらも取り入れ合うシーン、なんかでよく見たことある。。。グリーンブック観た後だと「あんたたちこういうの好きなんでしょ?」みたいな印象が強くなっちゃって…もう辟易してる自分がいるのが悲しい。見るタイミングが違ったな…。
こんなにいい映画なのに、あるあるだよねと消費してしまう自分が悲しい。
アクションものでも刑事ものでもない
何のジャンルかすら知らずに、邦題でアクションぽい映画だろうと
視始めた。
最初は車が暴走するシーンで始まり、そんな映画なんだと一旦仕分けして
その心づもりでいたら、序盤でいきなり肩すかし。
教養の無い粗暴で 前科もある失業者が、それでも職を求めて面接を受ける
何の映画か分からすに様子を見ている内、粗野なチンピラに見えてた
主人公が人間的に魅力のある者に見えてきて、一気に引き込まれた。
主人公はもう一人の主人公の障碍者の介護人だが、障碍者をかわいそうだと
いう目で見ていない。また主従の関係のようにへつらう意識もない。
このことが却って障碍者に居心地の悪さを感じさせず、人として対等に関わる
ことにもつながっている。
全部がこの映画と同じケースに当てはまるわけではないだろうが、
障碍者というと短絡的に「配慮」をあてがう最近の福祉の風潮は却って、
「配慮」することで自己満足する健常者との間に、壁ができることも
あるだろうと、感じさせる作品だった。
それにしても、オマール・シーのダンスの巧さにはびっくりした。
フォーカスがどこかわからない。
偶然ではなく、必然的だった2人の出会い!!
全375件中、41~60件目を表示