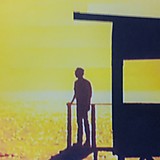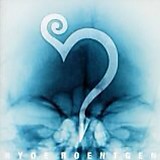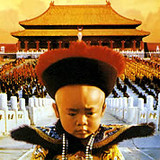ヒア アフターのレビュー・感想・評価
全140件中、61~80件目を表示
自分と対峙できる作品
オカルト臭を逃れた人間ドラマ
三つの異なる場所で進行する物語がどう結び付きをみせるのか、その点に見る側は引き寄せられていく。要約をしつつもそれぞれの日常や背負うものは提示され奥行きもある。二時間にこれだけの時間的背景を収めているのだから素晴らしい。
サイキックな描写も変にオカルト臭を漂わせずにドラマからははみ出していない。
ただフランス料理教室は恥ずかしくて見ていられなかったし、霊視を願い出といて消えた女はなんだかもやもやっとしている。
序盤の津波はこわいほどリアル。また、今日は3月11日…。
展開がゆっくりすぎ
クリント・イーストウッドの意図
正直、意味がよく解らなかった。3人をとりまく物語が最後に一つになっていくシチュエーションストーリー。でも、でも、でもでも雰囲気や細かいプロット、それぞれの物語が興味を引くものでなくってが正直あまり心が動かない。結局の所、脚本がつまらなすぎて最後のエンディング(おち)が全然理解出来なかった。何が、言いたかったのかイーストウッド?老いたな。
例えば、全く赤の他人である、マーカス君とジョージ氏の
雰囲気はいいけど、あまりおいしくない、有名レストランの料理みたいな映画でした。
普通の映画ならそこそこだけど、イーストウッド作品としては、最低の方だと思います。
イーストウッド監督の独特の映像と音楽などの雰囲気で、食は進むんだけど、肝心の味がおいしくないという感じです。
脚本が悪いと思います。
何が言いたいのか、さっぱりわからない。
死後の世界があるってことなのか?死んだ人と話ができたらいいなってことなのか?
臨死体験といっても、ほんの入り口だけで、その先に何があるのかまでは突っ込んでないし、キリスト教の世界ではすごいことなのかもしれないけど、日本人なら誰でも、どこかで多少は聞いたことあると思うし、特に驚かない。
それに他の人はどうか知らないけど、私は死んだ人と話をしたいと思ったことは一度もないので、まったく感情移入できませんでした。
死んだ人と話をしたって、おかしなことになって、さらに悲しい思いをするだけのような気がします。
へたしたら、ホラーかファンタジーに走りそうな題材を、あくまでリアルな感じでまとめたのは評価するけど、やっぱり中途半端かな?
スピルバーグが好きそうな話だけど、作風がだいぶ違うから、コンビは組まないほうが、いいような気がしました。
観て損した。時間を無駄にした。
Mデイモンの映画では無いし/タヒ後の映画でも無い‥
始めに強く言っときたい↓↓↓
JR福知山事故や/東日本大震災の‥被害被災の方々には‥
一部キリリとするシーンが有るので‥
見るなら心構えが必要だ。
■□■□■□
さて‥本作(^-^)
結果から言うなら‥
Cイーストウッド監督がやはり素晴らしいのだろう(*^_^*)
途中ちょっとダレたが‥基本は2時間を感じさせない&程良い緊張を途切れさせない‥
秀でた脚本劇だたo(^o^)o
◆アメリ‥
◆陰日向に咲く‥
◆バレンタインデー‥
らと同じく‥アンソロジー(←とは言わないか‥)
複数の話が交錯する御話です└|∵|┐♪┌|∵|┘
脚本がミソなので‥
予備知識は入れずに見ましょう~ヽ('ー`)ノ~
こちら‥
ただただ素晴らしいです(*'-^)-☆
☆評は‥
DVD100円水準にて‥(^-^)
DVD買う度⇒②★★
モ、1回見たい度⇒①☆
オススメ度⇒⑤♪♪♪♪♪
デートで見る度⇒②◎◎
観る相方o(^o^)o】映画経験値が要ります‥
女子には向かないか?
映画は?商品か?作品か?
映画は?娯楽か?芸術か?
映画は?入口広く取るべきか?排他的にすべきか?
映画に‥/偏差値や経験値は入用か?
これは‥
ミーでハーな俺らしくない‥シッカリした映画でしたヾ(*'-'*)
おすすめです~ヽ('ー`)ノ~♪
TUNAMIが無ければ
でも、知り過ぎない方がいいんだよ
映画「ヒア アフター」(クリント・イーストウッド監督)から。
「死者と語る人生なんて意味がない」という理由で、
霊能者を辞めた、肉体労働者のジョージが、
料理教室で知り合った女性に、その霊能力を使って欲しい、と頼む。
彼は何度も何度も断るが、彼女は引き下がらない。
霊能力を使う前に、彼が彼女に囁く。
「誰かのことを全て知るのは、いいことに思えるかもしれない。」
そう前置きをして「でも、知り過ぎない方がいいんだよ」と。
結局は、彼女の過去・人間関係を知ることになり、
元の関係に戻ることはなかった。
人間、生きていく上で、誰も知らないような「秘密」も必要、
そう教えられたような気がする。
好きだから、愛しているから・・あなたのすべてが知りたい。
そういう台詞は、ラブストーリーのワンシーンとしては素敵だけれど、
現実としては、息が詰まってしまい、ストレスが溜まることもあり得る。
適当な「秘密」と適当な「謎」の部分を持ち合わせた方が、
より親しい関係が築けるかもしれない。
これは、人間関係の大前提として、記憶に留めたい。
タイトルの「ヒア アフター」(Hereafter)は、辞書によると
「来世」の意味なんだろうけれど、あまり関係なかったなぁ。
「死後の世界」の方が、スッキリするのになぁ。
PS.
津波のシーンを始め、目を背けたくなる場面の連続。
たぶん、3.11の後では、作れなかったのではないだろうか。
クリントのトリック
美術では神・天使・神話および王侯貴族をモデルとしていたが、江戸の浮世絵は庶民を描き、十九世紀の印象派も普通の人々を題材とした。文藝も神話・伝説・英雄譚にはじまり、やがて普通の市民を描くようになる。バルザックもディケンズも十九世紀の人だった。
二十世紀に誕生した大衆芸術である映画では、いまも英雄や正義あるいは悪のヒーローが好んで描かれる。スパイ・連続猟奇殺人犯・銀行強盗・殺し屋・マフィアのドン。この映画の三人の主人公も特殊な人物である。
津波に襲われ臨死体験をしたことが契機となって、キャリアも愛人も失うフランスの人気ニュースキャスターの女。幼い頃に患った病のために臨死体験をし、霊能力に目覚め、霊媒師として働いていたがその仕事を嫌い、工場に勤めてもリストラされるアメリカ人の男。ヘロイン中毒の母を持ち、交通事故で二子の兄を失い、里親に預けられるイギリスの少年。三人の人物設定は、程度の差はあれ、バットマンやスパイダーマンと同じように特殊だ。
しかし物語には二重底の仕掛けがあり、三人に共通するものを探れば、ある過去のできごと(病気・天災・事故)を起点として、現在に大切なもの(人生・仕事・キャリア・恋人・愛人・兄・母)を喪失し、未来に希望を見いだせない人物が立ち現れる。これは誰にでも起こり得ることで、人間の存在に共通する普遍的な苦悩である。ここで特殊に見えた三人は普通の人々に変化する。
死もまた同じように、時と人を選ばない。他者の死に際して、人は問いかけ、答えを求める。答えも説明も最初から何もありはしない、と言い切れる人は稀だろう。答えを宗教に求める人もいれば、心療カウンセラーに求める人もいる。霊媒師に求める人もいる。そして、死に連れ去られた他者が、どこかにいまも存続することを願う。死者を忘れず、死者に見守られることを願う。死者をゆるし、ゆるされることを願う。「お兄さまは天使とともにいる」と答える神父と、「お父さまは君を見守っている」と答えるイカサマ霊媒師がそれぞれ果たす役割に大きな違いはない。
アメリカの男が霊媒を行うとき、ルールを立てて、被験者に質問にはイエスかノーで答えるよう促す。これは法廷において検事および弁護人が被告・原告・証人を尋問するときに使われる手法で、それぞれの目的(有罪か無罪か)に必要のない余分な情報を排除することを目的とする。では霊媒師が排除したかった情報とは何か。それは、津波のように押し寄せる被験者の苦悩と感情の束である。アメリカの男は自分が溺れてしまう前に、平静な人生を取り戻そうと、霊媒師の仕事を絶った。
臨死体験と霊媒という設定は、物語の切り口であって、主題ではない。臨死体験を数多く検証しても、霊魂の不滅や死後の世界の存在を証明することはできない。千人のイカサマ霊媒師の中に一人の有能な霊媒師を見つけられたとしても、何も証明はされない。イギリスの少年がアメリカの男はあの女の人が好きだと直感したように、アメリカの男も他者の感情や苦悩を感知する能力に長けているのかもしれない。イギリスの少年が霊媒のルールを破って、寂しい、哀しい、ひとりにしないで、と兄の霊に泣きながら訴えるとき、アメリカの男はもう霊媒師ではなく、少年の苦悩を分かち合い、二人ながらの痛みを癒そうと努める一人の人間にかえる。
他者の死に際して、人が説明や答えを求めるのは、この先を生きてゆくためである。悲惨な現実を受け入れて生きてゆく。答えを求めて人は尋ね歩く。それぞれが得られる答えの姿はさまざまだが、答えには同じ名がつくらしい。街のカフェテラスで待つアメリカの男がフランスの女の姿を目にしたとき、男の脳裏に鮮明な映像が流れる。霊媒師が予知能力を発揮したと見る観客もいるかもしれない。だが、このラストシーンは、男が見る幻こそ求めている答えだと静かに差し出し、その幻を「希望」と名づけていた。
女と握手を交わし、掌を重ね合っても、もう男は悪夢を見ない。
全140件中、61~80件目を表示