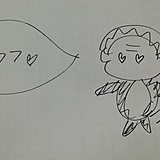ノルウェイの森のレビュー・感想・評価
全74件中、21~40件目を表示
文学的な匂いのする秀作
村上春樹さんの小説の雰囲気がすごくでていて文学的な匂いのする映画です。
美しい映像とセリフのひとつひとつと役者の方々の演技も村上春樹さんの世界観をとても大切にされていて文学的に徹しているように思います。
ベストセラー小説の映像化として成功しているのではないでしょうか。
映像はきれい。映像はね。 ホンマ純文学を映像化しているのがプンプン...
悪くないです。
いつかそれがぽろぽろとこぼれ落ちていく日が来る。
雪の結晶のように繊細であって触れると消えてなくなってしまう。
だから一秒一秒を丁寧に扱ってあげなくてはならない映画だった。
どこで停止ボタンを押してもポストカードになるであろう綺麗な映像。
アップの描写が多いのは後ろをぼかすためであって、それは人物だけをより浮かび上がらせるため。
原作を読んだあとに映画を観る、というのは初めてだった。
この場面でワタナベはこう考えているんだよなぁ、と記憶と答えあわせをする感覚。
やはり印象強く残っているのに端折られている部分が多すぎる。
突撃隊がいかに変人であるか。(劇中では名前さえもふれられない)なぜレイコさんが施設にいるのか。緑とワタナベが初めてキスをしたときに聞こえていたサイレンの音、など。
本を読んでいない人は、映画を理解できるのだろうか。
あまりにぶつ切りな感覚だったので、本当はすべてのシーンを撮影しているのだけれど、時間の都合上見どころを厳選したダイジェスト版、といった感じだった。
この映画では街が描かれることはなかった。
シーンはほとんどが家の中か自然の中。すごく閉鎖的で、それがワタナベと直子のまわりとの人間関係を浮かび上がらせていた。
大切な人を失った苦しみは、優しさやぬくもりなどほかのもので癒すことはできない。苦しみを受け入れて、そこから学ぶことしかできない。その学んだことは、次にやってくる悲しみに対して何の力も持たないけれど。
わたしたちはいま、両手いっぱいに大切な人たちを抱えている。
いつかそれがぽろぽろとこぼれ落ちていく日が来る。
その日のことを考えると恐ろしくてたまらない。
そしていまがどれほど幸せであるかをかみしめなくてはならない。
2011/1/21 @多摩センター
浮遊感から溢れる美しい台詞
壮大な生の美
暗すぎ
Kiko Mizuharaって美しいな。
原作を読んだ時、TSUBAKIのCMで見かけたモデルの風貌を完全に当てはめていた。
水原希子。
映画ノルウェイの森のキャスティングを知った時、ボクのイメージと一致していたことでなんだか陽気になった。
それが観ようと思ったきっかけ。
彼女、美しいね。ボクは大好きだ。
ミドリって女性も大好きだ。長い独白は格好がつくし、CANのShe Brings The Rainがかかるレコード店なんて喋らなくたって蠱惑的だ。
でも、ボクはミドリがそんな子だってことを原作読んでいたときからわかってるんだ。つまり希子は、すげぇ納得して観れたんだ。ところどころクエスチョンマークが頭に浮かびはしたけれど、概ね会心の演技だったと思う。
残念ながら、ミドリが登場してくるまでの何分間かは苦痛だった。松山ケンイチ君は、ボクの思った僕(ワタナベ君)と微かに、でも致命的にずれていた。表情が、違かった。挙動のどれをとっても、違う気がした。なんて酷い映画だ、春樹への冒涜だ、とすら思った。
ただそれは思い直す。
ボクはしっかりと最後までこの映画を見通したし、その苦痛は今はない(ような気がする)。
ミドリという女性が現れて歯車が動き出した感じだろうか。
あまりに感傷的な世界に唯一ボクらを繋ぎ止めてくれたのがミドリだった。そう、だから彼女がいなければ世界はもっと感傷的になってしまっていたはずだ。(彼女、登場したての頃はセンチメンタルなかっこつけみたいなのをしてたからボクは鼻持ちならない気分だったけどね、段々よくなった)。
だから、そういった点でミドリが登場するまでのシーンもあれで悪くはないんだよね、多分。
ほかの方のレビューを眺めさせてもらって気がついたことがある。ボクは今17だからもちろん60年代70年代は生きてないし、当時の学生が吸っていた空気の味なんて知りもしない。ボクはあくまでボクが知る世界の中でしか春樹の作品を読むことはできないんだな。もっと早く気がついてもいいようなことだけれど、今更気がついたボクにはちょっとしたショックだった。
けれどもこの作品を様々に解釈する人がいて、そこに大きな年代の幅があって、こうしてボクはボクの見ていた春樹ではない春樹を眺める術を手に入れることができたわけでもある。「ボクは本質的に楽天的な人間なんだよ。」なんてね。
そういった点で、春樹の作品を監督のもちうる感性で表現しきるというのは、たくさんの批評が寄せられるだけいいことなのだと思う。
補記:まぁ原作読まないと全くわからなさそうなのはいかんかなぁと。
全74件中、21~40件目を表示