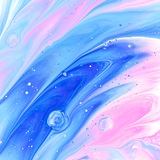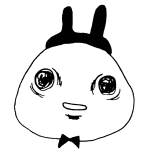ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1のレビュー・感想・評価
全108件中、1~20件目を表示
Time to Wrap It Up
In my view it wasn't really necessary to only split the final adaptation into two films, but with something as popular as the Wizarding World Hollywood must cash every last drop from the cow. Much of the drama is internal between Ron, Harry, and Hermione on a long, unhappy camping trip. Voldemort isn't seen until the end. The action and VFX are at their best here, so that's the high point.
試される三人の絆‼️
いよいよ「ハリー・ポッター」シリーズの最終章へ‼️前編である今作ではダンブルドアの意思を受け継いで、ヴォルデモートを倒すために必要な「分霊箱」を探す旅の中で、ハリー、ロン、ハーマイオニーの絆が崩壊寸前に‼️要はロンの勘違いなんですけど‼️そんな三人の様子を見て勝ち誇った笑みを浮かべるヴォルデモートの姿で締め‼️後編に向けて盛り上がるどころか、じれったいし、イライラしてしまった初見時の記憶が・・・‼️「LOTR」三部作や「インフィニティ・ウォー」の時は、胸トキメかせて待ってたんですが・・・‼️
助走長すぎて疲れるんだが?
前後編に分割されて最終章なんだから、それはそれは濃厚な情報の洪水にで丁寧ていねいに掘り下げに掘り下げたストーリ展開するんだろうな?そうなんだろ!?
って思ってたけどそんなことなかったぜ!!
①全然話進まないじゃん
ずっと逃げてキャンプしてるだけじゃん
ここにきて三角関係とかいいって。。。話進めろよ
争って和解して一致団結だ!ってパートは前作までの積み重ねで終わってるじゃん。
いままやってきたじゃん。
ここにきてソコを掘るなって
ペンダントでギスるんだったらつけるなって机とか鞄に置いとけ?
身に着けてないとダメなん?
②新キャラ出すぎじゃん
しかもそんな必要だった?分割した割に描写が丁寧じゃねーな
③結婚式盛大にやりすぎじゃない?
身内だけで、こじんまりとやるんかなって思ってたら、
思いのほか盛大にやりやがるの。
こんなご時世でも儀式として結婚式は大事なのは分かる
身内だけで内々にやるなら分かる
普通に3親等以上の人を呼ぶぜ!←わからない
音楽とか流しながら盛大にやるぜ!←わからない
普通に身内以外も呼んでやがんの!
そりゃ死喰い人の皆さんも駆けつけちゃうよ!
お祝いに死の呪文という盛大な花火を上げてくれますよ!
アホなんかこいつら?
関わる人が増えれば増えるほど情報は洩れるだろ
だいたい誰が死喰い人かもハッキリしないってのに
あの場にいる人だけでやればいいのに。。。なんだかなー
④ニワトコの杖警備ザルすぎ問題
ダンブルドア先生の持ち物だけど一緒に埋葬して墓暴かれる対策してないんだ
先生ってば遺言書くなら杖の事もキチンとするべきだったんじゃないの?
秘宝の一つを所持しておきながら何も対策してないってどういうことなん?
ヴォルデモートに杖単体を探知する術は無かったようなので隠したらいいのにな。
3人に渡す遺品の中にどうにかして紛れ込ませろよ!スニッチに石入れたかんじでどうにかして紛れ込ませる物品作れよ!
⑤死の秘宝そろえたところで、どうなるんだ問題
どうなんの?
とりあえず分霊箱あつめて壊そうな
ロンどうした?
【81.2】ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 映画レビュー
作品の完成度
本作は、シリーズ全体を一つの壮大な物語として捉えた上で、その終結に向けての重要な「つなぎ」としての役割を完璧に果たしている。最終章の膨大な情報量と物語の密度を単一の映画に収めることは不可能であり、二部構成という選択は必然的で、この判断が作品の完成度を格段に高めている。特にPART1は、ハリーたちが保護を失い、外部の脅威にさらされながら、内面的な葛藤や友情の危機に直面する過程を丁寧に描き出すことに成功している。
従来のシリーズが持つ魔法のきらめきやホグワーツの温かい雰囲気を意図的に排除し、代わりに冷たい現実と孤独、絶望を前面に押し出すことで、物語の終焉に向けた悲壮感を醸成。これは商業的な成功よりも、原作の精神を忠実に映像化することを優先した決断であり、その結果、シリーズ全体のトーンに深みを与えた。
しかし、その一方で、物語が分霊箱探しの旅に終始するため、アクションシーンの連続性やドラマティックな展開は抑えられている。観客によっては、物語の進行が遅く感じられる可能性も否めない。だが、この「静」の部分こそが本作の真骨頂。三人称視点から三人の視点へと切り替えることで、内面的な葛藤や疑念がより鮮明に描き出され、観客は彼らの苦悩を追体験する。
物語のクライマックスとなるドビーの死と、その後のハリーの行動は、単なる感情的な盛り上がりを超え、ハリーが真の指導者として立ち上がる覚悟を決める、物語上最も重要なターニングポイントとして機能。このような、登場人物の精神的成長を深く掘り下げることに成功した点で、本作は単なる「続編」ではなく、最終章を語る上で不可欠な序章としての高い完成度を誇る。
監督・演出・編集
監督はシリーズ後半を担ってきたデヴィッド・イェーツ。彼の演出は、登場人物の感情を巧みに捉えることに長けており、本作でもその手腕が存分に発揮されている。特に、三人だけの旅路において、言葉を交わさずとも伝わるキャラクターの心情や、閉塞感漂う自然の描写が秀逸だ。
編集のマーク・デイは、物語の緩急をつけながらも、不穏な空気を途切れることなく持続させることに成功。特に、分霊箱の影響でロンが精神的に追い詰められていくシーンや、「三人兄弟の物語」のアニメーションパートの挿入は、物語に奥行きと多様な視点をもたらす効果的な演出だった。
キャスティング・役者の演技
主演の3人は、長年のシリーズで培ったキャラクターへの深い理解と、個々の成長をスクリーン上で見事に体現している。
主演:ダニエル・ラドクリフ(ハリー・ポッター役)
シリーズを通して、ハリーの成長を演じ続けてきたダニエル・ラドクリフの演技は、本作で一つの頂点に達した。両親の墓の前で佇むシーンや、ドビーを失った悲しみを押し殺す表情など、言葉に頼らない内面的な演技が格段に深化。分霊箱の破壊に際して見せる怒りや決意は、もはや子供の英雄ではなく、運命に立ち向かう一人の青年として、観客に強い印象を残す。特に、孤独と重圧に苛まれながらも、ヴォルデモート打倒という使命を全うしようとする彼の覚悟は、その繊細な表情の変化からひしひしと伝わってくる。
助演:ルパート・グリント(ロン・ウィーズリー役)
ロンのキャラクターは、シリーズを通じてのコメディリリーフ的な役割から一転、本作では分霊箱の負の力に影響され、友情に亀裂を生じさせる重要な役どころを担う。ルパート・グリントは、その内面的な葛藤と嫉妬、そして後悔を見事に演じきった。特に、ハーマイオニーとの間の緊張感や、一人きりになってからの孤独感は、彼の表情や佇まいから深く感じられる。最終的にハリーと和解するシーンでの、彼の脆弱さと誠実さが混在する演技は、観客の共感を誘う。
助演:ヘレナ・ボナム=カーター(ベラトリックス・レストレンジ役)
狂気に満ちた死喰い人ベラトリックスを演じるヘレナ・ボナム=カーターは、登場する度に画面の空気を一変させる。彼女の演技は、単なる悪役の域を超え、純粋な悪意と享楽的な残虐さを体現。ドビーを殺害するシーンの無慈悲な笑みや、ハリーたちを執拗に追い詰める姿は、観客に恐怖を植え付ける。その特異なキャラクター造形と演技は、シリーズのダークファンタジーとしての側面を強調する上で不可欠な存在だ。
助演:アラン・リックマン(セブルス・スネイプ役)
シリーズ最後の最後でその真実が明かされるスネイプ役のアラン・リックマンは、本作では冒頭のシーンのみの出演。しかし、その短い登場時間でさえ、彼の存在感は圧倒的だ。ヴォルデモートの傍らで静かに佇む姿、そしてハリーの宿敵としての冷徹な眼差しは、観客の心に深い印象を残す。多くを語らずとも、その表情から読み取れる複雑な感情は、後の物語の真実を知る上での重要な伏線として機能する。
脚本・ストーリー
スティーヴ・クローヴスによる脚本は、原作の膨大な物語を忠実に抽出し、映画的な構成に再構築している。最終章を二部に分割したことで、原作の持つ物語の細部や登場人物の心理描写を省略することなく描くことが可能になった。特に、ハリーたちがホグワーツを離れ、魔法界の隅々を彷徨するロードムービー的な構成は、世界の広がりと同時に、彼らが置かれた絶望的な状況を視覚的に訴えかける。
映像・美術衣装
美術監督スチュアート・クレイグと衣装デザイナーのジェイニー・ティーマイムは、シリーズを通じて築き上げてきた世界観をさらに深化。特に、本作では従来の華やかな魔法世界から一転、退廃的で荒涼とした風景が中心となる。ハリーたちがキャンプ生活を送る自然の描写は、彼らの孤独を象徴し、マルフォイ邸や魔法省の描写は、ヴォルデモートの支配下にある世界の陰鬱さを表現。細部にまでこだわった美術と衣装は、物語のトーンを決定づける上で重要な役割を果たしている。
音楽
音楽は、シリーズ初参加となるアレクサンドル・デスプラが担当。これまでのジョン・ウィリアムズやニコラス・フーパーとは一線を画し、内省的で繊細なスコアを構築。特に、ハリー、ロン、ハーマイオニーの三人の旅を彩る、静かで美しい旋律は、彼らの孤独や不安を強調する。有名な「ヘドウィグのテーマ」もさりげなく挿入され、シリーズとの連続性を保ちつつも、独自の音楽世界を確立。アカデミー賞の音楽賞にノミネートされることはなかったものの、そのスコアは高い評価を得た。主題歌はなし。
アカデミー賞および主要な映画祭での評価
本作は、第83回アカデミー賞において美術監督賞と視覚効果賞にノミネート。このノミネートは、本作の美術・映像面での技術的な完成度の高さを証明する。特に、ハリーたちが旅をする様々なロケーションや、ファンタジーと現実が融合した独自の美術デザインは、映画界全体から高く評価された。
作品
監督 デビッド・イェーツ 113.5×0.715 81.2
編集
主演 ダニエル・ラドクリフB8×3
助演 ルパート・グリント B8
脚本・ストーリー デビッド・イェーツ B+7.5×7
撮影・映像 エドゥアルド・セラ S10
美術・衣装 美術
スチュアート・クレイグ
衣装
ジャイニー・テマイム S10
音楽 音楽
アレクサンドル・デプラ
メインテーマ
ジョン・ウィリアムズ A9
受け身の主人公で、ひたすら長く感じた🧙♀️
ハリー・ポッターが狙われていて常に襲撃を受けますが、主人公側は「死を制する者」について調べたりして、現実の敵に打って出ない為、受け身の状況がひたすら続いて、しんどいです。今までのシリーズで、勇気や魔法攻撃力は身に着けなかったみたいですし、仲間も死んだのに未反省で、主人公てしてヤバイです。スネイプがホグワーツの校長に就任した事しか、欲しい情報がありませんでした。
世界的ベストセラー作品の第7作
世界的ベストセラー作品の第7作である「ハリーポッターと死の秘宝Part1」。
ハリーポッターシリーズのラストタイトルであり、物語の最終章となる作品です!
Part1の見どころは何といってもハリー・ロン・ハーマイオニーの人間関係。
分霊箱をめぐる戦いの中で、仲間たちの葛藤や想い。その中で垣間見るハリーのリーダーシップやロンやハーマイオニーの決断の数々は見ものです!
自分だったらどう行動するか?誰に焦点を当ててみるか?で見え方が違ってくるのもおもしろいポイントです。
そして、なんといってもラストシーンが衝撃的すぎる‥!
あんなことが起きてしまうなんて…。感情が爆発してしまった人も多いのではないでしょうか?
Part1を見たらすぐにPart2が観たくなる!
まだご覧になってない方はぜひご覧ください。
亀裂によってさらに深まる絆
ハリー・ポッター・シリーズ第7作。
"金曜ロードショー" で鑑賞。
原作は未読。
分霊箱を探す旅を始めたハリー一行に立ち塞がる危機また危機。闇の帝王はどこまでも狡猾で、絆に入った亀裂にいったいどうなっちゃうのとハラハラ。亀裂が絆をさらに強固なものにする展開にはなるほどとなり、同時にホッとさせられた。
前編と云うこともあって、テンポが悪く冗長の気味は拭えないが、後編の期待値を上げるに充分な役割を果たしている。
特別上映 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1(吹替)で観賞
決戦に向けた最終章の前編!懐かしい場所や登場人物が出てきていよいよ...
決戦に向けた最終章の前編!懐かしい場所や登場人物が出てきていよいよ総力戦、という盛り上がりがありました。
ヴォルデモート卿を倒すという目的のために奔走するハリーたちですが、必要なことはわかっているのにどうしたらいいのかわからないという焦りに共感する人も多いだろうなと思いました。
かくいう私もその一人で、鑑賞後にはキャリアややりたい事に志を持ちながらもがいていた頃を思い出しました。
これをどう乗り越えていくのか?というところで終わる前編、公開当時は後編のPart2が本当に待ち遠しかったです。
17歳という年齢で人生最大の困難と立ち向かうハリー、絶望しながらも決して膝をつかない姿勢に勇気をもらえます。
私も人に勇気を与え続ける存在であるぞ!と改めて決意する時間になりました。
焦らし過ぎ〜
オイッ、ここでもドンパチしねぇのかよ!謎を解き明かしながらアイテムを集め、ヴォルデモートの秘密と武器を揃える内容が続いているが、ハッキリ言ってこの内容ならハリーポッターじゃなくてもいいし、魔法関係なく無い?便利な魔法をチョイチョイ使うだけで、バトルは痺れろ!、石になれ!、ふっ飛べ!位じゃん。敵側は、息絶えよ!か、何かビリビリするやつバチバチ放つだけだし。こういうのを求めてるんじゃないんだよね〜。まぁ、パート2で覚醒して何かする流れっぽいが、最後まで観て最終評価を決めますがね。
この映画に登場したルーナのパパ、マルフォイのパパと見た目被ってない?結婚式の時、ルーナとダンスしてるの観た時、何で?って思ったわ。あと、ハーマイオニーの成長が進むにつれて世の中の男性達から大きな心の声が俺には聞こえてくる。それは、何でロンなん?笑
part2への橋掛
他のタイトルと比較すると地味な印象。
大きく盛り上がるシーンが特別なく、part2に向けた準備回という感じがした。
ハリーポッターが終わるらしいと聞いてとりあえず今作だけ映画館へ行ってみた人は、全然面白くなかったかも。
私はAmazonプライムで賢者の石から通して見ており、分からないことがあれば一時停止して調べているのでゆっくりマイペースに解釈しながら楽しめているが
回を追うごとに説明不足が酷く目立つようになり、原作をよく知る人だけが付いていけるレベルになってしまっているように感じる。内容が複雑というだけではなく、配慮に欠けているなと思う。
一番これはちょっとと思ったのは、ハリーが突然に持ち出した鏡の破片。原作ではシリウスから送られた鏡をハリーが割ってしまう経緯があり、この先も重要な役割を果たすようだけど、映画では本当に何の説明もなく謎のアイテムと化している。これは完全に失敗なのでは…と思ってしまった。贈られるシーンや割ってしまうシーンを入れそびれたとしても、誰かにそれは何?と聞かせて説明するくらいならできそうなのに。
また、細かいところかもしれないけど、日本語字幕の人名がファーストネームとラストネームの片方しか書かれないのにどちらか統一しないのも不親切だなと思った。(セリフではフルネームで呼ばれていることが多い、吹替は見ていないのでわかりません)
字幕だけを追うと誰のことを話しているのか判断し難い。
でもやっと次で最終話。これまでに散りばめられた要素が全て繋がっていくのだろうから、とても楽しみ。調べるうちに相当なネタバレに触れてしまったけど楽しめるといいな。
暗く重い雰囲気
僕はもうホグワーツには戻らない。戦争を前に、三人の旅が始まる。
前提として
・原作は未読。
・『ハリーポッター』シリーズは『~と謎のプリンス』まで視聴済。
・デビッド・イェーツ監督の他作品は『~と不死鳥の騎士団』と『~と謎のプリンス』を視聴済。
前半は「おお!」となるものの、後半からはどうにも盛り上がりに欠ける。
まず前半。ついに「戦争が始まった!」という空気感が素晴らしい。魔法族だけでなくマグルまで集団疎開していく。
最重要人物であるハリーの移動にも、護衛と決死の作戦がつく。さらっと流されたけど、ヘドウィグには泣いた。
そこから先は色々と騒動が続き、分霊箱探しになる。この間に何悶着か起きたり、謎と謎を繋ぎ合わせるターンになるのだが、今まで以上に手探り間のある時間が続く。
"手探り"といっても演出とか描き方というよりも、物語の中でのハリー達の動向の話。暗さとか雰囲気は変わらないのでご安心を。
さて、後半。
三人の逃避行に、仲間割れ(特にロン。)が挟まりつつ、視覚的な激しさは無くなっていく。終盤にかけてひと悶着あるものの、そこからまた落ち着きがち。
PART1だからしょうがないとは言え、物足りなかった。
PART2への盛り上がりがあるわけでもなく、焦燥感をあおられるわけでもない。ただひたすら、パズルのピースだけ追加していくような感じ。フレームに一切はめ込んでいないのだ。
ダレると言われてもしょうがないと思う。
キャラクター描写について。相変わらず良い。逃避行中は外の世界が見えないので、自然と三人組の感情描写と関係性に焦点が合う。
まずはハリー。頼りたい指導者が居ない中、手探りで旅を続けていく。彼としては友達や仲間を誰一人として犠牲にしたくはないのだが、その思いとは裏腹に一人、また一人と犠牲になってしまう。さらには常にヴォルデモートの声が聞こえている状態。なかなかにキツイ。
二人には弱いところを見せまいとし続けるが、思い出や両親の墓などに隠れて縋っている様子がまだ一人の青年であることを想起させる。
次作で全てから解放される様子を観たい。
余談だが、"七人のポッター"はダニエル・ラドクリフの面白い部分が出ているのでかなり好き。
次にロン。前作のラストで二人から一歩離れて立っていたところに違和感があったが、しっかりと回収されている。
要は決心がついていないのだ。家族を助けたいから戦争に行く一人の青年。もちろんハーマイオニーのこともある。だが、二人ほどの覚悟はない。
仲間割れを引き起こしてから、戻ってきた瞬間のイベントは必見。障害を乗り越えたわけではないものの、それでも二人のところに戻る決心をつけた彼の心情に拍手したい。
次作で戦争とは関係ない世界に居る彼を観たい。あと、ハーマイオニーと暮らしている様子とか。ハーマイオニーを大事にしろよ?
そしてハーマイオニー。一番活躍してるかも。細かなサポート面はお手の物。それどころか命の危機を何度も助けてくれる。強くない??
でもやっぱりロンに激情をぶつけまくってる彼女が愛おしい。ロンがケガをした時の焦りようと、ロンが離反したあとの落ち込みようと、帰ってきたロンにキレる様子と、弁明するロン(名演説)に慈しみの視線を送る様子。全てが素晴らしい。能力とか活躍はピカイチだが、こういったところをみると彼女も一人の青年であることを思い出させる。
次作でロンと暮らしている様子が観たい。
この三人のキャラクター描写はピカイチだと思う。『~と謎のプリンス』での描写が、このためにあったのならすごく納得がいく。
しかし良くも悪くも周りの状況があまり描かれないので、他の生徒たちの状況も観られない。ネビルとかもっと観たかったよ? ドラコは両親との会話が観られるので満足。
そういえばルーナの父親も出てくるのだが、彼がすごく良かった。
最初の"ちょっとズレてるお父さん"が"憔悴しきった、娘を守りたいだけのお父さん"に急変してしまった様子が痛ましい。
こういった、戦争被害者が描かれるのはかなり好印象。ヴォルデモート勢への怒りにもつながる。
前回よりも目的が分かりやすく、そういった面ではついていきやすかった。
見どころはいくつか(ポリジュース薬など)あるが、それよりかは要素要素をつなげたり、準備する物語なので、次作が今作の面白さを決めると言っても過言ではないと思う。
それだけ次作に投げたものが多いということだ。どうなるかな、最終作。
三人組の行く末を見守りたくなった。そんな作品。
全108件中、1~20件目を表示