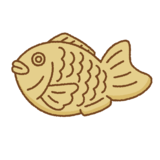ブレードランナー ファイナル・カットのレビュー・感想・評価
全171件中、1~20件目を表示
もはや新作と見まごうクリアさ。
『ブレードランナー』に関しては、リドリー・スコットが劇場公開バージョンで不満だった箇所を片っ端から直した「最終版」で止まっていたので、「ファイナル・カット」はデジタルリマスターくらいに思っていた。が、オールドファンにすれば冒頭の2019年のロサンゼルスを俯瞰で捉えた特撮ショットからして、仰天モノではないだろうか。
まず驚いたのはタイレル社のピラミッドビルの窓がこんなにも多かったっけ?ということ。昔観たバージョンのフィルムの質感とはまったく別種の、あまりにも細密でクリアな映像。ミニチュアのピラミッドに針の穴のように空けられた窓から漏れる光のひとつひとつが、猛烈に粒立っているのである。
特に65㎜で撮られた特撮シーンは一事が万事この調子で、まるで『ブレードランナー』を最新の撮影機材で寸分たがわず再現したようにすら見える。物語や展開的には「最終版」とほぼ同じだが、スコットこだわりのディテールを味わうためには一番のバージョンであることは間違いなかろう。
一番好きなSF映画かも
ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバルで鑑賞。
平日月曜日ですが、客席は多くの観客で埋まっていた。みんな好きなんだなあ。
上映前に戸田奈津子さんとフリーアナの笠井信輔さんがトークショーをしてました。
二人の興味深い話がたくさん聞けたのもよかった。ただ、ちょっと時間が長かったので、途中でトイレに行くことにならないか心配になった。
日本公開当時は17歳の高校生。SF好きが決定付けられた作品。デザインを担当したシド・ミードの絵には魅せられました。未来のロサンゼルスの都市風景、人々の衣装、乗り物、部屋の内装などのデザインが、何というかセンスが良くて素晴らしかった。映画雑誌のスクリーンやSF専門誌スターログなどを買い漁って見てました。
2023年のシネマコンサートに行って、なんとかもう一度劇場で観たいと思っていましたが、ようやく劇場で再鑑賞することができた。
高校生の時はSF的な要素にばかり目が行っていたが、登場人物の心の動きなどが実に味わい深い作品と再認識した。
ブレードランナー ファイナル・カット
WOWOWで死ぬまでに観たい1001本となっていたので観たがその価値はない
作りはグロテスクで初見はわかりにくい為観るのをやめ、そのまま録画を消そうかと思ったが、別日に観直した。
人間の勝手で感情を持つ人造人間を作り、見たくない・やりたくないような汚い酷い事をやらせ、苦しめた事で人造人間達が反逆をし、人間とやり合う話。
人間であれ、それ以外であれ、嫌な事を押し付け奴隷として無理やりやらせる事へのアンチテーゼというテーマは悪くないが、描写がグロテスクであり、あらすじを見て補完しないとわかりにくい点が評価としては大きなマイナス。日本人らしき店員とうどんが、日本と中国ごちゃまぜの店で出てきたり、カタカナもどき等が出てくるのはアメリカだからなのか、監督の日本の認識がそれまでなのかはわからない。パトカーになぜか警察の文字も併記されているが、日本語としてなのか中国語としてなのかもわからない(話の中で中国も出てくる為なおさら)。とにかく所々になぜか日本風が散りばめられている。
人造人間の苦しみには感情が揺さぶられたが、全体としてそれほどの作品ではない。
見入るクオリティ・だから浮かぶ「はっ!?」「えっ!?」「ふぇっ!?」
初鑑賞は3年前のことになります、アマプラでしたかね。
ストーリーは「逃亡したアンドロイドの抹殺」というシンプルなものなんですが世界観の作り込みがすごい。ゲームの「サイバーパンク2077」と比べても全然遜色ない世界観。空ビュンビュン飛び回る車・ところどころの和風・大気汚染された暗い世界観は全部元ネタはコレでしょうね。よくリドリー・スコットを始め制作陣は思いついたなぁ。
だからこそクライマックス〜エンドロール直前の展開にはちょっと驚きです。SFのメジャー作であるマーベル、スター・ウォーズとは真逆をいく展開。一つの物語としてわかりやすいベタ展開を意識せず、歌でハッピーエンドにしなくてもいい、自由な作風が作れた時代の良作です。これはおもしろい。
スタイリッシュな映像と音楽で人間の根源を問いかけるSF映画史上に残る作品
最初に見たのは10代だったと思います。スタイリッシュな映像と音楽がとても印象的でした。全編が夜かひどい雨天で大人向けの映画だと一発で感じました。見終わった後には少し大人になった気になりました。今の若い人たちはどう思うのか気になります。初回版ブレードランナーと大きく違うのは一角獣のシーンがあることです。これは原作を見ないとなかなかわからないと思います。一方、初回版では最後の逃走シーンがありますがそこでの語りでこの映画のテーマを言ってくれます。西洋思想によく出てくる自分はどこから来て、自分は何で、自分はどこに行くのか?で、あえてそれを言うのがいいのか言わないのがいいのかそれぞれ人の好みでしょう。あるにしろないにしろ人間とは何、神は何、命とは何、心とは何、を考えさせられます。若いうちに見たこともあり、映画の良さもあり、この映画のテーマをよく考えるようになりました。人生で忘れてはならないことだと思います。とにもかくにも心に残る映画でした。エイリアンに続きこのブレードランナーを出してリドリー・スコットを本当に好きになりました。
This is Tokyo
リドリースコット監督
これおもしろいと言うより発想が素晴らしいと思って観ていたら、不思議な世界観にどんどん引き込まれていって見ているだけで楽しくなった。レプリカント=アンドロイド、今ではAIだが1982年にこんな作品を作っていたことが信じられない。素晴らしい
いいものはいい
さらに美しく、難解になった芸術作品
オリジナル版は昨日も鑑賞していましたが、比較のために、Amazonプライムビデオで配信中の今作(ファイナル・カット版)と、Huluで配信中のオリジナル版を並べて同時再生して違いを確認しました。
目に指を入れるグロテスクな描写が長くなり、デッカードのユニコーンの夢が追加され、クライマックスの鳩が飛ぶ場面は青空ではなく曇り空に変更されていました。
画面のコントラストや色彩、登場人物にあたる光の強さ等が、微調整されています。
背景を奥まで鮮明に見えるようにしたり、逆に、敢えて暗めにして見えにくくしたり、僅かですがデッカードのシーンを削ったり追加したりもしていましたが、おおすじは同じです。
ラスト、デッカードがユニコーンの折り紙を拾って、納得したような顔をしながらレイチェイルの傍に行くところで終わります。
デッカード(ハリソン・フォード)によるナレーションが無くなったため、解釈の自由度が高まりました。
設定は好きなのですが…
設定はすごい好きです。
1982年の時に現代社会においても通用するような設定であるのはとてもすごいなと思いました。
でもその後のストーリーの展開はそこまででした。
最後の戦いのロイ・バティーはとういう心情だったの?
さっきまで今までずっといた女のロボット、仲間のロボットを殺され、悲しげな表情を浮かべていた。
なのに次になったらデッカードにまだ遊びたいから死ぬなと言って陽気な感じになったり…
分からなかったです。
アクションと書いてあったので、そこも期待していたけど、
あのバク転で来るシーン以外カッコよさをあんまり感じられない。
ラストバトルのデッカードもなんかずっと弱腰で、どう観ていいか分からなかった。
これはアクションというか痛々しい暴力に感じた。
お話も世界観も素晴らしい
初公開から43年も経ちましたが、一切CGを使用していないにも関わらず、全く古さを感じさせないのは驚きでしたね。
新文芸坐さんにて公開25周年を記念してリドリー・スコット監督自身によって編集された『ブレードランナー ファイナル・カット』(2007)を鑑賞。
『ブレードランナー ファイナル・カット』(2007)
劇場初公開は1982年ですが、本日鑑賞したのは公開25周年を記念してリドリー・スコット監督自ら編集した「ファイナル・カット」版。日本でも新宿バルト9さんで2週間限定公開が決定、慌てて観に行きましたね。
その後もブルーレイも購入したのですが、やっぱり大きなスクリーンでの鑑賞は良いですね。
初公開から43年も経ちましたが、一切CGを使用していないにも関わらず、全く古さを感じさせないのは驚きでしたね。
ヴァンゲリスのシンセサイザーを活用したサウンド、ジャン・ジロー(メビウス)の衣装デザイン、特撮監督ダグラス・トランブルのVFX、シド・ミードの工業デザインに基づいた美術デザインと多彩な才能が集結し、リドリー・スコット監督がまとめ上げています。
特に降りしきる酸性雨と怪しく光るネオン、『スター・ウォーズ』『エイリアン』でも採用された「ウェザリング(汚し塗装)」や「エイジング(経年変化)」によるリアルさ、日本(歌舞伎町)や香港をイメージした街並みは近未来のディストピア、サイバーパンク空間を見事に表現、細部に至るまで凝っており美麗ですね。
撮影も逆光はじめ光と影のコントラストを実に効果的に活用。潤沢な予算、CGを活用しなくてもきちんと陰影をつけるだけで印象的なシーンが撮れるお手本、好例ですね。
キャストもハリソン・フォード、ルドガー・ハウアーも好演しておりますが、レプリカント・レイチェルを演じたショーン・ヤングの息を呑むほど美しさは特筆すべき点ですね。
長年デッカード(演:ハリソン・フォード)が6人目のレプリカント(人造人間)ではないかなど公開後も熱く議論が交わされる本作ですが、映画史に残るSF映画の代表作であることに異論はないですね。
二つで充分ですよ!
あなたの「生命」はだれのもの?
完璧なるヴィジュアルーー世界が地球がアメリカを超えたロスアンジェルスが蠱惑的に明らかに確かに存在する。
この作品はそれだけで存在価値を超越した「何か」を観る者に与える。
その「何か」とは、まさに言語で表現することのできない体験だろう。
この複雑怪奇な時空間では、物語は必要がない。だから、極めてシンプルなのだろう。
且つ、登場人物を演じる俳優群もまるで小道具であるかのように配置され動かされる。まさに「創造主」によって。
レプリカントは執拗に「創造主」を探し求める。
そして、信奉している。それは、タイレル博士を、ではない。
生命の創造主、限りある儚いからこそ輝く生命の創造主。
ロイ(ルトガー・ハウアー)は知っている。生命の起源を。
ロイの生命の起源は「無」である、彼が懸命に生きて「有」したものは生命、そして、また彼が死して「無」となるものは生命なのだろうか。
しかし、ロイはデッカード(ハリソン・フォード)の生命を救うことにより、彼が死す間際に生命を「有」へと転換する。
ロイは知っている。生命の行く末を。
ロイは知っている。デッカードもまたレプリカントである、と。
同胞であるのだ。自身より進化した仲間なのだ。
すべてを悟るデッカードはレイチェル(ショーン・ヤング)を連れて、跳び出す。
レイチェルもまたレプリカントである。
デッカードはレイチェルとともに姿を消す
ーー果たして、どこへ向かうのだろうか。
この世界に「生命」ほど大事なものはない。
それを身をもって顕したロイ。
それを受け取ったデッカード。
レプリカントに宿る「生命」
それこそが、私という人間に宿る「生命」を・・・
これは皮肉ではない。必然なのだ。
この作品は「生命」のひとつの在り方を提示する。
それを、どのように捉えるのかーーー
各人の真価が問われる。
私の本音を述べよう。
「生まれてきて良かった
ーーーいずれ死するとも」
ビジュアル面で突き抜けた、ひとつの美術館
エイリアンに並ぶ、映像面においてリドリー・スコットの狂気を孕んだ拘りが炸裂しまくりの言わずと知れた傑作。ストーリーが哲学的だという評価もあるものの、個人的には映像:ストーリー=9.8:0.2くらい画造りに重きを置かれた、そしてそれがこの2024年になっても他の追随を許さない程にビジュアル面で成功した奇跡的な作品だと思ってます。ワンシーンワンシーンが絵画的で、まるで館内にヴァンゲリスの音楽が流れるリドリー・スコット作品展開催中の美術館に行った気分。その突き抜けたビジュアルが故に、ストーリーはそれらの映像に添えられた解説文のよう。映像に特化した作品は数あれど、本作は別格でそのビジュアルだけで観客を黙らせる、惹き込む、もの凄い魅力を持った作品だと思います。
アルティメットコレクターズエディション買うべし
ファイナルカットはリドリースコット監督の理想に最も忠実なバージョン(個人的にも最高峰のバージョン)であるが、そこに至るまでの紆余曲折についての特典映像がアルティメットコレクターズエディションに収録されている。ファンなら、いかにこのファイナルカットが奇跡のうえに成り立ってるのかを知って涙を流すこと間違いなし。
映画自体のレビューとしては、全てのシーンが何回見てもそのたびにハッと息を漏らす美しさだし、何回見ても新しい発見があるし、何回見てもクライマックスのTears in rainで感動する、そんな完璧な映画です。
全てのSF映画の前に聳り立つ巨大な壁です。
ヴァンゲリスによるサントラも超おすすめです。
レプリカント万歳映画NO1
めっちゃアクション映画なのかなってタイトルだけ見て思ってたけどそんなことなかった
街の至る所に日本のエキスが入ってて面白かった
おじいちゃんが話の通じないやつとして描かれていた
「2つで十分ですよ〜」←あなたは儲かるからいいでしょ
マトリックスみたいに、これ実は僕たちの世界もレプリカント、、、って思わせてくれるSFだった
SFの魅力って突飛な設定が現実と地続きになってると妄想させてくれる所だよね
もし二つの世界を採用するなら、この世界は仮想現実で全員レプリカントというもうなんかどうでもよくなるね
レプリカントが人間よりも表情が豊かで人間であることを疑わなかったりしていて、偽物の方がむしろ本物に近くなるって貝木泥舟みたいだな
あと主人公のハリソンフォードが弱かった
正々堂々映画映えさせながら戦っているレプリカントを拳銃で後ろから撃ってた
全171件中、1~20件目を表示