マクベス(1948)
劇場公開日:1952年3月6日
解説
シェイクスピアの悲劇『マクベス』の2度目の映画化1948年作品で、「ジェーン・エア」に主演してわが国に紹介されたオーソン・ウェルズが製作監督主演し、彼が年少の頃書いた台本(マーキュリー本)に基づいて演出したもの。撮影はジョン・ラッセル、作曲はジャック・イベールの担当。ウェルズをめぐる俳優たちは、ラジオ声優のジャネット・ノーラン、「わが谷は緑なりき」のロディ・マクドウォル、「邪魔者は殺せ」のダン・オハーリー、エドガー・バリア、アースキン・サンフォード、それにウェルズの娘クリストファーらである。
1948年製作/アメリカ
原題または英題:Macbeth
配給:リパブリック日本支社=NCC
劇場公開日:1952年3月6日
あらすじ
3人の魔女の予言を信じ、野望に燃えるマクベス(オーソン・ウェルズ)は、妻(ジャネット・ノーラン)にも唆されて、スコットランドの王ダンカンを殺し、王位を奪った。ダンカンの息子マルコム(ロディ・マクドウォル)と貴族のマクダフ(ダン・オハーリー)はイングランドへ逃れていった。しかしマクベスの後継者は、バンクォ将軍(エドガー・バリア)の息子であることも予言されていた。マクベスはこの予言が実現することを恐れ、バンクォを殺すが、息子フリアンスの方は逃してしまった。それからというもの、マクベス夫妻はバンクォの亡霊に神経をさいなまれてしまった。マクダフに気を付けよと魔女に警告されたマクベスは、彼が逃げ去ってしまっていることを知り、マクダフ夫人とその息子を死刑に処した。一方マクベス夫人はこうした度重なる事件に心も乱れ、自殺した。マクダフとマルコムはマクベスに立ち向かうべく軍隊を引き連れてスコットランドに攻め寄せてきた。バーナム森がダンシネン城までこない限りはマクベスは安全であるという予言によって、バーナム森の枝を楯にしたその軍隊はマクベス勢を圧倒した。だがマクベスは女から生まれたものは誰も傷つけることができないという魔女の予言を聞いて、恐れずに戦場でマクダフと相対した。しかし彼はマクダフが早産で母が死んでから生まれたということを聞き、勇気を失い斬り伏せられた。そしてマルコムはスコットランドの王位についた。
スタッフ・キャスト
- 監督
- オーソン・ウェルズ
- 原作
- ウィリアム・シェークスピア
- 台詞
- ウィリアム・アランド
- 製作
- オーソン・ウェルズ
- 撮影
- ジョン・L・ラッセル
- 美術
- Fred Ritter
- 音楽
- ジャック・イベール
- 録音
- ジョン・マッカーシー
- Garry Harris
- 編集
- Louis Lindsay
- 指揮
- Efrem Kurtz
- アソシエイト・プロデューサー
- リチャード・ウィルソン
-

Macbethオーソン・ウェルズ
-

Lady_Macbethジャネット・ノーラン
-

Macduffダン・オハーリヒー
-

Malcolmロディ・マクドウォール
-

Banquoエドガー・バリア
-

A_ Holy_Fatherアラン・ネイピア
-

Duncanアースキン・サンフォード
-

Rossジョン・ディアクス
-

Lennoxキーヌ・カーティス
-

Lady_Macduffペギー・ウェッバー
-

Siwardライオネル・ブラーム
-

Young_SiwardArchie Heugly
-

FleanceJerry Farber
-

Macduff_Childクリストファー・ウェルズ
-

Doctorモーガン・ファーレイ
-

Gentlewamanルリーン・タトル
-

First_MurdererBrainerd Duffield
-

Second_Mudererウィリアム・アランド
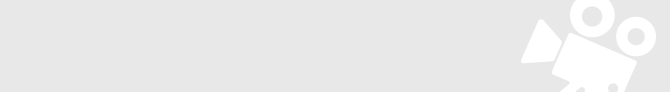
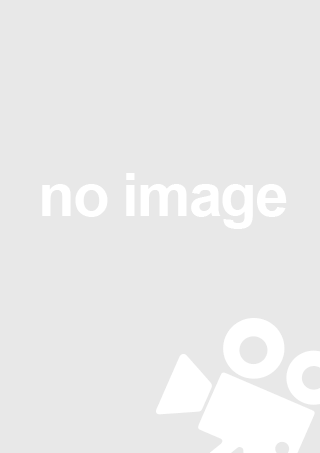
 市民ケーン
市民ケーン 第三の男
第三の男 黒い罠
黒い罠 「鬼滅の刃」無限列車編
「鬼滅の刃」無限列車編 侍タイムスリッパー
侍タイムスリッパー 燃えよ剣
燃えよ剣 忍びの国
忍びの国 引っ越し大名!
引っ越し大名! 関ヶ原
関ヶ原 銀魂 THE FINAL
銀魂 THE FINAL










