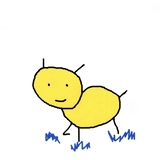愛と哀しみのボレロのレビュー・感想・評価
全47件中、1~20件目を表示
邦題が昭和テイストだけど名作映画の香り高い一品か これを十分に味わうには人生修行が足りない?
えー、なになに「愛と哀しみのボレロ」ってか。なんだか、阿久悠•作詞、平尾昌晃•作曲で唄うは五木ひろしとかの昭和歌謡のヒット曲のタイトルにこんなのがあっても不思議はないよな、と思いつつ、初鑑賞いたしました。まあ「お噂はかねがね」のレベルで、この邦題のクロード•ルルーシュ監督の名作があることは知ってはいましたが、製作されてから40年以上たってから、劇場にて目に触れるともなると、縁があったんだなと感無量です。原題は “Les Uns et les Autres” というそうな。フランス語で「ある人たちとその他の人たち」みたいな意味になる(?)のですが、私はこの言語に詳しくないのでニュアンスはよくわかりません。この作品では四つの家族のほぼ半世紀にわたる歴史が描かれており、その四家族がそれぞれパリ、ベルリン、モスクワ、ニューヨークを拠点としていますので、フランス語を話すパリの人たちからみたら、他の拠点にいる人たちは他人ということにはなるのでしょうね。でも、この四家族には「芸術」という共通項があります。それゆえ、それまでは独自の展開を見せていたそれぞれの人生は、独自であることに変わりはないのだけれど、最後にある一つの場所で一堂に会して交わることとなります。そのことになんだか妙に感動してしまいます。
この作品、ストーリーが追いにくいし、冗長な感じもするけど、名作感は確かにあります。今回、初鑑賞して思ったのは、完成直後の初公開時に当時20代半ばだった私が観てたら、まったく刺さらない退屈な映画だと思っただろうな、ということです。そういう意味で、それなりに人生経験を積んで古希に近い年齢になってから観てよかったとも思ったのですが、なんだか、この映画を本当に味わうには自分はまだ十分に成熟していないのではないかという不思議な感覚にも襲われました。ラストの場面に「悟り」みたいなものを感じて、でも、自分はそこまで悟りきれてはいないよな、と感じたからかもしれません。ともあれ、還暦を過ぎた爺いに「これを味わうにはまだ早い」と思わせた不思議な名作ということで、とりあえず真ん中の星3つにして、またそのうち機会があったら、再鑑賞してみようと思います。
複々線が交わってのボレロの演奏とダンスで圧倒されました
複々線で物語が進みます。
前半は何とか付いていけたけれど、中盤の戦後の話しは、世代が入れ替わるわ、人が歳をとるわ、で観ていて全く混乱しました。
でも、最後のパリでのチャリティーコンサートは、複々線が交わってのボレロの演奏とダンスで圧倒されました。
戦前の興行のシーンはとっても素敵だな。
ラスト10分だけ、もう一度観たい
タイトルなし(ネタバレ)
81年の初公開時に鑑賞して以来なので、40数年ぶりの鑑賞と相成る。
第二次大戦前のパリ、モスクワ、ベルリン、ニューヨーク。
バレリーナ、オーケストラ指揮者、バイオリン奏者とピアニスト、ジャズの作曲家と歌手の妻。
「あのひと、このひと」、多くのひとびとの人生。
いくつかの物語は、同じように繰り返される。
40年代、60年代、80年代と3つの時代・三世代に渡って・・・
といった物語。
なので、ダイジェスト感はあるが、「さわり」で魅せるとはこういう映画をいうのだなぁ、改めて感じた次第。
また、主要な登場人物は音楽関係者なこともあって、全編をフランシス・レイとミシェル・ルグランの音楽が彩る。
楽曲の指揮はルグランが担当している。
二枚組のサントラLP、初公開当時、頻繁に聴きましたなぁ。
さて、初公開時に観た十代の感想が残っているので、以下、引用。
=====
原題の意味は「あのひと、このひと」、そんな映画である。
いろんなひとのいろんな人生をみせてくれる。
劇的なのもあれば、平凡なのもある。
映画は劇的な四つの人生が中心となっているが、これら四つよりも良いのが、平凡な兄弟の話。
ふたりはいつも喧嘩ばかりしているが、それは戦場でも変わらず。
もうすぐ帰れそうだと手紙に書いたものの、戦死。
兄弟の両親はその報せを知るのは、ジェームズ・カーンの帰還パーティを向かいから見る中でのこと。
それだけの話。
しかし、だからこそ良いのだ。
映画は長すぎた。長いのだ。
いろんなひとを描き過ぎ、それがかえって奥行を少なくし、映画を平板にしてしまった。
それにしても音楽は素晴らしい。
ラストの「ラヴェルのボレロ」も素晴らしい。
=====十代の頃に観た感想=====
まぁおおよその感想はそれほど変わらないのだが、歳を経ての分析では、
60年代までは物語も厚みがあって興味深い。
が、80年代に入ってからはアルジェ戦争帰還兵たちの20年後の物語が中心となり、内容が薄く退屈。
初公開当時頻出したベトナム帰還兵物をかなり観たので、それらと比べても薄い感じがします。
その薄さから、最終的に、ユニセフ・赤十字主催のチャリティのボレロに集約されるが、物語的なカタルシスは乏しい。
まぁ、原題が「あのひと、このひと」といった意味なので、物語的結末は不要なのだが。
多くの俳優が二役をこなしているのだが、ジョルジュ・ドンも二役演じていたことに気づいて、これには驚いた。
(冒頭のロシア人バレエ団のセルゲイで、終盤、圧巻のダンスを披露する息子の二役)
もう一つ驚かされたのは、長回し演出。
特に、次のふたつ。
1)大戦後、収容所から帰還するユダヤ人女性バイオリン奏者と、ドイツへ更迭される指揮者が交叉する(実際には交叉しないが)駅ホームと跨線橋のシーン
2)80年代に、その女性バイオリン奏者と息子が再会する施設庭のシーン
いずれもカメラワークに驚かされる。
特に後者は、巻頭のボレロが流れるのだが、巻頭でジョルジュ・ドンの該当箇所の舞踏はみせているので、繰り返しにならないようという作劇を採っている。
ただし、音楽はこのままクライマックスへ続くのでじっくり聴かせようという意図で、この母息子再会シーンに台詞はない。
うまい、と唸る。
十代の頃に印象に残った喧嘩兄弟のエピソード、今回も泣かされた。
ふたりの戦死の報は、陰と陽の対比、台詞なし、窓の外から覗きこむカメラワークと、ここも名シーンです。
傑作というよりも、名作と呼ぶに相応しい映画でした。
クライマックス。ドラマが一気に収束、一堂に会してセッションされていく様は鳥肌が立つ感動
『男と女』(1966)のクロード・ルルーシュ監督の代表作『愛と哀しみのボレロ』(1981)がデジタルリマスター版に生まれ変わりBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下さんにて上映中。
半世紀近くずっと食わず嫌いで「観たふり」をしていた同作品を初鑑賞。
『愛と哀しみのボレロ』(1981)
ポスタービジュアルからずっと男性バレリーナ(バレリーノ)の話と思っていましたが、然に非ず、1930年代から第2次世界大戦で引き裂かれた1940年代、そして1980年代までの50年間をアメリカ(ジャズのビッグバンド)、フランス(キャバレーで知り合うユダヤ人カップル)、ドイツ(ヒトラーに認められるピアニスト)、ロシア(「ボレロ」を課題曲としたオーディションに挑むバレリーナと審査員)のそれぞれ音楽芸術に携わる4家族の2世代、3世代に渡る艱難辛苦のドラマが並行して描かれるグランド・ホテル形式を採用した3時間超えの超大河ドラマ。
例えば、アメリカでは『ゴッドファーザー』で豪放なソニー役を演じたジェームズ・カーンとチャップリンの長女ジェラルディン・チャップリンが最初は夫婦役(親)を演じ、さらに長男、長女役(子ども)の二役も演じるなどかなり混乱。4家族のそれぞれのドラマもドンドン広がっていって、一瞬たりとも気が抜けず、上映中頭はとにかくフル回転。
しかし並行に進んで交わることのなかった4家族のドラマがクライマックスのフランスの赤十字チャリティ公演で一気に収束、一堂に会して、それぞれの家族の音楽芸術の素養(バレエ、クラシック指揮者、歌手)がセッションされていく様は鳥肌が立つ感動でしたね。
フランシス・レイとミシェル・ルグラン両氏合作の音楽も抜群でしたね。
途中はどうなることかと思いましたが、やはり不朽の名作、チャレンジして良かったです。
人生は同じ物語の繰り返し
やっと見ることができました
アカウントが二つできちゃった問題は解決しました。三か月間の新アカウントの間に見た映画のレビューも従来アカウントに引っ越ししましたが、取りこぼしがあったみたいです。この映画レビューもそのようなので書き直してます。
ボレロ、私がライブで見たのはシュトットガルト・バレエ団のマルシア・ハイデだけです。同じ大きな赤テーブルのセット、全て同じ。彼女も本当に素晴らしかった。真っ暗な中、両手が上がりそこに照明が当たりますが、スポットライトが探るんでなくて、ピタ!と光の中にもう手があるんです、日本公演の時の照明さんは!劇光社という、バレエやオペラがメインの照明会社のスタッフの皆さんです。本当に彼らの技術は素晴らしい。
そしてこの映画で初めて全貌を見たジョルジュ・ドンのボレロ、素晴らしい。ベジャールはジョルジュのために振り付けしたのか?と思いこまされるほど、力強くしなやかで美しい。
世代に渡るドラマがついていることはこの映画で初めて知りました。戦争を挟んだ壮大なドラマでした。誰も自分でどこに誰のもとに生まれるのか自分で決めた訳でないのに、いろんなことに翻弄される。極めてアクチュアルで悲しくやるせなくなります。
やはり冗長な感じは否めなかった
「午前十時の映画祭」で鑑賞。
音楽と舞台芸術の世界を中心として、時代に翻弄される人々を描いた超大作。
「いや~、これは今こそ見るべき作品ではないか」と思いながらスクリーンを見つめていた。途中までは。
そう、中盤まではなんとか集中力を保てた。でも終戦からあとのお話が長かった。ダラダラという感じはしなかったが、さすがに長々となにをやってるんだろうという気がしてきた。いっこうに終わる気配がないので、ちょっと不安にさえなりました。
作品の力はじゅうぶんに感じたし、これくらいのボリュームにしないと表現できない内容なのかもしれないなとは思う。
でも、大しておもしろい話でもないので、やはり冗長な感じは否めなかった。
けっきょく、「なんなんだ、この映画は?」という印象を残したままエンド・ロールが流れはじめた。
ひょっとして、赤十字の宣伝映画なのかな?
追記
今期も「午前十時の映画祭」で数々の素晴らしい作品を鑑賞することができました。
関係各位に深く感謝いたします。ありがとうございました。
来期もよろしくね😊
わからんかった
正直よくわかんなかった。
たくさんの登場人物の顔や名前を覚えきれないし、状況的に時代や場所を理解しなければならなかったりで…。
(逆に、今の映画がいかに分かりやすく、親切になっているか、実感できる)
最後に関係者みんな集合して感動のフィナーレって感じなのだろうけど、もし話が理解できていたとしても、あまり感動できなかったんではないかかと思う。
歴史、音楽、バレエなどに造詣が深い人が観たらまた違ったんだろう。
ぼくはいずれもよくわからないので…。
改めて名作と感じました
「午前10時の映画祭」で久しぶりに鑑賞しました。以前観たのは25歳くらいの時だったのですが、スクリーンで観るのは今回が初めてなので、感激でした。
特にジュルジュ•ドンがオペラ座で踊るシーン(キービジュアルのシーン)は美しく、シビれました。亡命のため、飛行機の搭乗口でゲートを飛び越える姿も本当に美しいです。
この映画は、今回鑑賞して改めて名作だと感じました。今の中•高校生や大学生にぜひ観てもらいたいな。
戦争というものがどれほど、勝った側(この映画ではフランス、アメリカ、ロシア)にも、負けた側(ドイツ)にも、1人1人の人生に影を落とすか(それも、戦争に関わった世代だけではなく、その子供の世代にまで影を落とす)について考えさせられます。物語は、その影を乗り越えて明るい未来に向かおうとする人たちの姿を描いているので、救いの光がさすエンディングになっています。それでも、やはりこの映画が描く、戦争というものが人間に落とす残酷な影については、真実だと思います(現実は映画よりもっともっと残酷かと思います)
戦争は、その原因が実は自分たち1人1人の心の中にある限り、今のウクライナでの戦いのように、この世から完全に無くすことは出来ないかもしれない。もし自分がウクライナ人だったとしたら、戦うべきか否か、どちらが正解なのか、2つの選択肢の間で揺れてしまい、初めてこの映画を観た時から随分時を経た今の自分でも、迷いしかありません。
この映画は、ただ、人が人と戦うことで、人間の魂が深く傷つき、残酷な形で人生に影を落とすことを教えてくれます。そのことを知っておくことが未来の戦争を防ぐことにつながるのでは、と祈る気持ちを強くしながら、久しぶりの鑑賞をした私でした。
戦争に関する映画は、どうしても「観ておかなければ、知っておかなければ」という気持ちにつき動かされる部分があります。
(それでも「地獄の黙示録」は、耐え難いキツさしか記憶に残っていません。あ、戦争映画ではないけれど、血を血で洗う抗争を描いた「ゴッドファーザー」も自分にはキツいかな。俳優さんの演技がカッコイイ、とかそういう視点で観られないんですよね。なぜだろう?観ていて、苦しすぎるというか。地獄の黙示録もマーロンブランドの名演技が光る作品、と言われますが、もう一度観るとなったら相当覚悟が要りそう、、、否、やはり無理かも。
因みにオッペンハイマーは観る予定であります!)
追加コメント:
この映画は、2世代にわたって描くので、一人二役が多く(一人の役者さんが、親とその子供と両方を演じる)、それも見どころです。
これに関して今回自分の勘違いに気付いたのですが、、。ナチスの収容所に送られたユダヤ人夫婦の夫役は、作品を通して一人一役なのに(一人の役者さんが、その男性の大戦終結までと、戦後 - 特にアルジェリア戦争後 - を演じている)、自分の記憶の中では何故か一人二役をしているように勘違いしていました!ショック!(以前、この勘違いをしたまま、人にこの映画を薦めてしまった気が、、、会った時に訂正して謝らないと、、泣)。言い訳を探すとしたら、この人物が戦後、収容所で生き別れた奥さんと子供のことを思い起こすシーンが全然ないから?、、、いやいや、それでも普通に観ていれば、描かれている人物は一人だと分かるはずなんですが、何故か勘違いしていたみたいで恥ずかしい。映画をきちんと理解し切れないお間抜けな私が、この掲示板に映画の感想を載せるのはいかがかと思いますが、以後、正確に作品を理解するよう、注意しようと思いますっ!(大反省)
42年前のエブエブ なれどボレロ以外は杜撰
午前十時の映画祭13 B にて。
これも観たかどうか、記憶が定かでない作品。
42年前(1981.10.16日本公開)と言えば、自覚的に映画を観始めた頃だが、まだ映画の文法を読み取る力が不足していて、いわゆる自分なりの「みかた」も確立していない。
勢い、きちんと観て、それを自分のなかに飲み下して、記憶の棚に仕舞う、という作業が満足にできなかったせいで、観たのに全く記憶に残らない、という現象がやたら多かったのだと思う。
とにかく本作のタイトル、『愛と哀しみのボレロ』(原題はLes Uns Et Les Autres - お互いに - )は凡庸でありがちな邦題だと思うが間違いなく諳んじられたし、ジョルジュ・ドンが踊る《ボレロ》は鮮明に記憶している。
ただ、バレエ界の哲人ことモーリス・ベジャール(1927-2007)の振付による、この不朽の名作バレエ《ボレロ》は、本作のために作られたのではなく、20年前の1961年の初演。
日本でも、テレビなどでも盛んに取り上げられ、小生も、確か、ジョルジュ・ドン(1947-92)以外に、ジル・ロマン(1960- )、シルヴィ・ギエム(1965- )、首藤康之(1971- )で観ているはずだ(たいていテレビで。どれかを生で観たような気もするが、それも忘れた)。
ジョルジュ・ドン自体は、他の演目でも観ていたし、《ボレロ》に既視感があるのは当たり前なのだが、今日、本作を観て、他のシーンには何も記憶の手がかりがなくて困った。
大まかなプロット込みで、これだけ本作のことを認識しているのだから、たぶん観たのだとは思うのだが‥‥
さて、本作の概要、あらすじ等は、Wikipedia に充分解説されているので、詳細は省略する。
要は、冒頭示されるように、
◇モスクワはボリショイのバレリーナたるタチアナ・イトヴィッチ(リタ・ポールブルード)、
◇パリのキャバレー付きのヴァイオリニストたるアンヌ(ニコール・ガルシア)とピアニストたるシモン(ロベール・オッセン)のマイヤー夫妻、
◇ベルリンを活動拠点とするクラシックピアニストたるカール・クレーマー(ダニエル・オルブリフスキー)、
◇ニューヨークを拠点にジャズバンドを率いるジャック・グレン(ジェームズ・カーン)
の4組を起点とする、1930年代から1981年に至るファミリー大河年代記である。
ヤマ場としては、
◇発端のすぐあとの大戦、
◇それぞれの2代目が台頭する1960年代、
◇そして3台目の時代が幕を開け、プロローグで小出しした、エッフェル塔前で華々しく執り行われる、赤十字&ユニセフ主催のチャリティー・コンサート=ドンが踊る《ボレロ》のステージに4組の子孫たちが結集してクライマックスとなる、
といった運びである。
ラストのクライマックスまでは、4組の家族は、多少のニアミスはあっても深くは関係せず、それぞれ並行的に物語が進展する。
Wikipedia によれば、シナリオ技法的に言う「より縄形式」の代表例であるらしい。
まぁ、最近の例になぞらえるならば、ある種のマルチバース、42年前のエブエブだと見立てられなくもない。
でも、観ると、全然上手くないんだよなぁ。
何だか、最初、ナレーター(ルルーシュ監督本人?)が、
「今から始まりまするは全て実在の人物にて、演じまするは誰々‥」
みたいな前口上があって、エピローグでも、出演者のカーテンコールみたいなのがあって‥‥
まぁ演劇になぞらえてるんでしょうが、メタ的な作りを装おうとしてるけど、特段、効果的だったとは思えんし。
今回再見(?)しようと思ったのは、カラヤンが出てるって情報をどっかで見たからで。
で、カラヤン、いつ出て来るかと思いきや、全然出て来ないし(笑)。
要は、実在の人物云々は、芝居の中のセリフで、それ自体はフィクションだった、ってことで。
それに、2代目ないし3代目を同一俳優が演じたりするので、なおさらエブエブ感を増しているのだけれど、カラヤンがモデルという(ピアニスト転向)指揮者のカール・クレーマーはずっと同一人物だとか、統一感がなくて、観ていて混乱するばかりでしたな。
ヒトラーによるユダヤ人虐殺がドラマ全体のトラウマとして作用している構造なんだけど、被害者側(アンヌ、シモン→ロベール)の話も上手いとは言えないし、ヒトラーへの加担を問題視されるカールの件も中途半端だし、ね。
大戦を扱った大河ドラマとしては、ダメダメじゃないかな。
それに呆れたのが、カラヤンをモデルにしたカールの指揮ぶりが無茶苦茶。
ちょっと酷すぎ。
今期のTBSドラマ『さよならマエストロ』の西島秀俊の方が百倍まし。
ネトフリ映画でバーンスタインの指揮を再現した『マエストロ』(2024.2.11映画.com パングロス初投稿)のクーパーの爪の垢でも煎じて飲んで欲しい、って心底思いました。
で、ダメだ、こりゃ、
で、2.3 点
ってなところですが、フィナーレのドンの《ボレロ》は流石に神の領域で、こればっかしは本物で、感動の震えを禁じ得なかったという‥‥
で、+ 0.3 の加点にて、2.6 点とします。
あっ、ミッシェル・ルグランの音楽と、それに載せた何やようわからんコンテンポラリー群舞(最初、防護服で除染みたいなことしてるヤツ)も悪くなかったですよ。
でも、その分は基礎点のうち、ってことで。
*Filmarks投稿を一部省略して投稿
全部邦題のせいだ
長い、わかりにくい
タイトルなし(ネタバレ)
数十年におよぶ人々の営みを描いた群像劇。
戦争で命を落とす者、生き残り母国に無事帰還する者。
生きるために必死に生きたが売国奴と罵られ自殺した女。その娘も生きるために苦労するが、もがき苦しんだ末にテレビアナウンサーになり成功者としての人生を歩むことに。
「人生には二つか三つの物語しかない。しかし、それは何度も繰り返されるのだ。その度ごとに初めてのような残酷さで」という言葉が映画の最初にスクリーンに表示される。
亡くなった父が晩年寝たきりになり、その境遇を嘆き悲しんでいた。
高齢の母もケガで入院することになり、先日見舞った際に父と同様に嘆いていた。
人生は残酷で、生きるということは苦しいことと思った。
はたして己の天寿をまっとうするまで、生き続けるためにもがき続けることができるか。
初めて見るので
官能的な音楽が心を揺さぶる。懐かしい映画音楽全盛期の作品
原題の「Les uns et les autres」は難しい。全く関係のない邦題をつけてしまうはずだ。「自分は自分、ひとはひと」という慣用句でもあるし、反対に「ご一緒に」という意味に使われたりするようで文脈によって異なってくる。でもパリ、ベルリン、モスクワ、ニューヨークの4都市が出てくるものの、主な舞台はフランスで、フランス人が自分たちを中心としてパリにやってくる他の国の人々と一緒に芸術文化を成熟させていく話にもみえる。で、私の原題訳は「私たちと、あの人たち」
大河ドラマである。モスクワのバレリーナ、ベルリンの指揮者、パリのバイオリン奏者、ニューヨークのバンドリーダーの4人が主な登場人物でその配偶者、子供などが入り混じりった三世代、40年以上に渡る大長編。
これをいちいちセリフや状況説明で繋いでいくのは大変だし精緻な脚本と突出した演出力を要する。クロード・ルルーシュはそこまで構成力がある監督ではない。
大長編の成立を可能にしたのはひとえに音楽の力である。ラヴェルの「ボレロ」はもちろん、その他の音楽もこの映画ではとても官能的である。
それが我々の心の奥底を揺さぶり共鳴化させることによりドラマに対する説得力を高めている。
音楽の官能性を上手く活用していたのは「男と女」と同様である。
3時間の作品なので全てがうまく行っているわけではない。アルジェリアからの帰還兵がたびたび出てくるあたりからドラマは冗長になり音楽の出番も少なくなるためちょっと退屈だった。
この映画はミシェル・ルグランとフランシス・レイによる「映画音楽」映画であるといっても良いかもしれない。「ボヘミアン・ラプソディ」や「ホイットニー・ヒューストンI wanna dance sombody」のようないわゆる音楽映画とはちょっと異なる気がする。上手く説明できないが。
ミシェル・ルグランとフランシス・レイは既に亡くなった。「海の上のピアニスト」のレビューでも書いたけど、エンリオ・モリコーネとバート・バカラックも既に亡い。映画音楽の時代は既に終わったのかもしれない。
出会いは『交渉人 真下』でした
レビューの皆さんのように、この作品やダンサーを見たくて観たわけではないです。
映画を観たくて出掛けたら、これが待ち時間が一番少なかった。
なんか聞いたことあるタイトルだなって少し考えて、『あーっ!交渉人 真下正義で出てきたやつー!』と1人心の中で盛り上がり、選びました。
まさか3時間越えとも知らずに。
冒頭に出てきた言葉の通りの映画でした。
“人の営みは同じような2、3の出来事を初めてのように残酷に繰り返す”みたいなあの言葉。
繰り返されるボレロのリズムのように、愛と哀しみがかわるがわるやってきて、その中で人は生を踊り、命を燃やしていました。
身構えずに見せられるホロコーストのシーンは心をえぐり、辛く暗い気持ちにさせられましたが、人はそれでも笑い、酒を飲み、恋をして、そして戦争以外の場所でも人を憎んでいた。
なんという【いまと変わらなさ】であろうか。
登場人物が多く1人何役も世代を超えて演じていたので、一回では分からなかった人やシーンもあり、3時間超えの覚悟を持って、いつかまたみかえそう。
とりあえずその前に、出会わせてくれた交渉人を、久しぶりに観ようかな。
あの映画もラストが好きで、何度も観てしまうんだよな。
パリの空の下
「なぜ人間は同じことを繰り返すのだろう?なぜ運命はいつも同じ装いをしているのだろう?」
午前十時の映画祭13の大トリとして鑑賞。観たのは12年ぶりで、スクリーンでは初鑑賞。モスクワ、ニューヨーク、ベルリン、そしてパリ。セルゲイ・ヌレエフ、グレン・ミラー、ヘルベルト・フォン・カラヤン、エディット・ピアフをモチーフに、 1930年代〜1980年代にわたり数奇な運命に翻弄された4家族の物語が同時進行する。
有史以来、人類は数多くの音楽を生み出してきた。その中でもとりわけ奇妙な存在感を放つのがモーリス・ラヴェル「ボレロ」である。同じリズムを保ちながら2種類の旋律を繰り返し、その間徐々に楽器が加わっていく。その様子は音楽というよりは呪術と表現した方がふさわしい。この曲を根底に置きながら、本作では4つの家族の物語が展開され、パリを交差点としてクロスオーバーするのである。メインキャストは親子2役兼任という、曲に負けず劣らず特異な映画と言っていい。
ただ、その性質上難しい立場に置かれた作品かもしれない。本来この手の作品は「考える」よりも「没頭する」ことを求められるが、本作はクロスオーバーで物語が進行するため、頭の中で状況を切り替えながら観なければならない。よって考えることに神経を割かれてしまい没頭しにくい一面がある。複数回観た方が恐らく整理はしやすい。緻密過ぎて観る側の整理がなかなか難しい。
とはいえフランスが底力を示したような出来で、監督クロード・ルルーシュ、音楽フランシス・レイ&ミシェル・ルグランというまさにフランス映画界最高戦力を惜しげもなくぶっ込んだ本作。音楽映画にも関わらず劇中ではT-34/85戦車やクレマンソー級空母が当たり前のように登場し、一体製作費にいくら注ぎ込んだのか気になってしまった。キャストでいうとアンヌ役のニコール・ガルシアの飾らない美しさに魅せられた。
人生には2,3の物語しかない。しかしそれは何度も繰り返される。そしてその度にまるで初めてであるかのような劇的さを伴う。そういえばラヴェル「ボレロ」は、指揮者にとっては「手腕を問われる曲」らしい。音というものは、楽器が重なり厚みが増すと同じテンポでも遅く聴こえるため、指揮者はテンポを維持するために演奏中徐々にテンポを上げる必要があるのだそうだ。人生も恐らくそうで、同じことの繰り返しの中で少しずつ生きるスピードを上げていく必要があるのだろう。そこにその人の手腕が問われるのが人生らしい。
今日もパリの空の下セーヌは流れ、日々の営みの中で新しい物語が紡がれる。
あゝマロニエに 歌を口ずさみ…
全47件中、1~20件目を表示