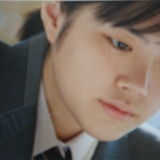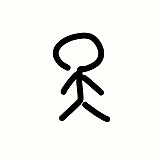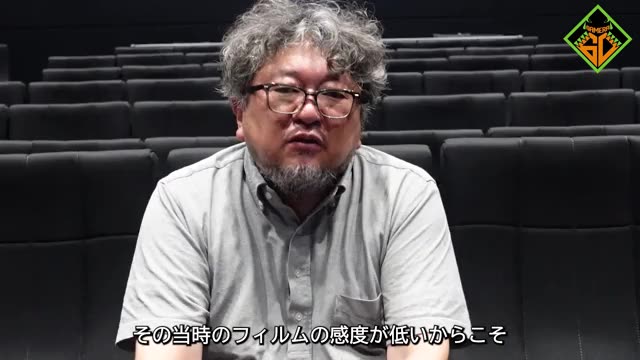大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオスのレビュー・感想・評価
全20件を表示
敵は凶獣ギャオス!
第一作では人類の敵だったガメラが、今回は人喰い怪獣ギャオスが相手でなかなか盛り上がります。いまさらながら、ギャオスの造形がいかにも凶悪、どこからみても悪役で分かりやすいし、人間を捕食する設定もエグくていい感じです。序盤は姿を見せず超音波でヘリを真っ二つにするシーンを実写でやってのけるのが凄く、その後も戦闘機や自動車を真っ二つにしまくり、ガメラにも手傷を負わせる文字通り出血サービスです。対するガメラも、高速回転飛行のバリエーションを増やしたり、側転甲羅攻撃など、戦い方に工夫があって楽しかったです。お子様向き映画なんで、相変わらず子供が絡んでくるけど一作目に比べるとだいぶお役立ちキャラになっています。
あー楽しかった\(´ω`)/
印象的なシーンが沢山あるのだ
ガメラの大きな転換となった作品
ガメラは前作まではゴジラと同じく街を破壊する制御できない怪物として登場していたのだが、今作で大きく舵を切って子供の味方となった。一応、1作目でも子供を助ける場面はあったのだが、味方というよりもゴジラと違って無闇に殺さない理性や優しさのある存在というのを表現しているのだろうと思うので、少し違う。(スポンサー対策だったという話もあるが)
子供の味方となったことで好きじゃないという人もいるかと思いますが、ギャオスが人を食べるので子供を出してコミカルにしないと悲惨になりすぎるので割と美味い塩梅なんじゃないかと思います。その配慮を取っ払ったのが平成ガメラなのかと。
子供向けにしたことで集客は伸びましたがシリーズは尻すぼみになるというゴジラと違う結果を見たガメラシリーズですが、その転換期といえるこの作品は全体的にバランスよくできていると思うので、ガメラを見たことがないなら是非とも一度は見てもらいたいところ。
【”あ、あれは何だ!鳥だ、飛行機だ、いやギャオスだ!”みんな大好きガメラシリーズ第三弾。名古屋城を壊すんじゃないよ!全くもう!今、修復問題で大変なんだから!ホントスイマセン・・。】
ー 怪獣映画って、何で城がターゲットになるのだろうか。
前作では大阪城が凍り付いたし、今作ではナント、名古屋城が破壊されるのである。
確か、ウルトラマンで登場した古代怪獣ゴモラも、大阪城の天守閣を壊していた記憶がある。壊しやすいのかなあ。-
■或る日、突然に富士山が爆発する。その影響で、怪獣・ギャオスが目を覚まし、人々に襲いかかってきた。
ギャオスは名古屋城を破壊し、辺り一面が火の海と化すのである。その火に引き寄せられてガメラが出現する。
人々が、ギャオスをくるくる回して斃そうなどと言う可なりチープな戦法で臨むのだが、アッサリ失敗するのである。
だが、子供の味方であるガメラが怒りの火炎を吹き、大怪獣同士の決闘が勃発するのである。
◆感想
・富士山は死火山ではない。活火山である。そんなバカな、と思った人は調べると良い。いつ爆発してもおかしくないのである。
・今作では、ギャオスが目覚めたのに高速道路を作ることを止めない道路公団のお偉いさんの叱咤激励する愚かしき姿が描かれているが、何となく昭和だなあと思ってしまったのは、私だけであろうか・・。
・今作のギャオスは狂暴である。何たって逃げる人達を、翼の先の手で握りつぶすのである。嫌だなあ。
・で持って、今作では”えいいちくん”なる少しませた富士の麓に住む少年が、元気にガメラを応援するのである。
■そして、矢張り見所はギャオスとガメラの戦いのシーンである。ギャオスの足先が引きちぎられたり(で、傷跡から生えて来る。)、ナカナカである。ギャースギャースとギャオスが煩いのである。カラスからヒントを得たのだろうか?
富士山での最終決戦のシーンも良いのだな。
ガメラがギャオスを引っ張って、富士山の加工に引きずり込んで、自分だけ出てくるのである。流石、甲羅は固いのであるなあ。
<今作は、みんな大好きガメラシリーズ第三弾である。名古屋城を壊すんじゃないよ!全くもう!今、修復問題で大変なんだから!>
■道路建設に当たり、欲を出して土地を買う村の人達を見て思い出した、どーでも良い事。
新東名建設が決まった後に、父が道路が通りそうな土地を買って大損した事である。ギャオスが出なくて良かったけれど、見事に新東名はその土地を掠めて建設されたのである。あの土地、どうすんのかなあ・・。
超音波怪獣ギャオス初登場の昭和ガメラ第3作への郷愁
昭和42年公開のガメラ第三作目は、おそらく小学3年生頃に観ていて、子供ながらとても興奮した想い出があります。今回偶然にもVODの期間限定公開を見つけて57年振りに観ることができました。手足の4か所から火を噴き空を飛ぶガメラと、今回初めて知った吸血バンパイヤーからの発想で生まれたコウモリ型怪獣ギャオスの空中戦の迫力に、固唾を呑んで観た記憶が蘇りました。その醍醐味はキングギドラやラドン、モスラの空飛ぶ怪獣相手でも、殆ど地上戦がメインのゴジラ映画には無かったものです。また格闘能力の優れたゴジラの絶対的最強怪獣の安心感に比べて、動きが鈍い特徴がある亀型怪獣ガメラは、簡単に敵を倒すことが出来ない上に、今回のギャオスの最大の武器である鋼鉄を切断してしまう超音波光線をまともに受ければ深い傷を負ってしまいます。子供目線では、ハラハラドキドキの想いで観ていました。この映画の鮮明な記憶は、そのレーザーメスと化したギャオスの攻撃によってガメラが傷つき青い血を流すところと、英一少年がガメラの甲羅に乗る二つのシーンでした。同じ年齢くらいの少年が怪獣の背に乗せてもらう親和性と非現実の空想の楽しみに、幼く無邪気な私が虜になっていたと思います。
資料によると第一作の「大怪獣ガメラ」で、灯台から落下する少年を手のひらで受け止め助けるシーンが子供たちに大反響を呼んだことに好感触を得たプロデューサー永田英雅の発案により、ガメラシリーズを子供に特化した制作コンセプトの娯楽作品に変更したとありました。この観ている子供たちを飽きさせないための工夫を施したことが、今回映画冒頭から改めて感じられます。三宅島の火山噴火から富士山が噴火、溶岩に誘き寄せられるガメラが登場、地殻調査の科学者と報道人を乗せた大型ヘリコプターが飛び立ち、それが二子山上空で謎の光線を浴びて機体が真っ二つと、間髪を入れずの展開の速さ。主役の怪獣二匹が開巻早々現れて、気を緩める暇がありません。そしてこのギャオスの形体や残忍さの悪役怪獣としての完成度の高さに好感を持った子供時代は、“お化けのQ太郎”と並び良く描いた漫画の双璧でした。しかし、今見直すと英一少年を見棄てた新聞記者を始め、新幹線の乗客を食べるなど、人間の血を好む残虐さに無関心でいられたのが不思議です。と言うのも、幼少の頃の私は、「モスラ」に出てくるインファント島の現地の人たちが実際にいて出演していると思い込み、テレビか映画の時代劇では正義の味方の主人公に斬られてしまう悪党の家来が本当に死んでしまうのかと憐みの気持ちで観ていたからです。流石に9歳になれば虚実の分別が付いて、怪獣映画のすべてがフィクションと理解するのが当然ではあるのですが。
ギャオスの超音波光線によって自衛隊の戦闘機が真っ二つになったり、名古屋城が破壊されるのは予想できても、新幹線の上部の屋根部分だけが剝がされるユニークさと新聞記者が乗っていた乗用車が分割されて走行する奇想天外のギャグには今回笑ってしまいました。しかし、この記憶がありません。鑑賞しながら、9歳の自分と今の初老の自分が同時にどう思うかを整理するのは、不思議な感覚です。小さい時トンボやカブトムシを捕まえては散々遊んだのに、大人になってからは触るのも嫌がるのに似ているかも知れません。
主演の本郷功次郎はこの時29歳で、前作の時は主演とは言え子供向け怪獣映画のオファーに詐病も使って抵抗したそうです。しかし、後年代表作の1つにガメラシリーズを公の経歴に明記した逸話を知り、映画ファンとして心が温かくなりました。確かに俳優として大人が満足する名作に出演したい気持ちは、色んな映画を観て来た私にも理解できます。それを記録に例えれば、このガメラ映画出演は記憶に残る出演だと言えます。映画は娯楽であり、芸術でもある。公開当時評価されても永遠ではないし、月日が経ってから漸く注目され評価されるものもある。題材がどうであれ、スタッフ、キャストの真摯な取り組みがある映画は命を持つという事だと思います。この作品では、国土開発の一環として奥州街道寄りに高速道路を強行する企業と、開発反対を標榜しながら実は地上げを目論む地元民の軋轢を扱っていて、今日の視点で観ても興味深いものでした。金丸村長のお金に執着する欲深さに辟易し翻弄される村民の姿も面白いし、そんな抵抗勢力に呆れながら開発に邁進する労働者の直向きさが、本郷功次郎によって表現されています。有名俳優は、他にその金丸村長を演じた上田吉二郎で適役の好演を見せます。第二作に比して制作費を制限された事情のキャスティングでもあるでしょう。
車のミニチュア撮影の稚拙な映像を観ていて、当時人気を博したおもちゃのレーシングカーを想い出します。父は、小学館の少年雑誌の月刊誌を子供たちに購読させ、トランシーバーやレーシングカーの流行りものおもちゃも買い与えてくれました。小学校に入る前には、珍しく父と二人だけで行ったデパートで、これはチャンスと思った私が、レールを走る電車模型が欲しくて駄々を捏ねたこともありました。兄姉の羨望をよそに、ひとり電車遊びに興じる私でした。この電車模型はプラレール以前の本当に簡素なものでしたが、レーシングカーは道路コースも応用が利き、車線の中央に溝があり、そこに車の中央に刺さってあるピンを刺して走らせるものです。車線には電線が通っていて、そこから電流を得た車を速度変更しながら走行させるものです。
怖いシーン。
中山忍ちゃんカワイイ!
0010 昭和ガメラ最高峰
1967年公開
子供が主役だが大人向きの映画。
ギャオスの光線はガメラの体に当たるもさらに貫いて
進んでいく。超音波光線の誕生。
円谷英二は人知を超えたモノとして怪獣を表現したが
大映は動物の延長線上として扱い、血も出す、痛がる。
お日さんに弱いギャオスが追い詰められる名古屋港の
対決はガメラも血まみれになるも咥えた足を離さない。
ここは滅茶苦茶緊張感が増す。
結局ギャオスは自ら足を切断し窮地を脱出。
特撮もかなり進歩して物語との違和感はない。
難を一つ言えば名古屋急襲の時ギャオスは
空を旋回するだけで終わってしまい
ラドンのようなソニックブームは見せられなかったか。
音楽は山内正。
伊福部曲に勝るとも劣らない対決シーンを生み出す。
エンディングは過去2作品も含めてダイジェスト。
なかなかのサービス。
場面も陸海空とさまざまで
今でも面白いんじゃないの。
75点
初鑑賞 TV鑑賞 いつやったっけかね?
鑑賞 2025年12月8日 TJOY京都1
配給 KADOKAWA
ガメラ60周年で終活鑑賞
昭和演技はクサいものの話の進行は申し分ない
やっぱり今見ても面白かった
今更ガメラ。
兎に角ですよ。
ガメラと言えば、ギャオスどす!
大スクリーンで観る迫力に気圧される、ってのはあるにせよ。最近のCG技術に慣れっこになった身としては、流石に着ぐるみとミニチュアの辿々しさには時代を感じてしまいます。
が。ところが。
今更ですが、ストーリーの運びやエピソードの一つ一つは、最近のエンタメものより、むしろ面白いんです。よく出来てます。と言うか、「お。コレはアレじゃない?」と、後々のアニメや映画を思い浮かべてしまうわけです。
名古屋港で、ギャオスの足を噛み止めるガメラ。迫る朝日。ギャオスは自らの足を切断して飛び去ります。
コレって、猗窩座と煉獄さんじゃないですか?
変電所を改造し、回転展望台のモーターを補強し、ギャオスを倒そうとする作戦は、まさにシン・ゴジラだし、ヤシマだし!山火事作戦も然り!
怪獣同士の派手な闘い任せにする事なく、人間側が知恵を絞って力を合わせるとことか、かなりの萌え具合。
あー、そうだよ。ワシら怪獣映画とウルトラマンを見て育った世代だもん。ってのを再認した次第です。
楽しかった。
とっても!
昭和ガメラ3作目。
主題歌は完全に子供向けなのね
67年大映。シリーズ2作目。
冒頭で富士山が噴火、そこにガメラが飛んでやってくる。中々に飛ばした展開。その後はビジネスの大人の事情が描かれる。昭和ガメラの初期は子供向けでない展開もやってたんだねえ。
ギャオスも割合と早く登場。どうかと思うその造形。牙をもちっとリアルに作って欲しかった…。ガメラも出てきて開始20分で前哨戦。
その後は対ギャオスに稚拙ながら硬派な展開に。(この辺りシン・ゴジラに影響を与えている気がする)
夜の市街戦・空中戦・港での戦い・ラストの肉弾戦と特撮は気合い入っていてまずまず見応えあり。
まあ怪獣映画なのでツッコミつつ楽しむのがいいでしょう。全体のバランスはよく出来てたと感じました。
東宝特撮の怪獣映画へ逃げずに真っ正面から挑戦
1967年の正月の怪獣映画は前年12月公開のゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘で始まりました
この1967年は前年に続き東宝特撮への挑戦がさらに拡大していった年で、前年の1966年と合わせて大変重要な年です
1967年公開の特撮映画のトップバッターが本作です
3月公開の春休みを狙い、東宝特撮との直接対決は避けてはいますが、その内容は全く逃げていません
真っ正面から東宝特撮の怪獣映画へ挑戦しています
第一作の監督であった湯浅憲明を、第二作のように特撮担当にせず、監督として復帰させて体制を整えています
特撮映画は特撮を大事に考えられる人間が全体を仕切らないと良いものが撮れる訳はないのです
前作は大人向けになっており第一作で意識したはずの子供とその親が共に楽しめる内容が忘れられていたのをまず修正しています
東宝特撮のゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘が同じ失敗を犯していることで気付かされたのでしょう
怪獣ももっと花のある東宝特撮のラドン、モスラに匹敵する敵怪獣を考えてきます
ラドンもモスラも飛ぶ怪獣なのだから、人気がでるのは飛ぶ怪獣という分析です
東宝特撮が前年はフランケンシュタインをモチーフにするなら、こちらは吸血鬼ドラキュラだ!と真っ正面から挑戦の方向性で企画しています
本気さが伝わり好感が持てます
特撮技術は正直東宝特撮に劣っていますが、逃げずに見せたい絵を優先して撮っています
スパッと車も戦闘機も真っ二つにしてみせるギャオスの超音波は素晴らしい視覚効果です
富士山の噴火、回転作戦、山火事作戦どれも、子供心にはワクワクするものばかりです
冒頭直ぐにガメラを登場させますし、子供をガメラが助けて甲羅に乗せて飛行するシーンは子供にはしびれるような名シーンです
さらにはエンドロールにガメラの主題歌を流してみせる、このプロ魂!
ギャオスの造形は素晴らしく、東宝特撮の怪獣に勝るとも劣らないインパクトがあります
ドラマパートも脚本が上手く大人も飽きずに楽しめます
主演の本郷功次郎も前作と変わらず熱演です
飯場の部下のコンビも良い脇役の仕事をしています
特撮映画をなめた仕事はどこにもなく、当時の自分たちが出来るベストを撮るんだ!という情熱を感じることができます
そこは正しく評価されるべきです
子供達はそれを見抜き圧倒的に本作を支持して大ヒット怪獣映画となりました
本作が成功したからこそガメラは息の長いシリーズとなり、平成にはリメイクまでされることになったのです
1967年の春
怪獣映画は本作を加え、なんと三作が公開され激突することになったのです
それも東宝が特撮映画を公開していないのにです
本作以外の二作とは何か?
ひとつは本作とほぼ同時公開になった松竹の宇宙怪獣ギララ
本作の10日遅れです
もう一つはそのギララ公開の1ヶ月後
日活の大巨獣ガッパが公開されることになるのです
そしてテレビでも東映がキャプテンウルトラと仮面の忍者 赤影を共に4月にスタートさせていたのです
大映、松竹、日活、東映
東宝特撮に当時の日本の映画会社のすべてが同時に挑戦をしたのです
海外作品も4月からタイムトンネルのテレビ放映をスタートさせていました
確かインベーダーもこの年の春放映スタートです
それが1967年の春だったのです
人間側の話は英一少年が主役。ギャオスの名前はその鳴き声から英一少年...
人間側の話は英一少年が主役。ギャオスの名前はその鳴き声から英一少年が命名した。
物語はじめからガメラありきというか、ガメラ当たり前の世界。英一にはヒーロー的な存在。
ガメラの体型からどうやって手を伸ばしたのかわからないけど少年を背中にのせて飛行するシーンもある。
人間も作戦をたてていろいろやるがギャオスには歯が立たない。ガメラが力技でギャオスを仕留める。映画らしいラスト。
タイトルは英一とガメラでもいいかな。
一番人気?
自然破壊にも繋がる高速道路建設と、地主が金儲けのために地価を釣り上げようとしている構図が面白かったりする。前作バルゴンのときと同じく人間の強欲さがにじみ出ている。
道路建設とは別に、光線の謎を調査する目的で新聞カメラマンが村長の孫英一とともに二子山に入るが、子ギャオスに食べられてしまった。そこへガメラが登場、英一くんは負傷したガメラに乗せられ助けられた。山梨県の村長が金丸という苗字というところが面白いし、その村長が上田吉次郎だということも・・・ハイランドパークというのは富士急ハイランドなのか?
ギャオスは声帯が二つあり、頭が音叉棒のように共鳴し、超音波光線を発するのだ。首が回らなく、後方が死角となっている。しかし、戦闘機はあっけなく真っ二つ。そのうち牧場の牛が全ていなくなり、ギャオスは夜にしか出てこないことがわかる。
ギャオスの羽ばたきでとてつもない風圧が起こり、戦車までもがひっくり返るのに、人間は一人がゆっくり飛んでいただけ。名古屋城を破壊し、住民はナゴヤ球場に避難。そして光線の威力は車を真っ二つにするほどだ・・・コメディ映画みたい。
オバカな作戦、その名も“回転作戦”・・・ギャオスは紫外線に弱いので夜現れたところを引きとめて夜明けを待つ。ホテル屋上の回転台でめまいを人工的に起こさせるため、人工体液でおびき寄せるというもの。わけわからん・・・
この映画がガメラシリーズで一番人気だということもわからない。バルゴンのパターンをそのまま用いて作戦のひらめきを子供に委ねているだけだ。しかも作戦の論理性は穴だらけ。上手くいくわけない・・・
ガメラ最高の相手
子どもの味方ガメラとあのサイズで人間を踊り食いする凶悪なギャオス(笑)の対比が凄い。
頭部の形が凄いインパクトを残したギャオスは間違いなくガメラシリーズで屈指のキャラクターと思う。
そんな2匹が闘うのだから、楽しい事この上なし。
空中戦と銘打ってるけど、クルクル回るだけのガメラがそれだけ戦えるはずもないし、もう半世紀前の作品になるのかと思えば、許せる。
公開時は産まれてなかったので移動でやってくる映画屋が公共ホールを1日借りきって上映したのを観に行ったのが懐かしい。併映は『大魔神』と言う豪華さだった。
ガメラのうたも本作品からスタートして、子どもを対象にしたガメラ映画が作られてるが、子ども向けにしては怪獣の出血シーンや人間を貪り喰うギャオスの姿など、幼い子にはトラウマになったかもしれない。
そんな凶悪ギャオスも首を後ろに向けられないし太陽に弱いと言う分かりやすい弱点も持ち合わせており、手に負えない程強い怪獣ではないが人気は確かなもので、宇宙ギャオス(色塗り替えただけ)として『ガメラ対大悪獣ギロン』にも登場しており、トコトン使い倒されている。
全20件を表示