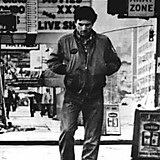ブルーベルベットのレビュー・感想・評価
全37件中、21~37件目を表示
リンチ君にしては良心的
深夜向けの雰囲気
青春映画にミステリーを加えたような映画ですかね。
見舞いの帰りに草むらで「耳」を発見した主人公が警察に耳を届けるのですが、その話を聞いていた刑事の娘が同じく興味持ち、内緒で一緒に追求することになる。
けどやっぱり彼氏いるし家にもバレたら...と、興味あるけど躊躇ぎみなのが少しイライラしたりする。
エロイ場面は芸術なのか本能なのか!?
今の映画に慣れてしまうと刺激が足りないかもしれませんが、効果音を控えめにすることで良い緊張感を作っています。車のエンジン、トイレ、足音、ドア等々1つ1つの動作音だけで、この手の映画は緊張感が出る、いい例だと思ったりした。
これはデヴィッド・リンチの個性を確立した作品のようですね。
未知な世界に一般人がハマッていく...性欲は三大欲望だしコントロールするのは難しいのかな。後半は変なシーンも少なく普通のミステリーなノリになります。自己満足、芸能人にありそう、裏社会の話とか思って個人的には退屈だったなぁ。
話が進むと、耳が誰かなんてあんまり意味ない気がするし。。。
ミステリアスな音楽はムードあって良かったので、深夜向けの映画かと思います。
彼氏は気の毒だな。カイル・マクラクランに乗り換えなくてもいいのにね。
【”Mystery of Love"デヴィッド・リンチ監督の変態的愛と暴力と耽美性に彩られた作品。アンジェロ・バダラメンディの奏でる曲が耽美的且つ幻想的雰囲気を醸し出している作品でもある。】
ー 尋常でない雰囲気が横溢する作品である。
特に、フランクを演じたデニス・ホッパーのFワードの多発や、イゼベラ・ロッセリーニ(イングリッド・バーグマンが夫と子を捨て、身を寄せたイタリア人監督ロベルト・ロッセリーニとの間に誕生)が演じるドロシー・ヴァランスの狂気を帯びた、妖艶さ・・。ー
・主人公のジェフリー(カイル・マクラマン)が、父を見舞いに来た時に、野原で見つけた”耳”。
彼が、それを刑事に預けるトコロから物語は始まる。
・ジェフリーは、刑事の娘サンディ(ローラ・ダーン:当然だが若い。)と二人で、なぞ解きを初めてしまったものだから、彼は狂気とエロスの世界に巻き込まれていく・・。
・サンディが聞きつけた、”耳は、ナイトクラブの歌い手、ドロシー・ヴァランスと関係がある・・”と聞いたジェフリーはドロシーの家のクローゼットに身を隠すが・・。
ー 江戸川乱歩の”屋根裏の散歩者”を想起させるシーン。
彼も、ドロシーに見つかり、パンツを脱がされちゃって・・。
ドロシーの家に乗り込んできたフランクの、ドロシーに対するSMチックな狂態の数々。
良い子は、観ては駄目だよ!ー
・徐々に明らかになっていく、ドロシーとフランクの関係。そして”耳”。
<フランクの家に有った、二つの死体。一つの死体は立ったまま、頭から血を流しており、もう一つの死体には”耳”が無く・・。
グロテスクなシーンが続くが、背後に流れるのは、アンジェロ・バダラメンディが奏で、ジュリー・クルーズが歌う幻想的且つ耽美な”Mystery of Love"である。
デヴィッド・リンチ監督特有の耽美的雰囲気を醸し出している、幻想的とも言える作品。
”Mystery of Love"が収録されているジュリー・クルーズの全曲アンジェロ・バダラメンディ作曲の耽美的アルバム「Floating into the Night」は、よく聞いたなあ・・。>
蠱惑的な世界
デヴィッド・リンチ監督作品は、「マルホランド・ドライヴ」に続き二つ目の鑑賞。(「ツイン・ピークス」、まだ観てない、、汗)
DVDのジャケットに「ブリリアントな悪夢」とあったし、あのマルホランド・ドライヴのデヴィッド・リンチだから…!と肩に力が入り、トラウマ覚悟で鑑賞しました。(トラウマになった場合の為の、口当たりの良いハートフルな映画まで用意して(笑)) でも、想像したほどの怖さではなかった。怖さ&哀しさではマルホランド~の方が、という感じ。
ま、でも、それもそのはず。公開が87年て、、たぶん、"ナウシカ"とか同世代だよね。その時代にこれは確かにセンセーショナルだろうなと。
主演のカイル・マクラクラン。監督の"僚友"らしいですね。 ずっと、SATC(※セックスアンドザシティ)のクレジットの最後にゲスト扱いで流れるこの名前、誰なんだろう、、と思ってたんです。 シャーロットの逆プロポーズに「オーライティ(いいけど)」って答えちゃう、あのマザコン坊っちゃまトレイ・マクドゥーガルでしたのね。ってまぁ、そりゃそうか。苗字がマク~だもんね。スコットランド系だもんね。
ずっと、トレイ若いなー、若いなーと思いながら観てた(笑) 独特の暗い感じとスリリングな展開。同じデヴィッドでも、デヴィッド・フィンチャーの暗さが知的かつ厭世的なのに対して、リンチの暗さは蠱惑的でセクシーというか、、やっぱり悪夢感、なのかなという気がする。
この主人公、けっこう自分から巻き込まれにいってますよね。こういう、能動的で正義感の強めなキャラクターも時代を感じさせる。
不条理、つまり、この場合で言うと何もしてないのに、とか良い人なのにどんどん巻き込まれてなおかつ痛い目に遭うものは後味が悪いからなー。その方が怖さは引き立つんだけども。
この映画のジェフリー、ナイフ突きつけられてるのにボスの顔面に一発入れたりとか、、強っ。鋼メンタルか(笑)
終盤、まぁまぁ大事なあたりでウトウトしたから、返す前にもっかい観ます。
予測不能と言うか不思議な展開
歌がいい
あの歌が耳にのこる〜👂
思ったよりも静かな映画で暴力シーンをド派手に演出しないところがよけいにサディスティックで恐ろしい。
実は家の隣近所にやばい奴らが暮らしてたり、人の秘密を覗き見するスリルだったりと狂気と日常の合間があやふやになっていく感じが面白い、洋風江戸川乱歩な変態映画。
好みは分れそうだけど独特の雰囲気は見応えありです。
耳に残るラブレター
映像の効果で、一聴その光景にそぐわない楽曲のかかる方法が、よくある。
専門用語があるのかもしれないが、わからない。
たとえば、混沌──天安門事変やベルリンの壁の崩壊や多発テロや東日本大震災のような画像をフラッシュしながら、バックには中島みゆきの時代がかかっている──といった技法と似ているが、映画でもっとよく使われるのは、スローモーションと併せて、画では格闘や殺戮などの狂乱が繰り広げられていながら、バックには甘美な歌謡が流れている──というやつである。
もはや常套な技法となっていて、うまく使わないと白ける。
この技法が、どんな効果を及ぼすかというと──むろん、その映画の脈絡のなかで、多様ではあるが、よくある訴求効果としては人の所行の戯画化だろうと思う。
繰り広げられる人間の醜悪さをスローモーションにして、甘い曲をながすことで、それらを俯瞰し、ポエムや愚かしさや退廃や終末観──などの情感を増幅させる効果がある。とみている。
たとえば日本映画界の雄と見なされているバイオレンスの鬼才監督の映画では、少女達の流血や狂気の背景に、軽快なポップが流れたりする。もちろんこれは悪例として挙げたのであって、がんらい、そんな稚技をほんとにやってしまうのは、桐島の映画部の前田涼也くらいなものである。
それはともかく、この専門用語のわからない映像効果を使った、個人的にもっとも琴線へきたシーンが、ブルーベルベットのラブレターだった。
わたしは当時このケティレスターという古い黒人歌手がうたうラブレターのソースを血眼になって探した記憶がある。まだ、ものの数秒でその楽曲へたどりつける時代ではなかった。
プレスリーもナットキングコールもJulie Londonも歌うがケティレスターのラブレターはムード歌謡の雰囲気がない。なんと言ったらいいのかわからないが、地獄の底のクラブで聴いたラブレター──であり、胸にくるというより脳にくる。むろんブルーベルベットのなかで聴いたから──でもある。
ジェフリーが部屋へはいるとふたりの男が死んでいる。ひとりは椅子にいてベルベットを口に詰め込まれ耳を削がれている。ひとりは立ったまま、死後硬直をおこしている。そこへラブレターが流れてくる。銃撃があり窓ガラスが砕ける。ジェフリーが独言する。
見返したら、それだけ、である。が、高校生だった私が、この映画から受けた衝撃はすさまじいものだった。
ロイオービソンが甘い歌謡からいびつな歌謡へ印象が変わる。──いうなれば、世界の見方を変える映画だった。
じっさいツインピークスやこの映画等によってリンチが世界中の映像作家におよぼした影響は計り知れない。数多のサイコサスペンスにその影響を見るし、日本の映像作家がどや顔でつくった刑事ものやスリラーにもリンチの影を感じない──ものはない。
センセーショナル?
In Dreams/お菓子のピエロ
デヴィッド・リンチの世界。普通じゃ思いつかないような展開
ジェフリー(マクラクラン)はウィリアムズ刑事の娘サンディ(ローラ・ダーン)とともに片耳の謎を追うべく、歌手をやってるドロシー・ヴァレンス(ロッセリーニ)を探る。害虫駆除業者を装い部屋に入り鍵を盗むジェフリー。その晩、ドロシーが歌うクラブで彼女の歌を聞き、すかさず彼女のアパートへ忍び込む。ドロシーが戻ってきてクローゼットに隠れていたジェフリー。悪党のフランク(ホッパー)がやってきて、彼女に変態プレイを強要する現場を目撃してしまう。ドロシーは夫ドンと息子が誘拐されている様子がうかがえた。やがて、ジェフリーとドロシーも禁断の関係へ。
ほとんどジェフリーを通して見たシーンで、通常のサスペンスの描き方と違うところもいい。どうしてそこまで好奇心を持つのかという不自然さもあるが、これがいいところなのだろう。冒頭で、父親が庭の水まきをして倒れるシーンも違和感があって印象的。犬が必死で水を飲もうとしている姿には笑えるし。終盤でドロシーの部屋で刑事の一人が立ったまま死んでるところもシュールだ。
光と闇
んー、、深い作品なのかな?
ちゃんと考えながら視聴すれば深い作品なのかなとは思いましたけど…
それ以前にあのアブノーマルな世界観が無理、、
とうゆうことはこの作品は自分には合わなかったのかな〜と思いますね 笑
途中軽く寝落ちしちゃいましたし…
言語化して考えるより感じたほうが適切
この映画は言語化して理由を説明できるところとできないところがある気がする。
デニスホッパーがガスを吸うシーンは、もともとはヘリウムガスを使うはずだったらしく、彼自身が映画で使った方のガスを選んだそうだ。ヘリウムガスで声が高くなり赤ん坊のようになるのもそれはそれで狂気じみて怖かったと思う。
見たことのない絵を見せられ、この構図が奇妙で、不気味さを感じられるのが面白い。適切な表現か分からないが、あの部屋で2人の男が死んでいるシーンの構図は完璧に奇妙で、格好良かった。
見れば見るほど感じられるモノが深くなる映画だと思う。
あのころワタシは若かった
全37件中、21~37件目を表示