ネタバレ! クリックして本文を読む
大島渚監督の1978年作品。同年のカンヌ国際映画祭でフランス映画高等技術委員会賞(いわゆる監督賞)を受賞しています。
明治期の日本、北関東らしいところにある寒村。
人力車夫の儀三郎(田村高廣)と妻のせき(吉行和子)が幼い子どもともに暮らしていた。
ふたりはもう四十過ぎ、どちらかいえば五十に近いが、せきはいつまでも若々しい。
ふたりのもとに足しげく通うのは戦争帰りの豊次(藤竜也)。
二十六も年の離れた豊次とせきだったが、いつしか懇ろになり、そして、ある日、ふたりして儀三郎を殺してしまうのだった・・・
といったところから始まる物語で、ふたりは儀三郎の亡骸を裏山にいくつもある古井戸のひとつに投げ入れ、義三郎は東京で車引きをしていることにする・・・
が、やがて、せきの前に、儀三郎が亡霊となって現れる・・・と展開する。
ま、こう書くと、普通の亡霊譚で、実際そうなのだが、映画の雰囲気はなんだか微妙。
年の離れた男女の愛欲を描くでなし、亡霊に悩まされる恐怖を描くでなし・・・
せきと豊次の睦事のシーンもいくつかあり、それも個々にはたっぷりと描かれるのだが、意外なほどエロチシズムは感じない。
つらつらと考えると、儀三郎を殺した後、豊次のせきに対する熱情が薄れてしまっているせいではなかろうか。
豊次の心は、儀三郎を殺した時点で何かが終わっており、生にも性にも固執していないようにみえる。
さらに亡霊譚としては異例のことなのだが、亡霊となった儀三郎はせきの前にしか現れないし、恨み言の一言も発さない。
田村高廣演じる亡霊は、血の気の引いた顔をしているだけで、おどろおどろしいわけでなく、ほんとうに幽玄というか、かそけきというか、けそやかいうか、儚く存在しているだけ・・・といった風情。
観ているうちに気づいたのは、「あぁ、三人は生と死の狭間にはまり込んだんだな」ということ。
後半、川谷拓三扮する巡査が登場して、せきも豊次もいくぶん生側に引っ張り込むのだけれど、三途の川の河原にいるふたりを生側に戻すことはできません。
そういえば、巻頭は、坂東の川に架かる木橋を渡る儀三郎の画なのだが、あの川は、やはり三途の川であったのだろう。
「L'EMPIRE DE LA PASSION」は「熱情の帝国」の意なのだろうが、PASSIONにはキリスト教における受難の意味もある。
儀三郎、せき、豊次の三人がはまり込んだ生と死のはざまの国なのかもしれません。
なお、美術も撮影もがっちりとつくられています。
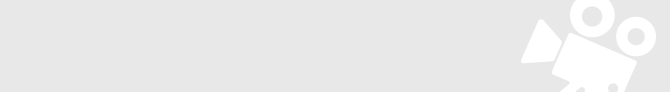





 戦場のメリークリスマス
戦場のメリークリスマス 愛のコリーダ
愛のコリーダ 御法度
御法度 マックス、モン・アムール
マックス、モン・アムール 夏の妹
夏の妹 ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 万引き家族
万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド















