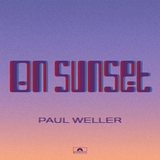2001年宇宙の旅のレビュー・感想・評価
全238件中、141~160件目を表示
神の領域
1968年作なのでアナログなフォトグラフックエフェクトが、現代の多様化されたCGのように感じます。
宇宙遊泳などはワイヤーで吊るして撮ったとか…
猿達も人間が猿スーツを着て特殊メークして…あの動きは猿でしかない。
IMAXの大迫力の音響が宇宙の映像と相まって素晴らしい。
途中、10分の休憩があるという3時間のストーリー…
壮大なる宇宙は、神の領域なんだと再確認しました☺️
モノリス(墓標)が各惑星に現れ、人類の進化を促す…
ラストの地球と誕生のシーンが目に焼き付いています。
因みにH ALは、スペルのIBMの一字前から取った文字だとか((̵̵́ ̆́̑͟˚̩̮ ̆̀̑)̵̵̀)
殺されずに生き残った類人猿
35年ぶりの再鑑賞。
人類の夜明け。
類人猿たち集団が水場で抗争をしている。
ある日、一方の集団が突如として現れた黒石板(モノリス)を発見。
その集団の一匹が、白骨化した動物の骨を握りしめ、それを道具として使い出し、水場で敵対集団の一匹をその骨で殴り殺す。
そして、その骨を空中に放り投げる・・・
といったところから始まる物語は有名なので、いまさら書くこともないのだけれど、とにかく「難解」という言葉がこの映画にはついて回っています。
で、改めて見直して、自分なりに解釈すると・・・
類人猿→人類→スターチャイルドという進化絵巻であることは間違いない。
が、何によって進化するのかが重要。
モノリスを発見した類人猿は、骨を道具とすることを発見し、それが進化をもたらした・・・と思っていたのだけれど、少々違和感を感じました。
「道具を得て進化する」ということならば、月で発見されたモノリスは、人類に何をもたらしたのか?
空中に放り投げられた骨が、宇宙空間を飛ぶスペースシャトルのカットに繋げられているので、骨→スペースシャトルという道具の進化のようにみえるけれど、本当のところは、スペースシャトル船内に漂うペンに繋がっているように思えます。
物理的な道具=骨、理論的な道具=ペン、そして理論的道具として最高峰のコンピュータ。
ただし、道具の進化にモノリスは関わっていない・・・
となると、モノリスが関わっているのは何か?
ディスカバリー号での木星探索な過程で、コンピュータHALが叛乱を起こす、とこれまで思っていたが、叛乱ではなく予め計画された行動ではなかったのか?
と、考えると、コンピュータ=道具であり、これは、道具を使って、人を殺すハナシだけなのではないか・・・そう行き着いた。
人殺しの度に人類は進化するが、進化するのは殺した方ではなく、殺されずに生き残った方(ボウマン船長はHALに殺されずに生き残り、時空間を超え、スターチャイルドとして生まれ変わる)。
進化を促す「人殺し」の度にモノリスは出現し、生き残った方が進化する・・・そう解釈するのは、いかがなものでしょうかしらん。
圧巻の映像…荘厳な宇宙へ
IMAXで2回目の鑑賞(字幕)。
原作は未読。
高校生の頃に廉価版DVDを購入し、観ようとして冒頭10分でリタイア。お猿たちが道具を使うことを覚えるまでのシーンまでで「こりゃ耐えられんなぁ」となってしまいました。年齢的に観るのがちょっと早過ぎたのかもしれません。
その後数々の名作・傑作映画を鑑賞し、かなりの時間を掛けて心と頭にある程度の下地をつくった上で、2018年1月に廉価版ブルーレイを購入して鑑賞。最後まで観ることが出来ました。ラストシーンはちんぷんかんぷんでしたが…
クォリティーの高い映像に魅せられ、AIの反乱と云う内容の先見性に目を見張り、壮大なクラシック音楽も相まって、ただのSF映画に収まらない芸術性を感じました。
2001年は過ぎてしまいましたが、それに伴って本作の価値が色褪せてしまうと云うことは無く、むしろ高まっていると云うか、ようやく時代の方が追いついて来たと云うか…。今日まで語り継がれる名作の魅力に引き込まれました。
上記の再鑑賞の後、2018年が製作50周年に当たることを知りました。こりゃ何かあるかもなぁ、と思っていたら…やっぱり。IMAX版で待望の劇場鑑賞出来ました。内容が理解出来る・出来ない以前に、この壮大なる名作を迫力の大画面とサウンドで体感出来たことの喜びを噛み締めました!
とにかく、映画への没入感がハンパなかったです。物語が醸し出すとてつもないリアリティーと緊迫感に震えました。
無音と云う音を感じる快感に酔い痴れ、誇張でもなんでもなく、宇宙を旅したような感覚に囚われてしまいました。
ワープ・シーンに幻惑され、文字通り目が眩みそうになりました。脳髄から何から、肉体の全てを揺さぶられるような感覚でした。どこから出て来るんだこの発想は、みたいな。
高画質になっても、全く粗の見えないセットや小道具が素晴らしい。つくり込みが精緻で見劣りしない。圧倒されました。
何より、全てが美しい。息を呑みました。これぞ究極の本物感。これが映画の神髄なのかもしれないと思いました。
一切の妥協を許さなかったと云うスタンリー・キューブリック監督の強いこだわりを全編に感じました。
[余談]
序曲と終曲で明かりをつけるのはどうかなと思いました。
これも映画の一部なのに…。そこがちょっと残念でした。
[以降の鑑賞記録]
2020/10/13:Ultra HD Blu-ray(字幕)
※修正(2024/06/18
SF映画の嚆矢にして究極
これまで、僕はこの映画を3回観ている。
名作を片っ端から観ていた学生時代に初めてビデオで観たが、さっぱり解らなかった。
その後、リバイバル上映があって友達何人かで観た。何人かで観たら、解るようになることを期待した。しかし、解らなかった。
最後は、友達のお父さんがレーザーディスクを買ったとのことで家に遊びに行った。(確か)「ゴッドファーザー」とどちらがいいか?と言われて本作を選んだ。友達のお父さんは映画好きらしく、納得のいく解説を期待したが、解ったことと言えば、大人にとっても難解な作品だということだった。
その「2001年宇宙の旅」がデジタルリストアされてIMAXで2週間限定上映とのこと。
これは観たい。
僕の興味は「いまの自分が、この映画をどう理解するか」という点にあった。
さて、第一印象は映像の傑出した美しさである。
これをIMAXのスクリーンで観られるのは本当に幸せだ。
有名な、「美しき青きドナウ」に合わせて宇宙ステーションが“踊る”シーンはもちろん、宇宙ステーションの中を歩くシーン、ディスカバリー号でのトレーニング、HALを“殺す”シーンなど、そこだけ切り取って静止画にして眺めても見とれてしまうようなシーンが続出だ。
白を基調にした画面作り、そして時折そこに加わる鮮烈な赤。この映像美は、もうアートの域と言っていい。
それと、技術的な考証の確かさも驚異的である。
「いまの」宇宙船、宇宙ステーションと説明されても疑いようがないほどの完成度。本作の公開は1968年、つまりアポロ計画が月に到達する前であることが信じられない。
監督のスタンリー・キューブリックは当時の第一線の研究者たちに話を聞いて設定を考えたのだという。キューブリックの完璧主義の賜物である。
映画は3部構成になっていて、初めは猿人たちのシーンから始まる。
ちなみに、この猿人がまたよく出来ている。日本だとウルトラセブンやってる時代に、この着ぐるみの猿人たちは本当にホンモノのようでびっくりする。
さて、第1部だが、猿人が暮らしているところに、ある日突然、モノリスが現れる。モノリスに触れた猿人は道具を使うことを覚え、動物の骨を武器に使い始める。武器を手にした群れは、別の群れが支配する水場を襲い、勝利する。
昔はワケがわからなかった猿人パートだが、今回は非常によくわかった。
道具がやがて人殺しの武器になる、というのは非常に象徴的だ。後半、コンピュータのHALが暴走して乗組員たちを殺すことにもつながるし、ダイナマイト、飛行機、核兵器など例を挙げるまでもなく、始めは人類の進歩に寄与するはずだったものが、やがて殺し合いの道具になっていくことを表しているとも言える。
この時代は冷戦の最中で世界は核の傘の下にあった。そうした時代も反映しているのだろう。
宇宙のシーンもいま観ると、いろんな「仕込み」が見つかる。例えばアメリカの衛星には「アメリカ空軍」のマークが付いていて、未来の宇宙は軍事利用されていることを表している。また、登場するスペースシャトルはパン・アメリカン航空(いまは倒産して存在しないアメリカの航空会社)のロゴが付いているが、一方、宇宙ステーションの中にいるソビエト人たちはアエロフロートのロゴ付きバッグを持っている。宇宙に進出する時代になっても国家の枠組みは変わらない、ということである。
第2部から舞台は“2001年”に。
月でモノリスが発見され、それが木星に向かって強い電波を発していることがわかり、木星探査の旅に出る。
原題は「2001: a space odyssey」。
オデュッセイアとは、古代ギリシアの詩人ホメロスによる遠大な旅の物語。
そうか、この映画は「進化の旅」の話なんだな、と理解する。
猿人はモノリスに触れて道具を使い始めた。そこから400万年もの時間を必要としたが、人類は「道具」を、宇宙に行けるまでに発展させ、月でモノリスを発見した。
そして、モノリスは木星へと人類を導く。
そう、人類はモノリスに触れて進化する。
初めのモノリスから、実に長い進化の旅ではあったが、こうして人類は地上から月へ、そして木星へとたどり着くのだ。
たどり着いたのは木星探査宇宙船ディスカバリー号の船長デイヴィッド。
ここで彼を待っていたのは宇宙空間に浮かぶモノリスだ。
そしてデイヴィッドはスターゲイトを通り抜け、そして奇妙な中世風の部屋に行き着くのだ。
デイヴィッドは、その部屋の中でナイフとフォークを使って食事をする歳をとった自分自身を見る。さらに、その食事をしているデイヴィッドは、ベッドに横たわる老いた自分自身を見る。そして最後は赤ん坊(スターチャイルド)となり、地球を見つめる。
見て、入れ替わって、年を取っていく。400万年前の地上から始まった月、木星とつなぐリレー。生物は海から陸に上がって進化した。それと同様、地球から宇宙に出た人類は進化してスターチャイルドとなった。
この映画、説明的なセリフもナレーションもない。ゆえに解りにくいのだが、大きな物語と取ることで「進化の旅」というテーマが見えてくる。
若い頃の自分は暗喩というものを理解できていなかったのだろう。
こうして本作を捉えると、その後の様々な作品への影響が見えてくる。
「スターウォーズ」「スタートレック」は人類以外の知的生命体が当たり前に存在するという世界観が共通する。宇宙船内の密室のサスペンスという点では「エイリアン」。宇宙に出た人類の進化という点は「ガンダム」のニュータイプにつながるし、「Zガンダム」の最終決戦の舞台が木星という点や、「00(ダブルオー)」における「宇宙空間が国家の覇権を争う場となっている」という設定にも影響を見て取れるだろう。
こうして、「2001年宇宙の旅」を語ろうとすれば、様々な切り口から、いくらでも語れてしまう。それほどの知的スケールを持つ作品ということだ。
次に本作を観るのはいつのことか。そのとき、僕はなにを感じ、どう思うのだろうか。
とにかく観よう
映像は
何度観ても変わらない感覚。
アナログの野生、デジタルの洗練
言わずと知れた傑作だが、劇場での鑑賞経験は無かった。しかし、先日機会に恵まれ、国立映画アーカイブにて70mmフィルム、そしてIMAXも鑑賞することができたのでその感想を記す。
70mmには、ノスタルジアが正しい評価の支障になるかと思ったが、杞憂であった。やはり70mmにはデジタルには無い魅力がある。
1つ目は、THE DAWN OF MANにおける風景の美しさである。これはいきなり度肝を抜かれたのだが、なんと言えば良いのか、所謂「淡さ」なのだろうか、まるでモネの絵画の光の描写のような空気感、景色の奥行きを感じたのである。これはIMAXデジタルでは感じることが出来なかった印象である。つまり、デジタルの洗練に対するアナログの「野生」を感じ取れるのだ。
2つ目は、HAL9000の狂気である。これはIMAXの大画面で観ても流石に抱く感情だが、HALが持ってはいけない「意志」を持つことの恐怖、コンピュータが人間の支配を脱した瞬間、この狂気は70mmの野生的な映像を通すと鳥肌が立つほどのものだ。表情の読み取れぬ真紅に灯るランプ、それがアナログのフィルムに揺れる。
公開50周年の節目にこの鑑賞機会に恵まれた事は、幸福な事だと感じている。
未来の映画少年へ。
IMAXで体感できる幸せ
キューブリックを映画館(IMAX)で感じるチャンス
SF映画の原点、そしてこの映画を超えられない理由
長い時を経てとうとう公開されました。
とても楽しみにしていた分少しだけ不満が、
冒頭の画面でなぜ館内を消灯しないのかだけでした。あの冒頭の真っ暗な画面でなぜ音楽だけが流れているかその真意を解っていれば!消灯するでしょう!!ねぇ!!(笑)
IMAXという環境を得て更に迫力が増しています。これこそ映画に潜入しているかの様などデカイ音量で『2001年 宇宙の旅』を満喫できます。
あの頭を抱える様な音量、正に体験です。
まず評価の点ですが、まずは映画の意味を理解できるまで、見て、また考える必要があります。
そして!その意味を理解した時にあなたは感激するのです!!
なぜここまで説明がナレーションがないのか、
それは洗練された内容だからこそ、あえて
あ!え!て!抜いてしまったのです。
監督自らの判断でこの映画には野暮な説明など要らない。そんな自身があったのです!
無論、最初に見られた方は呆然としたでしょう。
あの冒頭のわけのわからない無の時間、いえ!意味が解ってからは無ではないと解ります。寧ろ感激、感嘆、畏怖などの感情が込み上げてくるでしょう。
だって今あなたの目の前に、あるんですから…。
なによりまだ月に人がいってもいない時に作られた映像に、当時の人はピンと来なかったでしょう。
これがいかに驚愕な事かわかりますか?
今SF物がありあふれている世の中では当たり前な内容です、宇宙飛行、ロケット、コンピューター、冬眠計画、違うんです!観点を変えて見てください!この映画がSF映画の原点なのです!この映画よりも前の作品が存在しなかったのです。今のSF物の多くは、この映画の影響を受けていると断言できます。
だからこそSF物ではこの映画を越えるものはないのです。スタンリーキューブリックのリアルを求める姿勢の究極がこの映画には詰まっています。
時を越えて復刻され、あのIMAXの画面だからこそわかる明瞭かつ繊細な映像!終始圧倒されました。
ここまで読んでくださっているあなた!!
もし、まだこの映画を観ていないなら必ず見るべきです。そして意味が解ってから最低2度以上観るべきです!もうこんな映画をこの迫力のある環境で観れる機会はないですよ!
私は時間がある限り、この放映されている映画を観に行きます!
2001年宇宙の旅 IMAX版
何度か観てますが、映画館で始めて鑑賞。しかもIMAXの大画面! 改...
IMAXで観れてよかった!
この機会を逃すのはあまりにも勿体ない‼️
昔流行ったクイズ。
HALの名前の由来知ってる?
答え…IBMのひとつ前のアルファベットを並べた。
1964年 東京オリンピック(戦後わずか20年‼︎)
1968年 2001年宇宙の旅
1969年 アポロ月面着陸
と歴史的偉業と並べて語られても違和感を覚える人の方が少ないほどの作品。
アポロ月面着陸は捏造だと信じる人たちの根拠のひとつにこの映画の中で極秘裏に政府がスタンリー・キューブリックにNASA用の映像を作らせた、というのがあるほどですから、そのクオリティーの高さを是非劇場で確かめていただきたい。
今、アイマックスの大画面と高音質で再び鑑賞出来る…そのことだけでも大興奮‼️
昔、『ぴあテンもあテン』や『はみだしユーとぴあ』などにハマっていた世代の方は冒頭の〝ツァラトゥストラかく語りき〟を聴き終わった時には涙が滲んでいると思います。ヒトザルの放った骨から〝美しき青きドナウ〟が一段落する頃には並の映画1本分の情感を使い切ってしまいます。
でも、ちゃんと休憩があるので、最後まで見届けるのには影響ないのでご安心のほど。
勿論、昔を知らず郷愁の念など無い若い世代の方にも是非体験していただきたい。現代のSF作品……スターウォーズ、インターステラー、エイリアンなど名だたる作品の多くが何らかの影響を受け、或いはオマージュを捧げていることが分かります。
それでいて、今もなお古臭さを感じさせない普遍性を宿している。
上映期間がいつまでか分かりませんが、この機会を逃すのはあまりに勿体ないと思い、投稿しました。
全238件中、141~160件目を表示