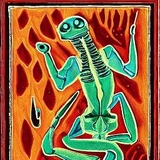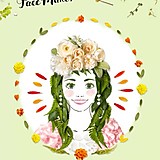時計じかけのオレンジのレビュー・感想・評価
全161件中、41~60件目を表示
いやぁな気持ちになれます
部屋とか衣装はおしゃれだけど、描写が見るに堪えない サイコパス
始めっから、気分が悪くなる映像です。
レイプのシーンや性描写ばっかりで、そういうような描写に触れたくない人は絶対に見ない方がいい!
そして、もちろん子どもは見てはダメだし、青年や若者は思考に影響を与える可能性があるので、みない方が良いと思います。上映禁止になった理由もよくわかります。
私も大人ですし、一線を置いて一つの作品として鑑賞できるくらい客観的に見れるようであれば良いのかも知れませんが、また私の脳みそに余計な画像がインプットされてしまったという気持ちがあります。
暴力が面白いとか言っている人は本当にやばいと思う。
ただ、スタンリーキューブリックの作品は、とにかくサイケでおしゃれ。
非日常の雰囲気を漂わせて、精神世界の話しのような感じにさせますよね。
あと、重厚感のあるBGMもキューブリックだなって思いますし、一つ一つの描写に妥協がないというのが素晴らしいなと思います。
そこが評価が高いポイントかも知れません。
50年も前の作品なのに、全然色褪せないし、斬新で新しいです。
評価が高い作品なので、頑張ってみました。
あんまり繰り返し見ると、精神病になってしまいそうです。
そこまで影響力のある映画だと思います。
精神力が落ちている時や、疲れている時はみない方が良いと思います。
映画に引きずられて病になってしまうと思います。
衝撃
ヒューマニズムの偽善批判と英国病理への風刺
この映画でキューブリックは二つのことを描いている。
一つは世界を覆うヒューマニズムはウソで、人間は他者に対する攻撃本能があり、バイオレンスは快楽である、ということ。
二つ目は、揺り籠から墓場まで個人の生活に介入し、英国病をもたらした英国福祉政策に対する風刺である。
1)ヒューマニズムのウソについて
一つ目のヒューマニズムのウソという点は、社会のタブーに挑むキューブリックの面目躍如たるところ。
主人公たちが悪ガキグループや安穏に暮らす人々を襲い、破壊し殴り蹴り斬りつけレイプするシーンは、人間にとって暴力がいかに快感かを、これでもかと言わんばかりに観客に見せつけた。
対立する悪ガキグループのリーダーは、主人公からの悪口雑言をニヤニヤ聞き、嬉しそうに飛び出しナイフを取り出して、グループ全員が闘いに突入していく。
今ならヘビメタコンサート会場で、聴衆が喜び勇んでモッシュ(押しくら饅頭)に突入するするさまに似ている。
バイオレンス映画といえばペキンパー監督作品がその代名詞であり、すでにこの頃、「ワイルド・バンチ」などが公開されている。
しかし、そこには暴力は人間にとって快楽であるという自覚的な思想は伺えず、そのような自覚的、思想的「バイオレンス映画」は、この作品から誕生したのだと思われる。
2)英国の社会国家政策の愚かさについて
次に、こうしたバイオレンス男を英国社会は、どのように扱うか。
英国の社会国家政策は「揺り籠から墓場まで」と揶揄されたように、個人の生活に過度に関与し、その財源を国民、企業から重い税負担で徴収したことから景気が低迷。そのさまが英国病と呼ばれたことは有名である。
重い税負担については、ビートルズの「タックスマン」やキンクス「サニーアフタヌーン」などが批判や揶揄をこめて歌っている。
本作の後半は、「揺り籠から墓場まで」への風刺と言え、犯罪者の教育、矯正、果ては人格改造にまで乗り出す、個人への国家の過度な関与への風刺となっている。
多数の専門家と物量と時間で、主人公はバイオレンス男から、見事に暴力のぼの字さえ恐れる哀れな少年に変身してしまう。
しかし、それは逆に本人に対する暴力を呼び込み、その果てに自殺にまで至らせる。
そのドタバタが終わった時、人格改造の呪いが解けると、何が現れるのか…もとのバイオレンス男である。
こんなバカな個人への干渉をやるのは愚の骨頂だ。何故なら暴力は本能なんだから…というのがラストシーンの意味だろう。
3)評価
社会のタブーに対するキューブリックのバイオレンスが、全面的に解放された見事な映画だ。
さらに英国的形式主義を揶揄したシーンもたっぷり盛り込まれ、例えば主人公が刑務所に収監されるとき、白線の前に踏み出さないよう脅されるところなど、「ああ、英国病だなw」と感じる。
自業自得
【暴力思想矯正映画かと思いきや、非人道的行為の数々を最後には許容してしまう、極北のエロティック&シニカル映画。ホラー映画と言っても、良いのではないかと思う作品である。】
ー 誰でも知っている、この映画で、キーとして使われる「雨に唄えば」と「第九」。大昔にこの映画を観てから、「雨に唄えば」のメロディを聞くと、あの、作家の奥さんのレイプシーンを思い出すようになってしまった・・。ー
◆感想<初見時に、強烈に記憶に残っているシーン&内容に触れています。>
・アレックス達4人の悪童どころではない、暴力思想に支配された青年達”ドルーグ”がホームレスを棍棒で叩きのめした後に、作家夫婦の瀟洒な家に、”嘘を付いて入り込み”作家夫婦に「雨に唄えば」を歌いながら、悪逆非道の振舞いをするシーン。
奥さんの身体にフィットした赤い服を鋏で切り取り、夫を棍棒で殴りつける。
トンデモナイシーンが冒頭から続くが、瀟洒な作家の家の、白を基調にしたインテリアと、エロティック&バイオレンスシーンは、強烈である。
更に、彼らは翌日、再びある瀟洒な一軒家に忍び込み、白いペニス上のオブジェを老婦人に叩きつける。
ー 悪趣味な美術品と、アレックス達の悪逆非道振りが、妙にマッチして、独特の世界観を作り出している。ー
・アレックスのみが、逮捕され、”ルドヴィコ療法”を受けるシーン。眼を構成的に開かされ、定期的に目薬を差されながら、只管に残虐描写を見せられるシーン。
ー 大音量で流れる、アレックスの好きなベートーヴェンの「第九」。故に彼は、暴力シーンや、「第九」を聞くと、吐き気を覚えるようになるのだが、彼から本当に暴力思想が無くなったのであろうか・・。ー
・出所し、且つて暴力を振るったホームレスに会ったり、”ドルーグ”の仲間二人が、警官になっていて・・。
酷い暴力を受けたアレックスが逃げ込んだ家。そこは、且つて悪逆非道を働いた作家の家だった。車いす生活の作家(妻は、死亡している)からのベートーヴェンの「第九」による強烈な復讐。
ー この時点までは、アレックスへの因果応報映画として観ていた。だが・・。ー
・病院に収容されたアレックスは、一夜にして政府の”ルドヴィコ療法”の犠牲者として、祭り上げられ、大臣が詫びに来て、記者たちが多数訪れ、フラッシュを浴びせる中、大きなスピーカーが二つ持ち込まれ、大音量で流れるベートーヴェンの「第九」。
ー だが、アレックスは、「第九」に拒絶感も示さず、且つての悪逆な眼に戻り、大臣と肩を組んで、写真に写るのであった。そして、セックスシーン・・。ー
<スタンリー・キューブリック監督の
”人間の悪性は、簡単には変わらない”
と言う思想と、独特の美術が印象的な、エロティック&バイオレンスが横溢する、今から半世紀前の映画とは思えない、強烈なインパクトを持った作品である。>
吐き気を覚える胸糞
やべーのをみた
狂喜ではあるが
暴力と官能に満ち悪が元気で栄える世界
1回目見た時は何が主題なのかさっぱり分からなかったが、2回見てようやく解った様な気がした。ただ、見誤ってる可能性もなきにしもあらずだが。
老作家は神的なものを象徴するかの様に赤ワインを主人公に熱心に勧める。その結果、自殺衝動に駆られ死にかけたものの、最終的には、主人公アレックスは良い子からまた悪に舞い戻る。あれだけ酷いことを老作家や金持ち老婦人等にしたにもかかわらず。アレックスを嵌めた連中も警官になっていて更生したアレックスに暴行を加える。ラストではアレックスはずるい政治家と組み生活を保証され、善なはずの老作家の方が処分されたらしい。近未来らしいこの世界では、神が不在であり、どうやらこれが主題の一つであるらしい。
ただ、神の存在は無くても、ベートーヴェンの芸術、暴力と官能に満ちたその音楽は素晴らしく、政治家もアレックスもかつての仲間達、復讐する老人も活力に溢れ、輝いている様にも見える。暴力にエロは、清く正しく教条的なものより芸術的で、圧倒的に魅力もあり、神の不在こそが、そういったヒトを惹きつける芸術性を創り出す。キューブリックの挑戦的なメッセージを聞いた気がした。
音楽と効果音がよかった!
70'sロンドンの雰囲気を愉しめる映画
暴力と風刺
全161件中、41~60件目を表示