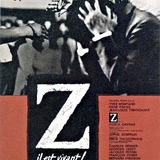十二人の怒れる男のレビュー・感想・評価
全85件中、21~40件目を表示
法廷ドラマの名作
地味目のおじさま12人が同じ場所(会議室)でひたすら話し合ってるだけの作品である。なのに、なんでこんなに!というくらい引き込まれ、気付けば1時間半、息を詰めて行方を見守っていた。1対11が12対0になるまでの、一人一人の意見の間違いが正されやがて各々の知見と良識を総動員して事件を検証していくさまはもう圧巻。
それにしても米国の陪審員制度って大変。全ての陪審員が私情や偏見を挟まずに慎重に検討する義務を果たしてはじめて成立する制度。特に、命に関わるような裁決の場合は、陪審員8番(ヘンリー・フォンダ)のような人が絶対に必要だけれど、こんな賢人、そんじょそこらにいるとは思えない…。
疑わしきは罰せず
ニューヨークのスラム街の自宅で、父親を殺したとして一人の不良少年が有罪判決を言い渡された。
もし刑が確定すれば第一級殺人として少年には死刑が言い渡される。
判決の行方は12人の陪審員たちに託された。
少年にとって圧倒的に不利な状況であり、刑の確定は時間の問題と思われたが、一人の陪審員が無罪を主張したために事態は思わぬ方向へ動き出す。
無罪を主張する陪審員8番にも確信があるわけではない。
しかし彼はあまりにも証人の証言が明確すぎることに疑問を感じていた。
そしてその他には状況証拠しかないことも。
彼は疑わしきは罰せずの精神で少年の無罪を主張する。
議論は平行線で行き詰まるかと思われたが、一人、また一人と無罪を主張する者が増えていき、事件は思わぬ真実を浮かび上がらせる。
法廷の一室のみで繰り広げられる会話劇だが、観る者の想像力を刺激する一級のサスペンスである。
物語が進むにつれて証人の証言が実は不確かなことが分かってくる。
もしかすると証言をした老人は、ただ注目を浴びたかっただけかもしれない。
もしかすると少年が殺す現場を目撃したと証言する女性にも見栄を張る癖があったのかもしれない。
ただそれらもすべて推測でしかなく、真実は法定では一切分からない。
おそらく事実がどうであるかはこの映画の描く目的ではない。
この映画が伝えるのは偏見によって物事を見てしまう人間の怖さだ。
人の命はどんな生まれだろうと、等しく重いものだ。
スラム街で育った不良少年だから人を殺しても当然だろう。
この映画の名シーンのひとつは、あくまでこのように主張し続ける陪審員10番に対して、一人、また一人と陪審員たちが背を向けるところだ。
そして男は自分の意見が無視されていく様に呆然となり、最後には無罪に同調する。
そして印象的だったのが最後まで有罪を主張する陪審員3番の姿だ。
10番の時とは反対に皆が無言で彼を見つめ続ける。
彼もまた個人的な偏見によって事件を見ていたことが分かる。
実の息子と疎遠な関係になってしまったことの腹いせとして、彼は何としても父親殺しの罪を少年に着せたかったのだ。
しかしついに彼も自分の意見の無理矢理さに気づき、観念して無罪に同調する。
個人的にはまっさきに8番の意見に同調した9番の老人の洞察力の鋭さが印象に残った。
観ているこちら側にも熱気が伝わってくるような凄みのある作品で、やはり何度観ても画面に引き込まれる。
別れ際に8番と9番がお互いに名乗り合うシーンも印象的だった。
議論だけなのに、面白かった。
『十二人の怒れる男』鑑賞。
*主演*
ヘンリー・フォンダ
*感想*
父親を殺した罪に問われた少年の裁判で、12人の陪審員が評決に達するまで一室で議論する様子を描く作品。
11人の陪審員は有罪、8番の陪審員だけが無罪から議論がスタートします。
たった一人だけ少年は無罪だと主張する8番に対して、他の11人は不満や苛立ちを全面に出してきます。11対1という完全不利な状況なのに、議論が進むにつれて11人の陪審員が少しずつ心が動かされていく描写が非常に上手かった。
舞台が部屋の一室で、アクションなど全くなく、12人の男たちが汗をかきながら、議論するだけの映画でしたが、とても面白かったです!
凄いのを見た
どんどん謎が解けていき、一人また一人と無罪の人が増えていくのが物凄く熱いし気持ち良いしで、後半の方はずっと興奮が抑えられなかった。
キャラが皆人間臭過ぎるのが本当にいい。ストーリーの為に動かされてるんじゃなくて、本当にキャラが考えて喋ってるかのようだった。皆好きになってしまった(笑)
演技も素晴らしかった。人間臭さを伝えられるのもそうだけど、心情の変化を細かなニュアンスで表現できてたのも凄いと思った。
12人の男たちが議論するという題材をここまで面白くできるとは思わなかった。制約が多くて、あまり動きのある画や自然の力などを使った画を撮れないからこそ、脚本、演技、撮影の細かな技術が光る、映画として完成度の高い文句無しの傑作でした。
反対派がギャーギャー五月蝿い。
再見。乗れず。
反対派が理不尽にギャーギヤー五月蝿いから、
直ぐ引いた。
巨匠ルメットは本作からしっとりと伸びた人と見よう。
これを過剰に褒めて若い映画ファンを逃さぬよう。
なので、まあよく出来たらしい有名な凡作、と言おう。
57年か。
有罪派の11人vs 無罪派の1人
少年が親父を刺殺したという事件に陪審員として集まった12人の男性たち。絶対に有罪やろという雰囲気の中、1人だけが無実と言いだしてから議論が白熱する話。
これは名作と言われるだけのことがある。
人生のベストに入るくらいの傑作。(偉そうだ)
裁判、殺人現場、回想といった映画ならではのシーンは皆無。ほとんど一室の中で完結する。
ただ12人のおっさんが汗まみれで声を荒げたりするだけの映画なのに、こんなにも1時間半ちょっとが一瞬に感じたのは久しぶり。
無実といった男性の理路整然とした推理にドンドンと周りが「確かに言われてみれば」と、考える気もしなかった人たちが逆転していく。
そこでそれぞれの人の態度や言動で人物像が浮かび上がる。12人の背景は全く分からないのに。
外が大雨で室内がジメジメした高温。おっさんたちが時間を追うたびに汗だくになっていくさまは、議論の白熱パラメータみたいで面白い。
そして最後は、全員の名前も知らないまま、それぞれの元の生活に戻っていく後ろ姿。あーオシャレ。最高。
タイトルなし(ネタバレ)
『十二人の怒れる男』
この映画は1957年のモノクロ映画で、監督シドニー・ルメット、ヘンリー・フォンダが主演の法廷サスペンスもので、ヘンリー・フォンダがプロデュースもしている。かなり前に観て、面白い、よく出来ているストーリーだと思っていたが、この度レビューを書くにあたって、改めて映画を観てみた。やっぱり面白い。
1時間半と割と短めだが、その中には、観ている人を引き込むエッセンスがギュッと詰め込まれている。
裁判所の法廷で、陪審員たちが裁判官から説明を受けるシーンから始まり、父親を殺害したとされる18歳の青年が、法廷を後にする陪審員たちの姿を目で追っている、悲しげな顔が印象に残る。
ここからは、名前も名乗らず、ただ番号で呼ばれる12人の陪審員の男たちの、鍵を掛けられた密室でのやり取りが展開される。
夏の暑い日、部屋にはエアコンもなく、扇風機はあるが動かない…
12人の男たちは、窓を開けたり、タバコを吸ったり、他の話をしたりして、汗を拭っている。
陪審員長が、どうするか?とみんなに問いかけ、先ずは投票しようということになった。評決は全員一致でなければならない。挙手で有罪が11人、無罪が1人という結果だった。無罪を主張したのは8番の男だった。彼は「自分も、青年の話を多分信じていないと思うが、私が賛成(有罪を支持)したら、簡単に死刑が決まってしまう。人の生死を5分で決めて、もし間違っていたら?」と言う。
その後、一人ひとりが8番の彼を説得する案が出て、順番に男たちが意見を述べている中で、ナイフの話が出て、実際に使われた凶器のナイフを持って来てもらい、4番のメガネの男が話しながら、テーブルにそのナイフを突き立てた。そのナイフは、持ち手部分に特殊な絵柄があるものだった。そして、ここからビックリするのだが、何と8番の男は同じ絵柄のナイフをポケットから出して、凶器のナイフの隣に突き立てたのだ。「昨夜、青年がいた町に散歩に行って、そこの質屋で買ったもの」だと言う。青年は自分でナイフを買ったが、何処かで落としたと主張していた。他の男たちはそのナイフを見て皆、驚いていた。同じ絵柄のナイフで、他の人物が殺害したかも知れない…ということだ。このシーンは衝撃的だった。
その後、行き詰まった空気になった時、8番の男が「もう一度投票を。皆さん方11人に無記名で投票してもらいたい。私は遠慮する。有罪が11票なら私も賛成する」と提案をし、投票が行われ、結果は有罪が10、無罪が1だった。その無罪の1票を投票したのは9番の老人の男だった。彼は「この方が一人反対された。無罪とは言わず、確信がないと言った。勇気ある発言だ。そして誰かの支持に賭けた。だから、応じた」と語った。
この9番の老人の男はその後も、裁判中の階下に住む証人の老人のことをよく観察していて、そこから推測されることを述べたりして、この映画のキーとなる存在のような気がする。そして、最後にも…
その他、青年は映画を観に行ったと主張しているが、何故映画のタイトルを思い出せなかったのか?…何故犯人なら、家に戻って来たのか?…証人である、階下に住む老人は電車の騒音の中、「殺してやる」という青年の叫び声や人が倒れる音を本当に聞いたのか?…青年が逃げる姿を本当に見たのか?…それは可能なのか?…実際に検証をしてみる。この時、男たちの額には玉のような汗、服には汗染みが目立っていた。それほど緊迫していた様子がよく分かるシーンだ。
その他、父親が刺されたナイフの向きについての疑問…目撃者である、高架鉄道を挟んで向かいの家の女性は、通過中の回送電車越しに、青年が父親をナイフで刺すところを、本当に確実に見たのか?…等々疑問点が幾つもの浮き彫りになってくる。
最初は、何の疑いもなく、有罪と決めつけていた男たちだが、議論を重ねていくうちに次々と、見逃されていた疑わしい点が出てくる。ということは、最初に8番の男が無罪を主張していなかったら、いったいどうなっていたのか?と思うと、恐ろしくなるような話だ。
8番の男が「偏見は真実を曇らせる。私は真実を知らないし、誰にも分からない。9人は無罪だと思っている。疑問がある限り、有罪には出来ない。でも、これは推理で間違いかも知れない」というシーンがある。「疑わしきは罰せず」ということだ。
途中、何度も投票をしようという提案があり、その度に一人また一人と有罪を主張する人数が減り、無罪の人数が増えてくる。
映画の中では、12人の各々の人間性も描かれている。誠実に向き合っている男、早く帰りたいばかりに、いい加減なことを言う男、自分の息子のことを持ち出して、個人的な感情を剥き出しにする男、偏見の塊のような男…
そして、9番の男が最後に、誰も気づかなかった決定的なことを言う。そのことで一気に流れは無罪へと向かう。あと一人だけ有罪を主張していた3番の男は、感情的に喚き散らしたが、他の11人の男たちから、問い詰められるようにジッと見られ、最後は弱々しく、無罪と言った。
これで、当初有罪が11、無罪が1だったのが、最終的には全員一致で無罪という評決に変わった。
ある意味、どんでん返しの展開だが、素晴らしい内容の映画だった。この映画の中には、教訓も含まれていると思う。偏見や思い込みで物事を判断してはいけないと…。
陪審員がいる一部屋だけで話が進行し、裁判の回想シーンもなく、登場人物も殆んど陪審員だけという密室の映画。
私は舞台が好きで、よく観劇に行くが、一室だけでの展開の芝居はあるが、人の出入りが全くないというのは、殆んどないかも知れない。映画と舞台は、勿論違うが…
大きなセットを作ったり、ロケをしたりすることなく、一室だけでもちゃんと映画は成立するということを証明した映画だったと思う。
ラストは、8番と9番の男がお互いに名前を名乗って、それぞれ帰って行くシーンで終わったが、清々しい気持ちにさせてもらった、いい映画だった。
証人の記憶の不確かさと、感情が判断に及ぼす影響
被告は有罪だと結論ありきの主張をする人や、憶測で意見する人が多い中、最初に無罪を主張した陪審員8番は、検証を通じて論理的かつ公平な主張を行う。まさに刑事裁判の原則である「疑わしきは罰せず」を体現している。議論とは本来こうあるのが理想なのだろうが、現実は中々そうはいかないのが、陪審員達の議論を通じて描かれている。
印象的なのは、証人の記憶の不確かさと、物事の判断に感情が及ぼす影響の大きさだ。陪審員8番による検証によって、裁判で出た証言と検証結果の矛盾が証明されてしまった。証人の2人が被告の少年を元々知っていたのかは分からない。しかしわざわざ被告が不利になる証言をするところから、被告の少年の素行の悪さを元々知っていたために、悪感情を持っていたのではないかと思う。その結果、不確かな記憶にもかかわらず、自分の感情に合致するように記憶が捻じ曲げられた印象を受けた。また、有罪を支持する陪審員達も、その主張の根底にあるのが、被告の少年が不良なために悪感情があることだ。人間が理屈よりも感情を優先し判断を下す生き物だということがよく分かる。
ストーリーの構成は、安易に犯人が判明したり、変に感動を狙うようなラストでないところが、リアリティがあり良かった。
いつ観ても、何度観ても、恐ろしく面白い
浮気して、昔過ぎる名作を観賞です。クーラーくらい用意したれよ!
前回に引き続き、この作品も、最初から“コレ!”と決めていたのではなかったのですね。
アマプラで偶然に見つけた『白鯨』を観ようと思って鑑賞スタートさせたのですが。
直後にAmazonからの「最近追加されたおすすめ作品」メールの中にこちらがありまして。
以前から、名作の誉れ高い作品とは聞いていたので、かなり興味をもって鑑賞スタートです。
エイハブ船長ごめんなさい。そして『ザリガニの鳴くところ』いつ観るねん!
この作品、議論が白熱するにつれ、発汗の量が尋常じゃなくなってくるんですよね。額も、シャツを濡らせる脇汗も。
クーラーくらい付けたれよ。せめて扇風機のスイッチの扱い方くらい教えといたれよ。と、ずーっと思いながら観ていましたね。
まだ肌寒い春先というのに、観ているこちら側まで暑くなってきましたよ。そして議論と同時にこちらのハートまでもが熱く。
?だったのが、観たのは吹き替え版だったのに、時々オリジナルの音声が入ってくること。why何故に?
観ていて思ったのは、それぞれのキャラクターのバックボーンが、見えてくるということ。
「この人の為人はこういう感じなんだなぁ」もっと言えば「こんな人生を歩んできたんだろうなぁ」というふうに想像が膨らみました。
お話の中では明確に語られることはありませんでしたけれど、シナリオと演技が何よりもそれを雄弁に語っていたように思えました。
お気に入りのキャラクターは主人公の隣に座っていた9番のお爺さん。突破口を開く鋭い観察力の持ち主の紳士だったので。
調べてみて「えつ!」と思ったのは、本作ってそれぞれのキャラクターに名前がないのですね。全ては陪審員〇番なのですね。普通なら名前のないキャラクターには感情移入しにくいと思うのですが。
本作は、あえてそうすることでリアリズムと臨場感を際立たせる手法の設定だと思いました。
劇伴が全くないことが、緊張感に一層輪をかけていたのは明らかだと思います。
てか、そもそもも現実の陪審員裁判って、「はっ!あんなふうにお互いの名前は明かさないのかな?」と思いつき。←えつ?勘違い?
職業とかの個人情報はダダ漏れでしたけれど。
陪審員裁判いついて、軽~く調べてみると、驚くべき情報が!
人の一生の中で、陪審員に選ばれるのって、約120人に1人なんだって。割と高確率。選ばれても私には耐えきれない重責。8番の人みたいな冷静で聡明な判断なんてムリ。ゼッタイ。
最後の最後に8番・主人公と、9番・お爺さんの名がお互いに明かされ。
雨の上がった屋外へ出た男たちが、やっとのことで重責を全うし、安堵と共に解放されていった晴れ晴れとしたラストシーンが素敵でした。優しく、爽やかなハッピーエンドを飾るに相応しい劇判もやっと流れてきて。
てか、紳士って真夏でもスーツ着なきゃだめなんだ。紳士でなくてよかった。ネクタイの結び方すら危なっかしい私だもの。
もといです。
それぞれの人物の心理描写の交錯が大変面白かったです。そしてディスカッションの中で本来あるべき姿、やっちゃいけないことのお手本となる教科書と言っても過言ではないとも思えました。
ディスカッションは、それ自体が映画向きの題材なのではないかと思いました。
入り乱れる思惑の駆け引き、お互いの主義主張のぶつかり合い、面子という自我の愚かさetc…
そして何よりも、私が好きなワンシチュエーションドラマです。
そもそも映画製作とは、試行錯誤のディスカッションによって完成されるものだと思います。←偉そうに
そんな現場の中に、本作のアイデアの源があったのではないかと思いを巡らせました。
ディベートともなると、刺激と業が強すぎるように思えて。私はディベートは苦手です。
今どきの若い子が憧れているらしい「はい論破」こそ、議論の最も愚かな成れの果てだと思います。←偉そうに
そして、監督以下制作スタッフ知識には、とんと疎い私ですが。(本作でも、お名前を耳にしたことのあるキャストはヘンリー・フォンダくらいです)本作が三谷劇場に多大な影響を与えたであろうことは、容易に想像できました。劇判のイメージまでをも含めて。
脇汗どころか、手に汗握る攻防に画面に見入ってしまった100分弱の大変楽素晴らしい体験でした。私の理想の尺の1時間半です。
謎なのがタイトル。そこまで怒ってた男って、3番の人くらいだったのに。私は、3番への皮肉も込めて『十二人の聡明な男』って脳内で勝手に解釈してしまいました。なんか弱っちい…
あれぇ、相変わらず“まくら”を置いている点を除けば、今回は全く私らしくないスタイルのレビューだぞ?
簡潔だし。
たまには真面目に書いてみたい時だってあるんです。←それでも、結構ふざけてるよ…
ワンシチュエーション映画の祖
裁判、怒りの言い合い。
改めて鑑賞して気がついたこと
言うまでもなく映画史に残る大傑作なのだが、2024年の今観てみると、昔観た時とは違った部分に目がいく。
・陪審員は男しかいない。
・陪審員にアジア系やアフリカ系がいない。
・女性を揶揄するセリフも普通にある。
・スラムの人々へのヘイトが思いの外激しい。
・ヘイトの構造はSNS時代の今も変わらない。
・移民の国なのに、移民を格下に見てるのか…。
・喫煙率がバカ高い。
・ウォーターサーバーがある!
・暑いという言葉通りみんなだんだん汗だくに。
・机上を片付けずに立ち去るのは文化の違いか。
時代の進んでいるところと、変わらないところが見えてくるのがおもしろい。
「脚本がよければ、シチュエーションを限定しても充分に一本の映画として説得力のあるものがつくれるという見本のような作品」としてだけでなく、リアリティがあるこうした映画には、「その時代を記録した資料的な側面」もあるんだなと思った。
そういえば、日本でも取り入れられた裁判員制度は、今はどうなっているのだろうか?
会話だけなのにひきこまれる
12人の陪審員
蒸し暑い部屋にカギまででかけられ、決定的証言や証拠があり有罪確定で
さっさと結論づけようという始まりから
ある男の有罪とは言い切れないということからスタートし
11人を無罪へと導いていく。
それぞれの陪審員が持つ背景からの発見や意見もとても興味深くつながっていて
面白かった。
周りに流されることなく簡単に決めず、自分の疑問や違和感を冷静に伝えていく
ことの大切さも感じた。
面白い
全85件中、21~40件目を表示