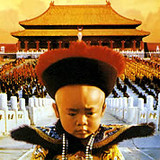フラガールのレビュー・感想・評価
全122件中、101~120件目を表示
スパリゾートハワイアンズで働きたくなる!
大泣き!号泣!
ちょっと若干弱っていたからかもしれないけど、
序盤から泣き始め、中盤から後半にかけては、
ハンカチグチョグチョ。
自分が生まれる少し前に、日本でも炭鉱があったなんて。
(なんか炭鉱=イギリスなイメージだった)
すごくストレートでわかりやすいお話。
老若男女みんな楽しめる良作。
なによりも蒼井優ちゃんのダンスシーンがすごく素敵。
『花とアリス』でもすごくかわいかったけど、
やっぱりバレエ経験があるってすごく重要。
この映画当時一番、girlyな女優さん。
松雪泰子も素敵だけど、蒼井優ちゃんと並ぶと、
年を重ねた感が出て、ちょっとつらい・・・。
フラダンスよりポリネシアンダンス(激しいほう)がやってみたくなる。
スパリゾートハワイアンズで働きたくなる。
福島万歳!!
2006年の日本映画の賞と話題を総ナメした感動エンターテイメント。
個人的にも、2006年のベストは今作か「嫌われ松子の一生」か大いに悩んだ。(悩んで悩んで、僅かな差で斬新な「松子」を選んだ)
僕はこの映画が無条件で好き。
何故なら、我が福島を舞台にこんなに魅力的な作品を作ってくれたから。
福島は都道府県の中でも目立つ県ではなく(悲)、今となっちゃ原発事故で変なイメージがついてしまったが(泣)、これほど福島の魅力を伝えてくれた作品はそうそう無い。
地元なので常磐ハワイアンセンター(現スパリゾートハワイアンズ)には何度か行った事がある。
この娯楽施設にこんな秘話があったとは。
炭鉱の田舎町にハワイを体験出来る施設を作る。
突拍子もないアイデアだが、最初から無理と決め付けるのは心外。
いつだって大胆なアイデアが現状を良き方向へと導く。
映画は、ベタと言ったらベタだが、それを最大限に上手く活かしきっている。
要所要所に見せ場を設け、盛り上げ方、笑いと泣きのメリハリの付け方、最後まで飽きさせない作り。
いい映画のお手本。
この映画の一番の話題は、蒼井優。
田舎娘を巧みに演じ、ラストのソロのフラダンスは見事の一言で、何の異論も無い。
でも、蒼井優と同じくらいに松雪泰子も素晴らしい。
しなやかなダンスはうっとりするほどで、男風呂に殴り込むシーンはブラボー!
気の強い中にほんの一瞬弱さも見せ、「優しくされるのに慣れてない」の台詞は特筆モノ。
この年、「嫌われ松子の一生」の中谷美紀が居なかったら、主演女優賞は独占だったろう。
富司純子も豊川悦司も岸部一徳もしずちゃんも徳永えりも、皆、好演!
公開時も今も支持されている人気作だが、それ故、アンチな意見も多い。
話がベタ過ぎという意見がある。だったら、苦悩と葛藤の複雑なドラマが見たかったのだろうか?
フラガールの事しか描いていないという意見がある。フラガールをメインにした事で、華のある映画に仕上がった。
史実に忠実ではないという意見がある。元々史実に忠実に映画化した訳ではなく、それなら何かのドキュメント番組を見ればいい。
映画の公開から数年後、福島は未曽有の大震災に見舞われた。
復興の今こそ、この映画を見直す価値はある。
復興と娯楽施設の開設…一見何の接点も無いが、希望と夢を追う姿に違いは無い。
もう何度も見ているが面白い。
何度見ても面白い。
練習はほとんどスクロール
正直、あまり何も言うことのない出来です。悪い意味で。
ただあえて言わせてもらえれば、フラダンスを題材にしてるってーのにそのフラダンスの練習シーンはスクロールです。いや、スルーっつってもいいんじゃないですか?
確かにフラダンスというのは競技スポーツとは違って、素人目から見れば練習の成果が分かりづらい類のものではありますが、(フラダンサーの皆さんスミマセン)それならば歌だって一緒のはずです。『天使にラブソングを…』はガタガタでズレズレの教会合唱団を、ほんのちょっとした工夫でたちまちのうちにファンキーな合唱団に仕上げたという展開です。それ自体がストーリー上での工夫なのですが、せめて『フラガール』もそういう展開を取り入れた方が……。
あと、キャラクターに誰一人共感を持てません。自分達が呼んでおいて「よそ者は出ていけ」とぬかす地元住民、呼ばれておいて最初から東京へ帰る気満々の先生、こんな人たちに「親の死に目に会えないのがプロ」などと日本人だけの琴線に触れるような講釈を垂れる資格はありません。
【本当の「苦・喜」の表出】
ドタバタ青春サクセスストーリーに昭和回顧・プロジェクトXの要素まで加え 且つ新進女優のアイドル映画的側面まで付与。 多くの要素を含みつつも その結合具合にムラがなく 作品にシッカリとした一本の筋が通っている。
作品の裏側ではダンス特訓の激しさが伺えるが、ラストシーンで女優達が見せる[涙雑じりの最高の笑顔]は、演技以前に その苦しい特訓をやり遂げた女優達の[本当の苦しさ・喜び][素]の部分を感じさせ 感動を最大限[Real]に近付けている。 ラストシークエンスのダンス後に一切の台詞・演技がない事も[素]の女優達である証だろう。
最高だが唐突な幕切れは、彼女達との別れを より困難で去り難くしている。
-
-
-
-
《劇場観賞》
団結を生み出すのは、体当たりのコミュニケーション
---------------------------------------------------------------
昭和40年(1965年)、大幅な規模縮小に追い込まれた常磐炭鉱。
危機的状況の中で、炭鉱で働く人々は、職場を失う現実・苦悩に
立ち向かう。
そんな中、町おこし事業として立ち上げた常磐ハワイアンセンター。
その誕生から成功までの実話が描かれている。
フラダンスの講師として訪れた平山まどかは、なかなか炭鉱の町の
人間に受け入れてもらえない。
しかし町の女性たちが、徐々にフラダンスの陣列に加わっていく。
そんな中、様々な出来事が起こる。
やがて平山まどかは、町から出ていくことも考えるが、生徒たちの
思いがそれを許さなかった。
講師の平山まどかと谷川紀美子の本気さが、やがて町の雰囲気をも
変えていく。
そして最後に、感動的なクライマックスが待ち受けている。
---------------------------------------------------------------
この映画には、
たくさんの名シーンがあります。
谷川紀美子が母親の千代の前で無言のままフラダンスを踊るシーン
熊野小百合が父親の訃報を聞かされながらも舞台に出演するシーン
フラダンスが大好きだった木村早苗が引越しをするシーン
その木村早苗がフランダンスをしていることを理由に父親に殴られた顔を見せまいとするシーン。
実はプライベートで苦労をしていた谷川紀美子の事実がわかるシーン
谷川紀美子の母親の千代がハワイアンセンターのために協力するシーン
そして全てが一つになった最後のクライマックスシーン
何度も胸が熱くなります。
笑いも泣きもあって、満足度の高い映画
邦画のレベルアップに貢献
主演の松雪泰子や蒼井優をはじめ出演者たちのフラダンスが見事というか、感動もの。
「スイングガールズ」といい本作といい、やっと日本の映画も誤魔化しのない役者魂が感じられる作品が多出してきた。
スピードを誤魔化すためのスローモーションが多い昨今、人間の動きの美しさを表現した本来の使い方のスローモーションが効いている。
ラスト、だらだらと出演者たちのアップを流さず、全員が舞台に繰り出して「やー!」ってフィニッシュしたところで潔く切りすてていたら、今年いちばんの作品になった。
p.s. 最近、制作会社が会社更生法を申請したが、映画を愛する気持ちが感じられる組織だっただけに残念。なんとか存続して、邦画の更なる飛躍に貢献してほしい。
ザ・ピーナッツの妹みたいに、可愛い
映画「フラガール」(李相日監督)から。
正直、どのシーンでメモしたフレーズか、
忘れてしまったけれど、これが一番面白かった。
東北弁?丸出しのいろいろな台詞もメモしたが、
この台詞には、勝てなかった。
たぶん、東京から呼び寄せたダンス教師(松雪泰子さん)を
初めて見た炭坑夫の反応だった気がする。
この台詞「ザ・ピーナッツの妹みたいに、可愛い」は、
一卵性の双子を見分けられることが前提だ。
それも瞬間的に、姉と妹を区別できるなんて。(笑)
脚本を書いた2人(李相日、羽原大介)に、
この台詞の意味を、確かめてみたい。
「こまどり姉妹」から「リンリンランラン」まで、
私は今でも、どちらが姉で、どちらが妹か、わからない。
「おすぎとピーコ」の違いが、やっと判るくらいかな。
蒼井優さんのセーラー服姿に萌え、
ラストシーンの彼女のフラダンスに、拍手してしまった私であるが、
こんな台詞が、気になる一言なんて・・「とほほ」って感じ。
2回も行っちゃった
拍手喝采
懐かしい常磐ハワイアンセンター
面白い映画でした
最初、映画のタイトルが出るのを見ずに、途中からみたので、方言が強くて、何の映画を見ているのかさっぱりわかりませんでした(汗)でも、しずちゃんが出てきたあたりで、何を見ているのかわかりました!!とても面白かったです!!笑いあり涙あり!!すっごくよかったです!!最後の方は涙がほろりと落ちてきてしまいました!!
古い考えと新しい考えが交錯…そんなところもみどころかなとおもいます!それでも、思いがつながる瞬間には感動です!!
これが実話であるだけに、頑張れば夢が叶うということを実感しました。フラダンスって手話なんですね。
常磐ハワイアンセンターの誕生秘話というと一見地味な話に見えます。
けれどもこの作品では、産業構造の転換によって追い込まれる炭坑町の町おこしと戦前からの古い価値観に束縛された女性の自立というテーマを見いだして、2時間のドラマを成立させました。
また本作が実話に基づいていて、著名な観光施設の物語であることと、主人公の平山まどかはまだ健在で地元でフラダンスを教えていることも、物語に現実感を感じさせる一因になっていると思います。
本作が2年前の映画賞を総ナメにした名作になった原動力は、なんと言っても出演者の本気度ですね。完璧な方便使い、3カ月にわたる猛特訓を重ねた、その成果が画面に結実していると思います。その真剣さは台詞回しでも激しい感情の応酬となり、すごく生き生きとした作品に仕上がっていると感じました。
それにしても、盆踊りしか知らない炭鉱娘にフラダンスを教えるとはなんと無謀なんでしょう。東京からダンス教師のまどかを呼んできたものの元花形ダンサーで気位の高いその女性は、最初は炭鉱や素人の炭鉱娘たちを馬鹿するばかり。練習を開始しても、感心ほどのダメダメぶり。なんでプロを呼ばないのよと岸辺一徳演じる担当の吉本に食ってかかったときの「田舎を馬鹿にするな!」という地元訛り丸出しの激しい抗弁がすごかったです。(まるで意味不明のレベル)
当初は渋々ダンスを教えていたまどかであったけれど、次第に生徒たちのひたむきな情熱に打たれて、本気で教え込むようになります。都落ちして人間不信にもなりかけていたまどかが生徒と一体になっていく様がすごくよかったです。
特に、フラダンスに反対する父親に生徒の一人が連れて行こうとした時、銭湯の男湯にまで乱入して、全裸の父親ととっくみ合いするところは迫力ありました。
また転居で生徒の一人と別れるとき見せるシャイな態度も、気持ちがこもっていましたね。
またこの作品にも富司純子がリーダー紀美子の母親役に出演しています。富司が出ていると作品が締まりますね。今回も強行に娘がフラダンスで踊ることを反対していたのです。偶然紀美子が真剣に練習しているところを無言で見つめているシーンが印象的でした。言葉に出さなくともわかり合えるって素敵ですね。そのあと炭坑閉山とハワイアンセンターに反対する労組員に向けて啖呵を切るところもすごく感動的でした。
本作でフラダンスは手話を兼ねていることを知りました。踊りで気持ちを伝えるという前振りは、終盤でとても感動的なメッセージを伝えてくれます。これを知ったなら皆さんもフラダンスって素敵!って思えるようになるでしょう。
随所にクグッと来るいい話を織り込んで、ラストのフラダンスに持って行きます。あのダメダメだったガールズがこんな立派なショーをこなしているなんて奇跡としか思えません。しかしこれは実話です。30年前に本当に田舎の炭坑町の少女たちがやり遂げた事実なんだと思うと、可能性を信じ、頑張れば夢が叶うということを実感しました。
追伸
その後、すっかりフラダンスのご意見番となった出演者のひとり、南海キャンディーズ・しずちゃんは、芸能界フラダンス部を結成。番組の企画で榊原郁恵、ユンソナらを従え、スパリゾート・ハワイアンズの舞台に立ったそうです。一番踊れなさそうな人だったですがねぇ。
ポータブルDVDによる車内鑑賞レビュー
まず、映画自体の感想を述べる前に、東北の寒村に ハワイ を作ってしまった当時の経営陣に心から敬意を表したいと思う。
炭鉱の閉山によって突きつけられた事業の変革に対して、豊富な温泉資源を活用しての 「常磐温泉センター」 という発想ならたやすくつくだろう。しかし、彼らは常人では思いもつかない付加価値を創出して、恐らく、日本で始めてのテーマパークを作り上げてしまったのです。
それが 「常磐ハワイアンセンター」 。
「東京デイズニーランド」 や 「志摩スペイン村」 「ハウステンボス」 なんてものは存在するはずもなく、テーマパークという言葉すらなかった昭和40年に、ハワイを創り上げてしまった彼らのプロデュース能力に大いに感心をしたのです。
ボクはこの一大事業のたったの一側面でしかない 「フラガール」 という限定された世界よりも、事業全体を経営的な観点から語っていく 「プロジェクトX」 にこそ興味を引かれていったのです。
正直に言うと、今作の題名ともなっている 「フラガール」 という一部分から、 「常磐ハワイアンセンター」 の事業全体を感じ取れる瞬間が少しでもあれば良いなと、いわば不純な気持ちで鑑賞を始めていたのです。
しかし、今作を鑑賞していく中で
【 「内」 ⇔ 「外」 の対比と、
「第1次産業」 ⇔ 「第3次産業」 という生き方の相違 】
【 ダンスの振り付けが雄弁に語る、物語進行上における法則性 】
という2つの側面がボクの興味を刺激していきました。
しょっぱなから、カワイイ女の子たちが福島弁丸出しで自分達のことを 「オレ」 と言うあたりにこの映画の狙いが見えてきました。福島の寒村に住む地元の少女たちと、彼女らをハワイアンダンサーに仕立てるために東京からやって来るダンス教師との ギャップ を、どうやら際立たせたい意向のようです。
「東京」 という記号に対して正反対の存在である、純朴で飾り気のない彼女達の存在が必要だったのでしょう。
ここから顕在化していった 「対比」 という予感は、松雪泰子演じるダンス教師が登場するシーンに象徴的に提示されていきました。
彼女は酒酔いと乗り物酔いによって 「橋」 の上で停滞を演じていくのですが、その場所が境界線を彷彿とさせる川の上であったのです。
「内 ⇔ 外」 という 「対比」 の関係性で考えると、川の向こう側である 「外」 から ダンス教師はやって来て、川のこちら側の 「内」 で生まれ育った 「オレ」 達 と出会うわけです。
このように 「内」 なるものと 「外」 なるものの 「対比」 の構図が、 「川」 という記号を軸にして提示されており、以降もこの表現方法は活用されていくことになります。
やがて、この 「内」 と 「外」 とのちょっとしたお約束的な軋轢があり、しかしながら、ダンス教師の踊りを目撃したことで、双方はあっと言う間に一つの方向に向かっていきました。
“激しい動きの後に、膝を折り仰向けに倒れるように沈み込む。
長い静寂の後、引き上げられるように膝を支点にして上半身をおこす”
この軋轢を沈静化させた振り付けを、監督がバランスを崩さんばかりのクドさで描いてきたことに対して、ボクは大いに反応をしていきました。 きっと、この振り付けに託された 「思い」 が、物語を推進させる重要な要因となっていくのだろうと直感したのです。
この直感をパフォーマンス系映画にありきたりなストーリーパターンを用いて、独善的に今作の行方を推察すると、
「序盤に軽度な軋轢を敢えて創り、何かのキッカケで雪解けムードとしていく。 (たぶんこの振り付けを含むダンス教師の踊りがそのキッカケとなるのでしょう)
そのことによって、物語は一つの目的に向かって順風満帆に進行していくことになる。
しかしだ、うまくいくように思わせときながら第三者的な要因で今度はより大きな挫折をしかけていくことになる。
その結果、物語進行上の 手痛い停滞 が提示されるのだが、当然のことながら、その障壁も乗り越えていくことになる。
この 手痛い停滞 の克服と、物語上のクライマックス ( おそらく、「常磐ハワイアンセンター」 での初パフォーマンス大成功! となるはずです ) を続けざまに投入してくることによって、
結果的には、より大きな幸福感に包まれた大団円を迎えることになるのだ。」
と、今作はこのように類型的な 「挫折の後の歓喜」 型ストーリーを残念ながらなぞってしまうものと、ボクは早々と断言をしてしまったのです。
そして先ほどの振り付けがこの 「挫折の後の歓喜」 型ストーリーに対して、象徴的な反復運動になるであろうことも、これ見よがしな演出から読み取ってしまったのです。
具体的に言うと、
「挫折の後の歓喜」 という物語を進行させるキーポイントに
「静止の後の再始動」 という 「思い」 を感じ取ることができる
この振り付けを
象徴的に活用してくるはず。 と思ったのです。
「内」 と 「外」 とのちょっとした軋轢を解消したこのシークエンスにおいて、前述の
【 ダンスの振り付けが雄弁に語る、物語進行上における法則性 】
の萌芽を見たのです。
一方、 「対比」 を発展させた、もう1つの鑑賞テーマである、
【 「内」 ⇔ 「外」 の対比と、
「第1次産業」 ⇔ 「第3次産業」 という生き方の相違 】
を推進するキーマンがダンス練習場に乱入してきました。それが蒼井優演じる紀美子の母親だったのです。
「裸踊りでラクして稼ぎたいのなら、てめぇ一人でやれ !」
とダンス教師に啖呵を切り、
「ヘラヘラ笑いながら男衆に媚びて、ケツ振ったり、
足おっぴろげるもんでねぇ !」
とのセリフを浴びかけるのです。
まさにこの局面にきて、 「内」 と 「外」 の本格的な軋轢となる予感を振り撒いてくれたのです。
そしてこの 「昔気質の炭鉱の女」 による発言で、 「内」 ⇔ 「外」 の対比というものが
「東京」 ⇔ 「福島」 という単なる地域の対比の枠を超えて、前述の 「プロジェクトX」 的な視野で考えるならば、
「産業構造の変革」 の問題
に拡大されていったことがわかるのです。
農林魚業と同じく自然相手の生産業である炭鉱の仕事も 第1次産業 に分類されるわけで、
一方の 「常磐ハワイアンセンター」 はサービス業の 第3次産業 となるのです。
しかも 「オレ」 達が目指すハワイアンダンサーは サービス業の中でも高度に専門家したエンタテインメントの領域に突入していくことになるのです。
汗水垂らしてコツコツと稼ぐ方法しか知らない 第1次産業 育ちの母親にしてみれば、 第3次産業 の仕事なんぞは (特に エンタテインメント業は) 軽薄で、人に媚びる恥ずべきものであると感じたに違いありません。だからこそ前述のセリフが発せられたのでしょう。
時は昭和40年。アメリカの大規模農場や東南アジアからの安価な木材の流入などがあって 第1次産業 が衰退し、製造業である 第2次産業 やサービス業である 第3次産業 に産業構造が本格的に移行した時代。勿論、炭鉱も中東からの石油という原材料の攻勢にあって、没落の代表選手となってしまったのです。
こんな時代背景を持つ今作の 「内」 ⇔ 「外」 という関係性は、
前述のように 「東京」 ⇔ 「福島」 という単純な地域格差だけではなく、
「外」 から侵入してきた 「第三次産業」 と
崩壊していく 「内」 なる 「第一次産業」
という問題に拡大され、夫々の人生観や価値観の相違へと波紋は広がっていったのです。
中盤、4人しかいなかったメンバーが急増していきます。
炭鉱の縮小による大量解雇がその原因で、収入が無くなったことで新しい食い扶持を求めた娘たちが フラガール に応募してきたのでした。
同じパフォーマンス系映画つながりで胸の内で比較してきた 「ウォーターボーイズ」 と今作とは、ここにきて決定的な違いをみせてきたのです。
「ウォーターボーイズ」 においてもメンバーの増員があるのですが、それはTVのニュースで男のシンクロが扱われたことによるPR効果のたまもので、あくまでも積極的な参加意欲によって増員されたものでした。
それに対して今作は、父親のリストラによって、娘たちが
生きる手段として
フラガール を選ばざるを得なかったところに、両者の差異が際立ってきたのです。
昨今におけるパフォーマンス系映画 「ウオーターボーイ」 「スウィングガール」、TV番組でありますが 「のだめカンタービレ」 と比べて今作が圧倒的な深みを持ちえた点が、
生活をしなくてはならない という側面なのです。
また、リストラの影響で、逆にメンバーの減少も発生することになりました。紀美子の親友である早苗が父親の転籍でこの町を離れていくことになるのです。その離別のシーンにおいても序盤に感じた 「内」 ⇔ 「外」 の関係性が反復訴求されていったのです。
早苗を乗せたトラックが走り去って行く場所、それがどこあろう... 「橋」 であったのです。
「内」 なる存在であった早苗は
「橋」 を渡って行くことで 「外」 なる者となり、
この地からも、そして映画世界からも姿を消していくことになるのです。
早苗離脱 のくだりは同じく序盤、紀美子の母親の存在で感じた 産業構造の変化 についても考察の種を提供してくれました。
早苗の父親はリストラされた腹立ちにまかせて、第三次産業に従事しようとする娘の晴れ姿に攻撃を加えてしまったのです。
第三次産業の機運を拒絶し、第一次産業に固執していった男が流れ着く先は... 夕張。
その後の夕張炭鉱の閉山、そして自治体の財政破綻を知る者からすると、時代の大流を無視し、反発し、消え去っていく者の哀しさ、憐れさを感じずにはいられませんでした。
さて、いよいよ「常磐ハワイアンセンター」 の開園を目前にして、フラガールたちのキャラバンが始まりました。
公民館などで踊りの実地訓練を行うのと同時に、フラガール達に 「常磐ハワインアンセンター」 の宣伝をさせてくるあたるは流石、日本初の テーマパーク を作り上げた経営陣。
ナイスなプロモーションです。
コンテンツのブラッシュアップとプロジェクトのPRを同時に叶えていくプロデュース能力の高さに、再び感服致しました。
やっぱり フラガール という一側面だけではなく、 「常磐ハワイアンセンター」 をリリースしていくもっと巨視的なドキュメンタリー映画を観たいものだと再確認をしたのでした。
↓制限文字数では完結せず、完成版はこちらまで
ouiaojg8.blog56.fc2.com/blog-entry-65.html
蒼井優のダンスが最高潮
主人公・紀美子(蒼井優)は、閉塞した炭鉱町の中で自らの夢を求めて、
またある娘は、解雇された父親の代わりに家族を支えるため、
それぞれの理由でフラダンサーに応募します。
フラダンスなど裸踊りと思われていた当時、娘たちは決死の思いでした。
紀美子の母親(富士純子)も、「働く」ということは汗水垂らし泥まみれになって、石炭を掘ることだと考えており、人前でヘラヘラしながら腰を振ることを「仕事」とは認めません。
石炭を守ろうとする者も、新しい時代に挑戦しようとする者も、どちらも真剣であり必死です。
両者の激しいぶつかり合いのシーンは見ごたえがあります。
時代や土地の価値観は、住む人間の生き方を否応なく締めつけますが、夢と情熱をもって、自分や周囲を変えていく人の姿が感銘を招きます。
紀美子の母親も、少しずつ娘の踊りを理解していきます。
フラダンスの美しい手の動きには、手話のようにひとつずつ意味があるそうです。
山場のエピソードでは、これが巧みに活かされ涙を誘いました。
クライマックスは勿論、ハワイアンセンター・オープンの日、フラダンスの公演の舞台です。
人間ドラマ,音楽が相まって盛り上がり、カットバックやスローモーションも挿入して、見事な演出でした。
主人公・紀美子のソロダンスのシーン、映画は最高潮に達します。
主演・蒼井優が見せるダンスの上達は、素晴らしいの一言につきます。
蒼井優の熱演が、この映画の出来ばえを2倍,3倍に仕立て上げました。
この年の屈指の一作でしょう。
全122件中、101~120件目を表示