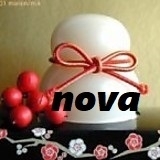七人の侍のレビュー・感想・評価
全191件中、21~40件目を表示
やっぱ古い映画だよね
何の得にもならない事に取り組む倫理観
戦国時代末期のとある山間の農村で、村人たちは、収穫期になると野武士たちに収穫した穀物を奪われていた。麦の刈り入れが終わった頃に四十騎の野武士達が村を襲う、という話をしてたのを聞いた村人が村に戻り、長老と相談し、侍を雇って野武士と戦うことにした。
侍を探すため宿場町を訪れた4人の村人は白米を腹いっぱい食わせるという条件で侍に声をかけたが、ことごとく断られた。そんな時、近隣の家に盗賊が押し入り、人質をとって立てこもる事件が発生した。通りかかった初老の侍が髪を剃り僧に扮してその家に近づき、握飯を与えて盗賊を油断させ、隙を見て斬り殺した。その侍は勘兵衛という浪人で、村人たちは彼に村に来てくれるよう頼んだが、四十騎もの野武士を相手にするには少なくとも侍が七人は必要だと言われ、断られた。同宿の人足たちが、断った勘兵衛をなじり、勘兵衛は翻意して村人の依頼を引き受けた。
勘兵衛は人を集めるため、通りすがりの侍・五郎兵衛に声をかけ仲間にした。また、過去に何度も同じ戦場で働いてた七郎次と偶然再会し彼も仲間に入れた。一方五郎兵衛は茶店の裏で薪を割っていた平八を誘い入れた。更に、果たしあいで剣術の腕を披露した久蔵も仲間に加わった。若い勝四郎も行動を共にすることとなり、六人となった侍たちは翌日村に向けて出立しようしていた。そこに、勘兵衛につきまとっていた男が現れ、持っていた家系図を見せ、自分は菊千代という侍だと主張した。勘兵衛らはこの男を相手にしないまま村に向かったが、菊千代は勝手について来た。
やがて侍たちが村に着くが村人たちは怯えて家から出てこなかった。すると、突然、急を知らせる板木を打つ音が鳴り響き、野武士が襲ってきたと思った村人たちは一斉に家を飛び出し、侍に助けを求めた。しかしこの板木は菊千代が打ち鳴らしたものであった。侍たちと村人たちとの顔合わせを成立させたことで、菊千代は七人目の侍として認められた。
勘兵衛たちは村の周囲を巡り、村の守るための方策を練り、野武士と対決することになるが、さてどうなる、という話。
午前十時の映画祭15にて鑑賞。
名作と言われていて、観たいと思ってたが、207分もある長い作品だし、なかなか時間も合わず、今回やっと劇場鑑賞出来た。
雨の中での野武士との戦いはなかなかの迫力だった。
ただし、同じ手に何度も引っかかる野武士達はバ○か?とは思ったが。
戦国時代の侍だったら、良い勤め先を見つけ、家来にしてもらい、手柄を立て、褒美や領土をもらう、というのがその時代の目的だったと思うが、勝っても何の得にもならない、飯を食べさせて貰うだけであんな命懸けの戦いを取り組む倫理観はちょっと理解に苦しむが、カッコよかった。
現にラストは百姓の勝ち?
侍は4人も殺されたし、やっぱり合わない戦いだったなぁ、と思った。
志村喬は終始カッコよかった。三船敏郎は何を言ってるのか聞き取りにくかったが、コメディ担当だったのだろう。鬱陶しかったが、重要な役だとは思った。
志乃役の津島恵子は凛々しかったし、島崎雪子は美しかった。
鑑賞できて良かった。
ついに観ました(午前十時の映画祭)
日本人として一度は観ておくべきかなと思い、午前十時の映画祭行きました。
正直、言うほど刺さらなかったのですが、冷静に思い返すと、日本人の気質というか、日本人社会の縮図が上手に描かれていたと思います。現代にも当てはまりますね。
・百姓は、自分では決められず右往左往。長老の意見に、羊のように従う。
・強いものに頼らざるを得ないのに、その侍を異端扱い。
・戦争のように組織として動くときは、優秀な長が必要。
・人が動くのは金だけではない、という状況はある。
・老人ほど頑固。それを助けようとする若者が犠牲になる。
・緊急時、規律を破るものがいるときは、そこから崩れる。
・真面目なようで、裏では何を隠しているかわからない。
・貧乏だけど、働かざる者食うべからず。
貧乏だし、色々と大変だけど、子供もたくさんいて、映画が作られた当時は日本に希望が持てる時代だった気がしました。
人間の描き方の奥深さに感服しました
これだけの名作を実は未鑑賞でした。
劇場公開を機に、この長さを配信で観るのは辛いと思って鑑賞しました。
タイトルバックの筆書きの文字が斬新だなぁ~といきなり冒頭に感服したあと、所々役者さんの日本語が耳慣れなくて聞き取れない部分があるものの淡々と鑑賞。中盤あたりで名作だろうけれど古風な雰囲気は今の作品と比べるとどうなの?とベルイマンの処女の泉を観たときと同じような感想を抱き始めましたが…
ところが中盤以降、人物描写が深々と心に染みてきました。
村人も、武士たちも、大義名分だけではない自分可愛さと自己都合を内に秘めながらもこうありたい自分と葛藤している様が浮かび上がってくるからです。
誰一人として完璧な人は居ない。
けれどこう有りたいと願う姿を持つ人と持たぬ人の差は既に青年、壮年においても歴然たる差を人にもたらすことを今更ながら痛感しました。
群像の心情をここまで深く描きながら、一概に人間の醜さという感想を観客に抱かせない手腕が素晴らしいと感じました。
それもこれも含めて人間なんだよなぁ。
ラストの勘兵衛のセリフがひときわ心に染みました。
劇場で鑑賞できて良かったです。
「この飯、おろそかには食わんぞ」 ジンと来る名台詞。それまでの会話...
「この飯、おろそかには食わんぞ」
ジンと来る名台詞。それまでの会話のやり取りがあってこその、言葉の重みを感じる。
午前10時の映画祭にて。
改めて残酷な映画だと再確認した。
第77回カンヌ国際映画祭でも絶賛されたバージョンを、更に進化した "高音質・高画質・新4Kリマスター版" での上映らしい。
映画館の係りの若者が「ななにんのサムライ、只今開場します」と言っていた(笑)。
「意気地なし、侍のくせに」コレも印象的。
痛快活劇
世界の名だたる映画監督たちがリスペクトし、影響を受ける伝説の本作品。
日本映画の原点とも言えるか。
映画館で観てみたいと、やっと初鑑賞となった。
まるでドキュメンタリーと見紛うリアリティ感と臨場感のある映像。
日本国民の大部分が農民だったであろう生活背景のその粗末さ、貧困、無力さ。そんな村民たちの状況打破に七人の侍が結集する。
いち個人では動かぬ物事も、力を合わせれば可能になる。誰もが観ていて心動く痛快活劇だ。
三船敏郎はイケメンでありながら泥臭く野性的な男をのびのびと演じる。
志村喬はその静かな物腰で正義感あふれる理性的なリーダーを。若き武士、ムードメーカー、剣の達人、、、みな個性豊かで魅力的だ。
どうしても考えてしまうのが、現代この作品を制作するとなるとつとまる俳優がいるのかと。とてもこの人たちの代わりが見当たらない。
日本映画の原点である作品だと思う。いや、世界の作品の原点か。
少々上映時間は長く感じたが素晴らしい作品だと思う。
黒澤映画を映画館で観たかった
静の勘兵衛 動の菊千代
3時間超えだけど全く長くない!!
初めて映画館で
観た。午前十時の映画祭、ありがとう。
途中で,休憩が入るんですね。みなさん何分間休憩なのか、知っているのかな。
お百姓の話が聴き取りにくい。のぶせり相手の事は聞き取れたけど。
映像はクリアになったのだろうけど、音声以外が音強めに感じる。
音声だけ分離してクリアに出来るんじゃないかな。わざとかな。
昔はシーン転換?がこんな感じなのかな。この映画だけかな。
お茶目な三船敏郎を初めて観た気がする。
志村喬、良い。『生きる』も黒澤だよね。午前十時でやらないかな。
旗は最初に亡くなったサムライが作ったのか?三角は菊千代だな。なぜ『た』。
しかし勝四郎、不甲斐ない。『荒野の七人』のこのポジションの人は村に残ったけど、多分出ていくだろう。
サムライに、四、五、七、八、九(久)は何かあるのかな。
麦の刈り入れ、のぶせりとの闘い、の次に田植え?時期はいつなのかな。
説明の少ない映画なのかな。余白が多い。
三週間やっているから,また観に行こう。
追伸 また観てきました(11月1日)。旗のところ、初回は寝落ちしてた。田んぼのた、だから百姓でしたね。
2回観ても余韻が残る映画です。だからみんな名作って言うんだな。
映画館で観てよかった映画No.1
何度も観るうちに感想や気持ちが変化してゆく過程を記録してます。
よかったらご覧下さいませ。
1回目鑑賞が2016.10.19日でした。
この時は歴史的名作の迫力に圧倒されて感想を文字に残す余裕がありませんでした。
2回目にやっと世界が認める娯楽作品の楽しさ面白さを私の言葉で文字に残せるところまで来ました。以下は2回目の2018年7月9日 鑑賞時の感想です。
2度目だからこそ前回見落としていた部分を再確認しました。
この映画を「別に普通」と言う人もいるが、そりゃそうだ!
この映画があったから、その後の殆どの娯楽アクションものが
この映画をいわば真似してる訳で〜
「普通」を最初にを創り出したのがこの映画と言う事。
台詞が解らないと言う人もいる。そりゃそうだ!
そもそも50年前の映画なのだから50年も過ぎれば言葉も変わっちゃうし
日本語スキルが劣化した私らに合わせた台詞は一言も無い。
それなのに地球上で1億強しか話さない原語の映画が
世界で同時多発的に色んな国の映画人から賞賛されている訳で、
要するに少々セリフが解らなくとも
真面目に観れば、ちゃんと解るように作られてるんだよ!
名作名作と構えずに気楽に観たら良い!
面白い娯楽作品なんだから〜!
福田里香氏の「フード理論」の最高峰は「七人の侍」である!
と言う評論を耳にして、改めてこの作品を観ると
食べる事=生きる事の重さが胸に迫って来る。
作ってる自分たちでさえ一粒も口に出来ない一番大事な米を
差し出すしかない農民と、そんな農民の困窮を見兼ねて
出世にも俸禄にもならない仕事を引き受けた侍達の矜持と、
意義ある死に場所を求める気持が合致して話が進んで行く。
侍の話だけでなく、農民たちの困窮しながらも
実はしたたかに生き抜く狡猾さも描かれている。
死にかけの落ち武者を竹槍で追い回して奪った槍や兜〜
決戦前夜、いつのまにやら始まった酒盛りや若い性の暴走などは誰にも止められない〜
生きるとは、綺麗事では無く、時には人を欺いたり文字通り命がけなのだと、
観るものに伝わってくる。
実は農民の出である三角じるしの菊千代が目指すものは「本当の侍」になること。
だから勘兵衛に「本当の侍」の理想を見てついて来たのであり
久蔵の振る舞いを褒め称える勝四郎の「本当の侍」の言葉に触発されて、
逆に「本当の侍」にあるまじき行為を行なってしまう。
その反省が、最後は彼を「本当の侍」にしたのだと思う。
今回改めてやっぱ三船敏郎って凄いな〜〜
圧倒的な存在感と、大きな動き、豊かな表情!そして画面全体を照らし出す、
溢れる様な愛嬌!!彼の愛嬌があればこそこの映画が単に重い話で終らず、
メリハリのある活劇になってるんでしょうね。
こんな役者は今のハリウッドを含めてもちょっと居ない気がする。
そして3回目 2020年3月3日 リマスター版で格段に観やすくなった「七人の侍」
一人一人の魅力的な人物描写に魅了され観終わった後、涙が出ました〜〜
私もあの貧しい村の一人になって現在ならさしずめ「理想の上司No.1」の
志村喬演じる勘兵衛さんや稲葉義男演じる五郎兵衛さんに
もっと色々教えてもらいたかった!
三船敏郎演じる破天荒な菊千代や、スッとぼけていながら優しさの滲み出る
千秋実の平八さんや加東大介演じる戦慣れした七郎次さんと一緒にお酒が飲みたかった!
宮口精二が演じたクールな久蔵さんの見事な剣の腕前に木村功演じる若侍、
勝四郎と一緒にもっと魅了されたかった!
あの世界に行きたい!あの七人と会いたい!これが本当に惚れると言うことやね〜〜
しっかりキャラの立った七人の侍たちだからこそ現在でもこんなに心に響くのでしょうね〜
そして今回4回目 2025年10月22日 新4Kデジタルリマスター鑑賞時の感想です。
今回新たな発見として結構気になったのが、村娘「しの」と若侍勝四郎のエピソード。
勝四郎としのは偶然村の外れで出会って何度か二人で過ごすうちに、
しのの方から勝四郎に迫って来た。
奥手の勝四郎が戸惑ううちに密かに村を偵察する野武士達を発見し村は一気に臨戦体制に。
やがて野武士達と村人たちの最終決戦の前夜、明日は死ぬかもしれない!
そんな思いに駆られたしのは勝四郎に改めて自分を投げ出して迫ってくる。
遂に思いを遂げた二人はその直後、しのの父親に見つかって散々罵倒される、
怒り狂うしのの父親を「明日は決戦という前にはこんなことはよくあること」と
勘兵衛さんや七郎次さんが父親を宥めるのだが当のしのはただただ泣くばかり。
ここで脚本を練りに練った黒澤監督や橋本氏や小国氏はなぜしのには何も語らせなかったのか?しのは結構グイグイ勝四郎に迫って来ていたから、例えば
「明日野武士たちが勝てば娘らは野武士の慰み物にされる!それならいっそ、
自分の思う相手と結ばれてしまった方がマシだわ!」と女のしたたかさを表す台詞を
しのに言わせることを、巨匠三人は思いつかなったのか?だとしたらこれは
昭和親父の限界かもしれない。しかし、反対によく考えた上でしのの台詞省いたのか?
出来るなら時間を巻き戻して御三方に聞いてみたい気持ちですわ。
@もう一度観るなら?
「定期的に映画館で!(笑)」
70年前
午前10時の映画祭で公開されていた「七人の侍」を、映画館で見てきたのでレビュー。
「七人の侍」といえば、黒澤映画というよりも日本映画の最高峰とされている。世界的にも評価されている、名作というか傑作である。
昔、見た記憶はウスぼんやりとはあるのだが、ハッキリとはしていないし。
今回、4Kリマスターで、声も聞き取りやすくなっているとのことだし、映画館で見る機会が今後そんなになさそうだし、思い切って観に行きました。
で、感想。
中盤で休憩が入る長めの映画だったのだが、全くダレることなく完走してしまった。
黒澤・橋本・小国の脚本に黒澤の演出で、ここまでの完成度は、当時、戦後8〜9年くらいで製作した映画としては驚異的だろう。
多分、製作時点で出来うることは全てやってしまっている、と思われ。
キャラクターとしては、菊千代と勘兵衛が目立っちゃうけど、他の侍五人も、農民たちも素晴らしくキャラが立っている。
アクションについては、さすがに近年のド派手な映像に慣れてしまっているから、若干の物足りなさを感じてしまったのだが、それでも本当に人が演じていると考えると凄まじい。
今回の4Kリマスターで、映像も音声もかなりクリアになっているようで、観ていてほとんど気になることはなかった。
いやあ、いいもの観せてもらいました。
人間のしぶとさと多面性
言わずと知れた不朽の名作とは知っていましたが、実はちゃんとスクリーンで観るのは初めて、というものです。
「ごろつきの暴力にあえぐ百姓の村を男気ある七人の侍が助ける話」だと思い込んでいましたが、そんな単純な内容ではまったくありませんでした。
休憩をはさむほどの長い作品なので、名高い(?)たたかいの場面にいたるまでのいきさつが非常に丁寧に、時間をかけて描かれていました。
百姓たちが用心棒の求人活動で町を訪れる場面で、「腹が減りゃ、クマだって山を下りるだ」という台詞があり、まさか現代日本人がこの台詞に震えあがる日がくるとは、さすがの黒澤明監督も予想できなかっただろうなぁ、なんて思いました。
前半は、腕に覚えありの食い詰め浪人たちが、人の縁があったとはいえなんの利もない仕事のために仲間になるのが、不思議でもあり、頼もしくも感じました。(腹いっぱいのゴハンが報酬とはいえ)人はパンのみで生きるものではなく、自分の能力を活かして働ける場=自尊心の満足、が必要なんだなぁと思います。
後半は、「助けがなければ何もできない烏合の衆」だと思っていた百姓たちが実は一番しぶとく、どんな災害もうまくやりすごして日常生活を守っていくんだ、こうやって歴史は続いていくんだ…というのを、空恐ろしくさえ感じながら思いました。
時間は短いながら鮮烈な印象を残す「娘」「妻」の場面も、この状況で??という人間の欲望をギラギラと映し出していました。
野武士の視点はゼロだったので、彼らは「マッドマックス」「北斗の拳」の悪役よろしく惨殺してもスッキリするだけの扱いですが、百姓たちが竹槍でめった刺しにする場面は「八つ墓村」の落ち武者惨殺シーンを思い出して恐ろしかったです。
人間にはいくつもの顔があり、複雑で不条理で、矛盾を内包しつつもうまいこと自己弁護しながらしぶとく生きていけるんですね。
うまくいかないことに直面した時、大人しく自分を責めて自滅してしまう人たちには、この百姓たちを見習って強く生きて欲しいものです。
日本映画の骨頂
4Kリバイバル上映で鑑賞。
まず、、長い!…のを感じさせないくらい面白かった。
初めて作品の中に休憩という概念があるのを知る。
慣れないモノクロ映画であったけれど、昔の役者は演技力が高くて映像にはなんら違和感がない。何を喋っているかわからないことが多いが、そこまで気にならない。
いきなり騎馬の迫力から驚く。どう撮影したんだろうと感心しながら観た。後に騎馬とも戦になるが、恐ろしくて立ち塞がれないだろう…と。
百姓のシーンから始まり、この時代に生きていくことの厳しさを知る。菊千代が侍へ百姓の生きていく厳しさを語るシーンも刺さる。
侍が続々と加入していく頼もしさたるや。
侍の指導のもと、一つの村が作り上げられていく高揚感。
村が襲われ、仲間が死んでいく衝撃。
戦が終わり寂しげに佇む墓。侍が得たものはなんだったのだろうか。
全てがスムーズにつながっていた。
見応えたっぷりの作品を堪能させてもらった。
午前十時の映画祭で体感!『七人の侍』の迫力をスクリーンで味わう
午前十時の映画祭で『七人の侍』を映画館で鑑賞。地上波やDVD、サブスクで何度も見てきたが、映画館での鑑賞は初めてだった。観客は約40名で、年配者が多い中、若年層もちらほら。
物語は、戦国末期の山間の村を舞台に、野武士の襲撃から村を守るため七人の侍が集結する話。中心人物は知恵と経験で村を導く勘兵衛、粗野だが情に厚い菊千代、若き勝四郎、そして村人たち。侍たちは村人に戦い方を教えつつ協力し、激しい戦いの末、村を守る。戦いで多くの侍が命を落とすが、村人の生きる力が勝利の本質であることを示す結末が印象的。
映画館で見ると、画面の迫力や戦闘シーンの緊張感、音響の臨場感がこれまでの映像体験とは全く異なり、侍たちの緊張や村人たちの必死さがよりリアルに伝わった。特に、七人の個性の対比や村人との交流の描写が鮮明で、人物一人一人の物語性を再確認できた。
総じて、これまでの視聴では気づきにくかった戦闘の緊迫感や村人と侍の関係性の深みを、映画館での体験で改めて味わえる鑑賞だった。
① 戦の虚しさと生きる力
侍たちは勝利しても多くを失う。だが百姓たちは再び田を耕し、命をつなぐ。黒澤はここで、「戦士の栄光よりも、民の生活こそが永遠」であると示す。
②「身分と人間性の対立」
菊千代が叫ぶ「百姓ほど悪ズレした生き物はない!でもそうさせたのはお前ら侍だ!」という言葉に、封建社会の矛盾が凝縮される。黒澤は、人間を分断する階級そのものへの批判を込めた。
③「共同体の力と個人の運命」
侍と村人の協働によって村は守られるが、侍は常に〝余所者〟〝根なし草〟として去る。これは、共同体の勝利と個の孤独という普遍的な主題である。
④ 「リーダーシップ論」
勘兵衛の判断力・菊千代の情熱・久蔵の技――それぞれ異なる「力」が集まり、戦いが成立する。黒澤は多様な個性の結束を描く。
最期にーーー
最後に残るのは、百姓の田植えと侍の墓。
「勝ったのはあの百姓たちだ」という勘兵衛の言葉には、
「命をつなぐ者こそ、真の勝者である」という黒澤哲学が込められていた。
「七人の侍」を"6人のおじさま"と観た。
黒澤明監督「七人の侍」
"午前十時の映画祭15"で、
20:15からの回で観ました。
終了が0:00とは何故に?
207分のはず、おかしいな??
答えはそう!
"本物の休憩"がありました(^。^)
どどん!と"休憩"の力強い文字が映し出されたが、インド映画のインターミッション詐欺、0分に慣れているので席を立つつもりはなかったが。。
おじさま達皆んなトイレ行った!
え!本物?!
じゃ、アタシもトイレ!
全員揃ってトイレへGO!
上映途中なのに誰も居なくなった。
何か不思議な感覚でテンション上がってしまい、トイレ帰り、又皆んなで部屋に戻る途中で、おじさま逆ナンしてしまいましたw
「休憩初めてです!」
「これはね、あるんだよ休憩♪」
おじさまが得意気で嬉しそうだったのは私の勘違いではないと思う。
今「七人の侍」を観に来ている。
話しかけても良いはずです♪
で、ですね。
この「名作」を今回初鑑賞なワタクシ。
はい。どなたも存じ上げない。
唯一お名前だけは知っている三船敏郎さんもどの役かわからずの鑑賞でした(°▽°)
追っている監督作品でもなければ、贔屓の役者が出ている訳でもない。
それなのにこんな私でも、この凄さがわかる凄さ!
噂通りのとても力強い映画でした。
聞き取りにくいセリフに加え当時の言い回しにも苦戦した。
加えて白黒映画という私にはハードル高めの作品にも関わらず、どんどん吸い込まれていった。
決して楽しい話しではないのに、この高揚感は何なんだ。
野武士から村を守る為に侍を探す前半、村に付いてからいざ、決戦!の後半。
ストーリーに100%のめり込んでいるにも関わらず、映画としての完成度の高さ、細部まで手を抜かない画作りに唸りっぱなしで、頭の中はそれぞれが同量の熱量で「七人の侍」が鳴り続けていた。
これは正に体験だった。
優れた作品は何度見ても心揺さぶられるし新たな発見もある。
噛む程に味が出るスルメ。
しかし私が味わったこの『驚き!』は、初めてこの作品に触れた人だけがもらえるギフトだ。
一生忘れない記憶の始まり。
私は体験してしまった。
今後は初見の人を羨ましく思うんだと思う。
凄い映画だった。
ラストの墓前のシーンと勘兵衛の台詞が深すぎて深すぎる。
(あれは中々出ないよなー
凄い脚本だな)
弱くて強くて愚かで賢くて、薄情で厚情で
したたか。
そして時には人の為に命をもかける不思議。
完全な善人も悪人もいない。
善悪で割り切れない事もある。
喜ぶし怒るし泣くし笑う。
しぶとく生きる人間の姿はいつの時代も変わらない。
人間の複雑さを見事に表現していたと思います。
『○○○○○○△た』
揺れる旗に全て詰まっていました。
全191件中、21~40件目を表示