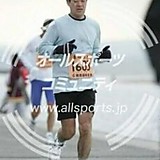こわれゆく女のレビュー・感想・評価
全26件中、1~20件目を表示
クロース・アップ
ジョン・カサヴェテス監督作品。
本作も顔のクロース・アップが多用されている。彼女の異常な振る舞いに引きつる顔たち。いつ場面が、家族が、彼女の精神がこわれていくのか。その緊張と弛緩の時間が流れていく。
彼女をヒステリーとして病理化することは危うい。彼女が壊れていく要因も理解できるからだ。夫婦の時間をないがしろにする夫。予定をドタキャンされて、その後すぐに大勢の同僚が家に来たら嫌だろう。さらに同族嫌悪ゆえか、冷たい義母。彼女を取り巻く環境も健全とは言い難い。
しかも彼女を治す心理的療法は現代からみたら間違いだらけのアプローチな気がする。
終わり方がいい。彼女は退院しても「症状」が完治したわけではない。興奮してカミソリを手にして、夫とのひと悶着で血を流すしまいだ。だが彼は彼女の傷を水に流し絆創膏を貼る。この優しさ。絆創膏で傷口を塞ぐように、彼の優しさが彼女の崩壊を塞ぐはずである。
パーティーの後片付けからベッドメイクをしてエンディングを迎える。これは日常への回帰だ。傷を抱えたままそれを修復する時間をもつ日常。彼女の崩壊がささやかな優しさで塞がれる日常を想う。
人間の内面に潜む“孤独”や“狂気”を見つめたカサベテスの傑作
精神を病んでいく妻メイベルをジーナ・ローランズ、その夫ニックを「刑事コロンボ」のピーター・フォークが演じています。美しく陽気で、まわりを明るくするメイベルですが、あることを発端に、異常な行動をみせるようになっていきます。その姿に見る者は心をかき乱されずにはいられません。
瞳の奥に宿る感情、顔の表情や身体の動きひとつで、リアルを超えた生々しさをローランズが表現。さらに、カサベテスの実験的な演出とカメラワークにより、心の揺れが見ていて痛いほど伝わってきます。
メイベルはなぜ精神のバランスを崩してしまったのか。こわれゆくのは誰なのか。映画に対する見方が変わることでしょう。
こわれゆく女
一体何を見せられているんだ?
どう考えてもドーパミン受容体が壊れて 覚醒剤中毒と同じ状態になってるように見えるのだが・・・これが精神疾患でありえるのか?ないだろう? 旦那の方も興奮しやすくて声がでかくなってるからやっぱりなんか 毒ガスの影響 じゃなかったのかな。 原題を直訳すると「影響下の女」になるから やはり暗に公害を批判した映画 なんじゃないんだろうか?・・・そこら辺が最後に何か説明してあるかなと思って期待して頑張って 見続けたが何もなかった。 ほとんどの人が 「で、何だったんだ」って感じになるだろう。
・・・ ただ・・・ おかしくなっていく 奥さんを一生懸命なだめようとしたり、怒鳴ったり色々やって・・正常に戻ってほしいという願いが怒りに変わったり・・その辺がリアルで少し胸を打つものはあった。 要するに これはストレスの影響でも毒ガスの影響でも宇宙人の影響でも何でもよく、このような状況下における奥さんに対する愛を描いた映画であろう。望遠レンズでカメラが首を振る 混乱シーンと落ち着きと緊張 醸し出す固定カメラのシーンが繰り返されていて 効果的だった
しかし やはり何も解決してないし 謎解きも回収も何もないので最後まで見なくても良いと思います。 2時間ぐらい見れば十分です
【精神の安定を欠きこわれゆく妻、母を戸惑いながらも不器用に愛する夫、子供達。この映画には或る家族の複雑なる絆が描かれている。ジーナ・ローランズとピーター・フォークの名演に釘付けになる作品でもある。】
■市のベテラン水道工事員・ニック(ピーター・フォーク)とその妻・メイベル(ジーナ・ローランズ)。
仕事で忙しいニックは帰りが遅く、メイベルはある時を境に心配の余りか見知らぬ男を家に上げる。
更には、ニックの同僚を集めて昼食を振舞うが、彼女の言動は上滑りし、気まずい雰囲気になり、同僚たちは家を後にする。
そんな状況下、ニックの母は、メイベルの様子を見て、3人の子、アンジェロ、トニー、マリアと引き離そうとするが、子供達もメイベルも激しく抵抗する。
だが、ニックはとうとう妻を精神病院に入院させる。
それから半年が経ち、メイベルの退院を祝うべく人々が集まる。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・観れば誰でも想うであろうが、精神の安定を欠いたメイベルを演じるジーナ・ローランズの物凄い演技に圧倒される。
だが、よく見れば分かるのだが、メイベルは只管にニックを愛し、3人の子、アンジェロ、トニー、マリアを愛しているのである。
故に、義理の母に子供達と離されようとすると、異常に抵抗をするのである。
・メイベルは、夫の同僚たちを一生懸命にもてなそうとするが、どこか歯車がずれた言動を取ってしまう。ニックはギリギリまで我慢するが、それでも堪忍袋の緒が切れてしまうのである。
・だが、ニックはメイベルと別れようとはしない。彼女が半年の療養から帰って来た時も、義理の母が招いた多数の友人、親戚を帰らせて、家族と、身近な人だけで迎えるのである。
<子供達は、母を気遣い”愛してる”と告げる。そして、ニックもメイベルの怪我を優しく治療して、家族四人で一つのベッドの上で、久しぶりの再会を祝うのである。
今作は、精神の安定を欠いた、こわれゆく妻を戸惑いながらも愛する不器用な夫、こわれゆく母を健気に心配し愛する子供達が描かれている。
この映画は、或る家族の絆が描かれている作品なのである。>
メイベルは孤独との付き合い方が下手なのでは
メイベルが精神的に不安定になる理由は、孤独との付き合い方が上手くないからではと思う。一人の時間を楽しく過ごすだけの趣味や取り組むべきことが何も無く、それが夫や子供への過剰な依存につながっているように見えた。そのため、家族がいない時間は空虚になり、それに耐えかねて発狂に至ったのかなと推察した。彼女を演じたジーナ・ローランズの狂気の演技も、リアリティがあって良かった。
彼女もおかしいが、夫のニックも感情的で暴力的で、実は中々おかしい。その割には意外と慕われているようで、広い交友関係を保てているのも不思議だった。
ラストの何事も無かったかのように家の片付けを2人で始めるシーンは意味が分からなかった。今作が描きたいのは、夫婦の愛なのか精神的におかしくなっていく人の姿なのか、結局何だったのかと思わされる。今作のジョン・カサヴェテス監督の『グロリア』もそうだが、過大評価されているんじゃないかと思える。
カサヴェテス特集3作目、
2度とみたくない映画
こわされていく妻
壊れてゆく妻。ジーナ・ローランズの快演が恐ろしい。
こわれゆく女とゆう題名だけど、家庭と亭主によって壊されていっているように見えるが、はっきりと明快な描写がないので観る人によって見え方が変わりそう。
原題の意味は状況下にある女。
他の方のレビューを読んでみると、「精神病によって崩壊していく妻を献身的に支える夫。」と受け取っている人もいた。
私は、仕事が全ての夫が家の家事と子供の世話全てを妻に押し付けて仕事で家にも帰らず無理解に怒鳴り散らす夫によって、孤独感とワンオペ育児に追い詰められて精神が弱っていってしまったように見える。
社会的メンツが1番大事、お前が大事だ愛してると宥めつつ都合が悪くなると怒鳴りつけるし、彼の母親も完全に彼の味方。
冒頭の、今夜は一緒に過ごすと約束していた日の朝には同僚をぞろぞろ連れてきて帰ってきたあげくに、その同僚の1人は「またパスタか」などと言っている。
他人の家に朝から押しかけた上に出す料理にケチつける時点で、は?って感じだし、「また」ってことは結構な頻度で来てるとゆうことで、自分ならこんなことされたら気が狂う。
一方で、冒頭シーン一生懸命帰ろうとする努力が見られたり、ピーター・フォークの温かみのある表情や、子供達を海に連れ出そうと努力してみたり(子供の扱い雑だし、一緒に行った同僚の方に子供が寄っていっているが)な部分で夫も頑張っているように観客に思わせる、ある種中立な描き方をしてるのが今観ても面白かった。
この家庭の状態は、今の日本でも絶賛継続中な気しかしないので、追い詰められた末に
頭がおかしいとレッテルを貼られてしまった人、狭い環境に押し込められ苦しい状況下に置かれている女性に思考を巡らせてしまった。
最後のパーティは、夫が気がおかしくなってしまった妻を認めたくなくって無理矢理に正常であれと動かし、
やっと壊れてしまったと認めて入院させたのを、じゃーん!完全復活!もう心配いりません(体面的に)
を近所、仕事場にアピールする為の会であることにゾッとする。
この映画で1番真実を語っているのはきっと子供達で
「繊細なところがあるけど良いママ」のセリフや。
母を守ろうと、何度も戻ってくる姿によってのみ
メイベルの正しさ示されているように思うと切ない。
それにしても、ジーナ・ローランズが
ほんとにリアルすぎて怖い。彼女がきっちり怖く見えるから、観客の見方を強く揺さぶっているように思う。
女もだが、その夫も声デカくてうるさい
インディー映画の父
高崎"女"祭大トリ登場であるw
ジョン・カサベテス この監督を初めて知ったのは内田英治監督「下衆の愛」で、主演である渋川清彦演じる映画監督の部屋に飾っていた外国人の写真
勿論、この人物は誰だかは解らないが、主人公のうだつの上がらない映画監督が理想とする憧れの人なのだと言うことは容易に想像できる演出である
しかし中々カサベテスの作品を観る機会はなく、DVDで観るには、やはり映画作品なのだからスクリーンで観たいという思いも捨てきれず、今に至る
まさか、今流行りのレトロスペクティヴ(映像レストア)で再上演という機会を経ての観賞である 有名な作品は今作品以外にもあるのだが、題名に惹かれての観賞
確かにぶっ飛んだ、今のインディーズ映画の監督達が魅了される程のインパクトの強い内容である
情緒不安が進行する妻、イタリア系移民にステレオタイプ的に描かれる家父長制というソースに塗される夫、そして次世代を担う未だ幼き子供達 周りのコミューンの多さや、すぐに集まる程のプライバシーの欠如 健康的な職場環境なぞ夢な仕事 そんな下地故に、益々追い詰められる夫婦が、精一杯の理性を振り絞りながらなんとか踏みとどまる関係性をゴリゴリと臼を轢くように演出されるストーリーテリングに心を鷲づかみにされる 少々乱暴なカット割りや心情描写の拙さを吹っ飛ばす程の力強さを荒々しく演じてみせる俳優陣もまた見事である
どんどんと壊れていく妻の演技は、観る者を恐怖のずんどこへと誘う 輪を掛けるように夫のDV的圧力 今の時代ならばもうホラーでしかそのカテゴリは当てはまらないであろう
あれだけしつこいほどのリピートと天丼を繰返しながらの、ラストの呆気ないベッドメイクは、してやられた感満載である このウィットとドライ感、そして地獄が毎日繰り返される日常感、諦観と藻掻く情熱の波状攻撃を、若い映画監督は渇望しているのだと、改めて思い起こさせるきっかけを描いてみせた今作、私も忘れられない一作に加えたいと・・・ どいつ目線なんだ、私は(苦笑
欲望という名の電車
タイトルなし(ネタバレ)
いやー、すごいものを見た。社会学で言う「パッシング」を扱った映画がとても好みなので(高畑勲『かぐや姫の物語』とか)、これも心打たれるというか、とても好きだった。
狂気という箱に入れられたメイベル(と子どもたち)だけがまともだよね??あとはみんなちょっとずつ変。メイベルのお母さんはまだましか。自分を尊重されないものが、自分の尊厳を守ろうとするときに出る叫びが、世間では“狂気”とされる。ドアに貼られた“PRIVATE”の札、アレが最後の砦と言うか、まさに心を守る御札だったんだろう。
メイベルが挙げた“5つの大事なもの”がそのまま、自分を殺す呪いになっている。周囲が掛けた呪いを必死に繰り返すうちに自分を縛り上げてしまった。
「(私のことを)バカだと思ってる」というメイベルの言葉(字幕そのままではないかも)も忘れられない。元々明るくて陽気だったのかもしれないけど、それが周囲から求められる枷でもあったよね、きっと。退院して夫がメイベルに繰り返し言わせようとした言葉があれだもの。強要される“自分らしさ”ほど強い呪縛もなかろう。
こわれゆくではなく「壊された」のでは
ある家族の形
病名ははっきり出てこないけど、躁鬱かボーダーかと思われる妻と、その家族の物語。
とにかくジーナ・ローランズの演技がすごすぎる。
表情ひとつ、指の動きひとつであそこまで表現できるのか。
そして、その妻を愛しながらも激しい言葉と態度もぶつけてしまう夫をピーター・フォークが演じる。
妻を深く愛しているのは伝わってくるけど、支えようとしつつも引きずられる故にああいう言動になるのか、途中から、妻が壊れてるのか夫が壊れてるのかわからなくなってくる。
そんな、はたから見たら危険すぎるバランスの家族を成り立たせ、救っているのは子供たちなんだろうな。
ジーナ・ローランズが最高
1人で過ごすわびしさを紛らわすため街に出て、酔ったいきおいで見知らぬ男を家に連れ込んでしまった。しかし、その男をニックと勘違いしてしまうほど精神状態があやふやだ。
メイビルのこわれていう過程をジーナ・ローランズが見事に演じていた。『きみに読む物語』でも老人になってからのアルツハイマーによって記憶力はなくなっていたが、この映画では軽度の記憶障害と強迫観念とそううつ症。精神病の患者を持った家族の辛さも胸が苦しくなってくるほど。
白目を剥いたり、医者に対して「悪魔よ去れ!」と叫んだり、徐々に病状が悪化する。悪魔が取り憑いているのは本人であるかのように二重人格ぶりも発揮する。。
インディペンデント系の名監督カサヴェデスらしい、ある意味ドキュメンタリータッチのような撮影法で、リアリティは十分すぎるほど。しかし、この調子で145分という長さになるのは、正直言って集中できなくなります。冗長部分が多く、うまく編集できるのになぁと残念でならない。
こわれそうな夫婦
壊れない家族を
全26件中、1~20件目を表示