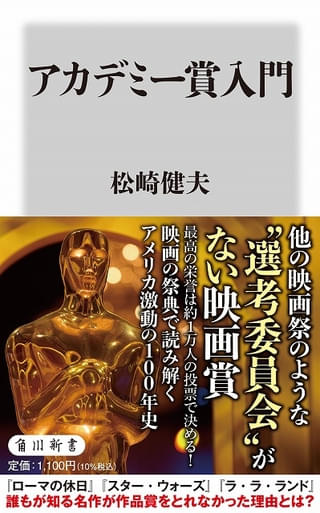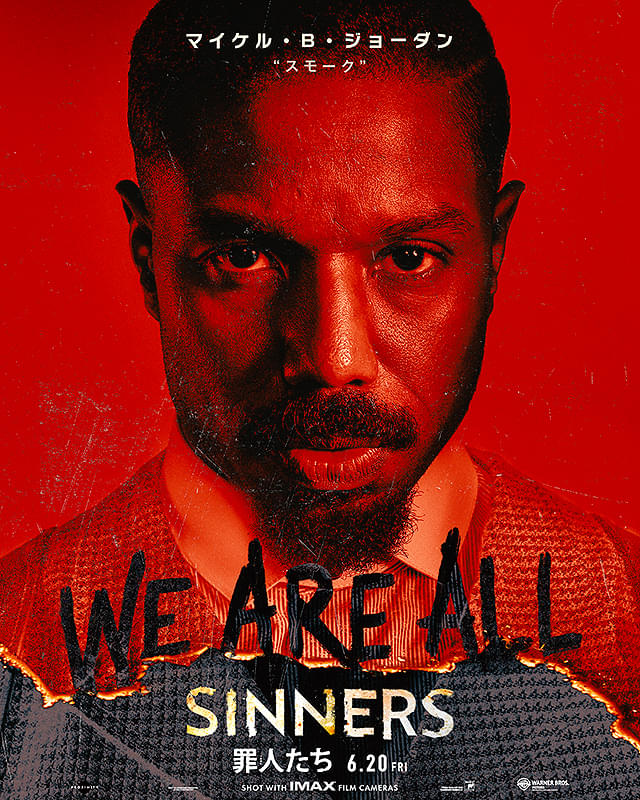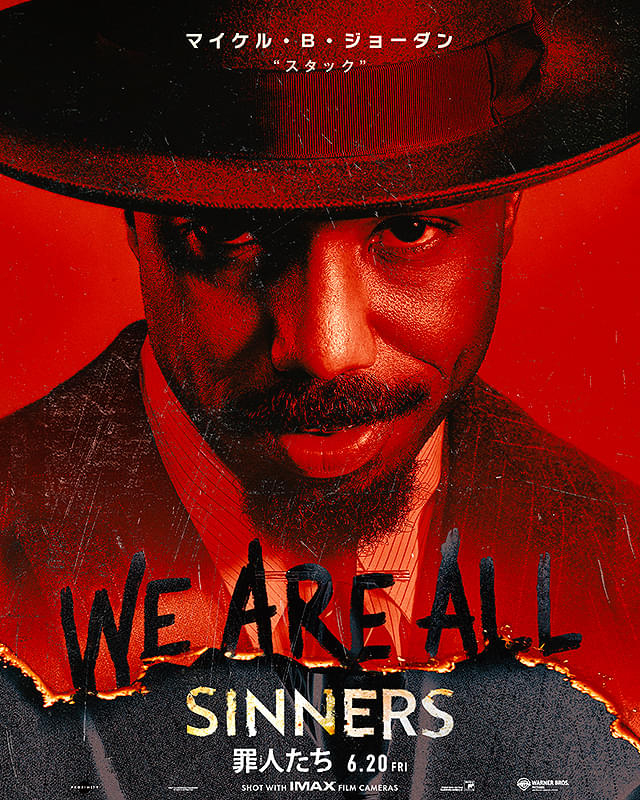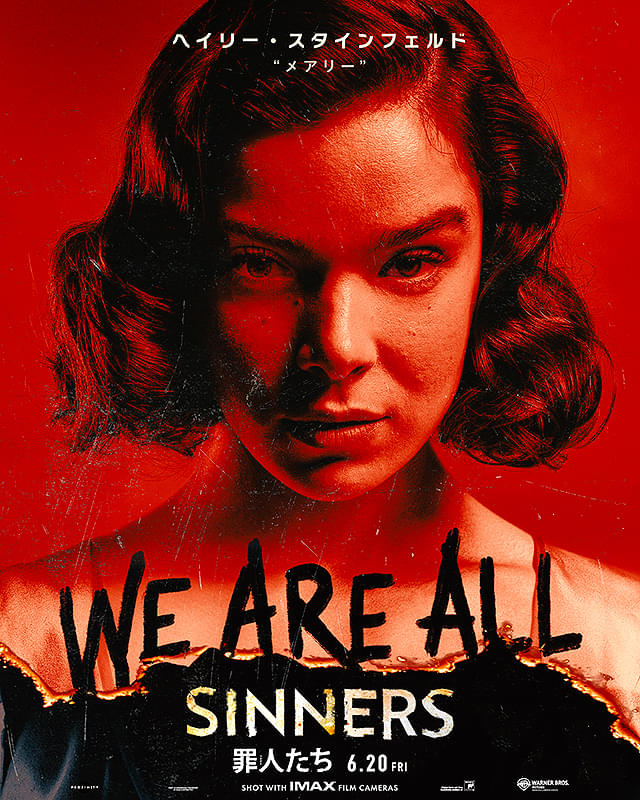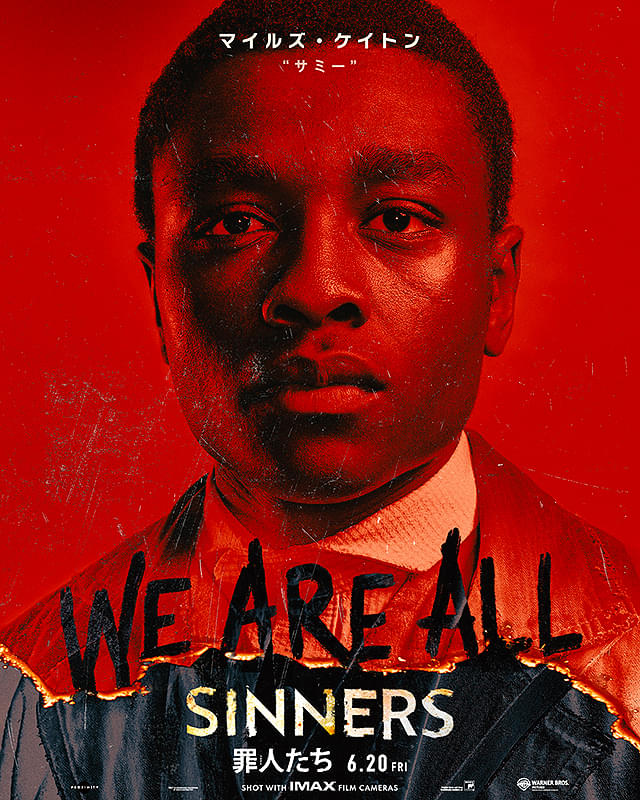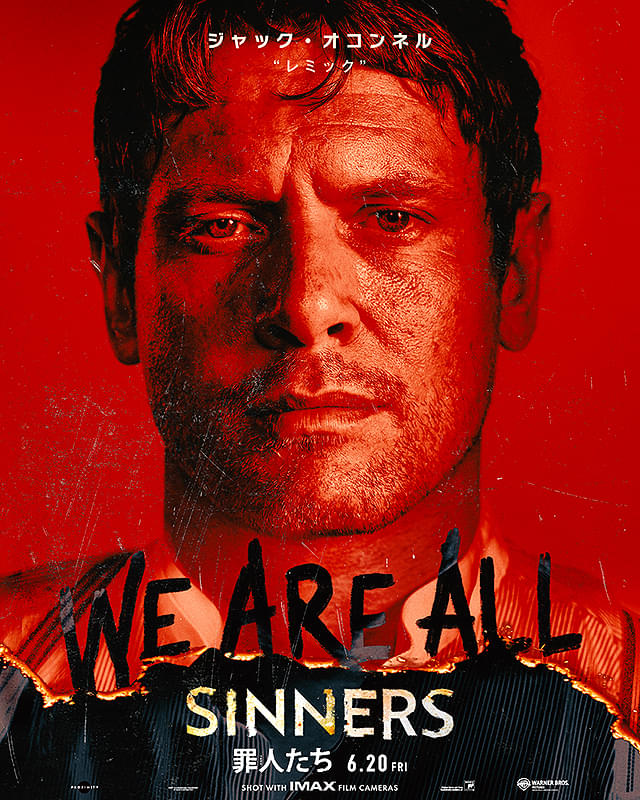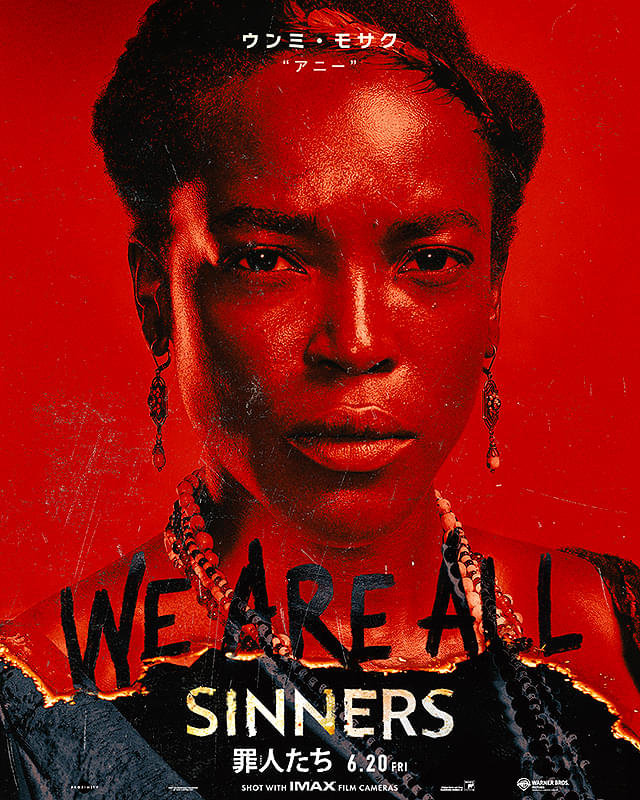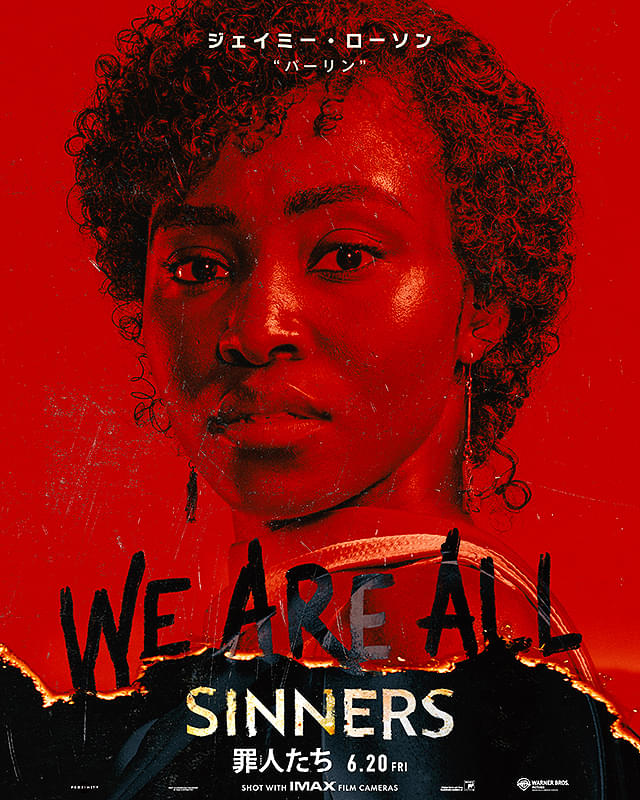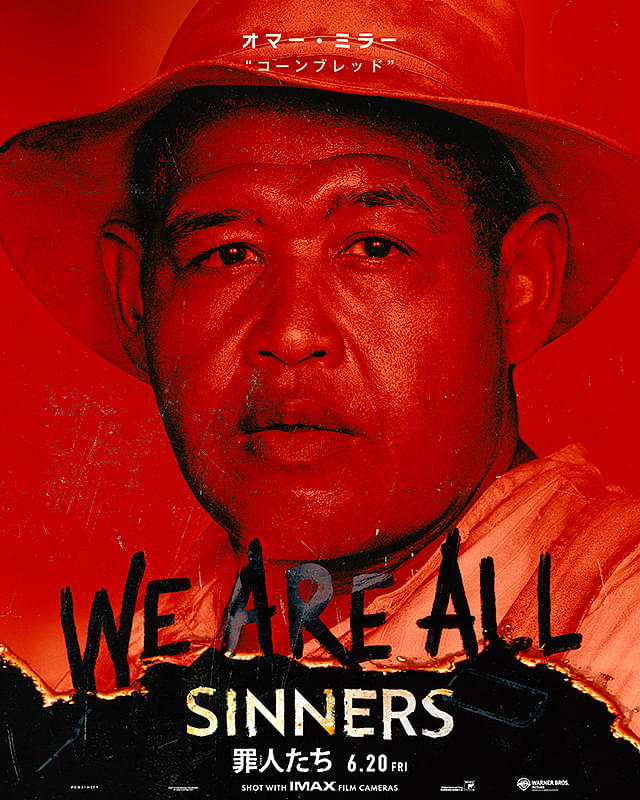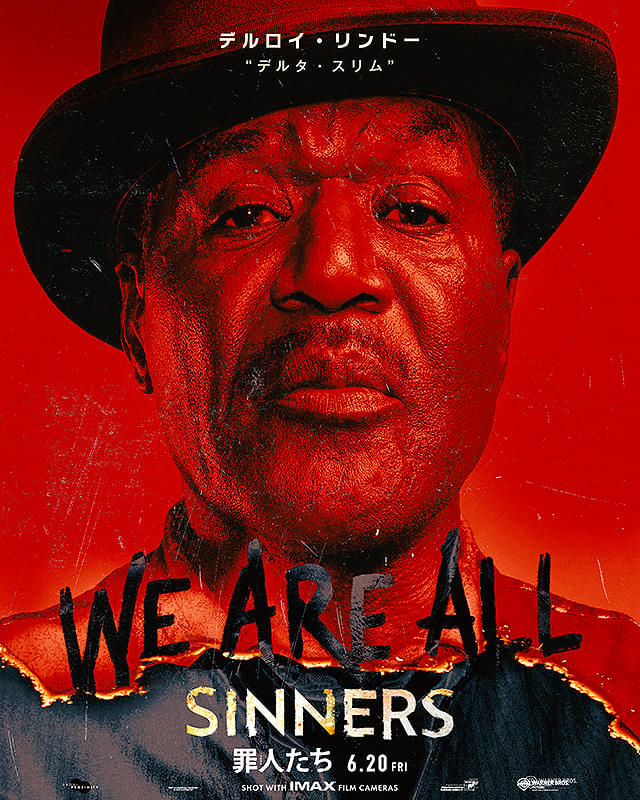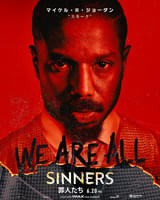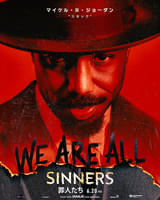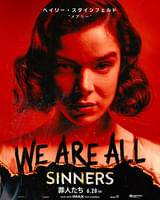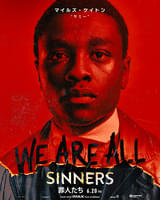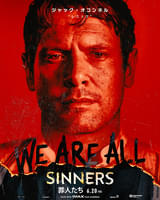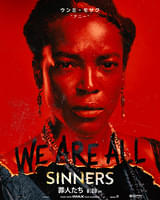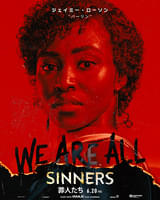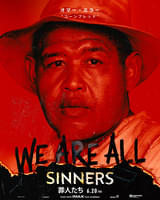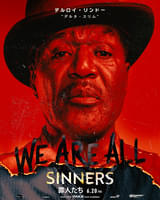罪人たち
劇場公開日:2025年6月20日
- 予告編を見る
- U-NEXTで
本編を見るPR

解説・あらすじ
「ブラックパンサー」「クリード チャンプを継ぐ男」のライアン・クーグラー監督が、これまでの長編作品でも数多くタッグを組んできたマイケル・B・ジョーダンを主演に迎えて描いたサバイバルスリラー。
1930年代、信仰深い人々が暮らすアメリカ南部の田舎町。双子の兄弟スモークとスタックは、かつての故郷であるこの地で一獲千金を狙い、当時禁止されていた酒や音楽を振る舞うダンスホールを開店する。オープン初日の夜、欲望が渦巻く宴に多くの客が熱狂するが、招かれざる者たちの出現により事態は一変。ダンスホールは理不尽な絶望に飲み込まれ、人知を超えた者たちの狂乱の夜が幕を開ける。
主人公の双子をジョーダンが1人2役で演じ、「バンブルビー」のヘイリー・スタインフェルド、「フェラーリ」のジャック・オコンネル、「ザ・ファイブ・ブラッズ」のデルロイ・リンドーが共演。クーグラー監督が脚本・製作も務め、スタッフにも美術デザイナーのハンナ・ビークラー、作曲家のルドウィグ・ゴランソン、衣装デザイナーのルース・ E・カーターら「ブラックパンサー」のチームが再結集した。第98回アカデミー賞では作品賞、監督賞、主演男優賞、助演男優賞、助演女優賞など主要部門を含む、アカデミー賞史上最多となる計16部門でのノミネートを果たした。
2025年製作/137分/PG12/アメリカ
原題または英題:Sinners
配給:ワーナー・ブラザース映画
劇場公開日:2025年6月20日
スタッフ・キャスト
- 監督
- ライアン・クーグラー
- 製作
- ジンジ・クーグラー
- セブ・オハニアン
- ライアン・クーグラー
- 製作総指揮
- ルドウィグ・ゴランソン
- ウィル・グリーンフィールド
- レベッカ・チョー
- ピート・チアペッタ
- アンドリュー・ラリー
- アンソニー・ティッタネグロ
- 脚本
- ライアン・クーグラー
- 撮影
- オータム・デュラルド・アーカポー
- 美術
- ハンナ・ビークラー
- 衣装
- ルース・E・カーター
- 編集
- マイケル・P・ショーバー
- 音楽
- ルドウィグ・ゴランソン
- 視覚効果監修
- マイケル・ララ
- 振付
- アーコモン・ジョーンズ
- キャスティング
- フランシーヌ・メイズラー
受賞歴
第98回 アカデミー賞(2026年)
ノミネート
| 作品賞 | |
|---|---|
| 監督賞 | ライアン・クーグラー |
| 主演男優賞 | マイケル・B・ジョーダン |
| 助演男優賞 | デルロイ・リンドー |
| 助演女優賞 | ウンミ・モサク |
| 脚本賞 | ライアン・クーグラー |
| 視覚効果賞 | |
| 美術賞 | |
| 撮影賞 | オータム・デュラルド・アーカポー |
| 衣装デザイン賞 | |
| 編集賞 | マイケル・P・ショーバー |
| 音響賞 | |
| メイクアップ&ヘアスタイリング賞 | |
| 作曲賞 | ルドウィグ・ゴランソン |
| 主題歌賞 | |
| キャスティング賞 |
第83回 ゴールデングローブ賞(2026年)
受賞
| 最優秀作曲賞 | ルドウィグ・ゴランソン |
|---|---|
| シネマティック・ボックスオフィス・アチーブメント賞 |
ノミネート
| 最優秀作品賞(ドラマ) | |
|---|---|
| 最優秀主演男優賞(ドラマ) | マイケル・B・ジョーダン |
| 最優秀監督賞 | ライアン・クーグラー |
| 最優秀脚本賞 | ライアン・クーグラー |
| 最優秀主題歌賞 |



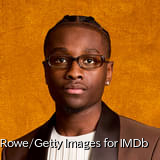












 バンブルビー
バンブルビー スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース クリード 炎の宿敵
クリード 炎の宿敵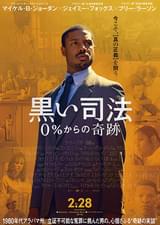 黒い司法 0%からの奇跡
黒い司法 0%からの奇跡 クリード チャンプを継ぐ男
クリード チャンプを継ぐ男 スウィート17モンスター
スウィート17モンスター フルートベール駅で
フルートベール駅で ウィズアウト・リモース
ウィズアウト・リモース 華氏451(2018)
華氏451(2018) ジョーカー
ジョーカー