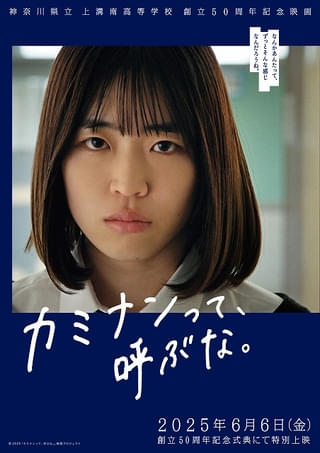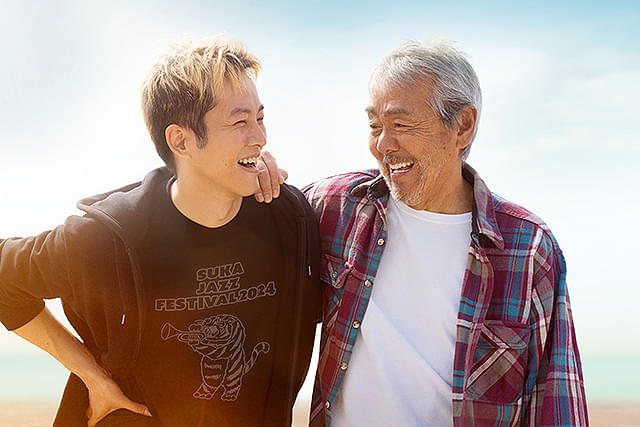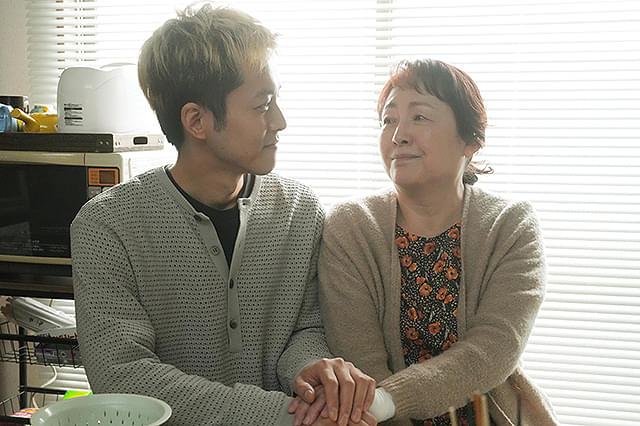父と僕の終わらない歌
劇場公開日:2025年5月23日
解説・あらすじ
若き日に諦めたレコードデビューの夢をかなえようとするアルツハイマー型認知症の男性と、彼を支える家族の姿を描いたヒューマンドラマ。2016年にイギリスで1本の動画をきっかけに80歳にしてCDデビューを果たした男性の奇跡の実話をもとに、舞台を日本に置き換えて映画化した。
かつてミュージシャンとしてレコードデビューを目指しながらも、息子・雄太のために夢を諦めた間宮哲太。音楽とユーモアをこよなく愛する彼は、生まれ育った横須賀で楽器店を営みながら、時々地元のステージで歌声を披露しては喝采を浴びてきた。そんなある日、哲太はアルツハイマー型認知症と診断されてしまう。すべてを忘れゆく哲太をつなぎ止めたのは、彼を信じて支え続けた息子・雄太と強く優しい母・律子、固い絆で結ばれた仲間たち、そして彼が愛する音楽だった。
寺尾聰が父・哲太、松坂桃李が息子・雄太を演じ、松坂慶子、ディーン・フジオカ、佐藤栞里、佐藤浩市が共演。「タイヨウのうた」「ちはやふる」シリーズの小泉徳宏監督がメガホンをとり、実写版「シティーハンター」の三嶋龍朗が小泉監督と共同で脚本を手がけた。
2025年製作/93分/G/日本
配給:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
劇場公開日:2025年5月23日
スタッフ・キャスト
- 監督
- 小泉徳宏
- 原案
- サイモン・マクダーモット
- 脚本
- 三嶋龍朗
- 小泉徳宏
- 製作
- 永山雅也
- 門屋大輔
- 菊池貞和
- 桑原勇蔵
- 長瀬俊二郎
- 坂本裕寿
- 松本光司
- 嶋田充郎
- エグゼクティブプロデューサー
- 福家康孝
- プロデューサー
- 渡久地翔
- 佐原沙知
- 巣立恭平
- 小柳智則
- 撮影
- 柳田裕男
- 照明
- 宮尾康史
- 録音
- 赤澤靖大
- 美術
- 五辻圭
- 装飾
- 前田亮
- ヘアメイクディレクション
- 古久保英人
- ヘアメイク
- 菊地由美子
- ヘアメイク(松坂慶子専属)
- 崎山彩実
- スタイリスト
- 新﨑みのり
- スタイリスト(松坂慶子専属)
- 安野ともこ
- サウンドデザイン
- 大河原将
- VFXプロデューサー
- 長井由実
- 編集
- 穗垣順之助
- 音楽
- 横山克
- 助監督
- 吉田和弘
- 權徹
- スクリプター
- 堀菜々子
- 制作担当
- 矢口篤史
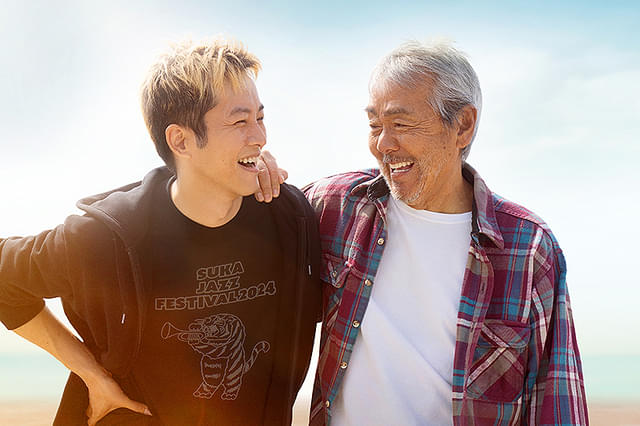













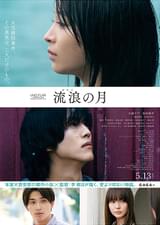 流浪の月
流浪の月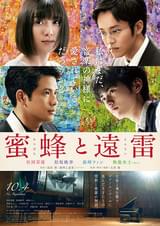 蜜蜂と遠雷
蜜蜂と遠雷 フロントライン
フロントライン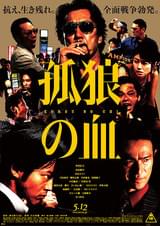 孤狼の血
孤狼の血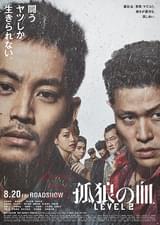 孤狼の血 LEVEL2
孤狼の血 LEVEL2 キセキ -あの日のソビト-
キセキ -あの日のソビト- エイプリルフールズ
エイプリルフールズ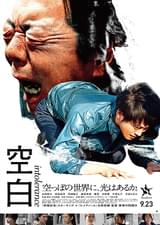 空白
空白 HELLO WORLD
HELLO WORLD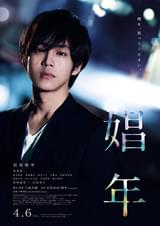 娼年
娼年