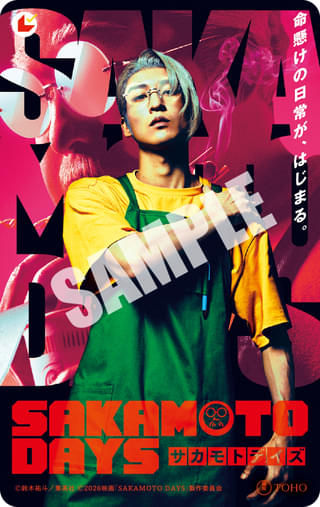コラム:下から目線のハリウッド - 第51回
2025年5月2日更新

映画祭はまさに「商品カタログ」 映画を”買い付け”する配給会社の知られざる役割
「沈黙 サイレンス」「ゴースト・イン・ザ・シェル」などハリウッド映画の制作に一番下っ端からたずさわった映画プロデューサー・三谷匠衡と、「ライトな映画好き」オトバンク代表取締役の久保田裕也が、ハリウッドを中心とした映画業界の裏側を、「下から目線」で語り尽くすPodcast番組「下から目線のハリウッド ~映画業界の舞台ウラ全部話します~」の内容からピックアップします。
配給会社には大きく2種類あり、ディズニー、ユニバーサル、ワーナーといったハリウッドのメジャースタジオと言われる会社と、それ以外のインディペンデントの配給会社があります。今回は、インディペンデントの配給会社のビジネスについて解説します!
三谷:実は映画って「作っただけ」では、お客さんには届かない、観てもらえないという残酷な現実があります。
久保田:そうですよね。配給しなきゃいけないわけだ。
三谷:なので、映画をつくる人が念頭に置かないといけないのは「この映画は、ぜひみんなに観てほしい。そして、権利を買い取って多くの人に観てもらえれば、儲かるかもしれない」と配給会社に思ってもらうこと、それを説得することだったりします。
久保田:どうして配給会社に?
三谷:配給会社が、映画とお客さんとをつなぐ役割をしているからです。そして、これは映画館だけに限った話ではありません。映画を見る場所って、飛行機の中や家でオンデマンドやサブスクで見るのもそうですし、テレビで放送されることもありますよね。で、それぞれの場所に映画を届けるために、配給会社が間に入ってさまざまな調整をしているんです。
久保田:映画が届くまでの流通ルートのコネクションを持っているのが、配給会社。
三谷:その通りです。なのでまずは、配給会社の目に留まらないことには、映画館では映画は観られない。YouTubeみたいなプラットフォームでも物理的には届けられますが、一般的な意味合いでは観客には届きません。
久保田:どうしたら作った映画を配給会社に観てもらえる?
三谷:色々なパターンがあります。ひとつは、映画が完成してから配給が決まるパターン。完成した映画を観て「これは面白い!うちで配給しよう!」と配給会社が手を挙げるわけです。
久保田:それはまだ世の中に出ていない映画ということ?
三谷:そうです。
久保田:それが映画祭で観られるんだ?
三谷:はい、それが映画祭や映画マーケットなどで発見されて、お金を出して買われていくというパターンがひとつ。実際に、映画祭で上映されている途中に会場から出てきて、「絶対売れるから、今からもうオファーしてください」みたいなことを社内に電話をしたり、あるいは、その映画のプロデューサーに配給したい旨の連絡を入れることがありますね。

写真:AP/アフロ
久保田:M1グランプリみたいだな。優勝後に仕事が続々と入るように。
三谷:もう一つのパターンは、映画が製作される前に配給を決めていくパターンです。映画の企画段階で、企画書を持って、配給会社に提案する方法ですね。
久保田:なるほどね。
三谷:映画祭や映画マーケットに映画の脚本と出演予定のキャスト案のプレゼン資料を持ち込み、各国の配給会社と商談を行います。そこで例えば、ドイツの配給会社が、持ち込まれた企画に対して「◯◯円支払うので、わが国(この場合はドイツ)の劇場での上映権を譲ってください。」といった交渉が行われます。
久保田:配給会社が逆にオファーをするんだ。
三谷:そうですね「お金を出すから、その映画の劇場公開やストリーミング配信などの権利を、◯◯地域で利用するための権利を売ってくれ」というようなやり取りをします。
久保田:あれだ、令和ロマンがツアーをやるってなったら客が集まるから、吉本側で仕切る。でも、地下芸人がツアーやるときは、地域によっては知名度がないから、自分でプレゼンしなきゃいけない。それが映画祭だ。
三谷:そうですかね(笑)? シビアですけど、映画祭はネタ見せみたいなところですね。
久保田:超えぐいじゃん。無名の監督なら、かなり厳しいのでは?
三谷:でも、大御所クリストファー・ノーラン監督も、とうぜん最初は無名ですよね。無名時代に作った「フォロウィング」という映画が当時話題になり、そこから少しずつステップアップしていって今に至りますし、クエンティン・タランティーノ監督はサンダンス映画祭のワークショップ経由で有名になりましたしね。

(C)2010 IFC IN THEATERS LLC
久保田:だからそういう意味でいうと、映画祭はネタ見せでもあり…。
三谷:久保田さんのお笑いの例えに乗っかると、テレビのバラエティー番組で「いま一押しの若手芸人!」みたいなコーナーってたまにあるじゃないですか。これに出演するための予選会…オーディションみたいなものがあるわけですよ。
久保田:オーディションありますよ。売れるランキングとか、天才ランキングみたいなコーナーって。
三谷:その予選会やオーディションが、映画祭だったりして、そこでテレビに出してあげてもいいよっていう、ある種フィルターされていますよね。
久保田:そうですね。
三谷:で、そのオーディションには権威がある人、若手芸人ウォッチャーの人がいて、芸人が発掘される。なので、テレビ番組と配給は、多少似ている部分もあるかもしれないですね。なかなかシビアな世界です。
久保田:なるほど。
三谷:そして、大手スタジオの世界になると、基本的には閉じた世界なので、自分たちで製作をし、配給もスタジオ自身で全世界に行うので、買い付けといった次元とはまた異なります。
久保田:ということは、配給会社と制作スタジオは別物なんですか?
三谷:基本的にはそうですね。大手スタジオの場合は、出資も配給も自分たちで行って、すべての儲けは自分たちの会社に来るようにやってるわけですよね。
久保田:日本だと東宝や松竹、東映もスタジオを持ってるじゃないですか。だから普通に映画を観てる人だとわからないよね。配給って制作会社のこと?って思うよね。
三谷:そう思いますよね。厳密には、配給会社は映画の「流通」する部分をいろいろコントロールしてるよっていう話ですね。
久保田:なるほど。洋画って最初の1秒くらいに、たくさんクレジットみたいなものが出てくるじゃん。あれがまさに配給なわけでしょ?
三谷:そうそう。配給会社や映画に出資した会社のロゴが出てきて、本編が始まる。
久保田:なるほどね。ちなみに、配給会社ってそれぞれ特色があるの?
三谷:ありますね。例えば「ミッドサマー」「シビル・ウォー アメリカ最後の日」などを配給しているA24なら、アーティスティックでエッジの効いた作品が多いです。
久保田:たしかに!
三谷:ホラー専門の会社なら「ホラーで一定のクオリティがある作品」といったイメージが持たれます。映画をつくる人からすれば、自分の作品のカラーと配給会社の相性を把握することが重要ですね。
久保田:うんうん。例えば「お笑い事務所の人力舎だとコントが強い」みたいなことですよね。だからコント芸人を目指したい人は、人力舎の養成所に入るとか。
三谷:なるほど。お笑い事務所に例えるとわかりやすいですね。
久保田:ネタ見せを行うオーディションが映画祭、配給会社はお笑い事務所やテレビ局。配給会社の構造が理解できました。
三谷:すごくざっくりいうとそういうことですね!今後「映画が○○ドルで買い付けされました」という話題があったら、配給会社にぜひ注目してみてください。
この回の音声はPodcastで配信中の『下から目線のハリウッド』(サンダンス映画祭もベルリン映画祭も...「買い付け」って何をするの?[S11-#04])でお聴きいただけます。
筆者紹介

三谷匠衡(みたに・かねひら)。映画プロデューサー。1988年ウィーン生まれ。東京大学文学部卒業後、ハリウッドに渡り、ジョージ・ルーカスらを輩出した南カリフォルニア大学の大学院映画学部にてMFA(Master of Fine Arts:美術学修士)を取得。遠藤周作の小説をマーティン・スコセッシ監督が映画化した「沈黙 サイレンス」。日本のマンガ「攻殻機動隊」を原作とし、スカーレット・ヨハンソンやビートたけしらが出演した「ゴースト・イン・ザ・シェル」など、ハリウッド映画の製作クルーを経て、現在は日本原作のハリウッド映画化事業に取り組んでいる。また、最新映画や映画業界を“ビジネス視点”で語るPodcast番組「下から目線のハリウッド」を定期配信中。
Twitter:@shitahari