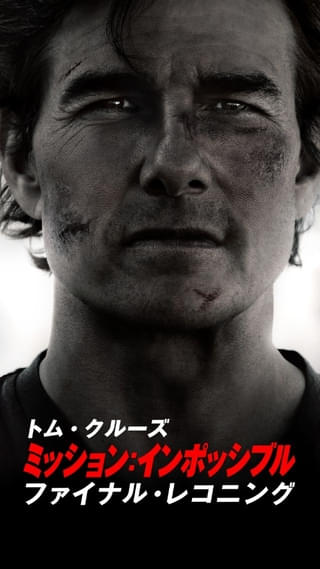コラム:清水節のメディア・シンクタンク - 第15回
2016年8月4日更新

第15回:脳感<ブレインダイブ>で震えろ! 体感を超えた「秘密 THE TOP SECRET」のヒミツ
■他人の感情と自分の感情が区別出来なくなる時代

(C)2016「秘密 THE TOP SECRET」製作委員会
脳内捜査は、現実社会でも荒唐無稽な話ではなくなってきた。脳科学や犯罪心理学の最前線にも耳を傾けた結果、大友啓史は、ジャーナリスティックな感覚でこのフィクションを構築している。現在の科学捜査はDNA捜査一辺倒だが、やがて科警研(科学警察研究所)が脳内捜査に着手する可能性は高く、まずは存命中の目撃者や被疑者の脳のスキャンから始まるのではないかと言われている。では記憶映像は、法的な証拠になりうるのか。そんな領域にまで本作は踏み込んでいく。ある事件の被害者の脳内映像の中で、一瞬、殺人犯の顔が鬼か悪魔のような形相に変わるシーンがある。そう、記憶とは実に主観的なものなのだ。記憶する段階でその人の知識や価値観が反映され、人それぞれの見え方、記憶のされ方が異なるのだという。トラウマによって改変されることもあれば、時間が経過して自分に都合のいいように書き換えられることもある。つまり客観的ではない当事者の記憶映像を、法的証拠として採用することは難しく、捜査を絞り込むために活用されることに留まるのだろう。
SF的設定を用いてはいるが、ここで描かれるのは、覗く者と覗かれる者の人生に起きる出来事だ。マスメディアが暴く著名人のプライバシーに土足で踏み込む現代人は、他人の脳内も覗きたがるに違いない。だが、本作に描かれるようなテクノロジーで他人の感情を覗き観ることが出来るようになったとき、重大な問題が発生する。それは、覗き観た他人の感情と自分の感情が区別出来なくなってしまうことだ。自分自身を規定するはずの記憶に、他人の記憶が流入する。それが憎悪に満ちた凶悪犯の感情であった場合、アイデンティティは崩壊せずに済むのか。捜査官に扮する生田斗真、岡田将生、松坂桃李は、そんな危急の事態に直面しているのだ。
■「羅生門」を思わせるエンディングに込められたもの

(C)2016「秘密 THE TOP SECRET」製作委員会
日本映画離れした映像の力で、一気呵成にブレインダイブを堪能させるジェットコースター・ムービー。とはいえ、練りに練られたシナリオに基づき、さまざまな主観映像が入り混じる構成を複雑だと感じ、あの映像の意味は? と疑問を抱く人も少なくないだろう。悪意を伴う過激な記憶映像が、自分の脳内に流入しそうになって抵抗するという人も現れるかもしれない。大友演出は説明しすぎず、手を抜かない。前述した「野性の叛乱」の意味を、大友は「ハリウッドSFのように科学が暴走するではなく、叛乱は人間の内側から生まれてくる」と説明する。そしてこの映画は、大友啓史という映像作家が、窃視症的な現代人がはびこる脳化社会/データ化社会を批判的に描きながらも、自らの心の闇にいかに決着をつけるべきかをさまよった軌跡と捉えることも可能だ。
繰り返し観ることで、いくつもの発見があった。創りようによっては、作家性の強いアート系作品になることもありうる骨太なテーマであるが、今の時代に大スクリーンで観ることの意味を追い求め、壮大なエンターテインメントに仕上げている。ラストの映像は多様な解釈を呼ぶだろう。真っ先に想起したのは「羅生門」の構造である。当事者たちそれぞれの利己的な証言によって、ひとつの出来事が多面的に見えてくる黒澤明の名作は、人間不信に陥りそうになった果てに「希望」を用意した。さまざまな主観が入り乱れたあと、大友が締め括る映像は、生きづらい現代へ大いなる皮肉を込めたメッセージではないだろうか。興行を成立させるビジネス面への配慮と、クリエイターが本気で創りたいものとの折り合いをつけるのがなかなか困難な日本映画の現状にあって、大友が自我を貫いた渾身の一作「秘密 THE TOP SECRET」の投ずる波紋が大きく拡がることを期待しよう。
コラム