【「ディナー・イン・アメリカ」評論】“STAY HOME”で居心地の悪さを感じている人にこそ観て欲しい“STAY PUNK”なふたりの恋
2021年9月18日 20:00

総代として卒業しTV局に就職した女性が失業の憂き目にあう。厳しい現実にどう向き合えば良い。ジェネレーションXにフォーカスしたベン・スティラー監督の「リアリティ・バイツ」(1994)は、時代を先取りしたキャスティング、ビデオ映像を交えた描写、ヒット曲を散りばめたサウンドトラックと三拍子揃ってスマッシュヒットした。
それから約四半世紀、ベン・スティラーがプロテュースしたアダム・レーマイヤー監督作「ディナー・イン・アメリカ」は、世代を超えて普遍のテーマを投げかける。
主人公は、特徴的なメガネに星条旗柄のシャツを超然と着こなすパティと無軌道な行動で周りを煙に巻くサイモン。パティの唯一の楽しみは覆面ボーカリスト、ジョンQが率いる“サイオプス”の曲で踊ること。一方のサイモンは、治験で稼いだ金を元手に小金を稼いでバンドを続けている。エキセントリックな風貌のふたりには共通点がある。好きなものはとことん好きで、大抵のことは受け流して嘘もつける。でも一線を越える奴には黙っていられない。つまりパンクなのだ。
主演のエミリー・スケッグスとカイル・ガルナーも、監督もほぼ無名、劇伴とは別に流れるサントラは6曲だけ。三拍子揃わずの逆境を跳ね返すのは、パンク愛に溢れたアダム・レーマイヤー監督の熱量だ。
「全員ぶっ飛ばせ 私たち以外、みんないなくなれ」 ──パティが歌う劇中歌 “Watermelon”より
目を合わせることなく規範を押しつける過保護なパティの両親、ハラスメントで憂さを晴らす高校生たち、適当に都合を見つけて不当解雇する治験医師とペットショップのオヤジ、前歴と先入観だけで悪人扱いするサイモン一家の面々。脚本、編集もこなした監督は、ふたりが直面する現実、偏見だらけの現代社会の歪みを抜群のリズム感でむき出しにしていく。変化球と見せかけて実はド直球なメッセージが、タフな時代を生きなきゃいけない誰の心にもグサリと突き刺さる。
“STAY HOME”を強いられる今、居心地の悪さを感じている人にこそ観て欲しい“STAY PUNK”なふたりの恋。ベン・スティラーが見出したのは、自分が描けなかったもうひとつの“リアリティ・バイツ”なのかも知れない。
(C)2020 Dinner in America, LLC. All Rights Reserved
関連ニュース





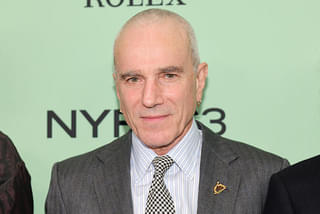
映画.com注目特集をチェック
 注目特集
注目特集 メラニア
世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?
提供:イオンエンターテイメント
 注目特集
注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!
【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!
提供:ツイン
 注目特集
注目特集 辛口批評家100%高評価
【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。
提供:Hulu Japan
 注目特集
注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?
【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!
提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント








































