ファティ・アキン、哀れな実在の殺人鬼をリアルに描いた新作は「ターニングポイントになった」
2020年2月14日 18:00

[映画.com ニュース] 1970年代のドイツ・ハンブルクに実在した連続殺人犯を描いたサスペンスホラー「屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカ」が公開された。敗戦後のドイツで幼少期を過ごし、5年間で4人の娼婦を殺害したホンカの日常をリアルに描き出した本作は、昨年の第69回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に出品され、賛否両論を呼んだ。来日したファティ・アキン監督に話を聞いた。
薄汚れた安アパートの屋根裏部屋に暮らし、夜になると場末のバーに通って女性を物色、アルコールに溺れて暴力的になり、正常な判断を失っていくホンカ。孤独な男の日常が淡々と描かれるが、ストーカーのような病的な妄想や、殺人シーンではスプラッター的な演出も加わり、観客は短絡的で哀れな殺人鬼の行く末をまざまざと見せ付けられ、戦慄する。アキン監督は今作を「本当に妥協することなく作った」と断言する。
「決して簡単な判断ではありませんでしたが、ホンカの半生を描いた原作小説をとても気に入っていたんです。ホンカは僕が生まれ育ったエリアに実在した殺人鬼で、今も彼が通ったバーがあり、ある意味ハンブルグについての映画。小説が自分に挑戦を突きつけているように感じました。果たして映画作家として、その知識や技術、度量の上で、この小説を映像化するだけの力を持っているだろうか? と。スポーツのように、どこまで跳躍できるのかその答えを自分で見てみたかった。僕のキャリアの中で、ターニングポイントになった作品です」
「今までの作品は、資金面で妥協が必要でした。あとは、観客におもねるというわけではないけれど、関わっている人を傷つけないために妥協したり…自分自身がプロデューサーでもあるので、その視点で妥協せざるを得ないこともありました。そして、今回は本当に妥協することなく作った作品なので、これまでにない満足感がありました」
小説に描かれた実際の出来事を基に脚本を執筆したが、ホンカが街で自転車に乗った美少女に一目ぼれする…というエピソードは、創作だそう。その狙いをこう説明する。
「唯一、フィクションとして描いたのが若いカップルの物語。小説にも出てくるのですが、実際にホンカとのつながりはなく、ふたりがバーに行ってみるという記載しかない。しかし、何とか映画に使えないかと考え、被害者となった女性達の若い頃を表現できないかと考えたのです。カップルの若い女性の方がよく出てくるのはその理由です。男性の方は、ホンカの若かりし頃だと見ていただいてもいいのです。アウトサイダーであり、愛を探している10代の男の子です」
「また、ホンカが殺したのが中年の娼婦だったので、年配の女性に性的なフェティシズムを持っているのでは? と考える人がいたのです。もちろん証拠はありませんが、それは間違っていると、僕が映画を通して証言することが重要だと思ったのです。実際の現場写真にも若い女性のピンナップが貼られていましたし。みじめな人物で、誰も自宅に招くことができず、出会うことができた女性がたまたま老いた娼婦だったということを見せたかった。そこで、架空の若い女性のキャラクターを膨らませたのです」
 (C)2019 bombero international GmbH&Co. KG/Pathe Films S.A.S./Warner Bros. Entertainment GmbH
(C)2019 bombero international GmbH&Co. KG/Pathe Films S.A.S./Warner Bros. Entertainment GmbHハンブルグ市民の間では、モンスターのように伝わる民話的存在のホンカ。戦争の傷跡が残る時代に生まれ育ち、育児放棄をされたり、性的暴行に遭うなど過酷な経験をした人物でもあるが、そういった事実については敢えて映画では言及していない。
「僕が10代だった90年代、ホンカが精神科の閉鎖病棟から出ることになって、物議を醸したのです。危険ではないかと反対する一派と、人権派がぶつかり合っていたのを子ども心に覚えています。しかしそれ以上に、小説での描かれ方で、一人の人間としてなにか自分とリンクするものを感じたんです。彼は脳の機能に問題があり、思いやりをつかさどる部分に障害を持っていたけれど、一人の人間でもある。その描かれ方が今作のイメージにつながりました」
「なぜ彼が殺人を犯したのか……僕は障害も原因のひとつだったと思うけれど、アルコールの要素も大きいと思う。でも、その答えは僕にも誰にもわからないし、この映画自体、わからないことだらけ。ホンカと同じ経験をした人間の全員が連続殺人犯になるわけではないからです。ほのめかすように取られてしまう可能性を出したくなかった。それは答えとして短絡的すぎます。例えば、それが『ジョーカー』だったらいいわけです。DC映画だというのが前提で、現実ではないことがベースになっている。だけれども、実生活はわからないこと、ミステリーがたくさんある。それがいちばん怖かったりしませんか。彼の場合も、なぜそういう行為に及んだのか、わからないとことが恐ろしいと思うのです」
(C)2019 bombero international GmbH&Co. KG/Pathe Films S.A.S./Warner Bros. Entertainment GmbH
Amazonで関連商品を見る
関連ニュース






映画.com注目特集をチェック
 注目特集
注目特集 配信を待つな!劇場で観ないと後悔する
【人間の脳をハッキング“レベルの違う”究極音響体感】戦場に放り込まれたと錯覚する没頭がすごすぎた
提供:ハピネットファントム・スタジオ
 注目特集
注目特集 感情ぐっちゃぐちゃになる超オススメ作!
【イカれた映画を紹介するぜ】些細なことで人生詰んだ…どうにかなるほどの強刺激!
提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
 注目特集
注目特集 なんだこの“めちゃくちゃ面白そう”な映画は…!?
【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!
提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
 注目特集
注目特集 エグすんぎ…人の心はないんか…?
【とにかく早く語り合いたい】とにかく早く観て! そして早く話そうよ…!
提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント










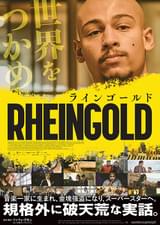










![We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME (初回限定盤)(3枚組) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/41QgEUzIZEL._SL160_.jpg)
























