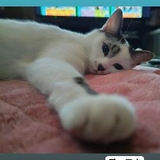月のレビュー・感想・評価
全205件中、1~20件目を表示
匂いは映像で伝わらない
生産性、という言葉が定着して久しい。いや、製造や仕事の成果という点で昔からあった言葉だと思うのだけど、人間を評価する尺度としてこれが定着してしまった。そのことをどう考えるべきか、過酷な競争社会に煽られてしっかりした議論ができないままに社会は動き続けている。あらゆる人間の評価が数字に置き換えられていきそうな時代になってしまった。
本作の題材となった事件は、そんな人間を生産性で判断してしまう社会の行き着く先を示したようで、大きな衝撃を与えた。だが、ニュースが出た時多くの人は、単純にクレイジーな人間がクレイジーな行動に出たという風にしか受け止めていなかったのではないか。
しかし、多くの人も、どこかにあの犯人にように、生産性を尺度に人間を評価する心情を抱えているのではないか。本作は犯人をクレイジーな人間として描かず、周囲の人間にも一歩間違えれば同じようになりそうな危険性も混ぜつつ描いている。
そして、現実を知るということの困難さも本作は浮き彫りにする。カメラは真実を映せるだろうかとこの映画は問うている。
カメラを通じてニュースを見るだけでは現実を知ることはできない。典型的なのが匂いだ。匂いはカメラに映らない。この映画はそのことに自覚的だ。きっとこの映画の作り手は、「誰も挑まない社会の現実を見せた」という自惚れはないと思う。津波直後の匂いも排泄物の匂いも映像では伝えられない、その限界をきちんと自覚しているのだと思う。
現実は重くて息が苦しい
【鬱注意】満月よりも心を抉る!映画「月」がしんどすぎて、今週マジで仕事行きたくない件
Amazonプライム・ビデオで話題の映画「月」を鑑賞。あの相模原障害者支援施設殺傷事件をモチーフにした作品ということで、覚悟はしてたんですが…想像以上にズシンとくる映画でした。
宮沢りえ、再び「月」で魅せる圧巻の演技力
主演は、我らが宮沢りえ様!「月」といえば、どうしても「紙の月」を思い出してしまう世代です。銀行のお金をズルズル横領していく、あの危うい美しさ…今回も、社会の片隅で生きる女性を見事に演じています。
知的障害を持つ人々に向き合い、寄り添おうとする主人公の姿は、時に痛々しく、時に力強く、観る者の心を揺さぶります。宮沢りえさんの演技力、マジでハンパないって!
オダギリ・ジョー、磯村勇斗、二階堂ふみ…豪華キャスト陣が織りなす人間模様
脇を固めるキャストも超豪華!オダギリ・ジョーさんの飄々とした雰囲気、磯村勇斗さんの狂気を孕んだ演技、二階堂ふみさんの芯の強さ…それぞれのキャラクターが、物語に深みを与えています。
特に、磯村勇斗さんの演技は圧巻。事件を起こすあの役を見事に演じきり、観る者に強烈な印象を残します。マジで怖いけど、目が離せない!
「命の平等」とは何か?重いテーマに打ちのめされる
映画全体を覆うのは、重苦しい空気感。「命の平等」という、綺麗事では済まされない現実を突きつけられます。障害者施設で働く人々の苦悩、命に対する価値観、そして、平等の均衡が崩れた時の凄まじい悲劇…
目を背けたくなるようなシーンも多いですが、それ以上に、考えさせられることばかり。世の中には、どうしようもない不平等が存在する。それを目の当たりにした時、人はどう生きるべきなのか?
ラストシーンに希望の光を見た…気がする
救いのない絶望を感じさせる映画ですが、ラストシーンには、僕はかすかな希望の光が見えた気がしました。それでも、この世界で自分なりに精一杯生きていく人間の姿に、人間らしさ。これが人間なんだと。
そして、改めて自分の社会での役割について考えさせられました。微力ながらも、誰かの役に立てるように、明日からも頑張ろう…って、咳止まれ!
映画「月」、鑑賞後はマジでしんどくなりますが、間違いなく観る価値のある作品です。心の準備をして、ぜひご覧ください。
…さて、明日も仕事か。憂鬱だ。
なんか見た後呆然としました
重い映画だった。レビューと言っても何を書いたらいいだろう。さとくん...
いつもはすぐにレビューを書けるけど、この作品を観たあとはしばらく考...
いつもはすぐにレビューを書けるけど、この作品を観たあとはしばらく考えた
気持ちを整理した
心、これがあるのかないのか
建前でなく本音で
考え方、捉え方で見え方はむちゃくちゃ変わる
彼にとっては正義
心は見えない
心はその人のものでその人にしかわからない
彼の考え方がそうなってしまった理由がなによりも問題だと感じた
彼に彼を思ってくれている人にも心があることを気づいてほしかった
何をしたいのか…
登場人物が「それって綺麗ごとじゃないですか?」という場面について
映画として映像化する意義は
「犯人の考えは理解できる」と言うと誤解されそうだが、
「この考えに至ってしまう、陥ってしまう事は理解できる」とは実際の事件の報道時から思ってはいた。
それを再確認できる映画ではある。
だだ、それ以上の何かをこの作品から得ようとするのは脳が拒否する。
観て良かったと言える程に何かが改められる事は無いのだが、「偏見を助長する恐れ」も無いかと言うと、それは有ると感じる。
並行して描かれる夫婦のドラマが、内容自体は濃く、質の高い作りではあるけれど、この強烈な事件に絡めて考えさせられる事に一種の抵抗感もある。
現実の施設を知らない自分が、この映画を観て分かった気になって、こうあるべき、こうすれば変えられるなどとは言えない。
その程度にはフィクションが含まれ、一方で描かれていない日常もあるように思う。
少なくとも、今もこういった施設で働いている方々への敬意は感じない。
問題提起と言えば聞こえはいいが、それは実際の事件によって既にされてしまっている。
これでは追い討ちをかけて糾弾しているだけではないだろうか。
結局、この作品を世に出す意義を自分はあまり評価したくないのだな。
この作品が社会に生み出すものをプラスとマイナスで言うと、半々、或いはマイナスの方が大きいのではないか。
植松という人間の主張を役者の声を通してハッキリと映像化した事の影響力はかなり有ると思うし、その喧伝する行為自体に嫌悪感はある。
自分としては、彼や事件について知るにはドキュメンタリーやYouTubeの解説動画で十分だ。
そして障碍者や障碍者福祉に関わる人々のネガティヴな面だけを徹底的に現実として突きつけた一方で、フィクションとしての登場人物である夫婦にのみ希望や救済を与える内容もとても好感が持てるものではなかった。
ラストシーンで光が差し込む描写はとてもファンタジー的だ。
映画のクオリティとは違う部分で低評価をつけたい。
うーん、映画にプラスやマイナスなどと意義を求めるのも生産性を求めてしまっているようで傲慢ですかね。
きれいごとでは済まされない
この映画を見た後に、YouTubeで元の事件の概要を詳しく見たのですが、
実際に介護施設や障がい者と関わっている方のコメントで
「犯人と同じことを一回は思ったことがある」と多数書いてあり、それがすごく印象的でした。
犯人に対して、「心がない人は死んでもいい無価値な人間」だと思うのは勝手だけど、
命を奪う権利はないし許されない!と部外者が責めるのは、
現実問題きれいごとなのかもしれない…と思ってしまいました。
私も生産性があるなしで人の価値は決まらない、その存在自体に価値がある
と考えてはいるものの、いざ自分が自分でなくなったとき、それでも生きていたい
と思うのかと問われたら、正直生きていたくない…と思ってしまいます。
でもこの映画を見て障がい者施設のことを少しでも知れたことは良かったです。
それと、主人公の女性が過去の出来事から、今も中絶するか葛藤していることについては
今回の映画とは別にしてほしいなと思いました。
重い、苦しい、目を背けたい現実。けれど映画としては引き込まれる
現時点で、自分の身内には障碍を持つ者も介護を必要とする者はいない。しかし、だからこそいつ自分が当事者になるかもしれない未知のことへの不安からこの分野に関心があるし、モデルとなった相模原市のやまゆり園の事件の犯人についての記事もいくつか読んでいる。
私が知る限りの少ない経験や知識を元にいえば、この映画は少なくともかなりシビアに障碍者介護の現実を伝えようとしていると思う。
目を背けたい、生理的に受け付けられないようなシーンもあるが、特に誇張しているとも思わない。施設によっては全く違う状況のところもあろうが、それが事実として存在する施設もある。
今回は事件をモチーフに、その事件を引き起こした状況・過程を描くために負の場面が多くなったのは否めない。しかし、その中でも「光」の存在も描くことも疎かにはしていなかったと思う。
「テーマがわかりづらい」と言いう感想が散見されるが、私はそうは思わなかった。原因も答えも一つではなく、そこに関わる人たちも様々な事情を抱えている。しかしながらその根底には「個の尊厳と現実についての問いかけ」がぶれずにあると感じた。
(そういう意味では「ロストケア」といい勝負だが、ロストケアの方がエンターテイメント性を重視しているし、この映画はどこまで具体的に現実を映し出せるかを重視していると思う)
役者について言えば、皆良かった。この映画が伝えようとするものに向き合う真摯さが伝わってくる演技であった。
特に、こんな感想をもたれても本人は嬉しくもないし公私混同しないでほしいと思うだけかもしれないが、実際に幼子を亡くしているオダギリジョーの心境やその仕事を受けた際の覚悟を勝手に慮ると胸が苦しくなるし感服する心持にもなる。(正直、オファーした方も色んな意味で凄い)
また、この映画に限らないが、オダギリジョーは独特の柔和さとそれゆえの危うさを持ち合わせた浮世離れした存在感を保ちつつもちゃんと物語からは浮かないのが凄い。いつも「〝オダギリジョー〟なのにちゃんとその〝役〟として存在できる」稀有な役者だと思う。
重苦しい障害者問題を扱うも、最も重要なポイントを外してしまった作品
1)本作のテーマについて
2016年に相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で利用者19人が殺害された事件をモデルとした映画である。
犯人の施設従業員は、当初は障害児のために紙芝居を演じてあげるなど、熱心な仕事ぶりだったが、周囲からそれを嘲笑され、非難されていくうちに、障害者への向き合い方を逆転させてしまう。そして、最後には「会話の出来ない存在は人間ではない」といい、社会をよくするために障害者を次々に殺していく。
主人公は同施設に勤務を始めたばかりの中年女性だが、数年前に障害児の息子を亡くした経験があり、つい最近、再び妊娠したものの、高齢出産の危険と障害児出産の可能性から、早期に中絶しようと考える。
しかし、彼女の決断には旦那や医師、施設の同僚から疑問が投げかけられ、激しく動揺しているところに、冒頭の事件が勃発してしまうのである。
この2人の人物の交差するところに、「障害者を殺す権利が誰にある」という疑問と、「出生前診断で障害者とわかった胎児を堕胎することは、障害者を殺すことと同じではないか」という疑問が重なり、何とも重苦しいテーマにウンザリさせられてしまう。
2)上記テーマを個人的に検討してみた
出産と育児は、主に母性の働きによるものだから、胎児の生きる権利と、母親の自己決定権との衝突とならざるを得ない。
宗教的、倫理的な観点から「人間の生命を選別する権利は、人間にはない」という声は大きい。米国ではトランプを支持するキリスト教原理主義者たちが中絶禁止を叫び、現在、14州で中絶が禁止されている。
他方、レイプで妊娠させられた女性や、貧苦にあえぐシングルにとって、出産を強要されるのは、自己を否定されることを意味するだろう。普通の生活を送る普通の女性にしたって、子供を産むかどうかを他人に決められるというのは、冗談じゃないと思うに違いない。
大江健三郎の『個人的な体験』は妻が障害児を産んだ直後の男の動揺と現実逃避から、最後に乳児を受け入れるまでを描いた作品だった。何故、あのように重い体験になってしまうかといえば、育児が親の生活の大きな負担だからに他ならない。
両者を両立させられるとしたら、出産後の育児を全面的に共同体が保障する等々の手厚い支援を行うことしかないだろうが、いかんせん、そんな社会的環境や条件を前提としないまま、産むべきか産むべきでないかの議論をし続けるところに、この問題の不毛さがある。
今やその問題は老人介護とパラレルの様相を呈し、中絶をするか否かは、親の介護を中断するか否か、障害者を施設に預けるか否かは、親を介護施設に預けるか否かと類比的に見える。
そして現在、その問題を決するのはやはり経済問題なのだと思わざるを得ない。とするなら、本作で描かれたように、死んだ障害児の子供への愛着とか、効率性とかで論ずるのは、何やらいちばん重要なポイントを外して、むしろ逃げているようにしか見えないのである。
心はあるのか
映像作品とは直接 関係はありませんが 『人間とは自己の利益を最大化にすることを目的として行動する個人』 或いは 『すなわち、諸君が産まれたての赤ん坊のとき、また中学生の時期、社会人になったばかりの頃そして現在の自分は、見た目や姿形は違っていても ずっと自分(という同じ人間、同一の存在)であり続けていたはずである(少なくとも、諸君はそう信じている)。人間の身体は数年間で細胞がすっかり入れかわってしまうと言われるが、そうであるならば、少なくとも分子や原子のレベルでは子供のころの諸君自身と現在の諸君は別の存在のはずである。それにもかかわらず、自分が自分であり続けてきたはずだと言い得るのは、何を根拠としてそう主張できるのだろうか。ここに自己同一性を説明するために、「真の実在」たとえば霊魂とか、精神とか、理念またイデアとか、、、をもちだしてくる根拠が存在する、、、云々。 』 以前、読んだことがある学術図書の文言をふと思い出しました。勿論、母親の幼子に対する無償の愛を否定するものではありません。 感想を述べるには躊躇してしまうほど難しい映画でした。作品から自分自身(私)を問う。戒め?を受けている。そんな印象を持ちました。衝撃的な終盤に向かって進むわけですが宮沢りえさんと佐野勇斗さんの対峙 問答がひとつのクライマックスだったのだと感じます。彼が恋人を抱きしめながら凶行を告白する場面は人が壊れていくところを見せつけられた様な気がしました。この映画の下地にある背景については自分の日常では経験していないので語る事は出来ません。 アップリンク吉祥寺・早稲田松竹にて鑑賞
オダギリジョーってすごい
彼はサイコパスではない
当時は衝撃的なニュースだった。フィクションとはいえこの映画を見たことで、少しその内面が見えた気がした。実際の犯人はどうなのか。事件の概要を見ると、再現できうるところは結構忠実にやってるようにも見える。真面目だからこそ、信念があるからこそ、そういう行動に出てしまった。利用者を邪険に扱って鍵をかけたり、てんかん発作を起こさせようと懐中電灯で遊ぶあの若者たちの方がよっぽど悪人に見える。恐ろしい。必死で止めようとも、言い返せない。そうかも、とちょっと思ってしまう自分がまた恐ろしい。だってあんな光景を目の当たりにしてしまったら。どうしようもない現実を見てしまったら。でも残された家族の思いを感じたらどうか。やはり親にとっては大切な子供だ。
その親はここにしか預けられないから仕方がないと言った。やはりこの問題は根深い。彼らを良い環境に生かす社会的な手助けが必要。閉じ込めるのではなく、ほったらかしにするのではなく、何か手立てはないのか。日本の態勢を思う。
全205件中、1~20件目を表示