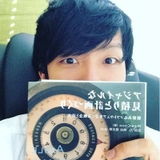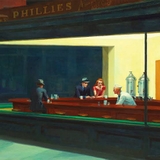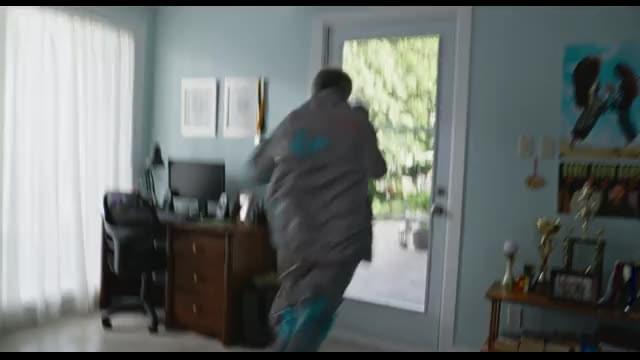ボーはおそれているのレビュー・感想・評価
全278件中、81~100件目を表示
最初の30分くらい面白くて(街の治安悪過ぎ)爆笑したかったのを他の...
最初の30分くらい面白くて(街の治安悪過ぎ)爆笑したかったのを他のお客さん静かに観てたので堪えてました
途中森の劇団四季辺りのところちょっとダレたかなて感じで睡魔が来そうになった
最初のテンションで突っ走るかもっと短くしてれば傑作になったかも
ボウのトラブル
どちらかと言うと
どこまでが現実で どこからが妄想かわからない物語
私は全部が誇張もされていない現実なんじゃないかなと感じました
私の両親は健在なんですが、途中死んだらどうしようと怖くなり 終盤の展開は救いでした
主人公は病んでヨタってますが、常に社会性を持ち合わせていて善良で。少なくとも、自分のことしか考えてないのに自分より他人を優先しています。見習わなければ...
臆病なことは罪なのでしょうか?劇中 彼が心配する不安な予測を嘲笑うかのように、常に予測不能な災難が降りかかります。不条理と言えばそれまでなのですが、よく考えたら世の中なんてそんなもん。罰でもなんでもないはずです
自分を責めることと 後悔と反省は別なもので。映画を通して主人公がとった行動の一つ一つは誰も責められないものでした
そう考えると。誰しも もし人生を何回やり直せたとしても同じ選択や同じ決断を何度もして、結局今と同じ自分になる。それが結局ベストだったと気がつくんじゃないかとこの映画を観て思いました
おばけやしき
他人の夢
眠っている他人の脳ミソをぐちゃぐちゃに搔きまわしながら潜り込んで、
その脳ミソが見ている夢の中を当て所なく彷徨っているような感覚でした。
出口がなく、他の入り口も見えず、
混沌の中を流され続ける。
それはラストシーンまで続きます。
その感覚は、遠い昔に桂枝雀主演の「ドグラ・マグラ」を観た時とそっくりです。
すっかり忘れていたのに、鑑賞後鮮明に思い出しました。
我が人生の中で、「ドグラ・マグラ」と「ボーはおそれている」は、
双頭のトンデモ映画になりました。
これが商業映画として成立しているのは本当に驚きです。
ホアキン・フェニックスの演技がなければ、星ゼロでした。
そう言えば、子供の頃にこんな夢を見ました。
学校から帰ったら家の中に誰もいなくて、
その後天井裏を覗いたら、
天井裏に母親の抜け殻がビッシリ隙間なく列んでいた。
びっくりして天井裏から降りたら、
母親が立って無表情でこちらを見ていた。。。
もしかしたら、今はこの映画を受け入れられなくても、
そのうち受け入れることになるのかもしれませんね。
これは傑作だった。
不思議な展開と取り返しのつかない結末
「ボーはおそれている」は悪夢のような映画だった
良い意味で悪夢みたいな映画だった。3時間の長丁場。
相当に人は選ぶ作品だと思うが、自分は良かった。
# 夢が現実か
世の中には、夢が現実か分からない映画というのは他にもある。
大抵の場合、まずは現実が舞台だと思わせておいて、途中から「これは夢ではないか?」と思わせる演出が段々と散りばめられ、後半に何が夢で現実かの区分けが明らかにされる。
この映画は逆だ。まず最初にまるで夢かのような出来事が繰り広げられ、それが「夢ではなく現実であること」のサインが突きつけられるのだ。
観客はずっと「何が夢で現実なのか」「どんな秘密が隠されているのか」「真実は何なのか」と揺り動かされることになる。
# カフカ
まるでカフカの小説の「変身」や「城」のように何をどこまで進んでも真実が分からず、永遠に彷徨い続ける。
# スラム街
ボーはスラム街に住んでいる。
その街でボーは走りながら自宅のドアを開く。何故ならそうしないと、わずかな瞬間に一緒に住居に侵入しようとするジャンキーがいるのだ。何故彼の自宅が狙われているのかは不明だ。
# スラム街の無関心
街の治安は荒れ果てており、人が人を襲って血まみれにしてきても誰も助けもしない。無関心が行き着くところまで行ってしまっている。
ボーが家を出た隙に、街の住人たちはボーの家にその大勢が押し寄せる。そしてボーの家をパーティー会場にしてボーは家から閉め出されるのだ。
こうやって文章に書くと浮世離れしている気がするが、映画を観ながらだと何が現実なのかが分からなくなる。
# 妄想と現実
「恐らく現実の一部分がボーの妄想なのではないか」と思わせはするものの、その区分けは巧妙に隠されていて分からない。
たとえば一夜明けて悪い夢から醒めるかと思いきや、そこにはパーティーの後の散らかされた部屋がそのまま残っており「それが現実だったこと」のサインが示されるのだ。
かと思えば風呂の天井には何故か太った弟が張り付いており、耐えきれずに落ちてきたりする。
精神疾病でせん妄という症状は本当に現実感があり、現実と幻覚の区別が付かないらしいが、この映画でもリアルとアンリアルを見分ける材料は巧妙に観客から隠されているのだ。
# セラピスト
ボーはスラム街に住んでいるにもかかわらず、セラピストにかかっている。どこからそのお金が出てくるのだろう。
海外映画ではセラピストを揶揄するような作品が多い。この映画でもいかにも信用ならなさそうなセラピストが出てきてボーにカウンセリングをする。
主に母と子の関係についてだ。
母の死母が死に、ボーは葬儀に参列しようと旅をすることになる。
# 様々な謎
なぜボーはスラム街に住んでいるのか?
なぜスラム街の住人たちはボーの家に押しかけようとするのか?
なぜボーは録画されていたのか?
なぜ録画内容に未来が映り込んでいたのか?
ボー保護した夫婦の目的は何なのか?
ボーの父親は誰だったのか?
# 真実は?
遂に真実が明かされるかと思いきや、明かされない。真実の次に妄想、夢、現実、そしてまた真実、いやこれは違う…。
マイナーな劇団の芸術みたいに自分は実際に見たことはないが「マイナーな劇団が素人には難解すぎる劇を演じる」というようなシーンがたまに他の映画に出てくる。
その難解さを素人臭いままにせずに、究極まで突き詰めるとこんな映画になるのだなと思った。
# ポップコーン男
今日の映画館では近くの男が規則正しくポップコーンを食べていた。
カップの中をゴソゴソ…ゴソゴソ…パクッ…クシャク…。これを映画の最初から最後まで繰り返すのだ。なんと律儀な。
ポップコーンは音が出にくいからこそ映画館のスナックとして選ばれていると思うのだが、食べ方によってはやはり音が出る。
長い
ホアキン・フェニックスが主演ということとこの作品のタイトルのこの二点だけに惹かれて映画館へ
どんな映画なのだろうとワクワクしながら観ておりました
えっ?? ??ん?…… ?んーん??……
何だこれ
見始めて1時間ほどでやっと何とか分かってきました
「常識に囚われていてはダメだ、映画の世界は何でもアリなのだから、裸のランチだってそうだったじゃないか」
などと説得力のない言い訳を自分に言いながら見続けていたら新たな問題が発生
な、長い、かなり長い
ボウの恐怖の妄想なのか何なのか分からないものをいつ終わるかも分からないまま見続けるこの刑はなんなのだ
これはかなり重い刑罰ではないたまろうか
しかし意外と見てしまう、訳も意味も分からないけど見てしまうのだ
この手の作品は知っていたらまず見な、絶対スルーなのだが見入ってしまってる
でももう二度とは見ないぞ、しかし今はとにかく気になる
ボウはどうなってしまうのだ
それにしても私はいったい何の映画を見ているのだろうか
やっぱり……
ボートでいくら逃げてもママの掌
毎日新聞の映画評が好意的でキネマ旬報の星取り評が良かったので騙されて観てしまった。いくら前作の「ミッドサマー」がヒットしたからといってこの手の監督にやりたい放題やらせてはいけないとつくづく思う。極度の被害妄想マザコン中年男は逃げても逃げてもお釈迦様(ママ)の掌のうちでありましたということなのだろうか3時間この出鱈目な世界に付き合っているのは映画的楽しさをとっくに通り越して辛いですもう勘弁してください(特に第3幕の森の中の演劇パート)。監督のアリ・アスターいわく「みんながどん底気分になればいい、居心地の悪い思いをしてほしいと思って作った」とは何たることだろう!オーマイガー!でもそんなこと言われれば恐いもの見たさの心理が働いてしまうのだからそれこそ人間の心理は恐ろしい。映画は確かにルールもお手本もなく自由っちゃ自由、しかしプロデューサーはもうちょっと興業のことを考えてもいいんではないか?「せめて2時間半にしろよ」とか。それにしてもエンディングで隠されていた「父親」の真実の姿があらわになるシーンの衝撃ったらありゃしない。エンドロール(そもそもロールしない!)に音楽が一切なくラストカットを延々引っ張って現場ノイズだけで押しまくった画期的幕切れは昨今のエンディング音楽偏重へのアンチテーゼでちょっと感心した。
最悪な妄想旅
母親が亡くなったことを知り、家に帰ろうとするが夢か現実かもわからない様々なトラブルに巻き込まれ、なかなか辿り着けない最悪の旅を描く。
極度な不安症で精神科にかかるボー(ホアキン・フェニックス)は最悪な日々を送っていたが、母親が住む実家に飛行機で帰ろうとするが、トラブルに巻き込まれ出発できないでいると、母親が急死したと聞かされ、慌てて帰ろうと家を飛び出す。
帰ろうにも帰れない奇妙奇天烈な旅路を4章仕立ての3時間の長尺で描く映画。
1章で登場する危険地域にある自宅の世界観があまりにも現実離れし作られた世界なのでこれは不安症の妄想世界で、現実と妄想を行き来する展開なのかと予測したが、
そのまま、夢かうつつかわからないまま物語はどんどん深みにはまっていくのだ。
2章、3章と世界観が一変するので飽きることはない。
ただ、何を言いたいのか考察し始めると難解すぎて、3時間は疲れてしまうだろう。
ここは考えるのを放棄し、イマジネーションの炸裂する映像世界をただ堪能するのが正解かもしれない。
とんでもない、最悪な旅を体現するホアキン・フェニックスの演技がなければこの映画は成立しなかったのではないか。
母親と息子の関係、血のつながり、献身的に育てた事の見返りは求められるのかとか、家族のつながりがテーマなのかとも思う。
ハマらなかった
新たなバディの誕生か。
弱さは罪か?正義なのか?
エディプスコンプレックス/去勢
寝不足だったのもあってか、「これはリアルか?それとも虚構か?」と意識を朦朧とさせながら鑑賞した。
なるほど『ボーは恐れている』では、何気ない日常のなかで私たちが想像しうる最悪の事態の結果が実際に起こる。ボーの不安障害からくる空想がすべて現実のものとしてボーに恐怖を与えるという意味で、この邦題なのか。
ボーの母親は、彼の祖母から随分酷い扱いを受けたと語っていたが、やはり生育歴は認知に大きく影響を与えるようで、ボーの母親の母性はかなり歪んでいる。ボーが幼い頃に母親の思い通りに行動しなかったのは、恐らく発達の遅れのせいだろう。ボーは、悪いやつではないと思うので、ただただ不憫におもう。
最初のカットが母親のお腹の中から始まるのは、ボーと母親がいかにエディプス的繋がり、同一状態にあるかを端的に提示するためだろうか。そして、ボーの分身と共に、父親が天井裏に閉じ込められてしまうのは、本来克服しなくてはならない父親からの逃避を意味するのかもしれない。天井裏に男性器のような形をしたモンスターがいたのは、はるか昔に閉じ込めた父親の象徴が永年の時を経て醜く肥大化した超自我?を意味するのかも?
さすがに無理がありますかね^^;
トンデモ級の里帰り
「ヘレディタリー継承」ではチャーリーの顔力に圧倒され、「ミッドサマー」では身勝手なカルト村に拒否反応が出て本作も観る前から身構えてしまいました。
が、所々笑える場面もあり(バスタブでボウとおじさんが回転していたのは最高でした笑)、作品を楽しむというより、アリ・アスターの世界を楽しんだ感じでした。
原案、脚本もアリ・アスターがやっているなんて
脳内どうなっているんでしょうかね…笑
劇中で流れたヴァネッサ・カールトンの「Thousand miles」は実家までの道のりを語っているようで笑えたし、ベッドシーンのマライア・キャリーも作風にはマッチしてなくて逆にそこが個人的には良かったですね。
序盤で怒った母親に手を引かれて連れていかれる男の子がいましたが、遊んでいた模型のボートが横転していてラストシーンと何だかシンクロしました。(真意は分かりませんが…)
なんだかんだで次回作も観てしまうと思います。
全278件中、81~100件目を表示