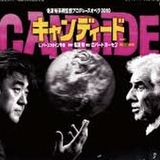落下の解剖学のレビュー・感想・評価
全157件中、61~80件目を表示
荒川良々みたいな検事
いつもの映画館②で
今月で閉館と 寂しい
この間はここでコットを観て落涙寸前だったんだな
今日は陽気につられて電車で来て昼にビールでも飲るかと
期待に違わぬ濃密で重層的な満足映画だった
テイストは怪物に近い気がするが
羅生門的な手法ではなく単一の視点で物語が進む
しかし観終わった後の気持ちは近い
あぁいろんな人のレビューを読みたい
20年くらい前のオラだったら
ん 結局どっちなのよ 気持ち悪いなぁ
とか もっと単純に意味を解せずハッピーエンドでよかった
なんて思っていたかもしれない
年間100本以上の鑑賞と55年の人生経験によって
こういう作品がいいと思える境地に達したことが嬉しい
あとからいろいろ思い出しそうだ いい映画の共通項
【本筋と関係ない話】
・荒川良々みたいな検事
・元ジャニーズのアイドル顔の弁護士
・フランスでは検事がサンタみたいな服とか
弁護士も奇妙な服を着ているのか 日本は取り入れなくてよかった
裁判員は取り入れたな
・イギリスは議会でカツラみたいのを被るんだっけか
もの凄い言葉の応酬に圧倒
観終わったて数時間。
まだ「落下の解剖学」というタイトルと観てきた話とを
整理している最中。
裁判劇ゆえにもの凄い言葉が出てくる。もの凄い量の言葉!
思考の切り替えとか、物事の見方、見る方向で全く違う
見解になるし、全部納得できそうだけど、全て受け入れられないし、結局は
誰も見てないから本当のことは誰も分からない
に着地するんだけど。本当のことじゃなくて、本当のこと「っぽい」のはどれか?なんだよなー。
昔宮部みゆきさんの「誰か」に書いてあった
“人は本当はどうだったか?よりどう見えたのか?に心を寄せてしまう気まぐれなもの”という言葉を思い出した。
そして今思うのはやはり子供は偉大だな、と。
法廷で明らかにされる同業夫婦の対立と内心
う〜む、これがパルムドールですかぁ、、
その上、アカデミー脚本賞まで、、
ちょっと、レビューサイトの平均スコア含めて、評価高すぎやしませんか?
いや、駄作とか、失敗作とかまでは思わないです。
ですが、いちばんのテーマは、法廷シーンの後半になって、夫婦喧嘩の録音と回想シーンによって明らかにされる、作家同士のカップルの複雑な心理的対立ですよね。
日本で夫婦ともに作家ってぇと、文化庁長官もつとめた三浦朱門(1926-2017)と曽野綾子(1931- )が一番有名ですかねぇ、少なくとも片方が存命の方だと。
学者、研究者だと多いですけどね、夫婦で教授とか。でも、その場合、微妙に専門分野を変えたりして、直接ぶつかり合わないように配慮(?)している場合がほとんどでさぁね。
大変ですよ、日常起居をともにするパートナーが同業、それもクリエイター稼業の場合。
書けたら書けたで、お互い能力ぐるみで比較されるライバルになってしまうのだし、いざ書けなくなったら(それが本作の不幸の原因)本業に関するジェラシーや焦燥感や苛立ちは全部相方に向かってしまうんですからね。
まぁ喧嘩の一部始終を聴いてて、観てて、明らかに妻のサンドラ(ザンドラ・ヒュラー)の言ってることの方がまともで、夫サミュエル(役名もキャストも公式に表示がないってどうよ?)の方は夏休みの自由研究の課題が休み明けになっても決まらない小学生が、必死に駄々をこねてる感じの混乱ぶり。
どう見ても、妻の方に正義がありましたよね。
視覚障がいのある息子ダニエル(ミロ・マジャド・グラネール)が、トラウマで爆発するとか、法廷で思いもよらぬ爆弾発言でもするのかと思いきや、上記の判断に基づく、まぁよく言って最も冷静な一証言者ってだけで、それ以上の役割は果たしていなかったですよね。
法廷で、サンドラが勝訴したあと、なにかドンデン返しがあるのかと、冷や冷やしながら見守りましたが、結局何事もなく母子が抱き合って、車でどっかお出かけして終わりなんで拍子抜け。
法廷も、年長の女性裁判長はちょっと怖くて威厳があったけど、それにサンドラ側の弁護士ヴィンセント(スワン・アルロー)の被告女性への接近ぶりもどうかとは思うけど、アントワーヌ・レナルツ演ずる検察官、相手側の証言を主観だと糾弾するくせに、自分こそ主観による決めつけ丸出しで実証能力あかん感じでレベル低かったですしね。
これだけ双方の言い分聴いて、勝ち負け明々白々なんだから、これを羅生門スタイルとか言うのは、モノのたとえとして間違ってますしね。
要は、ダニエルくんの知性に、あなた負けちゃってますよ、ってジュスティーヌ・トリエ監督に言われちゃってるよ、っていう‥‥
*裁判で親の嫌なところを聴かされたダニエルくんの今後を心配するレビューがやたら多くて、あれれ、と首を捻りました。あれだけ冷静な証言ができた彼です。むしろこの裁判を経験することで成長した。そして父親よりも男性として尊敬できる大人になるに違いない、というのが監督の伝えたかったメッセージだったはずなので。
何だか、クライムミステリーなのか、わくわく法廷劇なのか(まぁ比重的にはこっちですが)、視角障がい者の少年がキーなのか、何やら不気味なワンちゃんスヌープ(メッシ)が鍵を握っているのか、etc.‥いささか焦点を絞りきれず、とっ散らかってしまっている印象を受けました。
それら引っくるめて、「作品世界の作り込みでして」ってんなら、是枝さんの『怪物』の方がよっぽど作り込んでるし、スマートだし、ロマンチックだし、エモいですからね。
ところどころ間延びしてたから、40分短くして2時間に納めても同じプロットで、充分できるでしょうに、って感じ。
久々に、無駄に長い映画だなって思いましたもん。
あと、時々カメラ移動とかズームとかが手ブレしたりピンぼけになったりとか、あれ最近流行りの何とかですか?
ウェルメイドを避けるつもりかも知れないけど、今やありきたりの手法で、かえって「またか」と思うだけでした。
まぁ、妻の側が女性と不倫していたとかのところは『TAR』を思わせなくもなかったけれど、ともに自らのキャリアで生きている男女の夫婦の話としてはレナード・バーンスタインと妻のフェリシアの関係を描いた『マエストロ』に案外近いと思いました。
『マエストロ』のレビューは、私パングロスのFilmarks初投稿(2023.12.24)。
再見もして、バイの夫との夫婦関係を詳しく分析もしましたので、ご関心の向きは是非ご覧くださいませ(一部省略版を映画.comにも2024.2.11投稿)。
おっと、自己宣伝で終わるのも何ですんで、もいっかい『TAR』との比較だけ片付けときましょうか。
『TAR』の場合、クラシック界に取材して、本当は、バイだけど家族愛も強くてオシドリ夫婦をまっとうした、アメリカ出身にして世界の指揮界のトップに初めて躍り出たレナード・バーンスタイン(LB)だとか、全米クラシック界の頂点たるメトロポリタン歌劇場音楽監督の座で長期政権を維持しながら任期満了直前に昔の少年加害(ジャニー喜多川と同じ。ちなみにLBにはそうした噂は聞かないので味噌とクソを一緒にしないように)を訴えられて業界から追放されたジェームズ・レヴァインとかをモデルに作劇しようと、はじめ考えたらしいんですね。
ところが、それだと、そもそもクラシック界に少ない女性を排除する結果になって女性蔑視の批判を浴びるだろうから、指揮者をレズビアンの女性に替えて、ケイト・ブランシェットに演じさせたところ、キャンセル・カルチャーを見事に風刺した上に、ある種のフェミニズム批判にもなっているとか、大方の好評を博したわけですね。
要は、トッド・フィールド監督は、頭いいってか、まぁズルいやっちゃ、なんですが。
それに対して、本作のジュスティーヌ・トリエ監督、自身が女性じゃないですか。
だから、夫婦のうち、女性作家の方が仕事ができて、夫婦喧嘩しても言うことがいちいち正しくて、おまけに裁判でも勝ってしまうって、どうよ、男性蔑視なんちゃうのん、って批判は当然あり得ると思いますね。
だって、夫の方は、仕事が手につかなくて、うつ病になって医者にはかかるわ、夫婦喧嘩すれば正論でやり込められるわ、自殺して死んだら死んだで、法廷で恥ずかしい録音流されて、裁判でも女房には勝ち誇られるわ、‥これじゃ文字通り、踏んだり蹴ったりですよね。
なんか、「弱者男性は死んで良し」みたいな感じで。
まぁ、これは、小ずるいフィールド監督に対して、トリエ監督が、
「頑張ろうとする女に対して、男ってやつは、これだけ無理解で理不尽なんですぅ。
みんなぁ、わかってぇ!」
って、悪気なく、純粋に思っているだけなんだと思いますけれど。
だけど、自殺しても、妻からは一向に謝ってもらえない、ってのも、死んでも死に切れない、ってやつかも知れませんな。
本作、ありていに言えば、女性側の言い分が認められれば良し、弱者男性のことは(死んだって)知ったこっちゃない、ってゆう、割と原始的なフェミニズムに立脚した作品だと思いますね。
ちょっと乱暴に要約すると、自殺した死人(それも夫)に鞭打ってみましたって話だし、ね。
そうゆうとこ含めて、よくカンヌが賞を与えたな、という感想に戻ります。
《参考》
【前編】宇多丸『落下の解剖学』を語る!【映画評書き起こし 2024.3.7放送】
アフター6ジャンクション2 2024.3.6
※後編へのリンク、文中にあり
町山智浩の映画特電『落下の解剖学』を解剖する。ミステリと言うなかれ。
2024.3.2 ※YouTubeで検索してください
※以上、Filmarks 投稿を一部修正して投稿
父も母も大好きなダニエル
心安らぐ大自然の中での暮らしなのにざわつく。
犬の演技は素晴らしい。ここまでできるのか。
父は自殺なのか、事故なのか、母が殺したのか。
あまりにも辛い選択をしなければなかったダニエル。
母が殺したと思っているからこそあの選択だったのだろう。
これからのダニエルの人生について考えると辛すぎる。
20世紀は
米国が世界の中心だった
その米国の背後には英国がいた。
その彼らが世界に提唱し普及システムは
ビジネスとコンプライアンスの徹底だったかと思う。
本作はその中でも特に
コンプライアンスが幅を効かせる法廷での裁判を軸に
描かれている。
しかも扱う判例は人の死
そこにはその死を取り巻く様々要素、人心が紛れ込む
一筋縄ではない
絡みに絡みまくった要素
それを不確かで時には創作の可能性もある要素で
断じて行こうとする
そこに真実はあるのか?
その時限りの陪審員やその時代の価値観が
正確に裁くなんてできようがない。
そう言いたげな内容だな。と僕は思った。
が、最後のオチは、これからの時代のシステムの変化を
示唆しているようで面白くもあり恐ろしくもあり◎
pimpな気分だわw
家族・夫婦の人間と愛の解剖学
言葉もカルチャーも生き方(自己主張強めな妻と夢はありつつも実現できない夫)も違う2人が結婚して、事故により弱視になった子供がいる夫婦。
自宅で妻が昼寝中に起きた夫の転落死をきっかけに、裁判で第三者に詳らかにされていく夫婦の人間性。
妻のバイセクシャルな性癖や不倫、夫の鬱病や自殺未遂など、子供の教育方針の違いや押し付け合いなど、解剖すればするほど、子供からしたらショッキングな事実が見えてくる。
解剖学って、答えを探す学問じゃなくて事実を明らかにする学問なんだよね。
だから、この作品も答えはないし、あったとしてもそれぞれの答え≠正解がある。
ただ、誰も見ていないものは、なにかの事実を軸として「決定」するしかないのだ。
とんでもなく示唆に富んだ作品だなー。生きる指標はちゃんとしてるかね?と問われる感じ。
夫の窓からの物理的な落下、かと思ったら、妻の小説家として失落なども含んでの落下、なのね。
最後、裁判を1日延期させて子供の報告を受けて、結局妻は無罪になるけど、どう考えてもあの爆音の中昼寝はできないでしょ?!いやいや、妻よ…!って思ったけど、パンフレットにヒントが書いてあった。
エンディングシーンの犬が寄り添ってきたこと、元ネタのタイトルから考察すると、あれ?やっぱりやったんじゃね??と。
地下鉄で泣くより、車で泣く方が良い
こないだ鑑賞してきました🎬
ここ数年で客入りが一番で、8割方埋まってましたね🙂
私は前から2番目しか取れなかったですが😅
雪山の山荘で、そこに住む家族の1人であるサミュエルが謎の転落死を遂げます。
ミロ・マシャド・グラネール演じる視覚障害の息子ダニエルが第1発見者となり、次第に被害者の妻であり作家でもあるサンドラ・ヒュラー演じるサンドラに殺人の疑惑が…。
アカデミー脚本賞を受賞しただけあって、ストーリーはよく練られています。
ダニエルが終盤にお守役のマルジュに感情をあらわにするシーンや、死の前日に交わされたサンドラとサミュエルの激しい口論、そして無罪となったサンドラが帰ってきた時のダニエルとのやり取り…どれも良い演技でした。
犬のスヌープもかなりの好演🐶
結局事故の真相は語られませんが、状況証拠を考えると…。
あえて真実を伏せる、というのも時にはありですね。
色んな考察が生まれるでしょう。
考えさせられる映画でした。
名犬スヌープ
結局、夫の死の理由はわからない。彼は自殺だった、事故だった、殺された、どれでもありえる。サンドラは罪に問われなかったが、夫を追い詰めたのは確かである。でも、彼女も自分を犠牲にして、異国での不便な暮らしに耐えていた。どちらが一方的に悪いわけではない。死ぬことで夫婦関係は終息したが、もし夫が生きていたとしても、この夫婦は近いうちに破綻していたに違いない。
裁判は精神的にも肉体的にもキツい。こどもに知らせたくないこと、他人に隠しておきたいことも、明るみに出されてしまう。息子のダニエルは、初めは証言がグラつくが、やはり母を庇っていたのかな。ということは、父の死の原因を知っていた可能性がある。母と息子の間には、2人にしか通じない何かがあった。そして、ダニエルは裁判を終わらせる重要な証言をする。
自分が裁く立場だったら、どう結論つけるだろうか。サンドラがいくら耳栓したとしても、あの大音量で寝るのも信じがたい。ボリューム下げろって言いに行くと思うし、そこでまたケンカになるかも。つかみ合ってアザができた? サンドラが殴ろうとして、よけた夫がバランス崩して頭を打った? でも、やはり殺したとは思えないかなー。そこまで憎んでいないだろうし、彼を殺してサンドラに利益があるわけではないし、事故が妥当な気がする。
俳優みんな演技が上手かったが、一番は犬だね。スヌープすごい! 前足そろえて伏せした姿、超かわいかった! アカデミー受賞式にも呼ばれてたって。粋な計らいですこと。
追記(2024.3.27)
夫と弁護士の名前を勘違いしてた。
最後まで夫の名前がなかったことに気が付いた。
なんか、かわいそうだな、夫。
ヒューマンドラマ
ミステリーかな?と思ったら、ヒューマンドラマだった。
確かな証拠はなく、憶測が多い。
夫については誰かを介して知る。録音くらい、本人を直接感じるのは。
人の印象は、人によって様々なので、なんとも釈然としない。
妻も妻で、自分のことはなかなか語らないのでもやもやする。
夫婦喧嘩については、どうしても夫よりになったなぁ…。
「こちらはこれだけやって(あげて)るのに」と相手を比べた時点で、夫婦仲が良かったとは思えない。
その後の乱暴については、自分からグラスを叩き割って暴れておきながら、「乱暴しないで!」はないだろう…と思った。あと夫の呻き声と、柔らかいものに暴行するような音がしたけど、あれは倒れた夫の腹辺りを妻が蹴ってるのか…?と思ってた。
妻の発言も二転三転するから、心象が悪いのは当然。
ダニエルの発言も、あやふやなので、打算で発言した…?と思ってしまった。あれもダニエル視点の父の発言だしなぁ。
凶器はありません、殺意も憶測です。と言われたらそら推定無罪よなぁ。疑わしきは罰せず、ですもんね。
結局ハッキリしないので、モヤモヤは残った。
見ることの出来ない真相
ある雪の積もる人里離れた山荘で、作家のサミュエルが死体となって発見される。
第一発見者は目の見えない彼の息子ダニエル。
これは事故なのか、自殺なのか、それとも殺人なのか。
やがて状況証拠から彼の妻で同じ作家でもあるサンドラが容疑者として起訴される。
ほとんどのシーンが裁判での供述なのだが、この映画は真相を突き止めるためのミステリー要素に重きを置いているわけではない。
サンドラは夫を殺していないと主張するが、それを証明するための物的証拠がない。
逆を言えば彼女が殺したという決定的証拠もないのだが。
法廷で彼女は徹底的に攻撃されるが、裁判の印象を良くするために彼女は言いたいことを抑制されてしまう。
真実はどこにあるのか、あくまでもこの映画では登場人物の主観しか語られないために最後まで曖昧なままだ。
中盤までは観ているこちら側もサンドラに感情移入させられるが、サミュエルが録音していた彼女との喧嘩の内容が明らかになってから見方が一変する。
自分の時間が奪われたと主張するサミュエル。
一方、サンドラは自分は何も強制していない、小説を書けないのは自分のせいだとやり返す。
お互いに自分の正義を譲らないために、話し合いは激しい口論へと発展し、やがて泥沼状態になってしまう。
正直、このやり取りを聴くとサンドラの無慈悲さを思い知らされる。
ただ、だからといって彼女がサミュエルを殺した証拠にはならない。
物語はダニエルが証言台に上がるところでクライマックスを迎える。
彼は目が見えないため、実際に何が起こったのかは分からない。
彼は過去にサミュエルが自殺未遂したことにも気づいていなかった。
彼は母親の無実を主張するが、それも彼の主観でしかない。
結局、大きなカタルシスを得ることもなく物語は幕を閉じる。
サンドラ自身、もっと裁判が終われば何か見返りがあると思っていたと語るように、何もなく映画は終わる。
最後に彼女はダニエルと共にすべてを見てきた犬のスヌープを抱き寄せる。
言葉を喋れないことから、スヌープもまたすべてを見ていたとしても真相を明らかにすることは出来ない。
重厚な作品ではあるものの、展開が一辺倒なので時間が長く感じられてしまった。
無意味だった仮説s。
作家夫妻と視覚障害のある一人息子とワンコの家に起こる話。
雪の積もる山奥に住むその一家、犬の散歩から自宅に戻る息子ダニエル、そこで目にしたのは自宅前で血を流し倒れる父親だった…、自宅三階からの転落死と思われたが、転落死とは別の外傷が見つかり…。
スルーするつもりでしたが話題性と予告の「背筋が凍りつく、息もできない、最高傑作」という文字を目にし鑑賞。
結果から書いてしまうと私には合わない作品だった。長尺約150分使って何かうやむやな感じでスッキリしない、本作が100分位の作品なら納得出来るかもだけど。
死因にあたって数人の人間から色々な仮説が出るけど、その会話シーンも正直引き込まれず、旦那が録音してた音声とその時の映像シーンには、「おっ、ここからか!」何て思ったけど…。
この本作のテーマ、メッセージって予告にもあったけど「仲睦まじい夫婦でも…、調べれば色々ありますよ」的な?長尺使ってこのスッキリしないのは嫌だな!(笑)
でっ、無罪だった奥さんが実は犯人でOK?
あの録音の音からすると。
あと、ダニエル役は上白石萌歌!?
世の中に片付くものなど
それは想像です。主観です。作中で繰り返される言葉。これがこの作品の要なのだと思います。
探偵(推理)小説とは、探偵役が事件を解決して終わるのではなく、バラバラに存在する「証拠」(物的証拠に限らずいろんな意味で)を繋ぎ合わせて一つのストーリーに仕立てて語り切った時に終わるという言葉があります。これには、すべての「解決」は偽りを含んでいるという含意があります。
この映画は事件を一つのストーリーに仕立てて「解決」することなどできないさまを描いてます。その意味でたしかに「羅生門」的とは思いますが、もう少し複雑です。
証言の一人称性(非客観性)だけでなく、テレビの報道(真実より面白い方がいい)、創作物と現実の境目(検察官が被害者の小説を事実を書いていると強弁して法廷で読みあげるという滑稽ともいえる暴挙)、などの複数の異なる層の問題が重ねられ、我々が「真実」だとうっかり思ってしまったり、思いたがったりしてしまうさまが取り出されて晒されていきます。
録音されていた夫婦の諍いも、警察は妻が夫を殺害した証拠として出してきますが、聞きようによってはむしろ夫がヤバい奴だと思う人もいるでしょう。
しかもここには、妻が仕事で夫が家事という、古い家父長主義的な夫婦が逆転した関係が見えてきて、また別のレイヤーも重なっています。
そもそも、フランスにおいて解剖学は、いわゆる文学の自然主義の方法論でもありました。(日本の自然主義はそれを受け継がなかった)
物語でありながら、現実の姿が浮かび上がることを望む。その時、きれいに片付いた結末などあり得なくなる。
漱石も「世の中に片付くなんてものは殆どありゃしない。」と書いてますが、それを思い出しました。
しかしラストの犬の様子は……ここからもまた片付かない想像が始まります。
推定無罪
「落下」と「解剖学」とをくっつけるとは、うまい名付けと思ったよ。
これだけで見る気満々。アカデミーの候補にもなってるらしかったけど、当地では発表後の公開になってしまった。
お客さんは日曜にもかかわらず白い頭のベテラン勢が多く、地に足のついたサスペンスを楽しんでいた。
話は、家の3階から落ちて死んだ夫を巡る家族の話。だから密室とかトリックとか犯人とかが話の中心ではなく、なぜそうなったのかを暴く話になる。したがって法廷ミステリー。
結局、夫を殺したのか、夫は自殺したのかが焦点となり⋯妻は無罪となる。
釈然としない。
こんな話を前にも見たなあと思ったら、「ザリガニの鳴くところ」がこんな感じだった。
主人公は殺人を犯したのかどうか曖昧なまま幕を閉じる。
今作の名演は禿げの検察官だ。舌鋒鋭く家族の闇を暴く。私たちは妻の非を感じ旦那可哀想となっちゃうね。
しかも、妻は弁護士のイケメンといい仲になるようだし、過去に女性相手の不倫もしている。あかんやろ。
法廷劇が終わり無罪を勝ち取ったけど、どういう訳か作画に晴れやかさはない。
妻はスタッフと乾杯しあって遅めの帰宅、子供は寝てしまうけど、ベットに連れて行ってからのーひとことに愕然
⋯とはならなかった(笑)ベッドに入って犬が来て添い寝して襲撃おっと終劇。
結局なんなん?ハリウッド映画なら「何も起きないなら切る」でしょ。
そこそこ長いんだから。
英語、フランス語、ドイツ語の入り交じるところがセンスのいい面白い脚本だが私には冗長と感じたね。
何度か意識を失いそうになった。
すごい映画
犯罪モノでアクションも無さそうだしヨーロッパ映画だし難解で退屈しちゃうかもな…と思ってたら全然そんなことなかった!
3時間があっという間に過ぎたと思うくらい、飽きさせない作品だった。美しい景色の中、事件が起こる家は平穏に見えるけど、実は冒頭からじわじわと怪しさが伝わってくる。日常とか「普通」に見えることが、殺意にまでおよぶ凶悪さを内包しているとしたら…死んでかわいそうなのは夫だけど、夫婦関係に困惑させられて傷つく子どももかわいそうだし、犬なんかもっとかわいそう。殺人の嫌疑をかけられた妻もかわいそう?
真実よりも、「可能性」があること自体が怖い。想像できることは何でも実現できる、という考え方があるけれど、誰かの不幸を想像したことのない人なんているんだろうか。誰もが不規則発言しまくりの裁判で、回想なのか仮想(嘘か仮説)なのかわからないフラッシュバックのようなシーンが混ざり合うところは圧巻だった。
なお、残念なことに、映画館に赤ちゃんを連れてきた人がいたようで、上映中に何回も赤ちゃんの声が劇場に響いていた。赤ちゃんを3時間も暗闇に閉じ込める人の気がしれない。
やや消化不良感?
ミステリーではなく
家族の中の問題や、人間関係の問題が明らかにされていく。
外からみた家族と
実際の内情とは異なっていることもある。
自分が絶対的に正しいと信じ続けることの愚かさと怖さを感じた。
この事件の真相は、おそらく…妻が夫を手にかけた
ということなんだと思うが、
その事実を違うものにする
様々な演出、息子の感情
真実だけが真実ではないということか、と。
おそらくラストはこれで正解なんだと思うが
ミステリーやいわゆるサスペンスという感覚で見ると
消化不良を起こすかもしれない。
それにしても、この夫婦はお互いにお互いのことを想うということをもう少しできたらよかったのに、と思ってしまった。
誰かと生きていきたいのなら
独りよがりでは難しいということか。
まあ、つまりワンちゃんがお上手
これから見る人のためにお伝えすると犯人や事実はわかりません。
てっきり公判を進める中で事実に基づいたり証言の矛盾で犯人があぶり出されるということはありません。
それを期待すると私みたいに肩透かしを食います。
それを踏まえて
雪山で作家でというと思わずシャイニングみたいなイメージですがスプラッタラスなものもサイコなものもなく静かにというかやかましい中で夫が死にます。
それを巡っての自殺か他殺か事故かという話でして事実が曖昧な中での話は思わずダウンタウンの松ちゃんのアレによく似ていて劇中の弁護士の言う「事実がどうかより周りがどう思うか」ということで外野が空中戦しているのがオーバーラップしました。
そして人は知りたい(あってほしい)事実を事実と考えることなのかなと。
加えてフランスに住む英語をベースにフランス語を話すドイツ人という奥さん。
ネイティブから2回フィルターをかけるのだから語るに落ちるは難しそうという印象。
さらにバイセクシャルって役が大変。
それととにかくスヌープちゃん芸達者
緊張感が欲しい映画
映画『落下の解剖学』事故か殺人か自殺か、う〜んどっちでもいいかななんて無責任な声が聞こえてきそうな映画。まあ世の中で最も多い殺人の例が、夫婦間という統計もありますので。ただ、鑑賞中も感情移入できないのは、私的世界に終止するからでしょうか。
物的証拠のない犯罪の立証
倦怠期の夫婦。
作家の夫婦。
ただし、夫は泣かず飛ばず。
方や妻は、売れっ子の流行作家。
山小屋で、転落死した夫をめぐり他殺か自殺か事故かを巡っての裁判。
遺書などは無し。
夫は、売れっ子の妻に対して嫉妬心があり。
事故をきっかけに盲目となった一人息子の自己の責任を妻に。
なかなか難しい夫婦関係のようで。
さらに、彼女のセクシャリティーの問題も絡み。
夫が邪魔になったのかとも。
疑えば、きりがない。
そんな展開。
物的証拠のない事件の難しさ。
裁判の場面が、1/3を占めるだろうか。
退屈になりがちな場面ですが。
まあ、なんとなく、引き込まれるまでは行かないですが、鑑賞できます。
しかし、状況証拠だけですから。
立証は、難しいですよね。
検察官の作るストーリーも、何度も聞かされると真実かなと。
このあたりが、冤罪を生む原点かな。
争う方も、そうだったかななんて気になってしまうでしょうから。
とくに、拘置所などの閉鎖的空間で、味方もいない場面だと。
ただ、今回は裁判ですから、弁護士はいます。
有罪無罪どちらでもいいやと無責任な気持ちに。
結局、ことの発端は、夫婦間の問題ですから。
別に興味ないし。
なんて言ったら、見も蓋もないのですが。
それに、転落する山小屋の3階という中途半端な高さ。
結局1階の東屋に頭部をぶつけたのが致命傷。
だけど、自殺なら他の方法を選ぶのでは。
わざわざ、一階の屋根の部分めがけて飛び降りたんでしょうか。
そのあたりは、映画では、話題にもならなかったな。
裁判の後半では、どうも父はうつ状態にあったのではと。
そして、息子との最後の会話、自殺をほのめかす。
この証言が、決定打となり無罪となるのですが。
お話としてみると、あまり興味が湧いてくる展開ではなかったですね。
しつこいようですが、夫婦間の揉め事に興味はわきません。
それに、息子との最後の会話が無罪の決定打というのも。
事故の可能性も否定できないですからね。
状況証拠だけですからね。
このあたりの判断は、見た方の考えにおまかせ。
登場人物全員嘘つき
夫の転落死をきっかけに、殺人事件の容疑者となる妻だが、だいたい喋ってることはウソ。母親をかばう超弱視の息子も最初のウソを契機に泥沼に。
そんな母親を弁護する弁護士も最初はなんか好意を寄せていたのだが最終的にこの女はやばいと踏みとどまる。それもそのはず、有罪なら殺人犯、無罪でも自殺に追い込んだのはこの妻。夫婦喧嘩のやり取りは社会的成功をおさめている妻が一方的。家事も育児も夫に丸投げ。夫が負担を公平にしたいと言っても、私がいつやれと言った?なんて開き直る始末。不倫もやりたい放題。この女とは関わってはいけない、なんて雰囲気が漂う。夫の人生、1ミリも考えていない。
テーマ性はあるようであまり感じない。ポリコレ全方位をカバーして、珍しくウーマン・リブで押しつぶされる男性の叫び超えの代弁を夫にさせている。あのシーン長かったからね。
サスペンスではなく家庭劇。表面上うまく取り繕っていたけど、中味はグチャグチャ。グチャグチャが段階的に表に出てくるのでどんどんカオスに。そこに客観的事実なんて存在しない。
ああそうか、これは夫婦喧嘩を法定に持ち込んだらどうなるかっていう思考実験なんだ。最後の無罪判決も無罪というわけではなく、しらんがな、勝手にやっといてっていう意味かもしれない。夫婦喧嘩は犬も食わないって言うしな。ただそこにはもう夫は居ない。
事実と虚構の狭間を落下する「真実」
何が起きたかを究明するためには客観的な事実が必要であり、そのために関係者による証言の積み重ねがある。しかし、各々が語る「真実」には主観が含まれる。主観を排することによって削り取られてしまう、感情や想像等のディテールは、この事件の「真実究明」には必要不可欠に思えるが、それが主観的である以上他者には届きにくい。詰まるところ、「真実」なるものは存在せず、ことの全てを記録していた媒体がなければ事実の積み重ねにも限界が生じる。だからこそダニエルが言うように、与えられた状況から考えるしか選択肢はない。
サンドラの小説を検察が追い立てるシーンが面白い。著作には彼女の実体験が含まれているようだが、小説である以上それはあくまでもフィクションである。実体験をもとにしている以上、「彼女自身」が作品にはある程度含まれているが、アイデアによって虚構が多分に含まれたものでもある。小説は主観によって解釈されるものであるから、作者の全てがそこから分かるようでいて、実はそれが全くの嘘である可能性が潜在的に存在する。人をジャッジする材料としては非常に脆い。
夫婦の口論のシーンで、お互いのメッキがぼろぼろ剥がれていく様が目も当てられない。サンドラのほうが容赦なく相手を責め立てているようには見えたが。
ダニエルはかなり追い詰められていた(ように見える)ので、自殺だとしても彼女の日頃の言動は死因の一要素だとは言える。ただ、あくまでもそれは間接的な原因なので「殺した」とは言えない。主観と客観、事実と虚構の間に落下してしまったダニエルの真実は、死んでしまった彼によってでしか真に語られることはないのだろう。
落ちなし
予告編ではあまり食指が動かなかったのだが、法廷物という噂を聞いて、見たくなった次第。
ふたを開けてみたら結構ガチガチの裁判劇で、それはよしとするのだが、全体に殺伐としている。法廷シーンもさることながら、回想シーンの夫婦喧嘩などいたたまれない。
法廷ミステリーとあらば終盤快刀乱麻を断つ“finishing stroke”を期待してしまうが、何だか茫洋として終わってしまう。クリス・ペプラー似の弁護士もさして活躍するわけでもないし。ミステリーにおいて、盲目の登場人物は (「Yの悲劇」のように)通例そのことが事件の解明に重要な要素となるものだが、本作はさにあらず。
いくら検証のためとは言え、犬に薬物を過剰摂取させるのはアカンと思う。
全157件中、61~80件目を表示