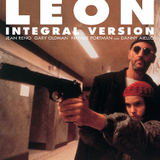落下の解剖学のレビュー・感想・評価
全486件中、221~240件目を表示
違和感のある会話・音楽・犬・少年・ロケーション、、、
すごく巧いプロットだなあと思った。全てに必然性がある。英語とフランス語のチャンポンも。
最後まで観る人にクリアな真実を明かさない。そういうのが許せない人には無理な映画かも。いやいやそもそも真実って何? 所詮観客が見せられているものは、恣意的に切り取られたカットの集積体なのだから。想像の余地は無限大だ。
ある意味密室のような山荘。事故か自殺か殺人か。事実があるとすれば、そのうちの一つが必ず事実なのかな。どうなんでしょう。組み合わせもあるのかな。現実の世界の捜査はどうなんでしょう。どれほど理に適っているのか、弁護士の腕次第なのか、、、。
それにしても、主演女優さん、のりうつったみたいに完璧になりきっていて、ドキュメンタリーかと錯覚する場面も。
おそらく白眉は「録音されていた夫婦喧嘩」。ともかく全編通じてセリフの応酬が多く、演劇の舞台みたいだった。
暴かれる人間関係
最初退屈だなと思っていたらサスペンスは本筋ではなく、明らかになる事実がなかなか気持ちの良いものではない。夫婦間の関係性、仕事間格差…しかもそれが夫を殺したのは妻なのかどうかを決めるために裁判で明らかになっていく、、プライベートがどんどんバラされていくのは溜まったもんじゃないよ。あの夫婦喧嘩はもう辛すぎるもう勘弁してぇと夫の立場になりながら観てしまった笑。
妻ザンドラのグレーな感じと見せる弱さがうまい。
それと癖強検事も印象深いがあのイケオジ弁護士は何者なんだい!2人の舌戦は目が離せない。
息子も知りたくない事実の数々にこの後本当に幸せなのかと不安だけど、葛藤しながらも自分で決めた証言はとっても立派だと思った!
あのイケオジとワンコの名演だけで観る価値はある笑
それと、心象次第で決まる裁判ほど後味の悪いものは無いんだなと実感。
登場人物全員嘘つき
夫の転落死をきっかけに、殺人事件の容疑者となる妻だが、だいたい喋ってることはウソ。母親をかばう超弱視の息子も最初のウソを契機に泥沼に。
そんな母親を弁護する弁護士も最初はなんか好意を寄せていたのだが最終的にこの女はやばいと踏みとどまる。それもそのはず、有罪なら殺人犯、無罪でも自殺に追い込んだのはこの妻。夫婦喧嘩のやり取りは社会的成功をおさめている妻が一方的。家事も育児も夫に丸投げ。夫が負担を公平にしたいと言っても、私がいつやれと言った?なんて開き直る始末。不倫もやりたい放題。この女とは関わってはいけない、なんて雰囲気が漂う。夫の人生、1ミリも考えていない。
テーマ性はあるようであまり感じない。ポリコレ全方位をカバーして、珍しくウーマン・リブで押しつぶされる男性の叫び超えの代弁を夫にさせている。あのシーン長かったからね。
サスペンスではなく家庭劇。表面上うまく取り繕っていたけど、中味はグチャグチャ。グチャグチャが段階的に表に出てくるのでどんどんカオスに。そこに客観的事実なんて存在しない。
ああそうか、これは夫婦喧嘩を法定に持ち込んだらどうなるかっていう思考実験なんだ。最後の無罪判決も無罪というわけではなく、しらんがな、勝手にやっといてっていう意味かもしれない。夫婦喧嘩は犬も食わないって言うしな。ただそこにはもう夫は居ない。
事実と虚構の狭間を落下する「真実」
何が起きたかを究明するためには客観的な事実が必要であり、そのために関係者による証言の積み重ねがある。しかし、各々が語る「真実」には主観が含まれる。主観を排することによって削り取られてしまう、感情や想像等のディテールは、この事件の「真実究明」には必要不可欠に思えるが、それが主観的である以上他者には届きにくい。詰まるところ、「真実」なるものは存在せず、ことの全てを記録していた媒体がなければ事実の積み重ねにも限界が生じる。だからこそダニエルが言うように、与えられた状況から考えるしか選択肢はない。
サンドラの小説を検察が追い立てるシーンが面白い。著作には彼女の実体験が含まれているようだが、小説である以上それはあくまでもフィクションである。実体験をもとにしている以上、「彼女自身」が作品にはある程度含まれているが、アイデアによって虚構が多分に含まれたものでもある。小説は主観によって解釈されるものであるから、作者の全てがそこから分かるようでいて、実はそれが全くの嘘である可能性が潜在的に存在する。人をジャッジする材料としては非常に脆い。
夫婦の口論のシーンで、お互いのメッキがぼろぼろ剥がれていく様が目も当てられない。サンドラのほうが容赦なく相手を責め立てているようには見えたが。
ダニエルはかなり追い詰められていた(ように見える)ので、自殺だとしても彼女の日頃の言動は死因の一要素だとは言える。ただ、あくまでもそれは間接的な原因なので「殺した」とは言えない。主観と客観、事実と虚構の間に落下してしまったダニエルの真実は、死んでしまった彼によってでしか真に語られることはないのだろう。
簡潔評価は、力作だが面白い作品ではない。
いかにもアカデミーが好みそうな作品で、一般の方には冗長かなと。自宅視聴なら、間違いなく再生速度アップ作品♪
まず短く良い点。
過剰演出や不思議描写は全くなく、事件を詳細に追って理屈の合う細かい点で裁判シーン等も描写している。 いい加減さが全くない力作♪
が、
私が映画評価の最重要視する点は、"時間を忘れさせてくれるパート"が、「その作品の何%をしめるか」という点。
ラストで大感動しても、前半ほとんどが睡魔に襲われた様な作品は、★評価が大きく下がる。
今作は作品時間中、見入ったのは約10%位しかない・・。
主には現場を図解解説しているシーンと、音声証拠シーン等くらい。
他の方もレビューしている、「スティーブン・キングは実際の殺人鬼か・」という台詞は唯一声を出して笑ったが♪
裁判シーンに見入ったと高評価してる方もいる様だが、私はかなり疑問も湧いた。 それは殺人容疑を掛けるには、最重要ポイントを2点も追求してないから。
1 動機
2 金銭損得
これらを争わず、状況証拠や二人の人間関係ばかりを追求し、説明しようとしている。
前日の喧嘩に争点がかなり向けられているが、夫婦喧嘩などあって当たり前。 私は子供時代に両親にもっと酷い夫婦喧嘩を何度も見せられた。 (まあ晩年にはしなくなったので、あの世ではお互いを気遣ってくれていると思うが♪)
特に口の悪い大阪のおばちゃんなら、夫に「あんたなんか死んだらええねん!」ぐらいの売り言葉を怒鳴る方も多々いるだろう。
が、実際に殺してしまう方はいない・・。
殺人までに至るには、耐えがたいDVを何度も受けたり、家計費を持ち出し自身の遊興費に使われ、借金まみれ等、もっと切実な動機があるはず。
次に今作は夫婦の金銭関係が一切描かれてない。(お互い作家だが、妻の方が多く作品を執筆しているというぐらい) すなわち、夫を殺した方が妻が経済的に得をするという説明もない。
本当の裁判なら、上記2点も争わなければおかしい。
さらに作品に感情移入出来る重要点、登場人物の魅力がほとんど描かれてない。 主演女優ノミネートになった、ザンドラ・ヒュラーは作品時間の8割ぐらい出ずっぱりで、そのシーン毎の感情はかなり巧く表現してるが、その人物の人となりが、ほとんど分からない・・。
これは彼女の演技でなく、脚本にそういう描写がないのだ。
(これは、「TAR/ター」や「哀れなるものたち」も酷似している。 逆に「ナイアド 〜その決意は海を越える〜」のアネット・ベニング やジョディ・フォスター は痛いぐらいに二人に性格が伝わっている)
と、マイナスに感じる点が多く、総じて自身平均点の★3.5の平凡評価に。
自分が配偶者殺しの容疑者になったら
落ちなし
予告編ではあまり食指が動かなかったのだが、法廷物という噂を聞いて、見たくなった次第。
ふたを開けてみたら結構ガチガチの裁判劇で、それはよしとするのだが、全体に殺伐としている。法廷シーンもさることながら、回想シーンの夫婦喧嘩などいたたまれない。
法廷ミステリーとあらば終盤快刀乱麻を断つ“finishing stroke”を期待してしまうが、何だか茫洋として終わってしまう。クリス・ペプラー似の弁護士もさして活躍するわけでもないし。ミステリーにおいて、盲目の登場人物は (「Yの悲劇」のように)通例そのことが事件の解明に重要な要素となるものだが、本作はさにあらず。
いくら検証のためとは言え、犬に薬物を過剰摂取させるのはアカンと思う。
ハマらなかったなあ〜
隔壁
んー、いや、まぁ…奥深い脚本ではあったかな。
1番最初に出てきた感想は「CGが無さげな作品を久しぶりに見たけど、絵が凄い生々しくみえる」だった。
正直スッキリはしない。
犯人探しが主題ではないようで…一応の判決は出るものの真実は闇の中だ。
父親が転落死する。
その第一発見者が弱視の息子で、その家には母親しかいない。で、他殺か自殺かってのが裁判の論点になってく話なのだけど…どうにも面倒くさい。
どんな家庭にだって色々あるわけで…家族だからこそ共有しなきゃいけない問題はあって、それは家族だからこそ、夫婦だからこそ共有せねばならない問題でもあって、それが悉く暴かれていく。
弁護士と検察も白か黒しかなく、どちらも自分の正義に準じてはいるものの、屁理屈だったりこじ付けだったり、憶測や推測の嵐で、真実の押し売りはするものの、真実の解明には程遠いような空間だ。
実際の裁判もああいうものなのだろうか?
裁判長と陪審員に「あなたが正しい」とどんな手を使っても言わせたら勝ちみたいな。
…まぁ、そんなもんかもしれない。
夫婦間のアレコレや個人的なアレコレや、おおよそ公にしたくない事柄が、否応なしに暴露されていく。本人は勿論いたたまれなくもあるんだろうけど、1番災難なのは子供だ。
聞きたくも知りたくもないアレコレが、他人の口から無遠慮に吐き出され、その杭に貫かれていく。
救いようがない程に残酷な状況だ。
この裁判の縮図は、夫婦間にも適用されていて、録音データが再現されたシーンは見るに堪えない。
どこまで行っても平行線だ。
相手の意見なんて聞きやしない。
自分の主張と要望と、それが受理されない関係から悪態しか出て来ない。
皮肉も嫌味もお構いなしなのである。
と、外野から見てるとよく分かる。
まぁ、そのスパイラルに陥らない夫婦は皆無なんじゃないかと思われる。
改めて自分たちの愚かさをまざまざと見せつけられてるようで、「こりゃ犬も食わんわ」と思う。
それにつけても俳優陣は皆様、素晴らしく…この夫婦喧嘩のくだりなどは台本の存在を疑う程の熱演だ。
旦那はまぁ病んでもいて、その閉塞感とかうんざりする程だし、奥さんは自分に負い目があるから寄り添うように話もするのだけれど、この環状線の如く繰り返される不毛なやり取りに心底辟易してたりする。
上手かったわー。
とまぁ、法廷同様「私が正しい」と「あなたが間違ってる」が銃弾爆撃かのように降り注ぐ。
子供に。
もはや、サスペンスではなく人間ドラマである。しかもだいぶ痛烈な。ダニエルを見るたびに良心の呵責に苛まれ…いや、過去を猛烈に反省しようと思う。
で、まぁ、サスペンスを見にきたつもりだったので、こっからは考察だ。
自殺なのか他殺なのか。
正直分からないのだけれど、引っかかってる箇所はいくつかある。
ダニエルの事情聴取の和訳に「開いた窓の下」って発言がある。窓が開いてるかどうかの認識が出来るようで…もしそこで何か動くものを見たのなら、おのずと母親一択になる。
彼は見間違いだろうと思いたいだろうし、その時の視界に確信が持てないかもしれない。
判決の前に車内で「ごめんね」と泣きじゃくる母親とか、その夜に母親を抱き締めるカットとか。
「帰ってくるのが怖かった」と言われた時の母親の距離感とか…絶妙に引っかかる。
まぁ、他殺に一票かなぁ。
表題の「隔壁」は対人関係において、お互いを拒絶したり反発したりして、自分を守る為の壁が見えたからかなぁ。どうやら一回出来ちゃうと崩すのは相当難しく、ベルリンの壁同様、崩れる時は歴史的快挙とも表現される程のものであるらしい。
途中に挿入されるワイドショーのような番組でコメンテーターのコメントに絶句する。
「そっちの方が面白い」…随分と極端な台詞だなぁとは思うけど、昨今の報道における良識の無さは世界共通なのかと思え、輪をかけてうんざりした。
夫婦こそサスペンス
フランスの雪山で暮らす夫婦と視覚障害のある子供に犬。
ある日、夫のサミュエル(サミュエル・タイス)が転落死する事件が起こる。
自殺なのか、他殺なのか、事故なのか、その真相を探る物語。
アウトラインはサスペンスそのものだが、いかにもな怪しい登場人物もいないし、他殺だとした場合の証拠も何もない。
そんな中、状況証拠だけで妻のサンドラ(ザンドラ・ヒュラー)が殺人容疑で起訴されてしまう。
映画の中心は妻は夫を殺したのか、その謎を解明する法廷シーンだ。
当事者の夫婦以外の第三者は第一発見者でもある視覚障害のある息子のみ。(それと犬)
ただ、目が見えないので音だけでしか証言ができないところがポイントだ。
前半で夫婦の関係性は詳しく描かれないが、この法廷で夫婦の関係性があらわになっていく。
夫が息子を見ていた時に起きた事故で視覚障害になってしまった事の負い目。
夫婦共に作家であるが、妻はベストセラー作家で夫は落ち目の作家。
家事分担の話し。
どれもこれも夫婦あるあるで、身につまされる話だ。
そう、事件など起こらなくとも、育ってきた環境も違う他人の2人が同じ屋根の下で長い人生を共に暮らす、夫婦こそサスペンスそのものでないのか。
そんな関係性を炙り出すこの映画はサスペンスでも法廷劇でもない人間ドラマだ。
ドイツ人でフランス人の夫と結婚し二人の会話は英語で、法廷ではフランス語を喋らないといけないという複雑な役を演じるザンドラ・ヒュラーの演技がすばらしい。
また、犬のスヌープ役のボーダーコリーの「メッシ」の名演も見もの。
先日のアカデミー賞授賞式にも出演し、話題になっていた名犬。
最後にこの映画を夫婦で観ることはお勧めしない。
解剖
真実はいつも一つ!という言葉があるけれど、大人になって思うのは真実って一つかもしれないけれど認識の仕方は複雑だという事。
たった一つの真実も見る人、見る角度、時代、立場、法律、タイミング、さまざまな要素によって意味が変わってくることがある。
今回の作品で個人的に素晴らしいと感じたのはスピーカーの字幕の訳し方のシーン。
主人公はドイツ人で英語とフランス語が使える。舞台はフランスだが話しやすいのは英語。なので、スピーカーの言葉が出てこない。それを確認した時、まずカタカナでフランス語の音表記になる。それから主人公が話すと"音声再生器"と字幕が出て、ルビにスピーカーと出る。(一瞬だったので見間違いがあるかも)
一つのことを伝えるためにも、伝える相手、状況によって多面性が見えてきたり、惑わされてしまうといった本作の核になるところが表現されていてとても良い字幕だなと感じました。字幕:松﨑弘幸さんでしたので今度から覚えておきたいと思いました。
物語は宣伝の感じより、シンプルだと感じたけれど裁判の進み方、物語の展開の仕方はとても興味深く、おもしろかった。
特にすごかったのは息子ダニエルと、わんちゃんのスヌープ。この男の子とわんちゃんの演技力がこの物語の骨格を強固なものとしていて本当に素晴らしすぎた。今年の個人的主演男優賞と主演動物賞は決まったかもしれません。
カンヌのパルムドール、アカデミー賞の脚本賞を獲った作品なだけありまして見応え抜群でした。ラストも見た人の解剖の仕方によって見え方が変わってくるでしょう。
どこにもスリリングな要素がない
いかにもフランス映画という感じ。説明的な前フリがなく、淡々と地味に進む。冒頭のあの気に障る音楽が本当にイラッとする。何かもっときれいなものを求めたくなる。音楽でも、キャストでも。メインビジュアルの雪の上への落下のシーンが一番インパクトがあったが、それで終わり。
夫の生前の描写がもっとあったらよかった。肝心の夫の人間性がよくわからなくて、ミステリー的な流れにするのなら、ちょっと不公平だと思った。
親しい弁護士の男性にやたらフォーカスしていたけれど、そんなに筋に絡むわけでもなく。冒頭の女子学生との関係もそんなに描かれるでもなく。普通の人間ドラマの印象。
あまりキュートではない少年と犬はよかった。
夫婦とは…パートナーとは…
まざまざと見せつけられた感じ、ぐったり疲れた。子供の事故、落ち込むよね、将来に気を病むね、自分を責めるかも。作家として壁にぶち当たったり、順調だったり。支え合う、知的に刺激し合う関係がバランス崩れたのかな。旦那の気持ちも解る。裁判終わって泣けてくる奥さんの気持ちも解る。子ともがお母さんとの関係を取り戻せてよかった。親をきちんと観ていたんだね、息子は。
真相は「藪の中」、最後に勝つものは…
だらだら長い法廷劇。現実なのか、想像なのか、みわけがつかないところが多い。真相は「藪の中」という感じ。検察側証人から、妻に不利な証拠が提示されるが、妻と懇意な弁護士が巧みに躱していた。裁判官は、息子の証言に最後の決め手を求めた。愛犬「スヌープ」が瀕死の状態になり、スマートフォンの検索で救命法が発見され、解決されていた。母親との協議を回避するように裁判官は世話係に求めたが、世話係は、息子にどちらか選択するように求め、「愛」を選択したようである。視覚障がいという息子は、判決映像がみえていたのだろうか。晴れ晴れとした表情であった。
自分のライフステージの変化やどんな立場に立っているかで感じ方が変わる映画かな、
熟成された良きワインを飲んだときの複雑な味わいを感じる映画。
ミステリー?サスペンス?
そう思って観始めたけど本質はそこぢゃない。
物事の一面だけを切り取って判断することの恐ろしさ。対人における一筋縄ではいかない関係性。嫌よ嫌よも好きのうち、とはよく言ったもの。口で言ってることと実際に意味していることが必ずしも一致してるとは限らない。それを視力を失った息子が聞いたらまた感じ方は違う。
夫婦の関係性なんて他人がどうこう言えるはずがない。人には絶対に見せない部分があるんだもの。それを公の場で裁くために開けっぴろげにすることに一体何の意味があるんだろう……
十人十色というように、同じ事実に直面しても受け取り方は人によって異なる。夫婦におけるパーソナルなものは本当にその二人にしかわからない。それなのに他人が介入する必要があるのはムズムズする。
裁判の最中に弱気になって味方の弁護士にホロっとしちゃう。ダメだとわかっててもね。良い悪いを超越したところで行動してしまう、そーゆーのが人間らしいってことなんだろうな。
観終わっても様々な感情があとを引く。そんな余韻の長さまで良質なワインみたいな映画でした✨🍷
全486件中、221~240件目を表示