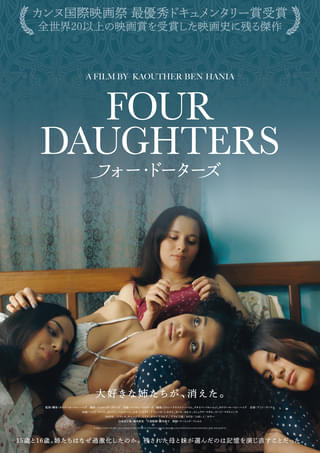Four Daughters フォー・ドーターズ
劇場公開日:2025年3月14日
- 予告編を見る
- U-NEXTで
関連作品を見る PR

解説・あらすじ
過激派組織イスラム国に加わったチュニジアの若き姉妹の決断と、残された母と妹たちの葛藤を描いたドキュメンタリー。
チュニジアに住む15歳と16歳の姉妹がイスラム国に参加した。残された母オルファと妹たちは、2人がなぜその決断を下したのかという疑問に向きあうため、プロの俳優の助けを借りながら、自分たちの人生の重要な出来事を追体験していく。その過程で、家族の複雑な歴史が徐々に浮かびあがってくる。
母オルファ本人が演じるには精神的負担が大きい場面では、「ある歌い女の思い出」で知られるエジプトとチュニジアの名優ヘンド・サブリがオルファ役を務め、国を捨てた娘たちに苦悩する母を演じた。監督は「皮膚を売った男」で世界的注目を集めたチュニジアのカウテール・ベン・ハニア。2023年・第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、優れたドキュメンタリー作品に贈られるゴールデンアイ賞を受賞。2024年・第96回アカデミー賞にて長編ドキュメンタリー賞にノミネート。
2023年製作/107分/G/フランス・チュニジア・ドイツ・サウジアラビア合作
原題または英題:Les filles d'Olfa
配給:イーニッド・フィルム
劇場公開日:2025年3月14日
スタッフ・キャスト
- 監督
- カウテール・ベン・ハニア
- 製作
- ナディム・シェクロウハ
- タナシス・カラタノス
- マーティン・ハンペル
- 脚本
- カウテール・ベン・ハニア
- 撮影
- ファルーク・ラリード
- 美術
- ベッサム・マルズーク
- 編集
- ジャン=クリストフ・イム
- クタイバ・バルハムジ
- カウテール・ベン・ハニア
- 音楽
- アミン・ブアファ
受賞歴
第96回 アカデミー賞(2024年)
ノミネート
| 長編ドキュメンタリー賞 |
|---|
第76回 カンヌ国際映画祭(2023年)
出品
| コンペティション部門 | |
|---|---|
| 出品作品 | カウテール・ベン・ハニア |
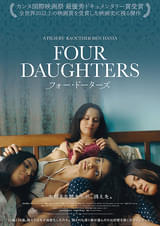

 皮膚を売った男
皮膚を売った男 行き止まりの世界に生まれて
行き止まりの世界に生まれて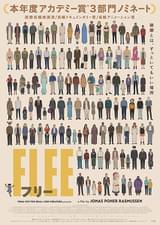 FLEE フリー
FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方
ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ
ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露
シチズンフォー スノーデンの暴露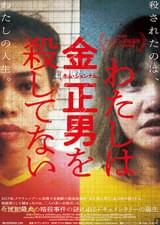 わたしは金正男を殺してない
わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ
ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ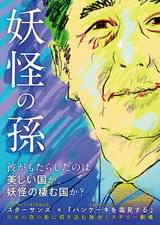 妖怪の孫
妖怪の孫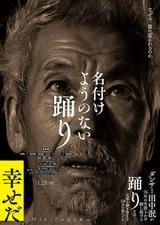 名付けようのない踊り
名付けようのない踊り