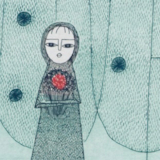若き仕立屋の恋 Long versionのレビュー・感想・評価
全23件中、1~20件目を表示
仕立て屋には悲恋が似合うのか
手は人間の体の中で最も多様な動きをする部分だから、全編にわたって主役と言ってもいいくらい。
憧れだった高級娼婦が連れ込み宿で客を取るまで堕ちていく。それを変わらず恋焦がれる仕立て屋の一途な想いが切ない。
『恋する惑星』で、日本でも一躍有名になったクリストファー・ドイルのカメラワークが素晴らしい。
鏡越しだったり、余白を十分に活かしたり、全部を見せないアングルだったりと多彩。
それに多くのメソッドを使った編集で、作品全体がアーティスティックでエロティック。
かつてパトリス・ルコントの『仕立て屋の恋』というのがあったけど、こちらも切ない恋物語。
北京語のウォン・カーウァイ
手という性癖
「手」は口ほどに物を言う
正直前半は中弛みを感じてしまい、これは「恋」なのか?と少々疑問に思ってしまった。
ホアはいつも電話しているけれど、割とお高くとまっているような、自分勝手な感じだし、どこに惹かれたのかピンと来なかった。
だいぶ衝撃的な出会いのシーンも驚いたが、様々な女に触れろ、女を知れという言葉が、ある意味本作の軸であったことに気付く。
その言葉とは裏腹に、ずっと一途にホアを想っていたけれど、"自分でない男に抱かれる彼女のため"の服を仕立てるために、彼女の身体に触れ、真っさらな生地に触れる。
その度に何度も彼女を抱いて、その全てを暴いて知り得てきたと言えるのではないか。長い年月の付き合いの中で、彼が知ったこと、想ったこと、成熟してきた日々を想った。
前半と対照的に、後半はグッと引き込まれる展開だった。美しい壁紙、生けられた花、丸く大きな鏡はもう無い。長く暗い廊下の奥にしか居場所が無くなり、武器だった身体的な魅力も消えてしまった。
それでも「あなたのサイズは全て知っている」と、そっと身体の縁をなぞり、背後から抱きしめる。それは、貴女が今ここに生きていることを私は認めている、と無言のうちに伝えているようだった。ホアが流す涙のように、雨が窓を打ち付ける。
ラストシーンの「手」で、ギュッと心を掴まれるとは思わなかった。唇に触れることを拒む手。身体的に結ばれなくても、手を介して交わる2つの人生。
触れそうで触れられない、果たされないものに、人はどうしたって惹かれてしまうのだと、スクリーンから切なくも溢れ出る本能的なその魅力に、身を委ねる贅沢な一瞬だった。
アジアの湿度
むむ。田山花袋の「布団」の世界ですな。
・・・・・・・・・・・・・
仕立てたドレスに指を這わせて、妄想と、イメージの”性行為“に耽る(ふける)一人の青年。
娼婦として他の男たちに抱かれ続ける彼女のために、まだだれも袖を通さず、まだ誰のものでもないまっさらなドレスを彼女のためにおろして
処女のシルクの上からチャンは初めてのホアを抱くんでしょう。
「ちまき」は、「無垢な子供時代」の象徴と思われます。
もう戻れない過去の自分を懐かしく思いながらも、二人で ちまきを愛欲の様相でむしゃぶりつく映像は、胸がチクっと痛みますね。
これってプラトニック?
でも吉行淳之介は言いました
― 向かい合って食事をする男女に肉体関係がないはずはない。
ちまきの皮を剥いてゆく・・あそこはエロチシズム、最高潮のシーン。
男女二人。手の動きをカメラが追います。
原題は「愛神の手」。
・・・・・・・・・・・・・
東座にしては挑発的な映画にドキドキでした。
どんな顔をしてロビーと もぎりの受付を抜け出せばよいのでしょう、映画の物語の終わりが近づく予感に困ってしまって、
自分のつま先を見ながら駆け抜けて館の外へ出ました。
・・と日記には書きたかったが、残念ー!上映を見逃してしまって、あとからこっそり配信にて個室鑑賞しました(笑)
小心男の妄想レビューは 中年の映画活動 (略して映活)の惑いゆえ。
短編映画のロングバージョンだけに、一切の無駄なくウォン・カーウァイ監督の映像美を堪能できる一作
仕立て屋という職業の醸し出す独自の雰囲気が物語映えするのか、これまでもパトリス・ルコント監督『仕立て屋の恋』(1989)やポール・トーマス・アンダーソン監督の『ファントム・スレッド』(2018)など、仕立て屋を主人公とした多くの名作が作られてきました。衣装という、身体と密接するものを自らの手で丹念に作り上げていく、という所作が、恋愛というテーマと絡めやすいのでしょうか。そして本作もまた、仕立てを通じてある種濃厚な接触を繰り返す男女の欲動そのものを描いています。
短編作品を膨らませているため、映像には一切無駄がなく、しかし物語としても十分な厚みを備えています。スタイリッシュな映像美で統一するのかと思いきや、仕立て屋の青年チャン(チャン・チェン)とホア(コン・リー)との出会いがなかなか直接的、扇情的で、単に美しい映像を見せるだけの作品じゃない、というカーウァイ監督の強いメッセージを否応なく感じました。
香港の雑多で生活感溢れる風景と、現世から超然としているかのようなチャンとホアの対比が織りなす映像は、まさにカーウァイ作品そのもの。あまりにも無駄がなさすぎて、決め打ち映像のダイジェスト版になっている要素も無きにしもあらずだったんだけど、よく考えてみれば独特の間が印象に残る『欲望の翼』(1990)も『ブエノスアイレス』(1997)も、『恋する惑星』(1995)や『花様年華』(2000)すら、独特の間と物語の厚みが印象的なカーウァイ監督の代表作群は概ね、上映時間100分以下と、長編映画としては短めなんですね。あたらめてカーウァイ作品の密度の濃さに驚きました。
【“貴女の手。”。匂い立つようなエロティシズムが横溢する、仕立屋見習いの青年と、美しい高級娼婦の切ない愛を描いた作品。】
■60年代の香港。仕立屋見習いの青年・チャン(チャン・チェン)は、美しい高級娼婦のホア(コン・リー)と出会い、魅了される。
それ以来、チャンはホアがほかの男のために着飾る服を、愛情を込めて仕立て続ける。
やがて時は移ろい、ホアはかつての精彩を欠いていき、全てを失っていくが、チャンのホアに対する想いは、微塵も揺らいでいなかった。
◆感想
・序盤の、仕立屋見習いの青年・チャンがホアと出会うシーンのエロティックさにまずは、ガツンとヤラレル。
ー ”ズボンを脱いで・・。下着も・・。そして、ホアはチャンの股間に手を入れて、”この感触を覚えていれば、良い仕立て屋になるわ・・。”ー
・そして、数年後再びあった二人の会話。
”服を作ってくれる。美しい服を。””採寸して”
”貴女のサイズはこの手が知っています・・。”
そして、チャンはホワを背後から抱きしめるのである。ホワの頬を流れる一筋の涙。
・更に数年後。落ちぶれたホワの宿舎の家賃を支払い続けるチャン。
そして、病(多分、結核)のために粗末なベッドに横たわるホワに対し、チャンは唇を寄せるのである。
それに対し、ホワは”私の武器だった身体はもう駄目。手で良い?”と言いながらチャンの股間に手を伸ばすのである。
<いやあ、凄いエロティックな作品である。しかも、嫌らしくなく品性が漂っているのである。ウォン・カーウァイ独自の演出で官能的で切ない愛を描き出した作品である。
無理してでも、映画館に行くべきだったなあ・・。>
ウォン・カーウァイ節
音楽が・・・
すごーく期待してしまったのが仇になったのかも知れない。手や指にいろんなことを考えたり感じることは悲しいほどにできたけれど、音楽が何だか合っていなかった。
二人のキャスティングは素晴らしかった。二人とも美しく、特にチャン役は60年代の髪型、ポマードにうなじと完璧でした。最後の二人のシーンは悲しかった。
上半身だけの映像がメインで、美しく仕立てられ彼女に装われたドレス姿全身を眺められなかったのは残念だった。下半身といっても彼女の足、可愛いサンダルを履いた足だけ。監督の意図で演出なんだろう。彼女の体の線を浮かび上がらせるドレスにアイロンをかける、細いウエスト部分。そんなドレスを丁寧にたたんだり、愛おしく抱きしめたり。ドレスが彼女そのもので、そのドレスに触れさせることが彼女の愛で、チャンにとってドレスから作り上げる妄想が彼女への愛なんだろう。
この監督さんのシリーズが好きな方ならぜひ。
今年141本目(合計792本目/今月(2023年4月度)36本目)。
シネマートに3日連続で行ったのも久しぶりな気がします。
この監督さんの映画は基本的に2時間級の長い映画が多いのですが、こちらは60分ほど(ただし、正規料金)。また、香港映画なので一般的な中国語の知識の援用は効きませんが、何にせよ漢字文化圏であるのである程度の類推はききます(字幕の不足している部分など)。
どうもかなり変というかわかりにくい部分があるかな…と思ったところ、2004年の作品のリマスター版か何かのようです(よって、2023年で(著作権表示の関係で)見ることがおよそない「完」(香港映画なので。The Endなどと同じ)まで出ます)。
どうしても60分ほどの映画で、個々個々小さいストーリーを組み合わせたストーリーという形式であることともともと60分であることから、何かしら映画としての主義主張が感じられるわけではないですが、中国映画、台湾映画(ここでは中国と台湾は便宜上の別の国扱い)とは異なる香港映画も良い映画で、さくっと60分見るだけならかなり高評価です。字幕がやや足りないかなと思える点はある(2023年基準で)ものの、漢字文化圏なのでかなりの類推がききます。
採点に関しては下記が気になったところです。
(減点0.3/やや体調を崩す方が出てきそう?)
映画自体は普通のストーリーなのですが、エンディングロールが妙に高速なかつ、赤一色で(ここでいう「赤」は、「真っ赤」のイメージ)、かなり目がちらちらしたり目を傷めたりする部分があります(よって換言すれば、60分ほどの映画ですがうとうとしていても、ここで「強制的に」起される)。エンディングロールも見づらい点があり(ただ、漢字を推定する限り、勝手にコピーするななどはあっても、中国と香港の政治関係について特段の意図はありません、などはない模様)、ここがちょっと厳しいかな、というところです。
なお、香港映画なので、苗字が独特な方が多く、「何」さんや「許」さんといった、中国映画や台湾映画ではあまり見ない(まったく見ないわけではない)方が大半を占めます(逆に「王」さんや「陳」さんなどは大半出てこない)。
映画としての主義主張は感じられないものの、当時の香港の文化などに接したいならおすすめの一作と言えるかなと思います。
昔読んだ谷崎潤一郎の小説が思い出された
やっぱり好きだな、王家衛。
全23件中、1~20件目を表示