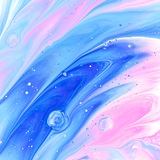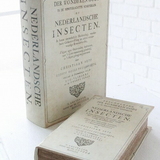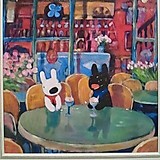バービーのレビュー・感想・評価
全514件中、1~20件目を表示
こんなに長時間ピンクをみたの初めて
マーゴット・ロビーとライアン・ゴズリングだから出来るバービー&ケン。
バービー人形からこのストーリー生まれてくるってすごいな。(アタシが持ってたのはリカちゃんだけどね)
ガーヴィグ監督がバービー?って、ずっと思ってたけどしっかりガーヴィグ節でした。脚本がパートナーのバームバックと共同も納得。
前半は「トゥルーマン・ショー」やウェス・アンダーソンみたいな展開なの??と思いきや、後半しっかりギアチェンジしてきたところがさすが。
先日観た「アメリカン・ビューティー」でも感じたことだけど、私の「幸せ」ってホントに私が求めてる「幸せ」なのかな。他の誰かが大量に垂れ流してる「幸せポルノ」に染められちゃってるのかなとピンクが少し曇ってみえるシーンもあった。
男だから、女だから、平等なんだからとかじゃなくて一人ひとりがその人らしい自分らしさを愛せる世界線になったらいいなってグレタ&ノアのIメッセージ(Weメッセージ?)
は力強かった。
難を言うなら、お二人の作品あるあるで後半のセリフ量がかなり多いのでメタバービーのキラキラ✨を求めて観たら消化不良おこすかも。
〈私〉至上主義ではバービーの鬱は治らない
本作をみてジェンダー不平等の現実を感知して、エンパワーメントされた経験は何にも代え難い。これほど多くの人々に観賞された事実も大きな意義があると思う。
しかし本作をみて、現代の問題が的確に描写されて、万事解決とされるならそれは困る。少なくとも私は本作をフェミニズム映画とは言えない。そうしてしまったらアニエス・ヴァルダやケリー・ライカートの仕事を、そして今も闘っている人々を無視することになってしまうから。
「バービーが女性の地位を向上させた」
私はバービーランドをオルダス・ハクスリーの『すばらしい新世界』のようにすばらしいディストピア世界とみたから、上述のセリフも大いなる皮肉だと思っている。もちろんそうであって、女性の地位を向上させたのはバービーといった「人形」ではなく、現実に闘った「人」である。
フェミニズムの「運動」が洗われている。バービーランドでは定型のバービーと同等にアフリカン系やアジア系、肥満体型や車いすのバービーが存在している。もちろん彼女らが同等に存在していることはすばらしいことだ。しかし浅はかな多様性とも思ってしまう。まさか自明に存在していたとでも言うのだろうか。バービーを産み出したマテル社の企業努力とも?そして彼女らの間には同じ「女性」だから何も問題がないとでも?
そんなわけがない。定型以外のバービーが存在できるようになったのは、アフリカン系のフェミニストの運動の成果だし、障害者運動やボディー・ポジティブの運動も起こったからだ。そして現在は同じ「女性」でも人種や階級、宗教、世代、障害などの差異の尊重と連帯が問題になっている。それは「インターセクショナリティ」という概念で記述され、今なお議論されていることである。
もうひとつバービーランドがディストピア世界と思うことがある。
それはケンが現実世界でホモ・ソーシャルを学び、「Kengdam」という王国をつくるが、バービーらが闘って元の世界を取り戻したとき、ケンのアイデンティティーを回復するためにバービーが放つ言葉である。
「ケンはケン」「自分でいることが幸せ」
〈私〉は〈私〉であって、〈私〉であることは幸せ。グロテクスだと思う。〈私〉であることの根拠が〈私〉でしかないことに。この自己参照。関係するのは〈私〉だけ。それは男といった他者や母といった役割、仕事によるアイデンティティー獲得からの解放にも思えるが、とても残酷だ。〈私〉を構成するのは何なの?もし〈私〉に何もなければ、または根拠を摩耗したら何を参照することになるの?
バービーの鬱は治らない。バービーランドを取り戻したとしても、この「〈私〉至上主義」からは解放されない。むしろその果てで〈私〉が死ぬ。バービーのプライベート空間であるハウスは、別のバービーに開かれていてー悪く言えば相互監視だー、バービーである〈私〉とバービーである〈あなた〉の境界はなくなる。みんな名前がバービーなのだから。
〈私〉はバービーであって、〈あなた〉もバービーである。〈私〉であることは〈あなた〉であることであって、それは幸せ。
私は気が狂うと思う。
気を狂わせないためには「ダブルシンク」をしなくてはいけない。グロリアのスピーチで語られた現在の女性の状況のように。ジョージ・オーウェルの『1984年』のように。でも「ダブルシンク」は鬱を治さない。
スピーチ=言論が洗脳を解くためには重要だ。けれどもうケンとの闘い方で「バカなふり」とかやめてほしい。いつの時代の誰のフェミニズムの闘い方ですか。そしてバービーが仕事でアイデンティティーを獲得するふりをして、産婦人科に行く結末も。もっと闘いは切実だ。それこそ法の逸脱が必要だし、死と触れあっている。だからケンたちの「ごっこ遊び」の闘いで終わらせてはいけないんです。
私たちはバービーランドをみて、ジェンダー不平等の現況を感知しなくてはいけない。と同時にバービーランドではない別の仕方の世界を創造/想像しなくてはいけない。その「ダブルシンク」が求められている。そしてそれを現実に反映させる運動が。そこまでの射程があるなら本作はアカデミー賞の作品賞に相応しいし、グレタ・ガーウィグが監督賞にノミネートされていないことは抗議してしかるべきだ。
ただ私はそもそもファーストシーンで人形を宙に投げることからアヴァンクレジットに繋げる仕方があまりにもダサいと思っているから、複雑な心境にいる。
ジェンダー平等と自己認識
U-NEXTで鑑賞。
バービーは日本で言うリカちゃんのイメージが強いですが、ジェンダー平等などのテーマで描かれていて奥深かったです。
ピンク一色のセットは派手で、可愛さ溢れる人形の街並みを実写で再現した光景には驚きました(その影響で、ピンクの塗料が品薄になったとか)。
人形をただ実写化しただけでなく、現実社会についても描かれていたのが好印象でした。男女ともに社会で活躍する機会を与えられる必要性や、自分が何者なのかを考えて生きる大切さが伝わってきました。
最近のアメリカでは、女性の社会進出が騒がれたり、自分軸を持つ人が増えているように感じます。日本でも実践されている部分はありますが、格差などの問題は未だに解決しておらず、課題は山積みです。そのため、自分らしく生きることが今後重要になってくるのではないかと考えました。
私も自分がどうしたいのかを意識しながら、少しずつ自信を持って生きようと思える作品になっていました。
アホになれれば楽しいはずが、フェミニズム要素で我に返る
マテル社公認映画でありながらいわば自虐的描写てんこ盛りなのはさすがハリウッド映画。廃盤バービーへのツッコミや男だらけの役員メンバー、一人ずつ壁で囲われて閉鎖的なオフィス空間。
なんだかゆるーく行き来できてしまう、現実世界とバービーランド。陽キャが過ぎてどこかシュールなバービーランドの住人たち。この辺はB級すれすれのノリというか、根底に流れるフェミニズム的テーマがなければ完全にB級と言ってしまいたい雰囲気だ。
世界のピンク塗料を枯渇させた、ガーリーにむせかえるようなバービーランドのセットはなかなかの見応え。バービースタイルでないと着こなせないようなファッションを次々びしっと決めてみせるマーゴット・ロビーはさすがの美しさ。ある意味狂気じみたケンというキャラを徹底的にやり切るライアン・ゴズリングも見どころだ。
こういうノリの映画は深く考えずに見られればアホになれて楽しいのだが、これだけフェミニズム色が濃いと、あれこれ考えてしまわざるを得ない。
(この辺さまざまな見方があるかとは思いますが、私個人が素直に感じたことです)
まず感じたのは、バービーランドにおけるケンたち男性の立ち位置は、現実世界における(少し古い時代の)女性の立ち位置をそっくり表象しているということだ。バービーに比べるとはるかに個性に欠け(ると見做され)、バービーランドという社会においてはバービーの付属物としか見られず、軽視される存在。
物語の中で、人間の世界に行って男性が活躍する姿を見たケンは、バービーランドに人間界の男性観(マチズモ限定)を持ち込む。そしてバービーランドの憲法を変えようとするが、バービーに煽られ男性同士の対立にかまけているうち憲法改正を阻止される。憲法改正は出来なかったが、バービーの「ケンはケン」と個性を認めるかのような言葉に満足する。さらにバービーは「ケンたちもそのうち力をつけるでしょう」(だっけ?)みたいなことを言い放つ……
それでいいのか?
フェミニズムは男女同権主義に立脚するはずだが、バービーはケンたちと共同で新たな憲法を制定したりはしない。彼らを(バービーランドの)法的には元の社会的に劣後した立場に戻し、バービーがケンに個人的ガス抜きをしただけで解決扱い。
これが男女逆ならば炎上案件になりそうだ。
純粋にバービーランドの中のケンだけを見れば、生まれながらに女尊男卑の世界の弱者なのに、本作のケンに対する扱いは、現実の男性優位社会へのカウンターになっている。
そもそもバービーの世界観の起源自体が、女児向けの玩具という性質上女性優位なので、男性の存在が空気にならざるを得ないという側面はある。男の人形に凝ってみたところでマジョリティには売れないということなのかもしれない。
だとしても、目覚めたケンの描写が現実世界の男性への偏見に満ちている様子には少々うんざりした。私自身はそういうことに人一倍神経質というわけではないつもりだが、多様性を押し付け……もとい標榜するポリコレの聖地アメリカの作品が、特定の属性(男性)を「現実界の男といえばマチズモ、馬、『ゴッド・ファーザー』を語りたがる」などと一括りにする、そのダブルバインドぶりにちょっと白けたのだ。
今の時代に女性の主体性や多様性を描くのに、そうやって他の属性を雑にまとめて貶める必要があるのだろうか。
終盤でグロリアが羅列する”女性を縛る不自由さ”の内容に、女性特有の問題ではなさそうなものが混じっていたり、頭脳労働的な職業とウェイティングスタッフのような職業の扱いに軽重が見られたりと、ケンの扱いで首を傾げたことをきっかけに他の重箱の隅も気になり出してしまった。
頭バービーなノリと、嫌でも目に入る定型のフェミニズム的メッセージのギャップを行き来して、思った以上に脳みそが忙しくなる映画だった。
パロディーなのでお気楽に
のっけから、かの有名な名作映画のパロディーからスタート。そして赤ん坊の人形を叩き壊すシーンからして、ああ、この映画見て怒っちゃ負けなんだな、と思いました。みんな、「2001年宇宙の旅」は知っているのでしょうか。
性差別とか男社会に女性軽視の問題とか、よくある議題の真面目なテーマが紛糾しそうですが、ありがちな話だと聞き流して、まっピンク色のビジュアルを素直に楽しむ、ポップコーン映画として見れば良いかと思います。そもそも人形遊びなんてしたこと無いし、リカちゃんならともかく、バービー人形なんてしらないけど、お祭り騒ぎの映像を気楽に楽しむだけなら、バラエティーな映画として十分役割を果たしているかと。
でもわずかに見せるリアルな美しさを魅せるシーンもあって、そこまでふざけた映画でもなかったと思います。バービー創始者を登場させるところは流石。
でも、スタッフロールに入る前の本物のバービー人形達はちょっとしたホラー。最初に魅せられなくて良かったw 音楽とか、スタッフロールのピンクのフォントも素敵ですね。やっぱり最後まで席を立たずに見てしまった。
みんな違ってそれでいい、の裏と表。
監督としてのグレタ・ガーウィグがこれだけのバジェットの大作映画の準備が整っていたかは、正直微妙だったかもと思う。美術や衣装のクオリティに比べて映像が充分にハネてないように感じてしまったからだ。作品から感じた面白みは、映像よりもコンセプトだったり多層に織り込まれた皮肉やユーモア混じりの問題提起だったりのほうが勝っていて、終盤になるほどセリフに頼りすぎではないかとも思う。
しかし間違いなく刺激的で、いろいろ考えさせられる作品ではあり、しかもこの映画について語られている言説がぞれぞれ微妙にベクトルが違っていて、観る側の価値観や先入観をあぶり出すような仕掛けになっている。この映画のどこに感じ入ったり、ひっかかったり、わがことのように感じたりするのか、結局は自分と向き合うハメになるのは、劇中のバービーやケンともシンクロする。
素晴らしいと思ったのは、クソバカ集団であるケンたちの代表としてライアン・ゴズリングとシム・リウが対決するバカげたミュージカルシーンで、戦ってるうちに通じ合ってしまうまでがわずか一曲の中で表現されていたこと。あの場面が古典ミュージカル『オクラホマ!』の「ドリームバレエ」の引用であることはグレタ・ガーウィグも明かしているが、「ドリームバレエ」のシーンは心の迷いからひとりの人間のアイデンティティが分裂する様を描いていて、いわばこの映画のケンたちも同じアイデンティティから生まれたバリエーションにすぎないと言える。
それはバービーたちも一緒で、マーゴット・ロビーの定番バービーだけが、バリエーションのひとつであることを捨てて有限の命を持つ人間になろうと決意する。正直、人間ってそんなにいいものか?と思ってしまうし、誰もが違っていてそれでいいというメッセージ性に100%ポジティブに共鳴できるわけでもないのだが、人生の次の段階に進むためにアイデンティティの根底から揺らぐような変化を受け入れなくてはならない局面が訪れるというのは心底その通りだと思うし、この映画の表向きの明るさとは裏腹に、選択には常に伴う辛さと哀しみを作品から感じられたことが自分にとっての一番の魅力だった。
同じように感じた人がどれだけいるかも知らないし、それが自分ひとりだったところで構わない。そういうことを伝えている映画でもあると思っている。
美術の素晴らしさ
プロダクションデザインが素晴らしい。この分野ではオスカーの有力候補だろう。キッチュでリアリティを追求せず、ドールの世界を具現化してみせ、そこに生身の役者がいても違和感のないバランス感とピンクを基調にしたカラーリングをケバケバしさを感じさせずに再現。レトロなポップ感が抜群に心地よさを感じさせる。芝居のあり方もあえて戯画的で、オーバーアクティブなものにしているのも良い。リアルなだけが良い芝居ではない、こういう方向性の面白い芝居もアメリカ映画でもどんどん追求してほしい。
スタンダードモデルゆえに特定の職業やアイデンティティを持たない主人公のバービーと、そんなバービーの彼氏というポジションでおまけ的に生まれたがゆえに、やはりアイデンティティを持たないケンの2人(2体)がフェミニズムや有害な男性性の体験を経て、自分らしさを獲得しようと試みる。現実社会のマテル社は男性経営者の支配だと本作は描かれている。事実かどうかは知らないが、その体制は特に破壊されない。資本主義とフェミニズムの関わりにはある種の課題があると本作は示唆している。
バービー世界かわいい
社会問題を羅列し、コラージュしただけで結局なんも提起してないところに温度差を感じた。
ライセンス的に欠陥のあるバービーとか、尖りすぎたユニーク(唯一)な個体は描けなかったからこんなにふんわりしてるの?
マーゴット・ロビーは本物のバービーみたいで美しいし、
ライアン・ゴズリングの筋肉は凄い。
タイトルなし(ネタバレ)
バービードールの世界を実写で再現というだけでも危険なのに、ヘタに男女差別の社会性を盛り込んじゃうのは失敗確定演出としか思えない。結果、極端な女社会vs男社会の対比とマーゴットロビーの大袈裟演技で予想通り撃沈。所々にバービー歴代衣装をMV風にカットインする演出がまたC級感を加速させている。『バービーは何者にもなれる存在』という創業者の想いオチも虚しく、近年まれに見るドタバタ映画として、マテル社の栄光の歴史に刻まれてしまったと思われる。バービー世界をアニメ、人間社会を実写にして魔法かけみたいなファンタジーにできなかったのかな~~残念無念。
アメリカの友達イチオシ
アメリカの友達イチオシ作品。アメリカで大ブームなのに、日本であまりウケなかったらしい。ノリが合う人と合わない人はいるかも。個人的にもっと尖っている方が好み。もっと振り切れてほしかった。全体的に明るく楽しいバービーワールド全開映画ですが、共感できる部分があって途中でホロリときました。挿入歌がとても良くてこの映画のあとずっとニッキー・ミナージュ聞いてます。
ピンクの世界
アメリカの国民的アイコンであろうバービー。
そのバービーの世界を使って、ジェンダーとは、アイデンティティとは何かを描いた映画。
バービーのような主人公のみが優遇されるのではなく、ケンやアレンその他名もない人誰もが輝ける国にしよう、と胸がすっきりとした終わり方。多様性の今の時代だから共感されるテーマであった。
ギラギラしたケン、アジア系ケン、へんてこバービー、妊婦や弁護士のバービーなど登場人物がシュールすぎる。カラフルでポップな世界観がいかにもアメリカ。
マーゴット・ロビーの魅力だけ
ピンクでカラフルなバービーの世界の再現が完璧でした。
私はバービーじゃなくてリカちゃんだったけど、いろんなドレスや作り物の食べ物や水の出ないシャワーのお家、あの世界で楽しく遊んだ事を思い出して、あの世界を観てるだけでワクワクしました。
毎日ハッピーなバービーの世界が崩れ、ケンと一緒に元に戻すために人間界へ。
人間界ではバービーは傷付く事だらけ、かたやケンは男社会に目覚めていく、そのシーンのケンの行動には何回も笑えました。
でも私が楽しめたのはここまで。
そこからラストへの展開が「うーん」でした。
ケンと対立するとかマテル社の社長との絡みとか別になくても良かったような。
「自分らしく生きる」、男女平等というメッセージは伝わりましたが、そういうメッセージ性のある作品ならこの作品じゃなくて良かったし。
マーゴット・ロビーはバービーのようにとっても美しくて、私にはマーゴット・ロビーの魅力を堪能するだけの作品でした。
anti-promotion
女性なら共感だらけ
観る前からフェミ路線と知ってはいたので、そこまで抵抗なく観られた。ケンがくそださファションに身を包むのも笑えたくらい。
ルッキズムやら性差別のあれこれ、潤滑になるよう女性たちが配慮していることにほぼ気の付いてないメンズたち。
現実世界だってイラつくわけだけれど、アメリカでもそうなんだなと妙な親近感を覚えた。
とはいえ女性男性どちらかが正しいってオチではなく、歩み寄って妥協点を探るのにはホッとする展開。
女子が夢の世界から出ると婦人科検診なのか~生々しいな。自分のボディに自分で責任と意志を持つということなんだろうな。
女性への新しいテーマ
この映画はとても新しく深い。一回見ただけでは、わからないかもしれない。
マーゴットがあまりにも美しく、アイドル映画だろうと思って見てはいけない。(マーゴットは当時30歳ぐらいだろうが、パーティーで踊る髪の毛ゴージャスなバービーは本当に綺麗で目を奪われる。)
バービーの頭をきのこ雲にするという不埒な宣伝をしなければ、もっとこの映画は良い映画だと認識されたであろうに、宣伝会社があまりにも愚かだった。
映画の冒頭、赤ちゃん人形で遊ぶ女の子達が、突如めざめて、遊んでいた人形の両足をつかみ、頭から粉々に割るというシーンは衝撃的だ。それほど、【女を家事育児要員にするな】という意思の表れなのだろうが、女が敵意をもって子供人形をぶっこわす、ってことをどう捉えるか。赤ちゃん人形の代わりに出てきたのがバービー人形だ。バービー人形は職業をもち、白人だけではなく黒人もおりアメリカで誰もが自分を投影できた。権威の象徴の大統領にもなれ、最高裁判所判事にもなれる女性の夢だ。
しかし、中盤、その何にでも素敵なものになれるというDreamが、現代の高校生女子には、逆にプレッシャーを与え、ストレスにもなっていることが明かされる。
そして、バービー自体も【死】を意識した時、人間の女性はどうしたらいいのか、問われることになるのだ。死ぬということは、どうやって生きるかになり、もちろん、時間が決められているからだ。いつまでもパーティー三昧で終わっていいのか、女が優位になることが誇れる最終目的なのか、それに子供をもつかもたないか。
最後に人間になったバービーが、婦人科にいって自分の女性としての機能を見てもらうことで終わる。それまではケンもバービーもお股のところはツルツルで何もなく人間どころか、本当は男でも女でもなかったわけだ。再度、女性は女としてどう人生を終えるかを問われている。人形だったバービーが、自分の内臓を初めて見た時、生殖器をみたとき、きっとそれを使って子供を産んでみたいという衝動に、私は、かられるとおもう。
この映画は、キャリアをもち独身で死ぬも良しだが、自分の人生だけで終わる人が増えた事への疑問なのであろうか?
「ただの人でもいい、お母さんになってもいい、ならなくてもいい」、と登場人物のヒスパニック系のママが言うのは、キャリア系バービー人形からの揺り戻しも垣間見える。
実際、自分の時代にはバービーもあったが【りかちゃん人形】を選んだ。自分の頭の中で何にでもなれるのは、もちろん、りかちゃんだったからだ。なんか、女性の権利のために、最近は【ままごと】さえ女性差別とされ、出来なくなっていることを憂慮する。
最後のビリー・アイリッシュの歌も素晴らしい。what was I made for?が心にひびく。
現実では男社会のままであること
女性主体の社会だったらの理想のバービー達。男社会である現実。女性が活躍できてないよーと言うメッセージを、バービー界と人間界を行き来できるファンタジー要素を満載にして、まろやかに伝えている。ミュージカルとダンスもありちょっと長く感じた。
バービーについて学べた
女性の社会進出を肯定しながらも、行き過ぎた女性優位社会に問題定義があり、とどのつまり、社会的には男も女も無く個人の能力を認めながら自分らしく!という理解が正しいか。
行き過ぎた昨今のダイバーシティを説くものでないのが良い。個人的には「君があっての僕なんだ」で居たいのだが甘えが過ぎるのか?🤨
映像技術や世界観が斬新。
何だかんだそこそこ楽しめた。
とりあえず、フェミニズム作品と言われてるし、もちろん制作側もそのつもりで作ってるんだけど、結局フェミニズムに限ったことではなく社会的弱者にスポットライトを当てていて、取り上げられてるのが女性のことだけではない。
明言されてはいないが、恐らく障害者や同性愛者など、社会運営の中心=若くて健康な男性以外の「はみ出し者」扱いされる男性や、社会のおかしさに気付いて反発する男性、「男らしさ」(アメリカでは特に筋肉)に悩む男性の苦しさも描かれている。
ここまで深堀りした作品あったか?というくらいゴリゴリのフェミニズム作品とも言えるけど、中でもアメリカで近年問題にされている「有害な男性らしさ(男はこうあるべきとする世間からの押し付けや無意識の思い込み)」への焦点がかなり強い気もします。
見た目は華やかで楽しげだけど、テーマはかなり現実的で重い。
女性差別を取り上げた作品で、しかも女性の地位が低いことすら理解できない人も多い日本では絶対ウケないだろうと思ってたけど、予想通りの評価(2024年現在★3.4)。
内容をほとんど理解できないまま、認めたくない現実を突き付けられてキレてる人も多そう。
また、演出としても、映画っぽい部分と舞台調(何もかも大袈裟)の部分とが混じり合っているので、苦手な人は苦手だと思います。バービーランド(ケンダム)のシーンなんか特に、大人がマジになってやってるお遊戯会の空気。
加えてコテコテのアメリカンコメディ(何もかも大袈裟)が入ってくるので、フェミニズム作品じゃなかったとしても、日本ではある程度評価が低くなりそうな作風。最後の方なんかもう何だコレ?コメディというより意味不明すぎて笑えます。
ミュージカル?コント?まじで何なんだよコレ???
でも、そういうのが好きな人は楽しめると思いますし、テーマがハッキリしているから、そこを「よく表現したな!」と評価できる人もいると思います。
あとは圧倒的に美術点。色にかなりこだわって作ったそうですが、色使いが素晴らしいのは間違いない。
自分はバービー人形とは縁もゆかりも無い生活をしていたけど(多分実物を見たことすらない)、作中で説明があるのでチンプンカンプンってことにはなりません。
バービー人形が大好きだった人達(今も好きな人達も)は、小ネタも拾えてより楽しく見られるのでは。
主演のマーゴット・ロビーがいつもよりやや老けて見えるのに、スタイルはバービー人形そのもの(不自然に綺麗)なのも、よくできている。この設定だったら顔もCGでピッカピカに整えそうなもんだけど、多分わざとなんでしょう。
今回が「やや老けて見える」のではなく、通常がこれで、他の映画に出る時はよっぽど塗りたくられてるんだろうな。他の俳優もそう。プライベートの写真(メイク室での1枚とか)を見ると、男女共に思ってたより老けてるなぁと感じる。でもそれは逆に、映画や雑誌、人目につくものなら何でも、今の時代は若々しく、シミや皺を消し、時にはCGで胸を大きくされたり贅肉を消されたり筋肉質にされたりして、作り込み過ぎてるせいで落差が激しくなっているだけ。
他の映画で俳優の肌の質感やボディの皺が気になったことはほぼないが、本作ではあえてバービー人形=「不自然な美しさ」に対抗して、人間の自然な状態に近い部分を残したのではないかと思います。この話の流れでピッカピカじゃ不自然ですよね。
その他、表現が結構細かくて、序盤のケンVSケンのケンカ(おっと…)の時、横からアイスを差し出されて「アイスは後」と押し退ける時、手とアイスが当たったはずなのに、プラスチックが当たったようなコンッという軽快な音がする。
その後バービー家でのパーティーシーンでも、様々なドレスを着て踊るバービー達を見ながら、ケンは何も言わないが、隣のケンの服をチラッと見て嫌そうな顔をする。
バービー人形はあくまで「女の子のため」に「女の子の理想」として作られた遊び道具であり、ケンはあくまで「おまけ」で、アイデンティティはなく、関心を持たれないために服のバリエーションもほとんどない(だからバービーの気を引くこともできないとケンは思ってる)、ということなんでしょう。
バービーもバービーで、実は「女の子の(目指すべき)理想像」を押し付けられているだけで、アイデンティティはない。毎日やることは決まっていて、永遠にそれを「し続けなければいけない」。そういう存在だから。
それに疑問を持った途端、空は飛べなくなるし、常につま先立ちだったバービーの足が直角になったりと、何もかもうまくいかなくなる。
バービーランドは夢の国。現実は見ない。見ない方が幸せ…らしい。
現実逃避をしていた人が現実に気付くと、今まで夢を見て良い気分でいれば良かったものが、そうもいかなくなる。
自分の実力がなければ他人の助けだけではどうにもならなくなるし、自分を成長させようという気がなければ置いていかれる。夢を見ている間に世間に取り残され、自分で自分を成長させる術もわからず、負のスパイラルにハマって堕落していくというのが、わかりやすく表現されている。
バービーが人間界で男にお尻を叩かれるシーンも、現実にアメリカであった事件。
生放送中、リポーターの女性のお尻を後ろから走ってきた男がニタニタ笑いながら叩き、大炎上した。後にこの男は会社もクビになったとか。アホだなあ。
女性の憧れ=男性の理想の女性像(が行き過ぎたバージョン)であるスタイル抜群のバービーが、人間界でずっとセクハラされ続けるのもリアル。
こんな下品な奴本当にいるのかと思っていた時期が自分にもあったけど…若い頃たまたま美人の女友達と街を歩いていた時、少し離れるとすぐ変な男に絡まれていて、でも友達の対応も馴れたもんで、何だか可哀想になった。
男同士でつるんでいては見えない世界があり、それを見ないまま作ったのが今の社会なんだなと。
ライアン・ゴズリングのライバル役としてシム・リウが起用されていたけど、彼はコロナ禍でのアジア人差別に対して色々な人が「差別良くない」「自分も受けたことある」「本当に悲しい」みたいな無難なコメントをしているなか、唯一女性に対する差別に言及していた。
「アジア人同士でも『男は性的対象として見られないが、女は性的に見られているから女の方が得をしてる』などと言う男がいるが、ありえない。女性も白人が定義したアジア系の女性らしさ(=娼婦)のイメージに苦しめられている」とハッキリ男女の受ける差別の形が違うことや、アジア人女性が受けやすい差別について言及し、きちんと自分の意見を持っていた。
何となく時代の流れを見て、好感度を上げるために「差別はダメだと思いまーす」程度なら誰でも言える。
今まで良かったことが時代の流れでダメになったのではなく、昔からダメだったのに罰がないからやり放題だったことに世間が気づき始めた、というだけのことを、理解している人が意外と少ないが、シム・リウの発言を見ると、しっかり世間を見ようと努力し考えている人だなと思ったし、本作の出演者が発表された時、だから彼が起用されたんだろうと思った。
上に書いた「有害な男らしさ」についても発言されており、普段からよく人を見ているのか、本作でも無知なフリをするバービーに「上から目線で教えてやる」ケンの演技が板についてます。
また、マーゴット演じるバービーの「私は冒険系じゃない、定番のバービー」という台詞も面白い。自分は「普通」だから、何もできない。そういうタイプじゃないからしない。困難を自分で何とかするなんて私には無理、我慢してた方がマシ。自信がない人は大抵こういう考え方をするし、女性は特に自信を持てないようにされてきた。
まさにこういう考えから、フェミニズムに反発する女性も多いのでは。今まで受けてきたのと同じ仕打ちには耐えられるが、その仕打ちを無くそうとするフェミニストのせいで女性全体が逆恨みされ矢面に立たされるのは許せない。数十年後、そのフェミニストのおかげで得た権利や立場は、当たり前のように自分のものにするにも関わらず。「時代の変化」などと言いながら。
時間が経てば自然と変わるかのように言われるが、世の中は勝手には変わらない。誰かの努力と犠牲で変わってきた。
夫が死んだら妻も連帯で殺されたのも、嫁いだ先で夫の父親に「味見」されるのも、女を政治に参加させない法律も、誰かが声を上げ、時に殺される人もいながら、それでも努力したから無くなった。
本作では決して女性をただの被害者のように描くのではなく、また女性だけが被害を受けているように描いてもいないのがまた素晴らしい。
男性には男性社会のしがらみがあり、囚われている「男性らしさ」があり、女性側も男性のことを理解する必要があることをしっかりと描いている。
フェミニズムは女性の権利だけを守るものではなく、フェミニズムを突き詰めれば結局、女性と同じように男性に押し付けられてきた社会的な概念があり、互いに縛られている偏見や無意識の差別意識を皆がなくさなければ、本当の「人権」などどこにもないということをきちんと理解している人が作ったことがよくわかります。
逆に言えば、ここまで人権や偏見、差別に関して深堀りしたことにより、そういった知識がフワーっとしかない人、フェミニズムを勘違いしている人には、言いたいことがほとんど伝わってない可能性が高いのが残念なところ。
ちなみに本作、アカデミー賞で監督や主演のマーゴットはノミネートすらされず、何故かケン役のライアン・ゴズリングだけがノミネート。これにライアンがドン引きするという笑えない話があります。
本作で伝えたかったことがまるで伝わってねーじゃん、と不快な表情を隠しもしなかったライアン、こりゃ株が上がるね。
まぁ、個人的にもエンタメというより教科書的な価値の高い作品だと思うので、面白くないという人が多くても仕方ないとは思います。が、アカデミー賞は過去にも当然真面目な社会問題を扱った、面白みは全くない作品を受賞させてきているし、むしろヒーローもののような完全エンタメ作を滅多に受賞させない方向性から見ても、こういった「教科書的」作品こそ注目してそうなもんだし、注目されればそれだけノミネートの可能性も高くなりそうなもんだが。
マーゴット・ロビーの演技力だけでいうなら、確かに「良すぎる」演技を見せ付けた作品はもっと他にあるとは思う。ただ、あれだけ注目されていた作品にも関わらずノミネートすらされないのは、本作の演技に特別何か問題があったのか?
監督も、こういった作品はそもそも作られること自体稀であり、かつこのテーマで作るにあたり男性俳優を集めるだけでも大変だったろう。
こんなに現在の社会問題をわかりやすく、データを元に緻密に作り上げた作品は現状、他にないと思うし、大抵こういうテーマだと感情に訴えるだけの作品になりがちななか、安易にその道に逃げなかったかなりの功労者だと思うけど、何故ノミネートすらされなかったのか気になるなあ。
エンタメの皮を被ったシリアス映画…でもなく、そもそもエンタメの皮を被ってもない、普通にシリアスで重いテーマの作品なので、間違いなくバービーで遊ぶような小さい子供向けではないです。少なくとも小学校高学年か中学生以上かな。
子供でも、女の子だからという理由で嫌な思いをしたことがある子、そういう女の子を見た、話を聞いたことがある男の子なら、子供でも理解できると思います。
仮に親御さんで、説教臭いポリコレ映画なんて子供には見せたくない!と思っているなら、大間違い。
これからの世界を生きていく子供達が、加害者にも被害者にもならずに生きていくために、必ず必要な知識と目線です。それを自分が気に入らないから見せない、というのは、子供のことを本気で考えているとは言えないかなと。
もちろん、子供が楽しめるかどうかは別なので、退屈なら押し付ける必要はありません。個人的にもスゲー面白いかと言われたら………なので(え?)。
ただ、途中に出てくる急な「新作の鬱なバービーだよ!」が地味に笑える。
どちらに感情移入・共感しても結局…
ケンたち側にムカついても、ケン側をかわいそうと思っても
結局リアル世界の女性の立場による事になり
かといって、後半のバービーたち側に酷い!と思っても
結局リアル世界ではそれを男性がやってきたことになり…
頭の中がぐるぐる回り続けます
無敵の人予備軍の人が観たらパニックに陥ってしまう……
そんな人たちにこそ引っかかって見てほしいけれど
楽しい映画というより、道徳・倫理・保険・歴史の授業で衝撃的なドキュメンタリーを見たあとの帰り道、その日の夜みたいな
この機会が貰えたことは素晴らしいけれど、明るいのを観たい人は違うかな
全514件中、1~20件目を表示