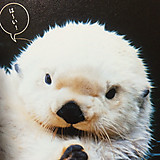怪物のレビュー・感想・評価
全1009件中、661~680件目を表示
面白いけど理解難易度は高め
おすすめできる人
いつもの是枝監督の作品が好きな方には自信を持っておすすめ出来ます!
今作はある出来事を色々な視点から描いていくものとなっているので鑑賞中に先の展開を予想したり、終わった後で話を振り返って考察する方向けです
この映画について一緒に見た人と意見交換するのも面白いと思いますよ!
おすすめできない人
最後には全部分かってすっきりしないとダメな人にはおすすめできません
「怪物だーれだ」のキャッチフレーズの通り様々な怪物候補の人物が出てくるのですが、それを表すため怪物的な人間性を多様に描写しているところを難解に感じてしまうかもしれません
難しくて見終わってもモヤモヤする映画、雰囲気が暗い映画よりも爽快感のあるアクションが好き!という人には微妙です
坂元さんが紡いだダイアログはやはり印象深い
坂元さんの脚本が好きです。人と人との会話の中で生まれる言葉に不思議なパワーや魂が宿っていると感じます。
最終的に少年二人の心に爽やかな風が入り込むようなラストだったのだが、1回観ただけでは消化不良になる点があるかもしれない。2回目3回目を見て、自分の中でゆっくりと各登場人物の心情を噛みしめていくような作品だなと思った。
目に見えていることだけが全てではなく、事実ではなく。自分から見た他者、他者から見た自分、それらはいつもすれ違いが起きている。他の先生からの視点や、星川くんの視点が描かれたとしたら、どんなだったのかなーと思う。湖、火事、廃電車、横たわる金魚、猫…人間以外のものが、どういう意味を投げかけているのか?とかも考え出したらキリがなく、やはり2回目を見なければ。
印象的なセリフを挙げてみる。(映画のシナリオ本、ぜひ欲しい…)
・誰かにしか手に入らない幸せは幸せなんかじゃない、誰にでも手に入る幸せが幸せなのだ
・牛丼は牛に戻って、うんこはお尻に戻る(笑
・親って気使うよね
最近、宮藤官九郎さんがラジオで言っていた。記憶はバケツのようなもの、と。ここ2〜3年の出来事はほぼ覚えていないのに、バケツの底にある昔の記憶はいつまで経っても忘れない。坂元さんは小学校時代の自身の同級生を思い出したそうだが、本当に、子供の頃のこういう記憶って消えないものだ。自分の幼少期を思い出し、切なくなったり、後悔が湧き上がってきた作品でもあった。
子供を怪物だと思い込んでいたのは周りの人達か…
なにが人を怪物たらしめるんだろう?視点によって怪物が変わる。
序盤は、いじめ?→母親が怪物?→先生たちが怪物だ…
と思ったら、息子の湊くんが怪物なのか!?→担任の先生ヤッバ…→あれ?誰も怪物じゃない???
→結論、中村獅童が演じる父親と校長教頭が、根っからの怪物だと思いました。
とかなり揺さぶられました。
そして、伏線がかなり上手く気持ちよかったです。
片方ない靴、水筒の泥、怪物のカード、耳の怪我などなど、見方によって捉え方が変わる面白い伏線でした。特に水筒の泥は感動すらしましたね。
最近の流行りなのか何でもかんでも伏線と叫ぶ人らがいますが、考え直して欲しいなと思いました。
・"人に潜む怪物"が伝播していたと感じました。
最初は湊くんの友達(星川依里)のクズゴミ父親です。
いじめがあり、対応が分からない湊も悩みを抱え、担任の先生にも誤解を産み、そこから母親まで…
・証拠がないことによる恐怖っておそろしいですね。特に担任の先生がガールズバーにいたらしいという噂から先入観を持ってしまい、もう冷静ではなくなっていました。誤解による怪物誕生。
ガールズバーにいたのは、クズ父親でも担任でもなく、前の先生じゃないかなって勝手に思ってました。
-
不思議に思ったのは、
なんで飴を食べたのか?
湊のとなりの席の女の子
前の教師はただの教師か
ってとこです。
隣の女の子はたぶん、依里のことが好きなのかなと思いました。初めは湊のことが好きで猫の件を咄嗟に庇ったと思ったのですが、それだと猫の件を密告した理由が分からないので…
あの女の子は、湊が依里をいじめている→本当は仲良し、ってことに1番初めに気付いたんじゃないかな?
飴は流れ的に、周りの先生からの指示かな
前の先生は今の担任の先生との比較で出していたと思うんですが、結局面倒事が嫌なだけの普通の先生だったので、良いキャラでした。
映画館で観るべきかと言われたら、断言は出来ないけど、少なくとも1回は観るべき映画だと思います。
とにかく演技も、ストーリーの早い流れも、決して難しくない理解しやすさも、観客に考える猶予をくれるところも全部満足しました!!!
【追伸】
2回目観ちゃった
個人的には、ラストシーンあの二人は死んでいると思います。
立ち入り禁止表記や天気など全てが二人にとって都合の良い、二人だけの自由な世界に行けたんかなーって
「怪物だ~れだ」のフレーズがまったく異なる響きに聞こえる
いくつかの出来事が、母親・教師・子どもの視点で描かれます。
視点が変われば、知れる情報や見えるものが違い、出来事が異なるものに見えます。
鑑賞後には、トレーラームービーでは不穏にも感じられる「怪物だ~れだ」のフレーズが、まったく異なる響きに聞こえます。
怪物とは、得体のしれないもの、理解できないものを指すのではと思いました。
母親の視点では、子どもに「なぜ?」と問い詰めるとき、母親にとっても子ともが理解不能な怪物に見えたかもしれません。
教師の視点では、自分の言葉を誰も聞き入れてくれないとき、他人のすべてが得体のしれない怪物のように見えたかもしれません。
子どもの視点では、どうやら普通ではないらしい自分のことが、自分でもわからない・説明できない怪物のように感じられるのかもしれません。
子ども視点のシーンがとても印象的です。
ピュアでまっさらで、まだなにも名前を付けられていない感情たち。
子どもたちの眩しく美しい笑顔に切なくなります。
ここを切り取っただけでも素晴らしいジュブナイルストーリーになるでしょう。
ラストはハッピーエンドだと信じます。
最高の役者陣で人間の性を鋭くえぐりまわす圧巻の衝撃作!
安藤サクラさん、永山瑛太さん、田中裕子さん、そしてガラスの様な小学5年の少年達を痛々しくも力強く演じる黒川想矢さんと柊木陽太さん、終始 皆さんの素晴らしい演技に圧倒されるあっという間の2時間でした
特に柊木陽太さんの演技が圧倒的、とても可愛い時もあれば、物凄く不気味でゾクゾクさせられる時もあり、彼の演技にグイグイ引き込まれました
本作は珍しく是枝裕和監督自身の脚本ではなく、伝説の大ヒットドラマ「東京ラブストーリー」や最近では「大豆田とわ子と三人の元夫」の脚本で有名な坂元裕二さんの脚本、それが先日 第76回カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞し世界中に報道され、同じ日本人の活躍をとても誇らしく思い、勇気をもらえました
是枝作品はあまり私には合わない様で、正直 過去作はあまり好きではありませんが、本作は素直に好きだなと思える作品でした
物事は視点を変えると全く違う世界が広がり、常に見えているものが全てではない
人は物事を上辺でしか見れない
人は物事を自分の尺度でしか解釈できない
人は人に言えない秘密を持っている
人は人に知られたくない秘密を持っている
人は自分の醜い所を知っている
人は自分の卑怯な所を知っている
人は自分の弱い所を知っている
人は常に拠り所を求めて生きている
人は・・・人に愛されたいと思って生きている
“怪物だーれだ“ゲームは外から見ている人が自分の本質に迫ると共に冷静な視点で語り、気づかせ、教えてくれるゲーム
孤独で辛い日々を送る少年2人がこのゲームを通じて相手の内面に寄り添い、共鳴し心通わせていくところがとても痛々しく切なくなりました
そういったそれぞれのキャラクターの性を時系列が行ったり来たりしながらの巧みなストーリー展開で描いていく、心揺さぶられる傑作が誕生しました
是枝監督こそが怪物
是枝監督はヒットメーカーと言っていいのだろう。「誰も知らない」のカンヌでの成功体験がその後の是枝チームの制作スタイルを形成し、子どもと家族をモチーフにした(これは彼のメインテーマなのだとは思うが)ヒット作を出し続ける中で海外を含めてトップクラスの役者やスタッフをふんだんに起用できる彼こそが「怪物」になってしまった。「ベイビー・ブロカー」までは許せるが今作はさすがにやり過ぎで中身のないデコレーション過剰な麻雀でいうところの多牌である。坂元裕二の脚本がやり過ぎなのだがこれに脚本賞を与えるカンヌはまともではない。「羅生門」的な登場人物ごとに視点を変える手法はややもすると技巧に溺れて今作のように「あざとさ」のオンパレードとなる。特に最初の母親視点での学校の対応はあきらかに過剰でこんな演出をするのなら安藤サクラの無駄遣いとさえいえる。唯一良かったのは、息子と病院から出てペットボトルを渡して歩きながら一気に学校での出来事を問い詰める長回しシーン。子ども二人の奥の鉄橋を貨物列車が走るシーンや二人が台風の中奥に行く手前で木が倒れるシーンもあざとくて興ざめる。もっとシンプルで切実な映画が観たい。
脚本賞に納得
これはベストマッチだったのかもしれない。是枝的でありながら、どう見ても坂元裕二の脚本。自分が惚れたのはやはりドラマの構造と散りばめられた会話が繋がるところ。役者は永山瑛太がまたまた良かった。ラストの晴天の中の二人。嬉しく悲しいエンディング。
LGBT的な部分については、あんな子供の頃から自覚するのか、と改めて。控えめながら想像以上に決定的に描かれている。インティマシーコーディネーターが導入されたと聞くが、子役たちに充分なケアをしてもらいたいと思った。
映画ゆえ
最初の早織の視点の第一幕で映画館を出ようかと思いましたが、
最後まで見てよかったです。
結局は、いじめや児童虐待が良くないということになるのでしょうけど、
そこに、人の多様性、幸せ、などのテーマが絡んでいて
楽しめる作品ではありました。
事実が明らかになっていくことや、誰が怪物なのか、推理ゲームのようでもありました。
しかし、心を病んだままの校長を現場に復帰させることや、
教職にある人間が足をかけて子供を転ばせる事、
飛び降りようとしていた担任がなぜか管楽器の音に反応していたこと、
バスタブで体力失ってた子が悪天候の中、自転車も使わずに廃坑まで行ったこと、
などいろいろと疑問点も残ります。
また最後もなんだか悲しくなりました。
個人的には、親達にとってもハッピーエンドにして欲しかった。
考えさせられる作品でした。
怪物だーれだ
母、教師、子供たち、とそれぞれの視点から出来事が描かれる。
冒頭は湊の母に感情移入して、学校側に憤り、徹底した事なかれ主義に気味の悪さを感じたが、時系列がいったりきたりする中で少しずつ出来事のパーツが明かされていき、事件に対しての印象が次々に塗り替えられ、関わる人物たちの葛藤が肉付けされていく。
怪物は、得体の知れなさゆえに嫌悪し畏れる対象のことなんだろう。
それぞれにとってそれぞれの怪物。
依里の境遇に対しては無力なまま、依里との時間を心の拠り所にすごす湊にとっては、コントロールできない自分自身が怪物?
いや、そう思わせる周りの価値観こそが怪物なのかもしれない。
校長は、そんな怪物と対峙しながらいつしか慣れ親しんでしまった人物なのかも。
シングルマザーだから。ガールズバーに教師がいくなんて。適当でいいんだよ。男だろ。普通に結婚するまでは。
あちこちに散りばめられた無自覚な既製の価値観のワードとと、この線から出たら地獄だよ、というなにげない言葉が印象に残る。
誰かじゃないと手に入らないものは幸せと呼ばない、という校長の言葉がその中で力強く救いだった。
怪物探し
鑑賞中、この「怪物」というキャッチーなタイトルに惹かれて怪物探しを誰もがしたことだろう。御多分に漏れず私も怪物探しに没頭して上映時間中緊張感を持続できた.。
映画を鑑賞した際には観客は鑑賞した作品の内容を自分の頭の中で咀嚼し、自分の中でその訴えてるテーマを紐解こうとする。あれはこういうことだったんだ、あれはこうでは、などなど、本作のように暗に示唆するような表現が多用された作品なら尚更だ。
カンヌで賞を取った後の凱旋上映、特に映画好きにとっては外せない作品。鑑賞は気合入りまくりである。特に日本映画初のクィア・パルム賞となれば、当然本作のメインは二人の少年の物語だろう。
まだまだ幼い二人の性に対する戸惑いといったなんとも繊細な描写が見るものを惹きつける。
当然彼らは保守的な今の社会では歓迎されない。父親から虐待を受け続ける依里はとても純粋に見えてどこか危うい感じがする。その彼に惹かれる湊も自分は男らしい人間なのかと、髪を切り取ったりと戸惑いを見せる。
小学生という設定がまた微妙だ。性に目覚めるには幼すぎる気もするし。その点ではなんとも罪作りな脚本だと思う。監督はいったい子役たちにどういう演技指導をしたんだろうか。
結局本作はいろいろすったもんだを散々見せた挙句、ラストシーンは嵐が過ぎ去りまぶしく光る太陽の下、駆け出す二人の映像で終わる。これを見て希望的なラストだと思わない人間はいないだろう。
今なお性的マイノリティにとっては受難が続く時代。誰に迷惑をかけるわけでもない彼らを否定する保守的な権力者が巣食う社会では彼らの未来はけして開かれてはいない。
現にこの国でもLGBT法案が審議中だがその中身は差別を容認するものだ。そんな社会に住む彼らに作り手は希望を持って生きて行ってほしいとの願いからあのラストシーンを描いたのだろう。性的マイノリティーに限らずすべての子供たちへのメッセージとして。
依里が書いた作文の題名は品種改良だった。自分を「人間」にしようと虐待をする父親を暗に皮肉ったのだろうか。
今のこの国では権力者に忖度する官僚やマスコミばかりだ。教育現場も例外ではない。時の権力者が自分たちに都合のいいように人間を品種改良した結果であろう。
やっと怪物を探し当てることが出来た。怪物とは母親の悲痛な訴えに耳を貸さない教師たちではない。担任を陥れた生徒でもない。息子を虐待した父親でもない。怪物とはこの社会に巣食う品種改良を目論む権力なのだと。
それは普段は目には見えない。しかし、彼らがその権力を振るう時、それの脅威にさらされる人間に対してはその恐ろしい姿を露にするのだろう。
目に見えない怪物は今もそこにいることだけは間違いない。
やはりカンヌの脚本賞は伊達じゃない。
さすがにカンヌの脚本賞を取るだけあって、濃密で見応えのある映画でした。
この映画をひと言でまとめるなら『物事は見る立場が違えば見方も変わる』そんなところです。
学校の内外で起きる様々な出来事に対し母親、学級担任、子供という3者の視点からそれぞれストーリーが描かれています。
この映画のタイトルである『怪物』とは関わると面倒で厄介な人、サイコパス的な人を意味しているわけですが、この映画にはそんな怪物と思わしき人物が次々に登場します。
観客は『こいつが怪物か』と見当を付けながら見進めていくわけですが、視点(立場)が変わると『あれ?この人、怪物だと思ってたけど実はまともだな』と何度も見方を覆されます。それがこの映画の肝です。
母親目線で見れば学校が怪物、学校目線で見れば母親や子供が怪物、子供目線で見れば怪物はいない(強いていうならクラスメイト)。
そんな具合に見る立場によって見方が180度変わってしまう。鑑賞後は『結局、怪物は誰だったのか?』と自問自答することになります。
この映画が教えてくれること。それは
『立場が変われば見方も正義も真実も違って見える。ひとつの側面だけを見てすべてを知った気になり、物事の善悪を判断したり、論じたりするのは危険なことだ。もっと多角的な視点で見て物事を判断して欲しい』そんなところでしょうか。
怪物?
ハロー今君に素晴らしい世界が見えますか? ”怪物”はいつも己の内に…。
麦野湊という少年の身に起こった出来事を、複数の視点から描き出していくミステリー&ヒューマン・ドラマ。
監督/製作は『海街diary』『万引き家族』の、名匠・是枝裕和。
脚本は『世界の中心で、愛をさけぶ』『花束みたいな恋をした』の、レジェンド脚本家・坂元裕二。
シングルマザーとして湊を育てる女性、麦野早織を演じるのは『百円の恋』『万引き家族』の安藤サクラ。
湊の担任、保利道敏を演じるのは『アヒルと鴨のコインロッカー』『64 ロクヨン』の永山瑛太。
保利の恋人、鈴村広奈を演じるのは『怒り』『キャラクター』の高畑充希。
港が通う小学校の校長、伏見真木子を演じるのは『もののけ姫』『ゲド戦記』の、レジェンド女優・田中裕子。
第76回 カンヌ国際映画祭において、脚本賞を受賞!
個人的に相性が悪い是枝裕和監督作品。
本作も観終わった直後は「えぇ…。こんな映画なのかよ🌀」なんて思っていたのだが、しばらく時間が経ってみるとこれはこれでアリな気がしてきた。いや、むしろ結構好きな味かも。
とにかく要素が多い上、藪の中に隠すかのような曖昧模糊とした物語だったため、自分の中でもうまく消化しきれなかったのだろう。レビューを書くまで色々と考えさせられた。
本作には一つの物事を多角的な視点で描き出す、いわゆる「羅生門アプローチ」という手法が用いられている。
三幕それぞれに主体となる人物を設定し、その人物の視座から物語を覗き見る。
同じ人物であっても、それぞれのパートでその印象が大きく違うのは視座となる人物の主観が物語に入り込んでいるからなのだろう。
自分は鑑賞前から本作が羅生門アプローチによって紡がれる映画であることを知っていたので、第一幕目が終わった段階で「あぁなるほど。それじゃあ次はああなって最後はこうなるのね」というなんとなくの筋道の予想をつけていた。
その予想は第三幕目で裏切られることになるのだが、その裏切り方というのがなんとも期待はずれで、それが鑑賞直後のモヤモヤ感に繋がってしまったような気がする。
この第一幕目はとにかく面白いっ!!
雑居ビルの火災から始まり、物語は段階的に不穏さを増していく。
湊のイジメ、加害者である絵に描いたようなクソ教師、そしてイジメへの対応をおざなりにやり過ごそうとする学校。生気を欠いたゾンビのような教師たちは何か秘密を隠しているとしか思えない。保利の口から飛び出した信じられない言葉。謎の少年・星川依里の登場。そしてある嵐の日、湊は忽然と姿を消してしまう…。
この謎が謎を呼ぶ怒涛の展開に目が釘付け!是枝作品に物語的な面白さを求めてはいなかったのだが、この第一幕目は文句なしに面白かったっ!✨
このパートの何が良いって、緊張感の走る不穏な展開の中に、意地悪なユーモアが混在しているところ。
学校に詰め寄る早織と校長を始めとする教師たちのやり取りはほとんどコント😂東京03の角田さんを起用しているあたり、この場面のコント感は意図的に演出されたものなんだろうが、最悪すぎる大人の対応には、怒りを通り越して笑えてきちゃうということが上手く表現されていたと思う。
第一幕目がこういう展開だったので、当然第二幕目は保利先生の視点から物語が進行する。
情熱に満ち溢れたその姿、そして綺麗な彼女がいるというリア充ぶりには驚かされたが、まあこのパートの展開は想定内というところ。体裁を気にする「学校」の醜悪さに辟易としながら、「なるほど。結局は”学校”という制度そのものが”怪物”だった、というオチに繋がるわけね😏」なんて思っていた。
プリミティブでイノセンスな少年少女が嘘をつくわけがない。この常識の隙をつくというのが、本作の嫌なところであり、また面白いところでもある。
無邪気な嘘が教師を追い詰める物語といえば、短編小説の名手スタンリイ・エリンが著した「ロバート」(1964)なんかが先行作品としてパッと思い浮かぶところだが、おそらく本作が下敷きにしているのは1980年代にアメリカで起こった「マクマーティン事件」だろう。
息子の性的虐待被害を疑った母親が、その子の通っていた保育園を告発。内部調査の結果、園児の多くが性的虐待を受けていたことを告白したのだが、その後そのような事実はなかったことが発覚。疑念と誘導的な調査が、子供達にありもしない記憶を植え付けたのである。
まぁ本作は保育園児ではなく小学5年生だし、嘘をついた経緯もマクマーティンのそれとは違うので、丸ごとこの歴史的事件を題材にしている訳ではないのだけれど、着想の一つとしてこれを用いたのだろう。
星川くんの純粋無垢な感じ、最初はなんか怖い。アル中の親父から「怪物」とか言われてたし。
となるとこれはあれか?わたなべまさこ先生の「聖ロザリンド」のように、イノセント故に他者を破滅させてしまう魔性を描いた物語なのか?それと”学校”における抑圧と教師たちの事なかれ主義が絡まり合い、強烈なイヤミスが展開されるんじゃないかと思い、この謎めくミステリーの種がついに明かされる第三幕目に胸を膨らませていたのだが…。
結局のところ、この映画は少年の性の芽生えと戸惑いの物語という文学的な着地をみせる。
せっかく豊かな広がりを見せてくれそうな映画が、いかにも是枝裕和らしい美少年のブロマンスに集約していってしまうのはなんとも勿体無いと感じてしまった。
もちろん是枝裕和監督作品にデヴィッド・フィンチャーばりのサスペンスを期待してしまった自分も悪いのだが、「怪物だーれだ?」というキャッチーなキャッチコピーを目にしている以上、そういうのを求めちゃうじゃない。予告編もスリリングだったしさー。売り方が悪いよ売り方がー。
とまぁそんな理由で、鑑賞後しばらくはモヤモヤっとしていたわけだけれど、そういう映画だと割り切ってしまえばそんなに悪い映画じゃない。むしろ、もう一回鑑賞したいかも、くらいには気になる映画になっている。
言葉にすると陳腐になってしまうが、本作のタイトルにもなっている”怪物”の正体は、拡大した自意識や凝り固まったマインドセットなどの、人間が内に抱える観念的なものなのだと言える。
それは自らを閉じ込める檻にも他者を打ち据える鞭にもなる非常に危険なものであり、さらに厄介なことにそれ自体の危険性に人はなかなか気付かない。問題意識もないままに、それに取り込まれてしまっているということも少なくないだろう。
自分の個性は間違ったものであるという考えに毒され、自らを蔑み傷つける湊や依里。そしてその内側の瑕疵から漏れ出た毒はやがて外部をも侵食していく。
その様はまるで「フランケンシュタインの怪物」のようだ。
子供たちに”怪物”を植え付けるものは何か。
自分勝手な価値観に縋って依里を虐待する父親、学校を守るためなら事故死した孫すら利用する校長、保身に走る教師たち、上司の命令に盲目的に従う保利先生、本作の大人たちは全てこうあるべきであるという凝り固まった考えに取り憑かれており、最善だと判断した言動が事態を悪化させていく。”良き”母親である早織も例外ではなく、彼女の常識が湊を深く傷つけることになる。
事故死した孫を引き合いに出し校長に詰め寄る際、彼女が見せた能面の蛇のように冷酷な表情は、世界を「内」と「外」に分けて捉えていることを意味している。
家族という「内」の安寧を脅かすものは「外」敵であるとし、それを激しく攻撃し拒絶する。そのマインドセットこそが”怪物”そのものであり、それが子供たちに伝播していることに、彼女は最後まで気が付かないのだ。
〈あるものをあるがままに受けいれる、と口に出すのは簡単だが、それに身を委ねるのは非常に困難である〉と我々大人は考えてしまう。しかし、旧来の価値観に囚われた保守的な思想/言動は世界の閉塞感を強め、新たなる怪物を次々と生み出していくことを我々は知っている。
「内」と「外」ではない、「正」と「誤」でもない、新しい観念を自分の中に見いだす一助に、本作はなるのではないだろうか。
最後に一つ、本作のエンディングについて触れておきたい。
湊と依里、2人の秘密の場所であり物語の終着点でもある廃電車。2人の少年と電車という組み合わせには、やはり宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を想起させられる。
となると、あの意味深なエンディングで2人がたどり着いたのは彼岸であると考えたくなる。もっといえば、あのバスタブの中で依里はすでに息絶えていた、と考える方が物語的には自然だと言えるのかもしれない。
しかし、これはすれっからした大人の見方なのではないだろうか。
湊の自殺を疑った早織、自殺しようと屋根に登った保利。この時2人が耳にするのはゴジラの咆哮のような、または黙示録のラッパのような奇妙な騒音である。
観客をも不安にさせるこの音だが、第三幕で明かされるその真相は、ただ湊がトロンボーンを吹いていただけだというものだった。
物事をシリアスに捉えすぎる大人と、それを嘲笑うかのように軽やかに遊んで見せる子供。大人と子供の対比が鮮やかに描かれたこのシーンから考えると、やはりあのクライマックスは、心配する大人を尻目に2人の少年が自由な生へと駆け出していっているようにしか思えない。
あるものをあるがままに受け入れる。本作から受け取ったメッセージを、そのままこの作品の結末にも当て嵌めたいと、個人的には思うのです。
全1009件中、661~680件目を表示