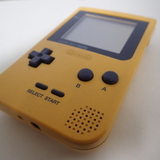怪物のレビュー・感想・評価
全1009件中、461~480件目を表示
認知バイアス
水中の怪物達
例えば、怪物は台風、ライフル。誰だは欠片、アゲハ。火事は愛。母はバカ…のように、水の中では母音が同じなら同じように聴こえる。でも全然違う。
そんな映画だった。
世の中の何かの事象は、誰か一人だけでは成立しないので、ワタシがいてアナタ1がいて、アナタ2がいて、アナタ3がいてと波紋は延々と拡がる。それぞれの視点でみるとそれぞれの波があり、全く同じ波はない。
怪物誰だをするように自分にはみえない答えを相手のヒントで解き明かしてゆく、ヒントをどう読みとるか、そんな映画でした。
観てから少し経つけれどふとした時にあのときの画が思い出され、あのシーンはもしかしたらこういうことだったのかな?と思うときがあります。
そんな映画です。凄いよね。
普通とは
ずっと観に行きたかった映画をやっと観に行けました!
最初ミステリーホラーかなと思って観に行けないなと思っていたのですが、レビューを見るとどうやら私のように思っていた人たちがチラホラい、怖いグロい描写はないと知ったので絶対観ねば!と楽しみにしてました。
物事を一点からしか見れない人があまりに多いこの世の中を表している作品ですごく感慨深かったです。
怪物とは、普通とはなんなのでしょうか?
大人が、世の中が、社会が押し付ける『普通』で怪物扱いされる者。
どちらが怪物か、二面性でもないかもしれないけど。なにが怪物か。その根底のなにかが本当の怪物か。
その無意識に押し付けられた普通に傷つき、苦しみ、恥じて、自分や近しい人を守るためつく小さな嘘。それが大事を起こし、また誰かを傷つけ、多面的に、いろんな世界観で描かれていく。
誰かの世界では誰かが怪物。
途中までは、誰が怪物だ?と犯人探しの気持ちで観ていましたが、それこそ気づかぬうちに自分の価値観で、自分の世界で、誰かを怪物に仕立てあげたり怪物扱いしてしまっているのかもしれない、またその末端の一員になっているかもしれないと感じました。
一言では言い表せないし、自分が感じてる世界は自分だけのものなんだと改めて考えさせられました。
人それぞれの世界があり、幸せがあり、見えてるものも違う。『人それぞれ』なんていう、そんな簡単なものではなく、生きている世界が違うくらいのレベルの違いだ。
それを、干渉しようとするのも、一辺から見るのも分かった気になるのも、すごく浅はかで、ラストシーンの二人の世界観にすごく感動しました。二人が楽しそうならそれでいいのです。
よかったです。
終演直後から記憶は曖昧になる
既に2回見ている友人に誘われ映画館へ
同じ出来事を複数視点で、しかし明確に誰の視点かを区別せず、時系列も絶妙に分かりづらくぬるっと描かれていく。
集団心理や思い込みの怖さという実態のないものを「怪物」とし、描かれたものだと解釈
是枝作品の特徴でもあるが、ドラマティックな展開ではなく淡々と話が進んでいく。
登場人物の魅せ方や、セリフの言い回し、場面の切り取り方が秀逸で、見ている側も気付かぬうちに勘違いや思い込みを起こしてしまう。
湊くん(安藤サクラの息子)が危ない思想の子供であるかの判断材料となるセリフだが
「猫と遊んでいた」か、「猫で遊んでいた」か、記憶が曖昧
私の中でその時湊くんは猫を殺めているが、友人の中でそれは勘違いである
私が作中で見て記憶したものと、友人が見て記憶したものでは少しずつニュアンスが異なる
映画なのでもう一度見て確認したいと思うが、現実ならそうはいかない
もう今の状況が作品に投げかけられた問いそのものにも思える
人と話すことで何倍も面白くなる作品
そこまで分かってるなら救ってくれよ!
Twitterをみてると、この映画がLGBTQをオモチャにしてるとか、傷つくから観ない方が良い、みたいな批判がバズってたけど、僕はそんな風には感じなかった。
子供の頃、女子みたいって揶揄われた事とか、親に本当の事を伝えようとしたけどTVに映るゲイタレントを「気持ち悪い」って言ってるのを聞いて伝えられなかった事とか、色々思い出して心がグッてなったけど、「消費されてる」なんて感じなかった。
寧ろ、何が奏や星川くんを追い詰めていったのかが緻密に、的確に描かれてて、こんな風に自分達と同じ目線を描いてくれるんだなって感覚の方が強かった。
でもだからこそ、描いているモノのリアルさに比べて、ラスト(救い)が抽象的すぎないか、という戸惑いもある。
この映画のラストは、湊たちが生きてるのか死んでるのか、どう捉えても正解な作りになってる。だって、他人が思い込みで誰かに、こうなんだよって言えないって事がこの映画のテーマなんだから。
だからもし、今まさに問題に直面してる人がこのラストをネガティブに捉えてしまわないかって考えが頭の片隅にあって、手放しで絶賛できない。
この映画が「答え」じゃなく「問いかけ」に重点を置いてるのも分かるし、多くの人に観てもらうためには効果的なのも分かるけど、ラストだけは大勢の観客の為じゃなく、今泣いてるたった1人の誰かのために作って欲しかった。
少なくとも、現実的な救済(解決策)を1つでも良いから描いて欲しかった。
校舎の屋上から下を眺めてた当時の自分がこのラストをみても、明日を頑張ろうとはならなかったと思う。
今、自分は大人になって少なからず理解してくれる人がいるけど、学生で同じ様な問題に1人で直面している人達にとってはかなりキツいんじゃないだろうか。
でも、そういう人は必ずいる。ってか居ないはずがない。湊みたいに、なんで自分は生まれてきたのって、人が望む幸せは絶対に手に入らないのにって苦しんでる人が。
だから、そういう人に伝えたい。
そんな事はないよって。
止まない雨なんて絶対ないって。
嘘だって思うかもしれないけど、今抱えてる苦しみは必ず和らぐ時が来る。
誰にも言えなくて、苦しくて、もしかしてずっと自分は1人ぼっちかもしれないって不安に押しつぶされそうになってる人がいたら伝えたい。
諦めないでって。
大人になって世界が広がれば、貴方を理解してくれる人が必ずいる。あなたの味方になってくれる人が、あなたのことを信じてくれる人が。
だから、あなたのままでいて欲しい。
願わくば子供が、なんで自分は生まれてきたの、なんて悲しい事を言わなくてすむ世界が、2人が駆け抜けた、晴れ渡った柵のない世界が、少しでも現実に近づきますように。
非常にいやらしいラスト
誰が「怪物」なのか想像しましたが、決め手になるような登場人物はいなかったように感じました。日常の中の非日常を描いたヒューマンドラマという映画でした。
ラストの少年2人が走り出すシーンはポジティブ・ネガティブ両方の解釈がとれると思いますが、個人的には2000円払って2時間映像を観るわけだから、最後に「観客に丸投げ」というのは腑に落ちない気持ちになりました。
是枝監督の作品は『ベイビー・ブローカー』から初めて見て『万引き家族』は未観賞ですが、疑似家族や「普通」じゃない家族といった異質な集団に脚色を加えるのが好きなんだと今作で感じ取れました。
今作でもシングルマザー・ファーザーという普通じゃない家庭環境で育った少年と教師が周囲を引っ掻き回す演出で、台詞に知性を持った大人がいないように感じて違和感を覚えました。
学校の場面でも見苦しい場面が多くて、校長が麦野少年にホルンを教えるシーンでも俯瞰して見ればただのストレス発散と読み取れるシーンに見える。教師というより近所おばあさんという印象でした。
知性を持たない人物がいないという点では登場人物全員「怪物」と解釈してしまい、リアリティに欠ける映画。
ただただ先生がかわいそう
怪物だーれだ。
怪物です。是枝裕和監督×坂元裕二脚本とくれば、見ないと!という作品ですが、
カンヌの受賞で普段映画を見ない層にも訴求したらしく、映画館は盛況でした。
小学生の兄妹を連れたお母さんとか、後期高齢者と思しき女性の二人組とか、珍しい観客がいました。
受賞については、クィア・パルムを受賞したということが、若干ネタバレやんとは思いつつ(もともとのあらすじではその要素は出てなかったから)、性的多様性においては、遅れている日本の作品が、クィア・パルムを受賞したというのは、寿ぎたいでき事でもあります。
また、数々のドラマでその脚本に慰められてきた坂元裕二の脚本賞受賞は、非常にうれしく思いました。
さて、作品自体については、以下のようなことを思いました。
坂本さん、また主要人物をクリーニング屋勤務にしてはるwww(woman、最高の離婚)
出演者が是枝映画の常連というよりは、坂元ドラマの常連が多い
形式が、「藪の中」である
※芥川龍之介の小説「藪の中」をふまえて、関係者のいうことが食い違って、真相がわからないことのたとえ。by故事俗信ことわざ大辞典
湊の母目線、保利先生目線、誰の目線かわからない3つ目の目線とを総合して、以下のように自分の解釈を記しておきます。
湊と依里は、性的に惹かれあった。
依里は父親に虐待されており、父親の言う病気とは、はじめは鏡文字を書くことから学習障害?発達障害?と思っていたが、恐らく同性愛傾向、男らしくないこと、を指していたのでは。
父親の暴力から、依里はだいぶ傷ついており、父を殺すため多分ガールズバーを放火した。
湊は、自分の同性愛傾向に戸惑っている(依里はそこまで戸惑っていない感じがした)。
母親は、シスジェンダー・ヘテロ的『普通』以外が思いつかないので、湊が結婚して子供ができるまで、などという明るい将来の定義にて、湊を苦しめている。
湊の父の死因は、どうやら不倫旅行中の事故らしく、そのことをないことにして(湊に知られていることを母が知ってるか不明)父を慕うよう促す母への同情というか、愛情もみられる。
依里と仲良くすることで、いじめを避けたい、でも依里へのいじめへ加担することへの罪悪感も強い、またテレビや親・大人の言動から、同性愛者の幸せが見えなくて、それを選べない。混乱の極みによって、走行中の自動車より落ちることになる。
多分、同級生の漫画を読んでいた女の子は、湊と依里にいじめっ子といじめられっ子という見せかけ以外のことを感じている(から、猫のことを保利に伝えた?)。
依里はわざと鏡文字を湊の母の前で書いて、作文に混ぜた暗号のようにして、目の前の大人を試した。
秘密基地の電車の中での結末は?
二人が死んだとの解釈もできるが、車体から出てどこかで夜を明かし、雨が止んだあとの森で、二人が楽しく走り回っていたと解釈したい。
自由に思うままに生きることができると思いたいから。
大人については、湊母、保利、校長以外の教員、依里父は特筆すべきところはない。
私が湊母で、保利で、教頭や2年生時の担任だったとして、彼らとは違うもっと“よい”、“適切な”言動ができたかわからない。違うことができたとして、それが誰かを傷つけないともいえない。わたしも生きた分、偏見を積み重ねて暮らしてるから。
謎が残ったのは、校長。
孫の死因はじつは校長自身が起こしたという噂について。
湊母がみた、スーパーで走る他人の子どもへの足ひっかけ。
湊母の申し出に対する対応の不味さ、考え方(ほんとのことなんてどうでもいいんだよ、と言っていたと思う)。
恐らく逮捕された夫とのやり取りと折り紙。
湊にトロンボーンを渡したやり取り、一部の人にしか手に入れられないものなんて幸せじゃない、的な発言。
結局分からなかったし、解釈することもできなかった。
田中裕子を配したのだから、初対面の観客が簡単に解釈できるような人物にはしないよね…というね。
人のことをまるっと理解できるというのは、有り得ないから、これでいいのかも。
でも、なんらかの解釈しないと先に進めないから、偏見を積み重ねるしかない。
ので、怪物だーれだ、の答えはわたし、であり、あなた。
トリッキーなシナリオ
是枝監督がデビュー作以来久々に自作以外のシナリオで演出。ビル火災を目印に、母親が見たもの、教師が見たもの、そして少年が見たものを種明かし的に据える3部構成となっている。
1部と2部はシナリオに沿って、是枝作品としては性急な感じもするが、3部の少年どうしの交流をじっくり描くあたりは、真骨頂を発揮している。
坂元裕二のシナリオは、「羅生門」というより「カメラを止めるな」を思わせるようなトリッキーなものだが、カタルシスを与えるものではなく、ところどころ「あれは何だったの」とすっきりしない点は残る。作品全体として、事柄は見方次第で変わる、ということを描いているのだろう。
大仰なタイトルのせいもあり、「怪物とは何か」ということに引っかかる。それは大きく言えば、「自分」であり、「他人」であるのだろう。ただ、意外だったのは、「お父さんのようにはなれない」少年の感情を描いていたこと。今どき特にセンシティブな題材であり、そうした感情を(少なくとも少年自身が)怪しく恐ろしいものとみなしていることを、どう見るか。カンヌでは、そのあたりどう評価されたのだろうか。
役者陣では、まず、安藤サクラが魅せる。永山瑛太は、ちょっとズレた感じがいい。そして何より、少年二人の存在感。二人だけのシーンは、観ているだけでどきどきする。高畑充希と中村獅童は、ちょっと浮いていたかな。
見終わった後、誰かと語り合ったり、もう一度最初から見返したくなるが、それもまた作者たちの狙いなのだろう。
映画の終わりの先がどうであれ
2人が仲直りしてまた会えたことがよかった。
大人の目線で見ると2人がどうなったかとか、生きてても亡くなっていてもと、考えてしまうことはたくさんあるが2人にとってはあの瞬間がハッピーエンドだと思う。エンディングで流れる坂本龍一さんのaquaからもそう感じた。
まさかの
ボーイズラブ?
ちょっと空いた時間、私は公開されたばかりの某DCを観たかったのだが、
妻の希望に従ってこの作品を選択。
私も予告編を観て興味は引かれたのだが、何しろ是枝作品とは相性が悪い。
また、カンヌをはじめヨーロッパの映画賞とも意見が合わない。
不安を抱えての観賞だったが、それは的中してしまった。
どうにもすっきりしない。
冒頭に書いたような一時的な感情というのは思春期にありがちなはずで、
それを過度に誇張して今はやりの風潮に繋げようとするのは作為を感じる。
また、それに対する父親の行為も過剰で異常、逆にしらける。
女子たちも何か思惑ありそうだが、よくわからない。
学校の対応も大仰ではあるが、現実として存在するだろう。
だが、それが田中裕子演じる校長の背景と絡んでわかりにくくなってしまっている。
あっちこっちに話が飛んでどれも中途半端、伏線回収していそうでしていない。
疲れもあって途中で眠気が差してしまい、余計訳がわからなくなった。
こういうのがカンヌ向けのゲージツなのかな。
やっぱりゲージツは私には不向きだ。
単純明快なのがいい。
線が繋がらない
伏線を多く張り巡らされており、後半で回収されるという展開だったと思いますが、やはり湊が、保利がいじめをしているという嘘をついた理由と、途中湊が車から飛び降りた理由が自分の中ではピンとこない。
あとは、映画の予告で怪物は誰だ?という形でされてましたが実際は明確に誰が怪物ということはなく、みんなに怪物要素があるということだった。これは予告のミスリード。わざとミスリードにして、思い込ませるということだったのかもしれないけど少し拍子抜けだった。
怪物だーれだ、の意味を知った時怖気がたった
怪物。そのタイトルが、この作品をむずかしくしている。
怪物だーれだ、それはこの物語の中にいる怪物を探す言葉じゃない。
それに気づくまでに時間がかかった。
だれが悪なのか、親なのか先生なのか学校という組織なのか、子供なのか。
見ていくうち、ずっと違和感があった。
ミッドサマーを見ていたときに感じたものと同じようなもの。
何かがおかしい。どこがおかしいのかわからない。こわい。
常識のない行動をする人、組織と闘うこと、チャッカマン、泥水の入った水筒、不可解な行動。
一方向から見ていると真実が見えない。
二方向目、三方向目。
誰かの正義、自分の見たいもの。
全てのことに意味があるのに、ここまでしないと見えない。
自分の見えている情報で相手にヒントを出し、"怪物"を当てさせるのはむずかしい。
同じ価値観でないと。
同じ人間ではある、でも、それぞれの立場が違うとこんなにも見えにくくなるのか。
わたしの信じている普通って、なんだろう。
静かにエンドロールが終わった時、真っ先に感じたのは自分に対する怒りだった。
理解があるほうだと思っていた。
"普通じゃない"、ことに。
だけど、今はっきりと深層心理で何も理解していない自分が分かった。
逆転現象が起こっても、状況は何も変わらないことを子どもたちは知っている。
ただ、
おもしろくない、意味がわからない作品と片付けないでほしいと思う。
問題を出されて、考えるのはわたしたち。
答えを出すのは、わたしたち人間。
怪物だーれだ。
あなたから見える怪物はどんな形をしている?
怪物って誰のことか。。
タイトルなし(ネタバレ)
私が見えているものなんて私の感情でしか作られない。誰かを可哀想な人や悪者にするときに思わなきゃいけないのは、それが全部私の気持ちだけで作られたものだということに自覚を持つことだ。どんな物語だってそう、悪役には悪役の正義がある。みんな自分を守りたいしそのために誰かを責めたい。映画を見てる私が怪物になっていたと、観終わってから自覚する。誰かを悪者にして怒りをぶつけるのは簡単だけど、全部は知るところから始まりたい。許すことも許さないことも、信じることも諦めることも。私には、どんな事情でも受け入れる覚悟と、知る勇気が必要だと知った。人のままならなさ、報われなさ、わかってもらえない悲しさを抱えながら、それぞれに大切なものがあり、それを守るのにどうにも必死で、自分の大切なものだけは、それだけは守られますようにと、登場人物の全員が思っていたと思う。それが他人なのか、自分なのか、そこで生き方が変わってしまう。この映画一本から、自分が向き合うべき対象がいくつも浮かび上がって、何にここまで心を震わせられたのかと一言では説明しづらいほどの濃密さだった。まだしばらくこの映画について考えると思う。でももう二度とこの映画を「初めて観る時」には戻れないのが悔しい。できるなら何度でも、初めてこの映画を観たい。
全1009件中、461~480件目を表示