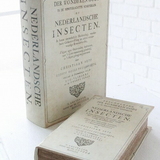正欲のレビュー・感想・評価
全292件中、101~120件目を表示
圧倒的マイノリティの「推し」
昨今話題の「推し活」は「推しが尊い」のはもちろんだが、「推し活仲間」こそ真に尊いのではないのだろうか。自分の考え方感情を共有共感し、共に楽しみ、語り、笑い合える。
そんな心の底から分かち合える仲間が1人でも見つかれば、なんでもない毎日が輝いて感じる。明日も生きたいと思える。
マジョリティにしたい、なりたいわけでは無い。
けどやはり1人ぼっちは寂しい。
クライマックスの言葉が刺さります!
マイノリティの方たちの生きにくさは、大衆の私には分かりません。
だけど、多様な嗜好や考えの人がいることは、受け入れたい。
この映画は、そういうマイノリティを中心に置いたもので、まさに今の時代の私たちはどう考えるのかを問題提起したものだと思います。
昭和の人は、昔は上からの強制に耐え、今はZ世代の人たちの理解をしなければならない的な風潮で‥昭和の人たちはいつまでも間に挟まれて大変なのよね😅とかも思いつつ
それは置いておくとしても
水に官能的な刺激を受流という設定は、ある意味とても美しい情景にも見えました。
ちょっと思うこともありますが、このクライマックスのために(無理くりでも)必要だったのでしょうね。
マイノリティの中のマイノリティ
小説読みかけだったけど、序盤にダイバーシティなんてマイノリティの中のマジョリティのためのものにすぎない、といった記述があってすごく納得したのを覚えている。
世のDEI活動は女性、LGBTQ+、障がい者とかに割と集約されており、もちろんそれが最早マジョリティであっても未だ根深い差別や無配慮が残ってるからこそ声を上げ続けないといけないのだろうけど。声を上げることすらできない、自分を肯定できない、自分だけが世の中と違うと悩んでる人は見過ごされてるんだろうなとよく思う。
水フェチ自体はそれほど隠すことでもなさそうだけど。。周りにはそう思えてもその真髄までは理解されないという気持ち、人と違う負い目がシャットダウンさせるのかな。水見てるの好きなんですよー、と軽く誤魔化すことすらできない何か特別な神聖な思い入れがあるのか。もしくは水を見て体が興奮しているのを見られたら子どもなら容赦なく攻撃しそうだし、そんなトラウマもあるのかも。
そしてそんな特別な「違い」がなくても、昔の同級生に会いたくない、自分の思いや自分が誰であるかを説明できない、別に生に執着はない、そんな辛さはわかる気がする。たまにそんな時がやってくる。無邪気に同窓会に誘ってくる人たちはきっとちゃんといつでも自分を語れる、胸を張れる生き方をしてるんだろうなと思うし、そんな人たちが行きたくない、今は誰にも会いたくないという心の闇を理解できないのもよくわかる。
人のことを分かった気にならないで。決めつけないで。それだけで救われると思うこともある。そんなメッセージを自分なりに消化しました。
見えない価値観
多様性にも含まれない人たち
地球最後の男。
検事の寺井は典型的な保守的人間。息子が学校へは行かず、YouTube動画を始めたいと言っても、頭ごなしにそれを否定する。
「普通」から道を外れた人間は負け癖がついて自分が楽な方へ楽な方へと行きたがるものだと、まったく息子の気持ちを理解しようとはしない。
おもちゃを散らかしっぱなしの息子にしつけをしない妻も息子を甘えさせてるだけだとして彼らの話に真剣に耳を傾けない。
水がほとばしる様に快感を覚えるとして罪を犯した人間の記事を見せられても彼の「普通」では考えられないこととして同じく頭ごなしに否定をする。自らの固定観念に縛られて、その範疇からはみ出すものはすべて理解できないものとして。
寺井のような人間が今の社会ではいわゆる主流派と呼ばれる人間ではないだろうか。個々人の個性やそれぞれが持つ嗜好を理解しようとはせず、画一的視点でしか人間を判断できない。彼らが考える常識や普通からはみ出すものは彼らにとって理解できないという理由で全力で排除しようとする。
寺井がただの一般人ならばさほど問題ないのかもしれない、しかし彼は行政権の担い手である検事なのだ。彼のような価値観で行政権力を行使することがどれほど個人の権利を侵害することとなるか。
最近話題だったLGBT法案。結局議論もろくに進まずに骨抜きに終わってしまった。権力の担い手たちが個人の権利を尊重できない国ではマイノリティーの人々は生きづらい。彼ら保守的な人間にとってLGBTQの人々は理解できない存在だからだ。
しかし近年、LGBTQの人たちが声を上げ始めた。自分たちの存在を理解してもらおうと街中でデモ行進を行ったりと。これは大変な進歩だと思う。
かつては自分の性的嗜好を誰にも理解してもらえず一人苦しんでいた頃に比べて。それが同じ嗜好を持つ者同士がネットワークを築き、孤独の苦しみから解放されて勇気を持てるようになった。自分の気持ちを世間に対して主張できるまでに。
SNSもこれに大きく寄与したことは確かだ。この広い世界で自分と同じ境遇の人間を探し出せるツールとして。自分をわかってくれる人とのつながりを感じることで自分は孤独ではないとを実感できた。これは大きな救いになったと思う。
引きこもりの寺井の息子も動画をやることで自分が孤独ではないことを知る。そんな息子を応援してやりたい母親。だが、寺井にはSNSの弊害にしか目がいかない。息子にとっては世界と通じ合えるSNSが寺井にとっては得体の知れない危険な人間と遭遇するというデメリットしかとらえることができない。
確かに幼児性愛などの危険な嗜好を持った人間がいることも事実だ、だがそうだからと言ってSNSのすべてを否定する根拠にはできないだろう。
夏月と佳道もけして他人には理解されない嗜好を持っていた。誰にも自分たちを理解してもらえない、地球で一人孤独に暮らす異星人のごとく孤独感にさいなまれて自死を考えるほど追い詰められていた。そんなお互いを理解し合える唯一無二の者同士が再会し、共にこの地球で生きてゆくことを決意する。
誰よりも孤独だった二人はかけがえのない理解者を手に入れた。それは二人にとって何よりの幸せだった。
同じ嗜好を持った人間同士でネットワークを築こうとした矢先、佳道は児童虐待の嫌疑で取り調べを受ける。
担当するのは寺井である。寺井にとって幼児性愛者と佳道、そして大也は同じに見えてしまう。彼には理解できない存在として。
佳道や夏月の言うことが理解できない寺井。彼は二人の気持ちをなぜ理解できないのか。なぜ息子と妻の気持ちを理解できないのだろうか。
できないのではなく、自分の固定観念に縛られて理解しようとしないだけなのではないか。
孤独だった佳道と夏月はかけがえのない伴侶を見つけた。もうひとりではない。けしていなくならないからと夏月は佳道に伝える。その言葉を聞いて愕然とする寺井。
固定観念に縛られて生きてきた寺井は妻と息子に去られていまや孤独の身だ。自分が当たり前だと思っていた、自分が主流派だと。
しかしそれはいつか逆転する時がやって来る。自分の信じていた常識や普通が通用しなくなる日が。
いまや個人の権利、価値観が尊重される時代。古い価値観に縛られて個人の感情を否定する時代ではないのだ。あってはならない感情はこの世にはない。
かつて寺井の信じた価値観は通用しなくなり、マジョリティーと思っていた自分がいつしか気づけばマイノリティーになっているのだ。そうして時代は移り変わってきた。
接見室から出ていく夏月、その夏月を見送り一人部屋に残された寺井の姿が閉じられるドアで見えなくなるラストシーンはとても印象的だった。
作家のリチャード・マシスンの「地球最後の男」は突然変異で吸血鬼となってしまった元人類たちとたった一人で戦い続ける男の物語だが、実は吸血鬼たちこそが新人類であり、ひとり人間として吸血鬼たちを殺し続けていた主人公こそが伝説の怪物として新人類から恐れられる存在だった。いつしか自分は主流ではなくなっていたという皮肉な物語。
古い考えにとらわれて気づけば世界はがらりと変わり、自分一人が取り残されていた。寺井のような人間こそが地球最後の男になるのかもしれない。
試してみようそうしよう
面白くなかったのは多分キャスティング
濡れてない濡場
眼の前の者を理解する
わかるとは何か
原作を読んだ後だと物足りなさ過ぎる
稲垣吾郎、磯村勇斗、ガッキーというキャストで何とか最後まで見れたけど作品としてはイマイチな感じでした。大学生のところもちょっと話を端折りすぎてるからよくわからないし。
改めて映像化されてみると、水フェチは人には言えないし親や周りから彼氏は?結婚は?子供は?と言われて苦しいけれど、まぁ簡単に手に入れられるし相手(水)に感情もないし犯罪とは無縁だよなぁ
小学校の教師で男児が性的対象で嫌がってるのに…は完全に犯罪だし。
真っ当なはずの稲垣吾郎家族もガタガタだし。
幸せって難しい
これが王道の恋愛映画と括れる時代までどれくらいの月日が必要なのだろうか。
非常に有意義な2時間強だった
現代的なメッセージ性が非常に強い作品だが、まず「物語」として純粋に楽しめた。
終盤の検事×夏月の静かで熱いバトルシーンに見事に凝縮された本作のテーマが
斧で殴られたのではなく水のように身体に(脳に)スーッと入り込めた感覚が素晴らしく
鑑賞後は清々しい気持ちになれた。
勧善懲悪な描かれ方ですが、検事は別に悪(意のある)人では無いんだよな、、、そこはもどかしい。
事実、無性愛者が世の中には非常に少ないが(当方、否定的では無いので悪しからず)
そのような人が中学のクラスに2人もいること、その2人がお互い同じ人種であることを認識できていることがまず奇跡に等しい
その2人が大人になり再会して、手を組む選択肢をとったこと、お互いがかけがえのない存在となったことは奇跡中の奇跡
ただ夏月と佳道、お互い恋愛感情が生まれないのを最後まで貫かれていたのは良かった。
私は本作をひと言で申し上げると「素晴らしい作品」だと思いました
しかしそれはガッキー×磯村くん という誤魔化しようのない顔立ちの綺麗な御二人が演じているから
作品が美しく思えるように感じます。まあ映画はエンタテインメント作品ですからね。
これが等身大の俳優さんでしたら傍観モードになってしまっているかも。
あとビジネスとして成立しないと思いますから正解です。
褒めてるんだか貶しているんだか分からないレビューですが
間違いなく観て良かった。あとVaundyと気付かず聞いていた主題歌が良かった。
さすがVaundyと思った。
もう一度言うが、
これが王道の恋愛映画と括れる時代までどれくらいの月日が必要なのだろうか。
朝井リョウ原作の見事な映画化!
何を持ってノーマルなのか?そんな人居るのか?
こういう題材でこれだけメジャーな人達集めて映画化出来たことは高く評価できる、まあ時代という事かな。
吾郎ちゃんのようにちんぷんな人、まだ居るのだろうか?同性愛は非生産的だって言ってる人が議員やってる国だもんなぁ。きっと閉鎖的な組織や地域に山ほどいるんだよね、そんな人が間違ってこの映画みちゃったらどうなるんだろうなぁ?ぜひレビューを見たいと思う。
少し無理かんじたのは水フェチ、ジャンル的にメッシーかな、、別に何の問題もないのよ、悩みすぎだよ。
ダム破壊して皆んな溺死したなかでセルフしたいとかじゃなけれは大丈夫。まあこれは原作の問題かな。
小児性愛(これあかんヤツ、思っててもやったらダメ)に間違われて捕まった2人の早期釈放をのぞむ。
吾郎ちゃんはよ気づけ。
「無くて七癖」というように誰にでも何らかの癖や拘りはあるもので、それが性癖につながっているかどうか、、またそれに気付く客観性を自身が持っているかどうかが分かれ道。
「一人一人みんな違って皆んないい」どっかの歌にも有りましたが1人として同じ人は居ない訳ですから犯罪になる性癖以外は自分に自信を持って生きましょう。
webが必ず仲間を見つけてくれます。
一人一人が違う事が当たり前の世の中に早くなりますように。集団で助け合い、社会を形成して生きなければならないとしたら、お互い違う事を認め合うしか方法が無い事をはやく皆んな知るといいな。
Yolo.
地球の真ん中にいる感じ
性欲ではなく正欲
いわゆるフェティシズムをテーマにした物語と捉えたが、拡大解釈すれば多様性についての物語、マイノリティの苦しみ、孤独を描いた物語という風に捉えることも可能だと思う。あるいはサブキャラに着目すればまた違ったテーマも見えてきそうである。本作は色々な切り口で語ることができる作品のように思う。
登場するエピソードは全部で3つあり、一つ目は特異なフェチを自認する男女、佐々木と夏月が運命的な再会を果たすドラマである。二人には過去の思い出がありそれが時を経て蘇るという、ややメロドラマめいたストーリーであるが、実際にはそう楽観的に見れる内容ではない。周囲からの疎外感、孤立感に苦しむ両者に焦点を当てながらシリアスに展開されていく。
二つ目は正義感の強い検事寺井のエピソードである。不登校の小学生の息子、妻との冷え切った関係を描くホームドラマを、インターネットの弊害やそれに伴う犯罪を絡めながらシビアに描かれている。
三つ目は、過去のトラウマから男性恐怖症になった女子大生がイケメンのダンサーに惹かれる恋愛談である。
夫々のエピソードは終盤で数奇な結びつきを見せるが、ここで最も重要となるのはやはり一つ目のエピソードであろう。ここを土台にして他の二つのエピソードが展開されており、終盤で夫々が相関することで社会の価値観、既成概念に対する疑念の目が観客に問題提起という形で示される。
それはつまり、世間一般の物差しでいう所の”普通”とは何なのか?”普通”と”普通でない”ことの差にどれほどの意味があるのか?といった問題提起である。
また、本作を観て橋口亮輔監督が撮ったオムニバスコメディ「ゼンタイ」という作品を連想した。そこには全身タイツフェチの同好会が登場してくるのだが、周囲の奇異の目をよそに彼らは仲間同士で案外楽しくやっていた。
本作の佐々木と夏月も同行の士として関係を深めていく。他人に理解を求めるでもなくひっそりと寄り添って生きていくその姿は実に健気で切なく観れた。
そして、ここが興味深い所なのだが、フェチというとどうしても”性欲”と混同してしまいがちだが、本作の佐々木たちも「ゼンタイ」の人達も性的な欲望を持っているわけではない。彼らは他人とは違う自分の存在意義、アイデンティティを保つために、同じ”癖”を持つ者同士で繋がっているだけなのである。人が生きたいと願う欲望。つまりこれがタイトルにある「正欲」と繋がるのだが、自分はこういう形で嗜好を持つ者もいるのか…と認識を改めさせられた。
岸善幸監督の演出は抑制を利かせたタッチで上手くまとめられていると思った。特に、佐々木、夏月を演じた磯村勇斗と新垣結衣の繊細な演技が素晴らしく、おそらくこのあたりには監督の演出意図も大いに寄与していたのではないかと推察する。
その一方で、ベッドの上の夏月が水に侵食されるシーンなど、陶酔的な映像演出も時折見られ、これも中々面白いと思った。
そして、最も印象に残ったのはラストカットの切れ味の良さである。この突き放すような終わり方は実に潔い。
佐々木と夏月が直に面と向かって再会するドラマチックなシークエンスにも上手さを感じた。その後二人はホテルに入るのだが、この大胆な省略の仕方には唸らされる。
一方、残念だったのは三つ目のエピソードである。他の二つのエピソードに比べると描き方が浅薄という感じがしてしまった。ヒロインがダンサーに惹かれる理由が分からず、その顛末についても今一つスッキリとしなかった。他のエピソードに比べると中途半端な扱いだったのが惜しまれる。
全292件中、101~120件目を表示