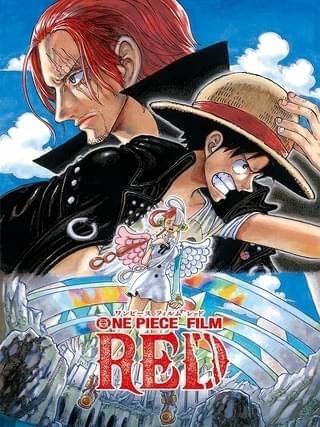炎の少女チャーリー : 映画評論・批評
2022年6月7日更新
2022年6月17日よりTOHOシネマズ日比谷ほかにてロードショー
再映画化は原作の軌道を離れ、逆にカタストロフの筆致へと迫る
パイロキネシス(念動放火)を持つ超能力少女の、過酷で苦衷に満ちた逃亡劇、じつに38年ぶりとなる再映画化だ。
だからって、なにも邦題まで受け継がなくても……と感じる人はいるだろう。だがタイトルが同じでも中身は違う。小説のプロットに忠実だった1984年の「炎の少女チャーリー」とは対照的に、本作は序盤でスティーブン・キング原作らしい錯時構成を共有しつつ、広く知られたストーリーに「おおっ!」と前のめりになるようなアレンジが加えられている。一部キャラクターにおけるジェンダーの入れ替えや設定づけの過激化に始まり、ストーリーの後半そのものが大きく軌道を外れていくのだ。なにより84年版は原作に従属することで、全体的に間伸びした印象を与えたが、今回はよい意味で見通しの利かなさと意外性が、観る者の驚きを持続させてくれる。

逆に経年なりの技術的な発達が、キングの巧みな筆致で綴られた炎のカタストロフィな描写に迫り、こちらは原作のテイストにより近づいたものといえるだろう。加えて怒りを大きな助燃性とするチャーリーの能力は、迫害や差別といった圧がそれを高める起因となって、観る者の共感を誘引する。そのために学校でのいじめやメディアスクラムといった要素が大きくクローズアップされ、はからずもそれがジェイソン・ブラムのプロデュース作らしい、社会へのシニシズムに満ちた視線へと通じていく。ドリュー・バリモアの可愛さ一点張りだった先代チャーリーに比べ、ライアン・キーラ・アームストロング演じる彼女は大人への不信を全身からにじませ、膨張する憎悪が表情を経て観客を射抜く。その様相はまさしく“炎の少女“だ。ここにきて、なんたる邦題の正当性よ!
まるで旧作に親でも殺されたかのようなディスりっぷりだが、タンジェリン・ドリームによる無機質なシンセサイザーのサウンドに乗り、巨大な火球がボンボンと放たれていくクライマックスなど個人的に嫌いではない。だが抑制を失ったチャーリーの猛火が周囲を容赦なく延焼させ、それをジョン・カーペンターのスコアが盛り上げるさまに「これこそがオレの望んだ「ファイアスターター(原作タイトル)」だ!」と高揚させられては仕方あるまい。もともと氏は84年版を監督する予定だっただけに、こうして捻りを経ながらの関与には感情レベルで涙を禁じえない。しかもカーペンターの作品でも観ているかのようなフレーズが全開で、カッコよすぎてこっちが勢いよく燃えそうだ。
(尾﨑一男)