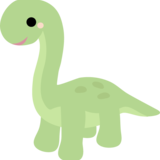聖地には蜘蛛が巣を張るのレビュー・感想・評価
全91件中、21~40件目を表示
イランの聖地で起きた娼婦連続殺人と世界の繋がり
実話に基づいた映画
映画が作られる元の話は、2000年から2001年のイラン第2の都市であり、シーア派の聖地でもあるマシュハドで起きた娼婦連続殺人事件である。16人の娼婦が犠牲となった。この事件を題材にした映画はこれが初めてではなく、「キラー・スパイダー」という映画が既にあった。この映画の製作者は今回映画を盗作だと主張しているらしいが、鑑賞する側としては、別の視点で事件を見ることが出来るので歓迎だ。
事件の背景に宗教の聖地の保守的な雰囲気
殺人の対象はすべて娼婦であり薬漬けにまでなっているものもいる。そんな彼女たちを殺して「浄化した」と新聞社に事を起こす度に通報するという行動に彼になかにある歪んだ正義感、偏狭な世界観が浮かび上がる。街を恐怖に陥れた事件だとしているが、犯人の行動パターンは知れ渡っており、犯人を英雄視する雰囲気があり、それが逮捕後に大きな運動となる。この映画は「イラン政府への批判でも、腐敗した中東社会に対する批判でもない。一部の人達、中でも女性に対する人間性の抹殺は、イランに限ったことではなく、世界中のあらゆる場所で起きている。(映画の公式HP日本版「『聖地には蜘蛛が巣を張る』が描くもの」より)と説明しているが、当のイラン政府がそう理解しないことが想像できる。実際、イランの文化・イスラーム指導省の映画機関は、カンヌ国際映画祭が本作に女優賞を授与したことを「政治的な意図を持った侮辱的な動き」と非難する声明を発表したとのことである。
本当の驚きは最後に
ストーリーは殺人犯は誰かというようなものではないし、犯人とそれを追うジャーナリストの駆け引きというようなサスペンスでも全くない。だから殺人事件の犯人が捕まって終わり、ではない。映画の展開は後半になるほど目まぐるしくなる。犯人の有罪が確定してもまだ終わらない。最後が女性ジャーナリストが取材を終えて現地から離れた後なのだ。
近年には稀な生々しい殺人の描写
殺人犯の残虐な殺人の様子が生々しく描写されている。なぜここまで残酷なシーンを見せる必要があるのか。オカルト映画的な表現もある。事件の残忍性を伝えるための描写とする評論もある。その生々しい描写が映画の最後に見事に繋がるので、最後まで見放せない。宗教の聖地だからこそ起きた事件なのか欧州の国は時に「表現の自由」を振りかざし、ムスリムとの摩擦を引き起こす。ムスリム女性の人権が十分に尊重されていないという問題は存在しないとはいえない。しかしながら筆者が想像するに、イラン・イラク戦争後のイランでこのような事件が起きる環境を作ったのは、イランだけに責任のある問題とは言えないのであるまいかと思うのである。約10年に及んだこの戦争で、国は疲弊したはずだし、多くの男性兵士が犠牲になったであろう。当然、その兵士には家族があり、家族にとっては大黒柱を失ったことだろう。ただでさえ米国の経済制裁により一般の市民の生活も楽ではないはずだ。そのような遺族の生活はどうなるのか。
遺族が救済されない理由とは
イスラムは一夫多妻制が認められているので、男性は未亡人を第2、第3の妻に迎えることができる。これは本来、ジハードで夫を亡くした女性の生計を助けるための制度であるらしい。では、イラン・イラク戦争で犠牲になった兵士の妻は救済されたのであろうか。筆者はそのような人は極めて少なかったと考える。なぜなら、この戦争に明確な勝者はないから、戦利品も賠償金もない。したがって、第2、第3の妻を迎えて生活していく経済力のある人も発生しない。さらにイラン革命から敵対する米国からの経済制裁を受けているため経済的にも困窮している。このため、第2、第3の妻を娶った男性はほとんどいなかったであろう。それまで多妻制のなかで暮らせていた女性が捨てられたケースもあったのではないか。こうしたなか要因も、聖地に困窮者が集まる要素ではなかったか。そもそもイランで困窮者が生まれる事情についても考察しなければこの事件の背景を理解したことにはならないと筆者は考える。
聖なる蜘蛛たち
蜘蛛は多くの人にとっては歓迎されないが、害虫なども食べてくれるの益虫でもあり、地球上の生態系のバランスを調整する働きを担っているといえる生物である。この事件で直接的に蜘蛛として表現されたのは犠牲者となった娼婦たちであった。イランで蜘蛛とはどのように理解されている生物なのかはわからなかったが、犯人の表現だとすると否定的な意味の可能性がある。冒頭に映し出されたマシュハドの夜景は蜘蛛(あるいは蜘蛛の巣)を形作っているようだった。昼間はシーア派の聖地という顔を持つが、夜には彼女たちのような蜘蛛を生み出す顔がある、そうした比喩がこめられていたのだろうか。犠牲者たちは腐敗しているから蜘蛛になったのではない。一人一人が尊厳ある人間で懸命に生きていたのだということをこの映画のタイトルから想う。
等速直線運動
聖なる蜘蛛
連続娼婦殺人事件の犯人を捕まえるために主人公が囮になる、ようやく捕まった犯人は一部で英雄視され、社会全体(警察やお役所すら!)から養護され優遇され、子供もあとを継ぎそうで、思想の次世代への連鎖を匂わせる、だいたい想像通りの展開と結末。
娼婦が聖地を冒涜する街の汚物なら、買う方はどうなんだ、という真っ当な問いをしたところで意味を持たない社会、男尊女卑、ミソジニーが「正論」とされるところは世界中でかなりあると思う。少女を暴行した成人男性が無罪になり、被害者のほうが男と密通した等の罪に問われる理不尽極まりない話も珍しくない。
こういう問題は、「目新しさがない」くらいしつこく世界中に言い続けて共有したらいいのだ。
また、狂信的信者タイプの犯罪者は厄介だ。
やっていることに誇りを持ち使命感がある分、シリアルキラーにもなりやすいと思う。
この映画の犯人は狂信的信者でもあるが殺すことに快感を覚えるようになって、殺さないと眠れないほどになっており、周囲をうまく利用したような気もする。
この映画をイスラム社会は許容したのだろうか、と思っていたら、イラン文化・イスラム指導省が「この映画はサルマン・ラシュディ『悪魔の詩』のような道をたどる」と非難したとのこと。
この作品は「単なる映画」の範疇を超えてしまったようです。
関係者の皆さん、どうかご無事で。
宗教の怖さでもイスラム特有の問題でもない
新味無し。
等速直線運動
憎悪が引き継がれる
デンマークでつくった!
イラン映画といえば、アッバス・キアロスタミの牧歌的な作風が思い出されるが、本作は対極に位置していると言えるだろう。いや残念ながら本作はイラン映画ではない。イランでは本作は作ることができないことがそのまま、本作の意味であると言ってもあながち間違いではないように思う。イラン出身でデンマークで活動するアッバシ監督が、自身がまだイランにいた頃、2000−01年、イランの聖地マシュハドで発生した連続殺人事件(犯人は16人の娼婦を自宅で殺害し、スパイダー・キラーと呼ばれた)をリアリズム的手法を用いて描いた作品だ。監督は本作を「フィルム・ノワール」と呼んでいるようだが、それだと随分と解釈が広がってしまう気がする。恐らくは主人公のように感情移入できる人物を配さず、観る側に作品の社会的背景も含め客体意識を与える作品構造を言っているのだろう。まるでそこに立ち会っているかのようなリアリズム演出は近年、その手法がとても洗練されてきた。本作も背景となる街並みなども含め、映像の中にある種の緊張感が漲っている。残念ながらイランでのロケは叶わなかった(申請したのは驚き!)ようだが、ロケ地のヨルダンも十分な存在感を見せている。
惜しむらくは、ジャーナリストであるラヒミが創作されたキャラクターであり、やはり存在感としては他の登場人物と比較して、どうしても薄くなってしまうことだろう。これは演者であるエブラヒミの責任ではもちろんない。彼女は振られた役割を、自身の背景も昇華して十二分に演じている。これは監督を含め制作側(彼女も製作陣の一人だが)の話で、ミソジニー(女性蔑視)というテーマを作品に理解しやすい形で提示したい思いと、やはり娯楽性を持たせたい欲が、ラヒミに必要以上のヒロイズムを与えたのではないだろうか?。とはいえ、本作の役者を含めたスタッフ全員に拍手を送りたい。ここに描かれている異常は、間違いなく日常であり、世界中どこででも起こり得ることだと、納得するに十分な作品である。イランから遠く北欧のデンマークでこの作品が制作されたということに文化的なグローバリズムを感じる。どういう経緯があったのか?パンフレットもその辺りに少し触れて欲しかった。
見終わったあともモヤモヤののこる
犯人が処刑されたあとに、息子が、「娼婦に対して何ら対策をとらずにいれば、第二第三のは必ず現れる」といったのが印象的だった。日本に置き換えれば、伊勢神宮のご神域の中で娼婦が商売しているようなものか。民族的宗教的感情から、犯人を無罪にせよと言いたくなる人々がいるのも、わからないでもない。ムスリムにとっての聖地を冒涜しているのだから。もし、これがサウジやアフガニスタンのような原理主義国家だったらどういうことになったであろうか。欧米的思考の限界をみたような思いだ。
予想外の結末?
作り手の強い主張が見える苛烈な作風
「人間が最も怖い」タイプの作品。確信犯的なシリアルキラーの犯行と公判を巡る世間・警察・家族の反応を通して、凝り固まった価値観や序列意識の恐ろしさが描かれていた。
作中の多数派の価値観は、宗教上のルールに加え、彼らが生活する上で連綿と培われてきた文化や歴史とも切り離せないもので、彼らの属する社会の秩序でもある。その構造はおそらく外から変えることはできないだろうが、外からでなければ本作のような視点では描けなかっただろう。
その皮肉な関係は、作品のニュース記事に掲載された、この映画を完成させるための紆余曲折からも伺えた。そういう背景があるせいか、もともとの作品構成なのかわからないが、作り手の視点がやや一方に偏り、攻撃的すぎるようにも見えた。
我々の暮らしの中でも、被害者に対し「そうされても仕方ない」というコメントをネット内外で見かける。この作品内で起きたことを「遠い場所の実在事件を脚色したもの」とせず、襟を正す材料にしたい。
道徳という名の魔女狩りはなくならないのか
昨年、テヘランで女性の頭髪を取り締まる道徳警察に逮捕された女性が亡くなった。頭髪を取り締まるとは、悪いヒジャブの付け方をしていないかどうかを取り締まることである。その後、抗議デモが広がったが、抗議デモに参加した女性達も警察の拘束後に亡くなっている。
連続殺人を起こしたサイードは敬虔なイスラム教徒であり、イランイラク戦争では戦死も厭わない程に軍人として祖国に尽くした。家庭では、良き夫良き父親である。彼の行為はPTSDによる可能性もある。しかし、娼婦に向けられたヘイトはPTSDだけが理由ではない気がした。
サイードはどんなに模範的に生きても国家に尽くしても社会に認められなかった。サイードは自身の虚しさを感じない様に怒りの矛先が必要だった。道徳心=不浄なものを浄化するというサイードの大義は、後付けに他ならない。
この間違った大義は、サイードだけに限ったことではない。それは、私にもあなたにも、一部の特権階級を除いた全人類に普遍的なテーマなのだ。例え私が国家の為に命を投げ出したとしても、国家にとってはただ一人の人間が死んだだけのことである。言いようのない怒りが湧いても、怒りの矛先は権力には向かないで弱者に向く。
特に慢性的な貧困と暴力が蔓延る社会では、誰もが容易くサイードになり得るし、娼婦にもなり得る。
日本においても貧困化の進行度と比例して、堂々と差別発言する人(特に男性)が増えたと感じる。高度経済成長期、バブル期には特に優秀でなくても男性であれば妻子を養う程度の賃金はもらえた。こういった男の沽券や面目が保持できなくなったことも差別発言に影響していると思う。
私はサイードと堂々と差別発言をする日本男性が被って見えた。また、サイードを支持した男性達と差別発言に同調する良き夫良き父親である日本人が同じに見えた。
(原題) Holy Spider
面白い処も有れば,あまり気持ちは良くない難癖付けて娼婦を…。
スパイダー・キラーと道徳警察
聖地があるイランの街にて娼婦をターゲットとした連続殺人が発生。事件を追うジャーナリストと、犯人を取り巻く異常な環境を描いた作品。
序盤からエグい描写満載。
少々不安定な様子はあれど、昼の顔は信心深く家族想いの良き父だが…。
この聖地に於いて娼婦は汚れと、夜には恐ろしき第二の人格が顔を出し…。
必ずしも、我々日本人の感覚がグローバルスタンダードでは無いことはわかるが、それにしても恐ろしき2000年代初頭のイランよ。。
信仰心も行き過ぎればやっぱり。
彼らが信じる神とは一体何なのだろう?
勿論、娼婦という職が褒められたものではないとは思うが…冒頭にもあるように、彼女らは彼女らで家族を養うために仕方なく、といった側面もあるようだし…やはりそういった人を助ける環境を整えることが大切ですね。簡単な事ではないけど。
殺人描写も恐ろしいが、より恐ろしいのは寧ろ犯人が捕まったあとか。16人亡くなってる事件の法廷であんな軽々しく笑うかねぇ…。
それだけ、悪だと思われて無いんですね。
そしてそして最も恐ろしいクライマックス。どうしてこうなってしまうのか。。
我々が簡単には感情移入できない厳しい環境と、行き過ぎた信仰心、世界共通では無い道徳の難しさに戦慄を覚えた作品だった。
イスラムの聖地が舞台だからこそのストーリー
倫理観と倫理観の戦い
イスラムの聖地マシュハドでの娼婦連続殺人事件を描いたクライムサスペンス。事件を追う女性記者と犯人の男のそれぞれの視点でドラマは進む。
事件の背景には、現代の西欧中心の倫理観とは大きく異なる価値観が横たわっていて戦慄する。
事件は穢らわしい職業の女性は徹底的に排除すべきという、女性蔑視職業蔑視のヘイトクライムなのだが、犯人の男だけでなくその妻子や少なくない街の人々が肯定的に捉えている描写に驚く。
娼婦をターゲットにしたシリアルキラーものは数あれど、犯人がここまで英雄視される作品は観たことない。
藤子F不二雄先生のSF短編で我々の世界とは全く異なる倫理観の世界に紛れ込み価値観を揺さぶられる作品が幾つかあるが、この作品を見ている最中同じような思いに囚われていた。
全91件中、21~40件目を表示