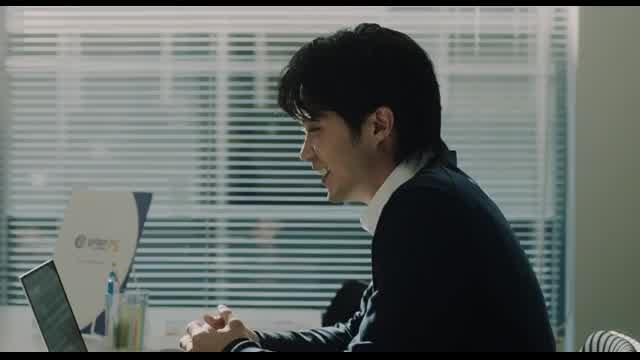PLAN 75のレビュー・感想・評価
全399件中、1~20件目を表示
焦燥感と行き場のない怒りで心が痛い。
合理的に考えると行き着く先はこうなんだろう。
携帯の勧誘のような「PLAN75」の販促と受付ブース。職員が顔色ひとつ変えず淡々と受付手続きを進める姿が恐ろしい。「貰える10万円は葬式費用に回される方もおられますよ~。」まるで旅行のプランニングや住宅ローンの説明のようだ。
藤子・F・不二雄の『SF・異色短編(1)』に出てくる 「定年退食」と「間引き」という2つの短編がオーバーラップした。「定年退食」では“定員法”というものが制定され73歳以上は年金や医療など国家による一切の保障が打ち切られる。「間引き」では人口爆発による食糧難で“カロリー保険”という早く死亡するほど遺族に食券が多く配布される商品が発売される。
NKHスペシャルの「終の住処はどこに~老人漂流社会~」には、1カ月毎に施設をたらい回しされる高齢者の現状があった。安心して居ることのできる場所がない。「定住できる安心感。心ある人が見守ってくれている安心感。これが最低限度の尊厳だがこれが損なわれている。」と専門家は言う。若いころは運送屋を営みバリバリ働いてきた老人が「家族とご飯を食べたい」と涙を流す。なぜ最後にこんな仕打ちを受けなければならないのか。
ボーヴォワールの『老い』も再読した。
・この社会は彼らに「かつかつの余命」をあたえるだけで、それ以上は何も与えない。
・独り暮らしの老人は「悪い健康と窮乏と孤独という三重の悪循環」に陥る。
・老年の悲劇は、人間を毀損する。この人生のシステムはその構成員の圧倒的多数者にいかなる生存理由(いきがい)も与えない。
角谷ミチ(倍賞千恵子)の住まいが一人で暮らす私の母の住まいに酷似していた。
「団地」「台所の瞬間湯沸かし器」「布巾を多用」「藤の間仕切り」「コードのある昔ながらの電話機」「観葉植物」、、、。物は多いが小綺麗で慎ましやかできちっとしている。このぐらいの年代の女性ってこんな感じが多い気がする。こういう人たちの尊厳が脅かされる世の中だけは見たくない。
PLAN75の受付をしていた市役所の青年、申込者がその日を迎えるまで話し相手になるオペレーターの若い女性、安楽死した人の遺留品を処分する仕事に従事する外国人の女性。。 救いはこの3人の若者が最後に見せた人間的な涙。そこには確かに血が通っていた。
そしてもうひとつの救いは、最後の場面で丘からの風景をみていたミチがその場を去る時に見せた毅然とした横顔。
映画的にどうというより、大きな衝撃と問題を与えた点で重要な作品である。
明日は敬老の日、、、。
生死の選択をめぐる「ざわつき」
75歳に達すると自分の死を選択できる制度、「プラン75」。コロナの日々でワクチン接種や治療の優先順位を示されるようになり、命をランク付けをするようなこの制度も、妙な現実味を帯びている。冒頭、高齢者を襲った男は「国のために死ぬ考えは、この国ではきっと受け入れられる」と遺書を残す。「プラン75」のPR動画に登場する女性は「生まれてくるときは選べない。だから、死ぬときくらいは自分で選びたいの」と微笑み、PRは「次の未来のために」というコピーで締めくくられる。では、この制度を志願する人々の実際は、一体どうなのか。
ホテルの清掃係として働くミチは、つつましくも穏やかな生活を重ねていた。黙々と働き、同年代の同僚と他愛もないおしゃべりを楽しみ、時には歌う。ある日、同僚のひとりが職場で倒れたことで、彼女の生活は一変する。彼女たちは解雇され、途端に生活に行き詰まる。職探しや転居もままならない。ためらってきた生活保護受給さえハードルが高いと感じたミチは、とうとうプラン75の選択に至る。
本作には、モデルケースとなるミチを軸に、窓口担当として働くヒロムとその叔父、ミチを担当するオペレーターの瑤子、関連施設で働き始める、フィリピンに病気の娘を残してきた元介護士•マリアが、主要人物として登場する。けれども、ミチと瑤子、ヒロムと叔父以外は、ほとんど接点を持たない。それぞれに「ざわつき」を感じながらも、声を挙げることはなく、黙々とプラン75に携わっている。観客だけが、それぞれの「ざわつき」と、彼らのすれ違いを垣間見ることができるのだ。
本作の持ち味は「ざわつき」。冒頭ゆっくりと流れるピアノから、美しいけれどどこか不吉で、気が許せない。そして、繰り返し現れるミチの常に張り詰めた表情、内実を知ったヒロムのためらいと驚き、職場の会話を立ち聞きした瑤子の沈黙、高収入の仕事の「中身」を知ったマリアの静かな動揺。美しく整然としているゆえの違和感が、じわりじわりと描かれていく。
さらには、プラン75が、あくまで本人の選択で、10万円の支度金が支給され、合同葬であれば費用が掛からない、といった(一見)完璧な至れり尽くせりのサービスであることも、「何かがおかしい」と心がざわつく。「今、(本当は)何が起きているのか」、「彼らは(内心は)どう感じているのか」を感じ取ろうと、流れに身を任さず、ふと立ち止まりたくなっていく。カギとなる「何か」を見逃さないよう、聞き逃さないよう、心のアンテナを高く伸ばす。そのような「静かな牽引力」が、本作には満ちていた。
ミチが最後に見た光は、きっと、それぞれの場所にいる彼らにも、静かに降り注いだはず。「生まれてくるときは選べない。そのかわり、「死なない」で「生きる」ことを、人は日々選択している」と、自分なりの結論に至り、2時間弱の旅をひとまず終えることができた。
設定と演出とキャスティングの妙
勿論、間近に迫る日本の近未来を見据えた視点には震えるものがある。75歳を過ぎると自ら生死を取捨選択できる制度が導入された社会というのは、実際、年金制度の見直しが決定したこの国では、すでに近未来ではないからだ。
しかし、本作のリアルはより細部に宿る。ある日突然、高齢を理由に解雇された78歳のヒロインが、役所に出向いて『まだ、働きたい』と申し出ても、担当者は年齢を理由に彼女の意向を遮断してしまうシーンには、行政の冷酷さと、まだ生かせる労働力を適切に社会に還元できない政治の対応力の遅さがあからさまなのだ。そういう意味で『PLAN 75』がいかに短絡的な制度かがよく分かる。
細部がリアルなのは、演技者たちのスキルに負うところも大きい。政治への疑問や不満を声高に訴えられず、未来へのわずかな希望に縋って生きる主人公は、これまで、庶民の喜びと悲しみを映画を介して代弁して来た倍賞千恵子ならではの役どころだし、『PALN 75』の申請窓口で働く青年を演じる磯村勇斗の、老人たちに対する優しい目線には、思わず引き込まれるものがある。
すぐそこまで来ている厳しい現実が、俳優たちの魅力によってより身近なものに思える。本作の高評価は監督の演出力とキャスティングによるものだと思う。
想像と解釈を喚起する「余白」の巧みさ
これは、少子高齢化のような“正答”のない難題に直面したとき、誰もリスクと責任を取って解決にあたろうとせず、ひたすら先延ばしにしようとする日本的なメンタリティへの静かな抗議ではないか。本作を観ながらそんな風に思っていたのだが、鑑賞後に資料を読むと、早川千絵監督の意図は違うところにあったようだ。本作を着想するきっかけのひとつに、2016年に相模原で起きた障害者施設殺傷事件があり、「人の命を生産性で語り、社会の役に立たない人間は生きている価値がないとする考え方」への危機感が、映画を作る原動力になったとしている。
とはいえ、75歳以上が自ら生死を選択できる制度が施行されている近未来の日本を舞台にした本作は、特定の意見や主義主張を明示する映画ではない。登場人物らの苦悩や心の触れ合いを描いているが、彼らに思いのすべてを語らせるのではなく、観客のさまざまな想像や解釈を喚起する“余白”が大いにある。1983年のカンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞作「楢山節考」で描かれた姥(うば)捨ての風習を想起する人もいれば、スイスやオランダなど一部の国で合法化されている安楽死と関連付ける人もいるだろう。この国では安楽死について口にすることさえタブーのような空気があるが、本作をきっかけに議論が活発化するなら良いことだと思う。
本作の主演に倍賞千恵子をキャスティングした点にも感心させられた。当たり役は「男はつらいよ」シリーズでの寅次郎の妹“さくら”であり、高度成長期に日本の国花の役名で知られた女優が、本作では衰退する日本、“日(ひ)没する国”を象徴するようなミチを演じているのだ。このアイロニカルな巡り合わせに思いをはせる観客も多いのではないか。
なかなかどうしてしっかり作ってある。
死選択の自由
リアル
倫理で救われないけれど、制度も正解ではない。
※セリフ、シーンネタバレあり
序盤10分で、もう画面を見ていられなかった。
音だけを聞きながら、冷たく進む説明と、
「家族の同意も審査も必要ない」という言葉の軽さに、
なにかがずっと胸の奥でひっかかっていた。
でもその後も目を逸らせず、最後まで見届けた。
“先生”と呼ばれるコールセンター職員と、
申し込みをした女性の15分だけの会話。
制度として整えられた優しさ、仕事としての思いやり。
そこに確かにある人間らしさと、
制度に押しつぶされる感情の揺れ。
「所詮情、されど情」という言葉が、静かに頭に残った。
見終わったあとも、すぐに答えは出なかった。
怒り、納得、悲しみ、同情、不安——全部が混ざっていて、
どれも間違いじゃない気がして。
倫理で救われないけれど、制度も正解ではない。
それがこの映画の正直な形なんだと思う。
終盤、
フィリピン人の女性が自転車をこぐ姿、
磯村くんが叔父の遺体を車で運ぶ姿、
そして“プラン”を辞めて歩き出す女性の姿。
誰もがそれぞれの事情の中で、
どうにもならない生を、なんとか進めようとしていた。
倫理や制度では測れない現実が、あの静けさの中に詰まっていた。
そして忘れられないのが、「先生」とこちらで目が合う瞬間。
最初は“急に安っぽい問いかけをしてきた”と思って落胆した。
けれど時間が経ってから、あの目線の意味が分かった気がする。
同僚の言葉に対して私自身も怒りを抱き、
何も言えない苛立ちを感じていた。
私はあの瞬間、完全に「先生」と同調していた。
だから、彼女がこちらを見た時、
彼女と私が分離して、
“共犯である自分を責める自分”に変わった。
その目線は、観客ではなく、
私自身に向けられていた。
エンドロールの間、心はとても静かだった。
涙はもう出なかった。
映画を見たあとの非日常的な高揚もなく、
ただ“自分に戻ってきた”感じ。
結局は他人事として消化したのかもしれない。
でも、それが今の私の現実であり、
無自覚な残酷さでもあり、幼さでもあると思う。
この映画は、たぶん人生のどこかでまた見返す。
その時、どんな自分で、どんな感情で受け止めるのか。
きっと今とは全然違う景色が見えるだろう。
でもそれでいい。
答えを出す映画じゃなく、
時間をかけて“自分の中で育つ映画”なんだと思う。
姥捨山の是非
前から見ようと思っていたが、数年経過した今ようやく鑑賞。
成人まで生きた多くの人が75歳を超えるまで生き続ける。そのとき、本作のようなオプションがあったらどうか?利用したいと思うだろうか?社会の圧に屈する形で生を終える選択をするだろうか?
年齢を重ねる毎に、心身共に衰えていくのは事実。皆が同じ道を辿るのだから、それを社会全体で受容して生きていきましょうよ、と思うのだが、バッシングすごいし、現実的に選択肢は狭められるし。仕事や住居に窮するようになったら実際ショック受けるだろうな。高齢者を責め立てている人たちは、自分が今この瞬間その高齢者に転生したら、粛々と非難を受け入れるのか?ジタバタするんじゃないのか?
とはいえ、もう十分生きたと思えたとき、生きていることが苦しくて仕方がないとき、楽になる選択肢があるといいな、と思っている自分がいる。切腹、飛び降り、縊首、どれも苦しく痛そうだし。最後くらい穏やかに逝かせて下さい。
寅さんのさくらが歳を重ねて本作の主演。時間だけは皆に平等に流れているのだな。そうヒシヒシと感じた。
タイトルなし(ネタバレ)
今日は私の誕生日なので、もう一度これが最後と思い見てみた。
旅の途中で何も見る物がなかったので。
「ルノアール」が自分の体験や感情を脚本に盛っていたので、称賛したけど、この映画は大日本帝国の悪しきDNAの力学を感じずにはいられない。
つまり、それ以上書くと消される。
人間の高齢化が社会を悪しき姿にしていると誰もが勘違いしている。
今の問題は近現代の殖産興業、富国強兵の考えに基づいて「生めよ増やせよ」の考えを捨てないからこんな事になっていると考えるべきだ。
つまり、人間が長生きする事に問題があるのではなく、子供が生まれない事に問題があるんでしょ。
生きて行くと言う事。
とうとう…この作品を観て一番最初に感じた事。出るべくして出た作品とも思ったし、実際、目を逸らしたくなるけど逸らさない。決して気持ちを萎えさせない。この作品が訴えかけて来る事への私なりの答えだ。
例えどんなに豪華な施設に入っても、感じ方は人其々。決して裕福な事が幸せとは限らない。中には「もっと仕事をしていたかった。」と言う人も。以前TVのドキュメンタリーでオーシャンビューの、入居に何千万もかかると言う施設の入居者に今、幸せかどうかと言う質問に対しての答えだ。多くは「幸せ」と答えてたけれど、仕事が出来て社会と繋がっていたかったと言う人も。張り合いは大切だと思った。
ミチ(倍賞千恵子)はとても幸せな人だと思う。自分で生きようと決る事が出来たから。この先、どんな仕事をしてどんなにプライドが傷付く様な事があっても、生きてみせると言う覚悟と前向きな姿勢。それこそ映画の中の「プラン75」と言う制度の無能さを晒す物なのでは無いだろうか。ミチはその事を示してくれたのだと思う。
日本の未来を考えさせられる
セリフは多くはなく、表情や仕草、間から登場人物の心の揺らぎを感じ取る映画。
見る人の年齢や境遇によっても感じ取り方は異なると思う。
高齢者の人口が増え、それを支える若年層の人口が減り、外国人労働者が入ってくる。
高齢者には仕事も住む場所も、提供する医療も八方塞がりとなり、自ら安楽死を選ぶ様になる。
今のままの政治活動ではこうなる未来もありえるのかもしれない。
ラストシーンは主人公の背後には雲間に夕陽が覗いています まるで、お釈迦様の瞳のように自分には見えました
PLAN 75
2022年公開
とにかくPLAN 75のディテールが素晴らしい
受付の説明資料やポスター、のぼりなどの宣伝資材、販促ビデオ
説明トークなどの様々な実在感に製作陣の努力が結実していて、本当にPLAN 75 が存在して既に運用されているかのような世界が、嘘っぽくなくごく自然に表現されていました
ただ、そこにエネルギーを使い過ぎたのか、脚本の練り込み不足は否めません
それで?と
物語が始まりそうなところで尻切れトンボで終わってしまうのです
50年昔のハリウッド映画「ソイレントグリーン」でも安楽死システムのお話が出てきていました
その作品ではその紹介だけで終わるのではなく、物語がそれを受けてそこから始まっていくのです
本作は、そのような娯楽作品では無いことは承知していますが、それでも、そこからどう物語が始まるのかを期待してしまいました
ベンチに手すりを取り付けるシーン
その手摺りは、お年寄りが立ち座りし易いようにするためのものではなく、ホームレスが公園のベンチをベッドにしないように排除するための仕組みだという告発でした
弱者の為のように見えて実は弱者排除の為のものだということです
かと言って、その手摺りの工夫が無ければ、ホームレスが公園のベンチを占有して、子供達やお年寄りが使えなくなってしまう現実もあるからそのような工夫が生まれ全国に広がったのも現実です
同様に、年寄りを働かせたら可哀想だという投書で解雇されるシーン
高齢者雇用を進めることが良い企業であったはずが、非難されてしまう現実
高齢者雇用が失われたら、当の高齢者がどうなるのかの現実も本作では紹介されます
物事には二面性どころか多面性があるのです
PLAN75もそうです
安楽死提供システムの恐ろしさは
その一面にしかすぎません
劇中で、PLAN 75 を自らの意志で申し込む主人公にとっては、どうだったのでしょうか?
難病に何年も苦しんで、治る見込みが無い人にとっては、生きている限り永遠の拷問が続く監獄に入れられているように苦しんでいる人によっては、救いの仕組みなのかも知れません
そうではない!
それでも生きたいという人ももちろんおられるでしょう
他人が判断できることではありません
かといって、本人がそのような意志を持っていてもそれを認めてはならないというのもそれはどうなのでしょうか?
答えはなく堂々巡りです
せめて、そこへ少しでも切り込んで物語をさらに前に進めて欲しかったと思いました
単なる安楽死の是非だけでない視点の広がりがあったのに活かせないままで終わってしまってもったいない限りです
それらの視点も物語に組み込んで作品メッセージにまで至っていたならば、恐ろしい程の傑作になっただろうと思うと残念で仕方ありませんでした
たかだか2時間程度の映画で取り扱えるテーマでは無いのかも知れません
だからこそ、そこまでには立ち入らないということも、ひとつの見識なのかも知れません
それこそ、こういうことは宗教が扱うべきテーマなのかも知れません
それぞれの信じる神仏がどう導いて下さるかです
ラストシーンは主人公の背後には雲間に夕陽が覗いています
まるで、お釈迦様の瞳のように自分には見えました
それがこの作品の結論だったのかも知れません
私達に投げかけられた問題提起
俳優さん達の演技がとても素晴らしかったです。
社会派ストーリーなので、冒頭の事件を絡めて、登場人物の誰かがplan75に対して声を上げるのかな?と思いましたがそうではなく。
ただ淡々と賛成も否定もせずその政策を受け入れ、その下で働く職員や、自分の死に方に悩む高齢者達の姿。
最初はもう少し動きのあるストーリーが良いなと思いましたが、見終えた今、逆にそれが日本人らしいというか、国民性をも表現されている気がしました。
昔からずっと言われ続けている少子高齢化社会。
実際はこれと言った政策が練られる訳でも、改善される訳でもなく、今でも日本人皆が見てみぬふりをし、政治や将来の話をする事を避けてきた現実。
それらを私達に問題提起されているのかなと思いました。
ベタに社会問題を描くことを避けた詩的な演出
全399件中、1~20件目を表示