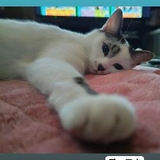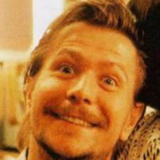ケイコ 目を澄ませてのレビュー・感想・評価
全276件中、21~40件目を表示
うむむむー
だから日本映画嫌いになったんだよ!というお手本のような、雰囲気重視あとは皆さんがどう思うかが重要です的な放り投げ映画。言いたいことないなら映画作らなくていいって。キャラクター描写も中途半端よなー。トレーナー2人いるけど役割微妙過ぎ。現実はそうかも知れないよ、でもあんたが作ってるのは映画なんだから、もっと描き込みなさいよ。弟(なの?)の恋人もダイバーシティノルマを果たすためだけのような唐突な黒人ハーフ、しかもお姉さんとお話したくて手話を習いましたと取ってつけたような善人キャラ。何が言いたいの?こういういい映画でございヅラした日本映画は見てはいけないんだよなー、でもまた愚かにも見てしまうんだろうなー流されて。
耳も澄ませて
2回連続視聴した。
ジムでのトレーニング中のリズムカルな音(ダンダンダン...とか、スタンスタンスタンスタン...)、アーケード街での放送(不要不急の外出を避け....マスク...お願いします)や、自動車と電車の走行音、生活音が特徴的。
試合前のノートを音読するシーン、小河聖司(佐藤緋美)の弾き語りだけが唯一の挿入歌。
エンディングは、昭和ドラマのようにロールしないクレジットに音楽が一切ない。
小河ケイコ(岸井ゆきの)が通うジムの会長(三浦友和)は、宝くじを疑ったり、健康を害する検査に言及する。
2020年の主人公をピックアップしながら、リアルな世界を16mmフィルムに収めている。
小笠原恵子の自伝『負けないで!』が原案になっている。
Small, Slow But Steady
タイトルは、本作の英題。
私は、邦題よりも、こちらの方がこの映画の本質を捉えているように思える。
小さく、ゆっくりと、しかし着実に。ケイコは前に進む。そして、それはコロナ禍という異常事態であっても変わらず移ろいゆく「時の流れ」も同じ。
この作品は光と音の映画だった。
光。16mmフィルムは、解像度が低く、粗いようでいて、暗闇の中の街灯や電車の光を鮮明に、それでいてやさしく映し出す。
音。主人公ケイコ(岸井ゆきの)の台詞らしい台詞は、私の記憶が間違いなければ、「はい」という声とリングの上で相手に向かうときの咆哮だけだ。彼女を取り巻く人物達も決して雄弁ではない。
登場人物の台詞以上に雄弁なのは、都市の日常音、環境音である。中でも、何度も何度も出てくる電車の音。電車は、何かを遮るように突然現れ、音を残して去って行く。しゃべらないケイコのざわついた心情を代弁するかのように。
ケイコは耳が聞こえない。音が聞こえない。それなのに何故これほど日常の音を溢れかえらせるのか?三宅監督は、私たちがほとんど無意識に聞き流しているような音をあえて強調して聞かせることで、彼女のいる無音の世界を意識させようとしているのかもしれない。
ケイコは表情の変化にも乏しい。しかし、彼女は一人で戦っている。恐らく自分と戦っている。会長の妻(仙道敦子)が会長(三浦友和)のベッドの側で読む彼女の日記を聞いて、私の中でそれは確信に変わった。
そして彼女は敗れる。リングに倒れる。それを見た会長は、「よし!」と言って自ら車椅子を転がす。ケイコも走り始める。
終わってなんかいない。一歩一歩、着実に、前に進む。もう後ろには下がらない。前に進む。それは静かで、しかし力強いラストシーンだった。
三宅監督の力量に恐れ入った。
台詞無しでケイコという存在を演じきった岸井ゆきの。言葉少なくても味わい深い演技を見せた三浦友和。演じるとは何たるかを見せつけられた。私はノックアウトされた。
人間としての器量
冒頭の説明的なテロップの効果もあり、フィクションでありながらまるでドキュメンタリー映画を観ているような感覚を抱いた。
これが演出的にとても成功しているのだろう。
特にミット打ちのシーンは、演技ではなく本気で向かい合っているのが画面を通して伝わってくる。
そのリアルな臨場感がこの映画の持ち味だろう。
主人公は耳の聞こえない小柄な女性ケイコ。
王道なストーリーであれば、耳が聞こえないというハンデを克服し、ケイコがプロボクサーとして成長していくまでの過程を描くのだろうが、この映画では既にケイコはプロボクサーのライセンスを取得している。
そしてプロボクサーとしてリングに上がり、順調に勝ち星を重ねている。
リアルな空気感をまとったボクシング映画でありながら、ケイコがボクサーとして成長していくことに焦点は置いていない。
そもそもケイコがボクサーを目指した動機も謎のままだ。
この映画では語られない部分がとても多い。
ではこの映画の主題は何なのだろうと考えさせられた。
障害を持つ人間に焦点を当てているが、社会の生きづらさをテーマにしているわけではない。
印象的なのは、会長がインタビューでケイコにはボクサーとしての才能はないが、人間としての器量があると答えるシーンだ。
この台詞がこの映画ではとても重要なのではないかと思った。
ケイコは連続して勝ち星を重ねるが、突如ボクシングへの熱を失ってしまったように感じる。
それは会長がジムを閉めることを決意したことと無関係ではないだろう。
彼女がボクサーを目指したのは、そしてモチベーションを保っていられたのは、おそらく会長の存在が大きかったのだと思う。
認められたいという欲求とも違う気がするが、とにかく彼女は会長がいない世界でボクシングを続けることに意義を見出だせなくなったのかもしれない。
ボクシングとしての才能はないのかもしれないか、彼女はひたむきになれる強さがある。
そして無愛想だが実はとても親切で心優しい。
彼女が掛け持ちしているホテルの清掃の仕事で、新人にシーツの畳み方を教える時の柔らかな表情が印象的だった。
ケイコはボクシングを休みたいと伝えるために会長の元を訪れる。
しかしそこで会長が熱心に自分の試合の録画を見ながら、トレーニングメニューを組んでいる姿を見て驚く。
ケイコと会長が二人でシャドーボクシングをするシーンは印象的だ。
言葉を介さなくても、二人は心で繋がっていることが分かる。
そんな折り、会長は病に倒れてしまうが、再び彼女はボクサーとして戦う気力を取り戻していく。
ひたすらロードワークとミット打ちを繰り返す日々。
派手な試合のシーンよりも、そうした単調な基礎の練習の積み重ねを描くことの方が、この作品にとっては重要だったのだろう。
確実にミット打ちが上手くなっているケイコの姿に感動を覚えたのも確かだ。
努力を積み重ねても、必ずしも結果が伴うわけではない。
それは障害の有無とは関係がない。
悔しい思いをしても、地道に努力を積み重ねるしかない。
そしてひた向きに生きていれば、理解を示してくれる人は絶対に現れる。
ケイコの人物造形といい、かなりリアリティーのある作品ではあったが、どこにこの作品の肝があるのか、最後までいまいち理解出来ないままだった。
理屈抜きに好きになれるかどうかがはっきり分かれる作品だとも思った。
映画というより…?
ケイコの勝利
生まれつきの聴覚障がいのため耳が全く聞こえないケイコ。ホテルの下働きをしながらボクシングジムに通い、プロのリングにも立つ。だがこれは、そんな不遇のボクサーのサクセス・ストーリーではない。むしろ挫折の物語だ。
彼女はなぜ闘うのか。勝とうが負けようがリングに立ち、ジムで汗を流す。そのことだけに命の輝きを求めようとしているかのようだ。荒川あたりの河川敷で共にシャドウボクシングに励むケイコとジムの会長、岸井ゆきのと三浦友和が、まるで『ミリオンダラー・ベイビー』のイーストウッドとヒラリー・スワンクに見えてくる。会長に甘えるような岸井ゆきのの楽しそうな表情が印象的だ。
試合に負けた数日後、ケイコは偶然出会った相手ボクサーからリスペクトに満ちた挨拶を受ける。彼女の勝利の瞬間だ。映画は静かに主張する。試合に勝つことだけが勝利じゃない、時に挫けそうになる自分に打ち勝ってこそ、真の勝利があるのだと。
気迫と生き様が見事に光る
『夜明けのすべて』を監督すると知って、どんな監督なのか観てみた作品...
『夜明けのすべて』を監督すると知って、どんな監督なのか観てみた作品。
それまでもこういった、落ち着いた雰囲気で主人公が何を考えてるのか観客が読み取ることを求められる作品は苦手だったので、賞をたくさん受賞して期待してたけど、私には響く部分は少なかった。
今回『夜明けのすべて』が凄く好きだったので何か感想が変わるかなともう一度観てみた。
初見の時より、光や音、色々こだわってるところは見えてきたけど、やはり私は『夜明けのすべて』の方が好きだった。
”セクシー田中さん”事件どころやない 無知な素人の原作者をおいてけぼりにしている しかしタイトルに、普通、ダジャレを入れるかな
ボクシングは素人なのでよく分かりませんが
身体は作ってきてますね
でもボクシング自体は、後付けのパンチ音で迫力をだしているだけ
スピードはないし頑張って腰を入れて打つところがオーバーアクションでいかにも素人っぽい
まあ、もろに付け焼き刃
マシントレーニングもどう見てもキレイフォームとは言い難い
演技はいつものように、なんにでも対応できる上手い役者だから、こんなもんでしょう
作品は聴覚障害のある女性ボクサーの話なんですが、はっきり言って薄いし浅い
ボクシングを始めた理由も普通、聴覚障害のために起こるトラブルも目新しさはない
それどころか耳が聞こえにくいとわかったのに、マスクをしたまま大声で話すのをを笑うところなのかどうか、戸惑ってしまう
簡潔に言うなら、紆余曲折したけど小さな日常から、勇気を貰って再起するという話
自伝好きならいいかもしれないけれど、普通は何も心を動かせるようなものが無い
ドキュメントとしてもね
そういう意味では、難しい役どころだったのかもしれない
そういう意味での
アカデミー賞主演女優賞かいな
よくある、役者にストイックな挑戦をさせるために選んだ題材という気がする
今回は岸井ゆきのがターゲットになっただけ
岸井ゆきのの挑戦映画です
つまり、主演女優賞狙いの作品でしょう
ネットで原作者の小笠原恵子さんのインタビュー記事を読んで驚きました
映画よりずっと波乱万丈な濃い人生
熱いハートとガッツのある魅力的な人でした(美人だし)
ジムの会長は映画以上にスゴい人で、彼女に影響を与える存在だった
その上
本人の知らない間に映画化が進んで、主役まで決まっていたとか(映画化の話はあったそうですが、いつの間にか立ち消えていたそうです)
本人は素人だからこんなモノくらいにしか考えていないけど
ストーリーも何も、映画を観るまで知らなかった
なんてこったい
”セクシー田中さん”事件どころやない
もっと言うなら、家族構成を変えたのは仕方ないにしても、主人公の職業は歯科技工士だったのに、ホテルの清掃係に変えられているのも腑に落ちない
職業に貴賎はないけれど、ボクシングといえばバイトしながらハングリー精神で頑張っているという固定観念を持たせたかったのか
それとも、時間の都合で単純な仕事に変えたのか
よくある”事実を基にしたフィクション”で誤魔化してるんですが、なんか嫌
本人はなんとも思っていませんけどね
ただ、共通点は暗かった事だけと言っています
つまり、聴覚障害の女子ボクサーという題材だけを利用した別の作品です
なのに、名前を恵子にしたり、目の悪いジムの会長とかはつかっている
もう、こんな映画は、はっきりいって作り直した方がいい
タイトルの”目を澄ませて”はしらけます
原作?の”負けないで!”では聴覚障害というのが分かりにくい
だからといって普通、ダジャレを入れるかな
全ての人たちをきちんと描く
「夜明けのすべて」があまりに良かったので過去作をと思い観ましたが、これも評判は知ってたけどとても良い作品でした。
耳が聞こえないボクサーという主人公の映画なので当然セリフは少ないわけだけど、目、歩き方、普段のオンオフ、ボクシングの身体性のアクション(素晴らしい!)で見事にそこにいる人として描かれていました。
生活音(電車の音、水面所の音、車の音)が際立つ音響で、これを主人公は聞いていないと思いながら見るととても不思議な感覚でした。
この映画も登場人物すべてがそこにいると思わせてくれる作品で、それが本当にこの作品をスペシャルにしていると思います。
エンドロールの生活風景のショットたちの中にも、今の映画の中にいたような人たちがたくさんいるのだなと思わされて、とんでもない作品と思いました。
この時代ならではの展開にグッときた
ケイコにとって最後のボクシング大会になるかも知れない重要な試合が、まさかの無観客ネット配信試合になってしまった所で涙腺崩壊しました。
あの時代、大事な人の試合を直接見守る事も出来ず途切れがちな配信映像を、必死で食い入るように見る事しか出来なかった体験がある人にはグッと来るシーンだと思います。
フィクションという形をとったノンフィクション
現実の世界では、理由とか目的とかは、だいたい後付け。私たちは何となく何かを決め、日々の流れの中で何かが始まり何かが終わっていく。自分の気持ちをなぞってみると、理由らしきものを見つけ出すことはできるのだけれど、ぼんやりとした曖昧なものだったりする。普通の人の日常って、そんなもんでしょう、きっと。
岸井ゆきの演ずるケイコがボクシングを始めた理由も、またしかり。説明されるのだけど説得力はない。そして、やめる決意は中途半端で、ジムの人間関係の中で迷い、ダラダラと続けていく。ケイコの表情はいつも複雑で、見るものに明確な答えを与えてくれない。言葉にしない分、多くの思いが積み重なって、笑いながら泣いているような、泣きながら笑っているような。
リアリズムを追求すると、こういう映像表現になるのかもしれない。ボクシング映画といえばドラマチックな展開とカタルシスを求めてしまうけれど、現実のボクシング、そしてボクサーの日常には映画音楽なんて流れてこないわけだし。
だから、ケイコのリアリズムが強い説得力をもつ。ケイコが、迷いながら同時にひたむきに日々を積み重ねる姿に、心を動かされる。強さと弱さをあわせもつ彼女が身近にいるような感覚になる。
多くを語らない。そのことが、こんなパワーを生むとは。ちょっと、驚き。
独特な
生まれつき難聴にある主人公がボクシングを通して、語る人間の強さを描いた作品でした。
主人公を演じるのは、岸井ゆきのさんです。全編通して、セリフは、ほぼ無いです。それでもボクシングの動きや表情でどんな気持ちを写しているのか分かるくらいすごい演技でした。
実話を基にして作られた作品です。実際に耳が聞こえない中でボクシングの試合に臨むのは、とても怖い事だと思います。
誰の声も聞こえず、ただ1人相手と向き合い続ける。
怖さの中にある勇気が本当の強さに変わるのかなと感じました。
BGM
練習そのものが画
この映画の紹介文が全て。
コロナ禍で他人と距離をとりマスクをしている様は難聴の主人公にとってはさらに音を奪われた気持ちだろう。そんな彼女はマスクで読唇はできず、残されたコミュニケーションの手段である手話するその手にグローブをはめて人を殴り飛ばす。
それでも会長やトレーナーや彼女の家族をはじめとするケイコの周囲のいく人かの人間はそんな彼女と丁寧に接することをやめない。
ケイコは実はただ障がいのある人ということではなく、コロナ禍にあった私たちの象徴、もともとコミュニケーションに難のある現代人がコロナによりさらにその機会や能力を奪われた人たちだ。ケイコのボクシングは醸成されつつあったギスギスした人間関係がコロナでさらに悪化したことを表しているようだ。
しかし物語の最後、そんな現代人ケイコの前に現れたのは1人の作業服の女性。先日の試合の対戦相手だ。
これはケイコの殴っていたそのグローブの先の人間にも一つの"生"があることを気づかせた。
以降、ケイコにとってボクシングの意味は確実に変わったであろうということがわかる堤防の上の彼女の影、すれ違う人の影。エンドロール背景には時や人の営みを現すシーンが映し出されている。
……そんな解説を入れたくなる作品(笑
ついでに、、、
・カタカナでケイコとしたのは現代人を現すコードネームのようにしたかったのかも。
・岸井ゆきのの演技はまるでケイコという人物がそのままそこにいるような感じ。彼女の演技は☆5つあげたい。
・が、あまりに淡々と描きすぎているので離脱やつまらない等の感想を持つ方がいたらもったいない。
今回誰のレビューも見ずに作品を観て、レビューを書いたけれど、似たような作品印象が多いといいなと思ってる。
悪いとは思わないが過大評価?
岸井さんをはじめボクシングジムのキャストの演技は上手いと思う。画も雰囲気が合って良いと思う。岸井さんの演技を観たのは99.9とCMくらいだったが、これはとてもハマっているとは思う。岸井さんの努力も感じる。が、映画として魅力がない。勿論、格闘技に全く興味がないのを差し引いてもだ。
ジムの会長の妻がケイコに話した後のシーンと後半の弟の彼女とのシーン、ラストの仕事場のシーンは良かったが、そのくらい。
ダメな所というほどの所もない為この評価。何がテーマかよくわからないがケイコの心の成長がテーマだったのだろうか?
高い読解力が求められる
とにかく情報が少なく静かな映画なので、些細なしぐさや繊細な心情の移ろいをとらえきれないと意味不明な映画
だから、自分にとっては意味不明でした
どの辺が世界中の映画祭で絶賛されるポイントなのか教えてほしいです
鑑賞動機:岸井ゆきの10割
『愛がなんだ』や『前田建設ファンタジー営業部』でのコミカルでちょっとダメな人イメージが強かったけど、ここではガラリと違う硬質の人物像で、こんな顔をするのか、と新しい発見だった。
最後はちょっと成長したってことかな。
全276件中、21~40件目を表示