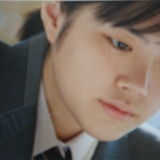ケイコ 目を澄ませてのレビュー・感想・評価
全276件中、1~20件目を表示
恵子の語りに耳を凝らして
三宅唱監督作品。
「全身で感じる振動=音は快感そのものだった」(小笠原恵子(2011)『負けないで!』創出版 p.96)
そのように本作の原案である本で恵子さんは語っているのだが、本作をみた私も同じように快感を得た。
フィルムによる味わい深い画、繊細に録られた音。
それらは各シーンに具体性をもって現れる。
序盤のケイコが更衣室で着替えるときにみえる背中の筋肉。会長と妻が病院帰りに歩道橋で歩くシーンで、電車の通過とその後の彼らの位置が決まっていること。ケイコが夜に河川敷で立っている姿。高架下で電車の光が点滅すること。会長がインタビューされている姿。生活音。紙に文字を書く音。電車が通り過ぎる音。声。唸り声。
もちろんボクシングの仕草も。スパークリングがあんなにも心地よいのは、ケイコとトレーナーの息が合っているからで、いやむしろ合っていなければスパークリングはできなく、美的価値を帯びない。
本作がカメラに収める出来事は、私たちの生活の地続きにあるものだ。それらを映画として再現前させて、観客は「目を澄ませる」ことになる。するとそれらの〈美しさ〉を再認識できる。その快感。三宅監督はそんな魔法を観客にかけるのだと思う。
だから本作をみた多くの人の感想は、「なんかよかった」何だと思う。よいのは間違いない。けれどそれだけでいいのかとも思ってしまう。
端的に思ったことは「なぜケイコはボクシングをやっているか」である。ボクシングをするのが快感だから?それはそれでいいけれど、「だからなんですか」になりかねない。もちろん聴覚障害であることの葛藤を全面に出すことはステレオタイプな障害/者表象になりかねない。けれどケイコが「人間」としてなぜボクシングに励み、闘うのか。その物語は必要なのではと思ってしまう。
それは私だけの感覚なのだろうか。ケイコはジムの退去に立ち会わなくていいし、会長からもらった帽子を被って、いつもと変わらないトレーニング、いつもと変わらない生活を送ればいい。それで「ケイコ」や物語は描かれたのだろうか。
ケイコがなぜボクシングをやっているか気になって、原案である小笠原恵子さんの『負けないで!』を読んだ。正直、映画よりもこの本の方が「面白い」。それは映画と比較して恵子さんが生い立ちからボクシングのプロとして活躍するまでといった語られることの多さもあるが、何より恵子さんがボクシングに実存を賭けていることがよく分かるからだ。
恵子さんは、生まれながら左耳が聞こえなかったが、右耳は聞こえていたため中学生までは普通学級に通っていた。しかし右耳の聴力もだんだんと落ちて、それに伴い学力も低下し、同級生が障害を理解することもなかった。そんな諦めや無力感が、彼女をグレさせた。高校生の時は先生の顔面を殴り、専門学生の時は寮から追い出され、バイクを乗り回して留年した。
ボクシングを始めたのは20歳の時で、動機は「なんとなく」。だけど強くなりたかったそうだ。この動機はなんとなく分かる。みんなと同じ普通になりたいのに、障害によって上手くできなくて、その解決方法が見つかったわけじゃない。将来の漠然とした不安の中で、何かしないといけない。障害による他者からの眼差しに抗うためには自身が強くならなくちゃいけない。そんな人生をかけた暗中模索で見つけたボクシング。恵子さんがボクシングをやる理由が、この本では語られている。
それは障害者がプロボクサーになる物語ではなく、恵子さんがプロボクサーになる物語だ。そこで障害は語られるが、それは一つの側面でしかない。だからこそ恵子さんが語られることは、私たちの「諦め」や葛藤とも普遍性を持つし、「面白い」と感じれる。もちろん恵子さんの苦しさを〈私〉の苦しさと安易に同一化することはできない。けれど確かに通じる部分はある。
恵子さんの面白さは事欠かせない。ボクシングをやり始める前の高校生の時、彼女は先生や親に暴行を働き、鬱憤を晴らしていた。なぜそんなことをしてしまうのか自問すると、部活動に所属しておらず力が有り余っているからと思い、ジョギングをやり始めた。そしたらそれが習慣になってしまったらしい。
実際、運動神経もよかったらしいが、さらに手先も器用だった。周囲の人と馴染むことができず、ひとりでこもることもあって、絵を描いていた。絵を描くことも上手で、市のコンクールで入賞するぐらいの腕前だった。絵に関して言えば中学生の時の出来事が面白い。当時、支援学級の先生が彼女に寄り添わず、指導要綱に沿って彼女と接したから、洋梨の絵を描いて渡したそうだ。その意味は「用無し」。恵子さんの賢さが分かると同時に笑えるエピソードである。手先の器用さは、その後恵子さんがボクシングの傍らでやる歯科技工士の仕事にもつながっている。
彼女がボクシングのプロになることは、女性で競技人口が少なく、さらに聴覚障害があるから尚更難しかった。だから彼女がプロになりたいと言うこともできず、ジムも転々としていた。そこで見つけた「トクホン真闘ボクシングジム」。ジムの会長も実は中途失明者らしい。だが障害に理解があるわけでもなく、恵子さんが耳が聞こえないことは「気で直せる」と思っているらしい。とても根性論だとは思うが、会長と恵子さんが向き合ったからこそ培われた関係はあって、だからプロになれたのだと思う。さらにジムのトレーナーも根気よく接してくれて、セコンドの指示がみえるようにリングサイドを動き回って指示したり、ボクシング用語を伝えるために、オリジナルの手話まで考案してくれたそうだ。
このようにこの本には、恵子さんの人生が語られている。さらに「面白く」。そしてふと思うのである。本作は、この「面白さ」を翻案しているのかと。もちろんこの本を忠実に映像化として再現する必要は全くないし、原案に留めることは問題ない。それは映画の制作における限界としてあるからだ。だが翻案においては、原作にあった普遍性や本質を取り出す必要はあるのではないだろうか。それがないとも言わない。けれど足りない。「試合中の母の不安がブレた写真から伝わってきた」(p.137)を映画で再現することでもない。なぜケイコが歯科技工士ではなくホテルの清掃員なのか、ボクシングをするのか、妹ではなく弟が登場するのか、所属ジムを変えることに拒否反応を示すことの意味が足りない。必然性が足りない。
恵子の語りに耳を凝らして。それもまた、私たちがケイコをみる時に必要なことだろう。
登場人物が全員温かい映画があってもいい。
話としては耳が聞こえない女性が、ジムの会長やコーチ、周囲の人々に支えられながらボクシングに打ち込む話。大きな起伏も伏線もなく、淡々と静かに進む。それ故に「退屈」「つまらない」という感想も抱いたのは正直なところ。
でも、この映画の良さというか存在意義はそこじゃない。
冒頭のコーチとのミット打ちのシーンに既にそれは現れていた。コーチが耳が聞こえないケイコのために小さいホワイトボードに「コンビネーションミットやろう!」と書いて伝える。ミット打ちの間も一言も発さず一生懸命身振り手振りだけで教える。あー、このコーチいい人だあ、というのが画面いっぱいに伝わってくる。(末尾に!を付ける時点でもう。)
これが全編通してこうなのである。三浦友和扮するジムの会長も、仙道敦子扮するその奥さんも、もう一人の厳しめのコーチもケイコのためにしらみつぶしに移籍先を探したり、同居する弟もそのハーフの彼女も、心配して試合をみられないお母さんも、応援する職場の同僚も、ケイコが乗り気でない対応をしてしまった移籍先候補のジムの担当者も、顔がボコボコになった対戦相手も。。
みんなどこか優しく温かい。手話やジェスチャーが多く静かに進むことも相まって、優しく穏やかなトーンが全編をまとう。
殺伐とした世の中、こういう一服の清涼剤のような映画があっていい。
人を信じることができる。この映画の存在意義はここにある。
コロナ禍の人間模様
2020年を舞台にしていると明確に設定されている本作は、人々がマスクをして生活している。コロナ禍に制作された作品の多くは、マスクをしておらず、その作品世界ではコロナが存在しないかのような、奇妙あ平行世界っぽさを感じさせるのに対し、この映画にはコロナが存在している。そして、耳の聞こえない主人公にとって口元を隠すマスクは、コミュニケーションの障害となることも描かれている。
主人公の通うボクシングジムが閉鎖される理由にもコロナが関わっている。元々、古びたジムでオーナーが病気がちであることなど、複数の要因が絡み合っているが、本作は明確にコロナによって人生の分岐点を迎えた人物が描かれている。
後年、コロナ時代の映像表現を研究する時、この時代の作品の中の人間がみなマスクをしていないことに違和感を感じる人が出てくるかもしれない。そんな中にあって、この映画は時代の感覚を的確にフィルムに焼き付けていると思う。
表現者として高難度の挑戦を見事に成し遂げた岸井ゆきの
生まれつき耳が聞こえないがプロボクサーのテストに合格し、通算3勝1敗の成績を残した小笠原恵子さんの実話に基づく。彼女をモデルにした主人公・ケイコを演じる岸井ゆきのは、プロのレベルに見えるボクシング技術の習得(+体作り)と、台詞に頼らず手話と表情だけで感情を伝えるという、どちらか1つだけでも難易度の高い挑戦を、映画1本の主演で同時に2つに取り組んだ。引き受けるのも相当な覚悟だったと察せられるし、これを成し遂げたことで表現者として2段階も3段階も成長したのではないか。
題に含まれる“目を澄ませて”のフレーズもいい。ボクシングは敵の動きを注視して瞬時に反応し、攻撃する。手話のコミュニケーションも相手の手や表情をしっかり目視する。そして俳優も、人の動作や所作を観察して自身の演技に反映させる。観客の私たちもまた、ケイコが言葉を発しないぶん(手話の字幕はあるが)、彼女の一挙一動に目を澄ませて思いや感情を想像する。「視る」という行為に意識的になる鑑賞体験でもある。
16mmフィルムに刻まれた気迫と生き様に圧倒される
16mmの映像から生き様が伝わってくる。岸井ゆきのがリングで拳を構える時、その鍛え込まれた俊敏な動き、瞳にみなぎる気迫と執念にただただ圧倒される自分がいた。勝ち負けなどではない。強いのか弱いのか、あるいはボクサーとしての才能に恵まれているのかすら関係ない。主人公にとってリングや潰れかけのジムは、己の魂を唯一ただひたすら燃焼させることのできる場所。絞り込まれた体と筋肉が躍動し、一発一発のパンチが鈍く乾いた響きを放つ。日常生活における意思疎通や感情表現を体全体を駆使して行うケイコだからこそ、彼女が闘う時、そこには自ずと人生の全てが凄まじいエネルギーで集約されていくのだろう。岸井ゆきのによる映画史に残るこの役どころに留まらず、カメラはその周辺に生きる人々にも目を向ける。とりわけ、岸井とは異なるリングで生きることの”闘い”を体現した三浦友和。三宅監督が描いた二者の対比とつながりと併走に心が震えた。
実在の人物からインスパイアされた物語。主役を演じた「岸井ゆきの」が役者としての勝負をかけた作品。
本作は、生まれつき聴覚障害を持つ女性がボクシングに挑戦する「実在の人物」からインスパイアされた物語ですが、劇中で音楽を一切使わないなど、様々なリアリティーにこだわった意欲作となっています。
そして、本作で注目すべきは、何と言っても主役を演じた「岸井ゆきの」の存在感でしょう。
私が初めて「岸井ゆきの」を認知したのは、「愛がなんだ」(2019年)のスマッシュヒットを受けてからです。「神は見返りを求める」(2022年)から体を張りだしたなと変化を感じていましたが、本作では、役者としての「勝負をかけてきたような本気度」を強く感じました。
「岸井ゆきの」の演技は必見レベルですし、彼女を見守るボクシングジムのオーナー役の「三浦友和」の演技も相乗効果を上げていました。
欲を言えば、もう少しボクシングのシーンを見たかったですが、様々な葛藤を描いた作品なので、それを踏まえておけば問題はないでしょう。
16ミリフィルムで撮ることにより、事前に徹底的に準備をし、必要なものだけを撮るなど、様々なチャレンジをしていて、役になりきった「岸井ゆきの」の演技は「賞レース」等で大いに注目されるのは間違いないと思います。
ケイコ 目を澄ませて
立派なボクシングテクニック
「特別に」見ていないか?
ボクシング映画は当たりが多いなんて話も聞く。邦画だと「Blue」とか「百円の恋」とか。この作品もその仲間に入れて欲しいと思える。自分には全く分からないけれど、ボクシング映画の醸す魅力というのはなんなんだろうね。
シンプルに良い映画だったなと感じるのです。
本作の印象的なところとしてはサウンドエフェクトの大きさだろうか。
耳が聞こえない主人公でありながら音が大きいというのは、よくある、主人公と似た体験を視聴者にさせるというのとは違うだろう。
となると、観ている私たちはケイコと対戦するボクサーや、周りの人間ということになる。
先日ジェーン・カンピオン監督の「ピアノレッスン」を観たのだが、主人公は話すことが出来なかった。
その主人公に対して周りの人間は「おかしな人」という扱いをした。話せないというだけで。
人は自分と違う人間に対して普通ではないというジャッジを下しがちだ。自分が標準であると考えるからだ。
では本作のケイコに対してはどうだ?。
ケイコの周りの人間と同化させられている私たちは、危ないからとボクシングをやめさせたいか?。もしくは応援したいか?。この作品が伝えたいところとしてはどちらも違うのように思う。
ケイコは耳が聞こえないことで周りの人間に対して負い目を感じていたように思う。迷惑をかけているのではないかと。周りの支えに値しない人間なのではないかと。
エンディング。
ケイコは対戦相手のボクサーとたまたま出会う。そこで礼を言われた。
相手のボクサーからみれば自分と対戦してくれたケイコは自分を支えてくれた人ということになる。
そこでケイコは誰かに支えられているのは自分だけではないと気付いたのかもしれない。耳が聞こえないことで自分をある意味で特別扱いしていたのは自分自身だったのだと。
そして観ている私たちも、耳が聞こえないからと良くも悪くもケイコに対して「特別に」見ていないか?という警鐘だった。
「女性なのに」とか「耳が聞こえないのに」といった謎の理由づけは必要ないのだ。
ケイコを演じた岸井ゆきのはかなり良かった。ボクシングシーンも頑張ってたよね。
そして、ジムのオーナー役である三浦友和は少ないセリフの中でも印象を残したと思う。
セリフの少なさで言えばケイコはもっと少ないわけだけれど。
あんな優しさが映画にあったとは
スポーツ純文学
元ボクサーの自叙伝「負けないで」を原作にしたこの作品
そして純文学的にこの物語が描かれている。
聾唖
健常者には嫌でも入ってくる音 雑音
音の周波数が捉えられないケイコ 彼女の世界
ボクシングを始めようと思ったきっかけは定かではないが、記者の質問に会長は「いじめでグレていた反動かも、喧嘩が強くなりたかったのかな」と答える。
ケイコは日記を書いているが、そのほとんどがボクシングの練習日誌のようだ。
ホテル清掃の同僚から「仕事とボクシングの両立ってすごいね」といわれ、「仕事のストレス発散のため」だと答える。
しかしケイコにとって、ボクシングほど打ち込むことができるものと出会ったものは初めてだったのではないかと思った。
試合の緊張感
相手に勝つことこそ、彼女が今までしてきたことが正しいと証明されることだと、そう信じていたのではないかと感じた。
それは単に練習そのものではなく、考え方や生き方など、彼女自身のすべてが「間違ってない」と証明されることことと同じだったのではないか?
少なくともそう信じていたように思った。
弟の彼女 ハナ
ケイコにとってハードルが高いのが「彼氏」を作ること。
健常者の弟はそんなことも難なくできる。
それが、ケイコが無意識的にハナを無視した理由だろう。
ケイコの迷い
ケイコは、好きでしているボクシングと母の心配を天秤にかけた。
ボクシングをすることで他人からとやかく言われたくはないが、昔グレていたころに母を精神的に傷つけたことが、ケイコの頭の隅に残っているのだろうか。
自分のためにしていることと、他人のために止めることを天秤にかけた。
同時に感じる疲れのような脱力感
会長に手紙を書くが、なかなか渡すことができない。
そんな中で起きたジム閉鎖 移籍
会長が倒れて入院したこと
ケイコにとって、いろんな出来事に対する感情の優先順位がぐちゃぐちゃになってしまった。
彼女は完全に自分自身を見失ったのだろう。
弟が「最近イライラしてない?」と尋ねても、それに反論するかのように答える。
自分自身がわからなくなったことを誰かに伝えることもままならない。
そして同じように過ごそうとしても、ボクシングに向き合えなくなった。
音が聞こえないもどかしさ
以前はボクシングに気持ちをぶつけることができたが、今は空虚な感覚しかない。
聾唖者が感じる閉塞感
それをこの作品は描いているのだろう。
心で感じることは、健常者とは違うと思っているのだろう。
どっちが正しいのか、ケイコは絶えずそんなことを思いながら生きているのかもしれない。
会長が入院した後、指導者とミット打ちしていたら、指導者が泣き始めてタイムを取った。
ケイコは彼の気持ちがわかったのだろう。
同じ気持ち
自分も人と同じ気持ちを共有しているということに気づいたのだろう。
満を持して出た試合
レフリーの見落としによる理不尽なダウン
それに怒り、自分を見失い、カウンターを決められてKO
試合に負けたという意味 「私は間違えている」と受け取ってしまう。
練習に身が入らないまま河川敷に佇む
そこへやってきた作業員 試合相手
「試合、ありがとうございました」
この純粋なスポーツマンシップと彼女のいでたちを見たケイコは、彼女の中に自分自身を見たのだろう。
親の心配やなぜボクシングしているのかという疑問
辛い毎日のスケジュールと練習に感じる、報われない気持ち。
迷い
ここにこそ自分自身が向き合うべきものがあった。
それをケイコは再発見したのだろう。
好きなことを純粋にしているだけだった。
最古のボクシングジムの閉鎖は、物事の変化を象徴している。
そして、好きなものを好きでいながら続けていく想いは、変わらない人の気持ちを象徴している。
それでも時折こんな風に流れに乗れない時もある。
しかし流れはまたやってくる。
変わらないものなどない無常の世界
そして何より、聾唖者も健常者と同じ気持ちを共有できることを知ったこと。
これがケイコの気づきになったのだろう。
静かで、雑音しかない都会の音
そんな音さえ聞こえないケイコ
耳を澄ませないケイコに、目を澄ませと付けたタイトル
目を済ませて見えた気づき
なかなかいい作品だった。
画面が暗い
聾唖の女性ボクサーのお話。
鑑賞中「果たして主演はろうあ者である必要があるのだろうか。」と思った。聾唖故に事情を知らない人に誤解を招くシーンなどが挿入されているが、傑作とは言えないけれど、同様のテーマの「コーダあいのうた」の様に、「聾唖」の事実が上手に脚本に練れ込まれていなかったのは残念である。
カメラや記録媒体の発達で、光量が少なくても映像が撮れる様になったのは良いが、いかにも流行っていそうな他のジムのシーン以外は暗い画像が続くのは気になる。もう少し明暗にメリハリが有れば良かった。
ただ、観客としてだけでなく、自分もボクシングをやってみたいと思わせる構成力は良かったので、その分星を0.5加えさせていただいた。
岸井ゆきの、凄くいい。
映画はワクワクするスリルやサスペンス。はたまた不幸のどん底ストーリーで観客を惹きつけたりするものである。だいたいは。
しかし、ここまで淡々と一人の女性を描くドラマになると、かえって、とてつもなく惹きつけられ、じゅわんとした感傷にひたれ、心地よい気分になれる。
聾啞者でボクサーという主人公のキャラクターはとても特徴的ではあるが、ストーリーの中に大事件も大事故も不幸の押し売りもない。
そして、主人公の周りの人々も皆、ケイコのことが好きで良き理解者である。意地悪な人なんかも出てこない。それがとても良い。
ジムの会長を演じた三浦友和がケイコを「人間としての器量があるんですよ」と記者に答えていたように、岸井ゆきのは映画の中で、直向きで努力家で人に優しい主人公を演じた。しかもセリフで発したのは、か細い声の「はい」とボクシングの試合で吼えた「うぉー」のみで、あとはしかめっ面の表情と時折みせる笑み。殴られた顔でさえ愛しく思えてくる。
岸井ゆきのは主演女優賞級の役者になったのでは?
とてもいい映画です。最高の作品に出会えました。
岸井ゆきの、虚空を見つめすぎ問題勃発
何かの作品でも同じような寡黙キャラあったぞ。
タイトルと主人公の障害とは裏腹に、音にケアした作品で、ミット打ちや鳥のさえずりなどの環境音の音量をあえて上げてるんではないかと。最後の試合もあっさり描くあたり、主人公含む一人一人の日常を見てほしいという監督の思いが伝わってくる。エンディングで対戦相手とばったり会ったあとの何ともいえない空間、時間、心情がこの映画を体現している。
次のジムに訪問する際に、トレーナーが警備員の恰好している場面が作中ではまったく言及されてないが、たったその絵だけでこの人物の苦労とそれでもボクシングが好きなんだということが想像できて、個人的には一番好きなシーンでした。
負けないぞ❗️
岸井ゆきのさんの聾者の演技、
演技では終わらせないボクサーとしての体、
フットワーク、パンチ力、技に感嘆した作品。
顔の表情も、『愛ってなんだ』と別人。
聾者でプロボクサーになったケイコ、
足さばきも堂に行っている。
ホテルの仕事と掛け持ち。
弟とルームシェア。
会長役三浦友和さん、むさい雰囲気醸し出しても
往年のイケメン、ロマンスグレー🩶
ケイコ勝つ。母と弟観戦。
母は試合後、もうやめてと言う。
ケイコの左目、お岩さん風。
考えるケイコ。
インタビューで会長が耳が聞こえないことは
致命的❗️と言う。
ケイコの人間としての器量でここまで来た、とも。
弟だけでなく同僚とも手話会話。
会長の奥さん役仙道敦子さんに驚き‼️
ケイコ不安定。
聾者の友達と喫茶店で語らうが。
ボクシング🥊ができたこと。
プロになれたし、勝ったし。
これから先のこと❓が悩み?
ちょっと当分休もうか?
ジム閉鎖してしまう。
会長の身体思わしくない。 って松本泣く。
でも会長は前向き。
試合で負けた。
堤防でぼんやり座っていると、
近くで工事中の現場から作業服着た対戦相手が、
自分を見つけて近づいて来て
気をつけして頭を下げて自分に試合の礼を
言ってくれた。
その真摯な姿を見て、
ケイコ、
またファイト湧いて来たやんか‼️
何回も観ていたのにレビューまだでした💦
ジムのコーチ役の松浦慎一郎と三浦誠己の両名がいい味だった。 ジムの会長三浦友和と久しぶりに見た妻役の仙道敦子も印象的だった。
動画配信で映画「ケイコ 目を澄ませて」を見た。
2022年製作/99分/G/日本
配給:ハピネットファントム・スタジオ
劇場公開日:2022年12月16日
岸井ゆきの(小河ケイコ)
三浦誠己(林誠)
松浦慎一郎(松本進太郎)
佐藤緋美(小河聖司)
中原ナナ
足立智充
清水優
丈太郎
安光隆太郎
渡辺真起子
中村優子
中島ひろ子(小河喜代実)
仙道敦子(会長の妻)
三浦友和(ジムの会長)
三宅唱監督といえば、「きみの鳥はうたえる」(2018年)を見たことがある。
ケイコの弟役の佐藤緋美は浅野忠信の息子らしい。
耳が聞こえない元プロボクサー・小笠原恵子の自伝『負けないで!』が原案。
ケイコは、生まれつき両耳が聞こえない。
しかし、彼女はボクシングジムに通うプロボクサーである。
デビュー戦と第2戦を勝利した。
母親からは「いつまで続ける気?」と問われる。
ケイコ自身も、ボクシングを続けるかどうかの悩んでいる。
ジムの休会を願う手紙を書いたが、
会長に手渡すこともできずにいる。
ケイコはジムが閉鎖されると知り、次第に心が揺れ始める。
主演の岸井ゆきのだが、
手話とボクシングの両方を習得するのは大変だっただろうと思う。
ジムのコーチ役の松浦慎一郎と三浦誠己の両名がいい味だった。
ジムの会長三浦友和と久しぶりに見た妻役の仙道敦子も印象的だった。
映画冒頭からラストシーンまでずっとエモーショナルな雰囲気がとても良かった。
満足度は5点満点で5点☆☆☆☆☆です。
聴こえない世界にいつのまにか没入する
評価が難しい作品
全276件中、1~20件目を表示