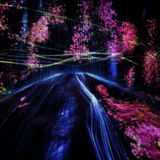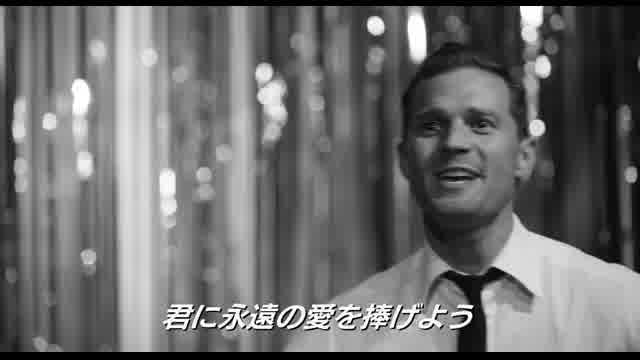ベルファストのレビュー・感想・評価
全278件中、61~80件目を表示
時間の無駄でした
予告編を観て「つまらなそうだな」と思ったのですが、なんかちょっと気になったので観にいきました。
でも、やっぱりつまらなかった。時間の無駄でした。
こんなことを言ってはなんですが、ケネス・ブラナーの思い出話(?)にえんえんと付き合わされているような気持ちになりました。
モノクロームで撮る必要性も感じられなかった。デジタルの白黒画面は黒の締まりがないし、なんだか薄っぺらいですね。
「女性の心をつかむには、――ただ愛することだ」とか、おじいちゃんは、なかなかいいこと言ってたけれど。
どうもストーリーに入り込めないので「脚本が悪いのかなぁ」と思いながら観ていたのですが、な、な、なんと、これ、アカデミー賞の脚本賞を受賞したんですね。「やっぱり僕の見方が浅いんだなぁ」と大いに反省したかというと、そんなことはまったくなくて、「アカデミー賞がなんやねん!」とあらためてメラメラと闘志がわいてきた次第です。
というわけで、人生の半ばを過ぎて残り時間の少なくなったような方には、あまりオススメできません。
この世で観るべき映画はほかにたくさんあります(『ベルファスト』のファンの人、ゴメンね)。
家族
挿入歌が多く、映画を見ながら疲れてくるのを感じた。しかし、これらの歌詞とストーリーのマッチしていたようだ。 ベルファスト生まれの、バン・モリソン、が音楽を担当、それに、この映画は北アイルランドのベルファストで育った、ケネス・ブラナーの話のようで(映画の最後)で、彼が監督してるんだね。ケネス・ブラナーは子供の時、『チキチキ・バンバン』や『失はれた地平線』(おばあさんが好きだった?)ジョン・ウェインの映画などを見て育ったんだね。当時のエンタメと言ったら、ゲームやネットがあるわけでなく、家族で映画を見に行くのが最高の楽しみだったのではないか?子供の頃の興味が彼のキャリアになったわけだが、三つ子の魂百までの例えがあるように、人間形成・興味などは子供の時に受けた影響に左右されるのだろう。 私も、ハリウッド贔屓の大正生まれの父親に育ったので、よくコタツのお前で、映画鑑賞させられた。父との最後の映画はミニシアターで観たロシア映画の『父帰る』だった。その後、映画・読書から離れることがなく、今でも続けている。 こんなもんさ!!
家族の影響は多大だよ!
多くの人が見ていて、レビューを書いているので、みなさんのコメントを読んだ方がいいと思うが、
好きなシーンはバディ(ジュード・ヒル)が『バイオロジカル』という洗剤をいつまでも大事に抱えているシーン。不思議なくらい可愛く見えた。それに、この主役の笑い顔はケネス・ブラナーとよく似ている。なんで、スーパーマーケットに母親に連れられて行った時、洗剤を置いてこれなかったのか不思議だった。多分、私はそのシーンをよく理解できていなかったのかもしれない。
ケン・ローチ監督の『ジミー、野を駆ける伝説(2014年製作の映画)Jimmy's Hall』 『麦の穂をゆらす風(2006年製作の映画)THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY』 などでアイルランドの宗教・政治闘争の歴史は少し学んだが、ベルファストを観た時、何もかも忘れていた。北アイルランド(イギリス領)の中心地ベルファストで、かなり昔のイメージがあったピューリタン革命、同じキリスト教でもカトリックに対する迫害の強さはこの北アイルランドでは何年も繰り返し起こったんだね。ケネス・ブラナーの家族はおばあさんを除いて、イングランド本土に移住していく。複雑だけど、この移住がケネス・ブラナーにより映画の道を進ませたのかもね。 それに、テレビに出ていたけど、ハロルド・ウイルソンが首相だったんだね(18歳以上の男女に選挙権を与えた首相)。
いい映画なのに、『カモン・カモン』を観た後だっから。
環境にやさしい洗剤♡
いいね!
悪しき時も肯定しきるヒューマニズム
大人の理屈。
子供の無邪気。
愛と暴力と、絆と断絶と。
誰もがうまく、良く、生きようとするほどに
上手く行かないその相手が「世の中」という
これほど大きなものはないはずもまるで見えない相手。
翻弄される主人公一家はどこにでもいる
きっと平凡な家族で、だからこそ時代を象徴しているように感じられた。
監督の半生を題材にしていると聞くが
克明に当時を描写した演出が秀逸なれど、
それをノスタルジックだといったところでセンチメンタルにはなっていない。
モノクロで映し出されておな力強く、イキイキとした伸びやかさにまみれると
そこに作り手が人を強く信じていることを、その温かな眼差しを感じて止まなかった。
古くとも「良き」時代とは言えなかった当時だが、
それすら肯定するような人間愛が本作を骨太に押し上げていると感じる。
そんなヒューマニズムがじんわりと、底から確かに伝わる一作だった。
一見ダメ夫かと思いきや、頼れるとーちゃんだったり、
最悪な夫婦仲かと思いきや、信頼し合っていたり、
老夫婦のストレートなのろけにほんわかしたり、
子供らの悪さに眉をひそめたり。
光景には日本なら、「昭和」という時代を過らせるのではなかろうか。
それにしても洗剤を選んだ理由が、地球に優しいからは吹いたなw
バディー君の質問に自分ならどう答えるのか
史実を残すための記録映画
そこで生まれ、育たないと分からない、人の気配、匂い、感情まで詰め込んだ映画でした。
その街の歴史博物館の一角の室で永遠に上映されるべき作品だと思います。
ただ、映画としてどこか特筆すべき点や、個人的に変化をもたらされたものはありませんでした。
レイトショーで見ましたが、10人ほどいて、3人くらい寝ていたのが確認できました。
本作にアカデミー作品賞を獲って欲しかった、という声が上がるのも納得の、魅力溢れる一作。
ケネス・ブラナー監督の半自伝的な作品である本作、映画監督の少年時代が物語の下敷きとなっている点や、モノクロームを基調とした映像といった様々な点で、アルフォンソ・キュアロン監督の『ローマ』(2018)を彷彿とさせます。もちろん両作は非常に完成度が高く、それぞれに多くの見所がありますが、本作は特に、家族、隣人一人ひとりの多面的な描き方が非常に印象的です。そこに、長年培ったケネス・ブラナー監督の人物観、そしてその表現方法の巧みさが光ります。
主人公バディの父も母も、それなりに魅力的で、自らを省みず「善きこと」を為そうとする意思を持った、いわゆる「善人」です。ところが日常のそこかしこで、実にどうしようもない部分も垣間見えたりします。そうした多面的な側面を描き分けることで、より人間味を持った、愛すべき人々として強く印象づけられます。それは近隣の住民、知人も同様で、ジュディ・デンチら老夫婦はもちろん、特にバディの、年上の女友達の振る舞いには驚き。『ジョジョ・ラビット』のトーマシン・マッケンジーのような位置づけなのかと思ったら…。
本作は1969年の、北アイルランド問題に揺れる最中のベルファストを舞台にしているため、作品の全体像を理解するためには、どうしても概要程度でも当時の状況を知っておく必要があります。そうでないと、なぜ主人公達は暴徒に襲われるのか、そして暴徒達は誰なのか、が分かりにくいためです。ただバディも、突然降りかかる理不尽な暴力の意味が全く分からないまま日常を生きているため、敢えて情報を入れずに、あくまで彼の立場で作品を鑑賞するという見方もあります。バディと隣人達が交流する場所とか、一瞬カラー映像となるある場面など、印象的な映像や台詞を挙げればきりがない作品。第94回アカデミー賞では残念ながら作品賞は逃しましたが、多くの人がこの作品に獲らせたかった、と言うのも納得の、魅力に満ちた一作です。
子供の記憶でもただ優しく美しいなどということはない
少年の目が、訴えかけてくる
ケネス・ブラナー監督が自らをを投影した、愛らしい少年が主人公。彼は生まれ育った北アイルランドの街で家族に慈しまれ、同じ路地に住む人々と笑い合い、TV番組や映画を、同級生の少女を、そして突如街を襲ってきた過激派たちを、目を見開き見つめる。その心に刻まれた喜びや悲しみ、戸惑いや疑問が、モノクロ映像を通して深く染み込んでくる。
結束の固い隣人たちの間に、宗派の違いというもっともらしい理屈を暴力的に投げ込み、憂さを晴らしにくる外部の大人たち。
悲惨な場面は撮らず、少年の目が捉えた世界を作品の軸に据えたところに、監督の信念を感じた。子どもは、未来は、守られるべきものであり、それは私たちの選択次第で可能になるのだと。
鑑賞前の前知識は必要です
今こそ、公開する意義がある作品
北アイルランド紛争の直下、首都ベルファストがあれほど荒んだ状態だったことに驚く。つい数十年前のイギリス国内でのことだ。(燻りは現在も残っているらしい)
アイルランド島の北東端の国である北アイルランドは、アイルランド共和国と分離して連合王国に属するという、イビツな状態。
加え、移民とアイルランド先住民の民族対立や、プロテスタントとカトリックの宗派対立が絡み合う。
自分は、このへんの歴史にも社会情勢にも疎いので、よく理解はしていないけれど…。
この街で育ったケネス・ブラナーの実体験が、この映画には反映しているという。
ハードな背景設定ではあるが、所々にウィットがあり、画的なエンターテインメント性もある。
渦中のベルファストに暮らす家族。
子供たちを必死に守っている母親は、夫の行動に不満を持っている。
どんな環境下であっても、夫が外で働き妻が子供の面倒を見ている家族に生じる亀裂というものの本質は変わらない。
幼少期のケネス・ブラナーを投影したバディ少年(ジュード・ヒル)からの視点を反映して、父母はパパとママであって名前が出てこない。
母親の両親や姉などの親族も暮らしているこの街を出るか、留まるか…。母親は厳しい選択を迫られている。
この母親を演じたカトリーナ・バルフが私は好きだ。
子供を守ることを課せられた母親の強さと弱さを確実に表現していたと思う。
ファッションモデルとして輝かしい経歴を持つ彼女は、女優に転身して始めて主演したテレビドラマ「アウトランダー」で惜しげもなくスレンダーな肢体をさらして熱演していた。
本作でも、ミニスカートからスラリと伸びた美しい脚が魅力的だ。
スーパー襲撃事件からの一連のエピソードが、母親の毅然とした強さの裏にある女性の非力さを示し、父親(ジェイミー・ドーナン)の頼もしさを見せるエンターテインメントになっていて、ケネス・ブラナーの演出が冴えている。
遂に、親子は祖母を残して街を出る。
祖母を演じたジュディ・デンチが、振り向かずに行きなさいとバスに乗った娘一家に言う場面は、アカデミー賞助演女優賞に彼女がノミネートされたので、何度となくメディアに流されていた。
深くシワが刻まれたデンチの表情を正面からアップで捉えた、重みのあるシーンだ。
群で生活する人間が知性をもったその時から、縄張り争いと他の群との対立が宿命のようにつきまとう。
その人類の宿命が、ヒトラーやプーチンのようなモンスターを産み出したのだ。
今、不安定なこの世の中だからこそ、この映画が問いかける何かを、考えたい。
家族愛と故郷の大切さ
未来に笑おう
パンフレットにあった
「明日に向かって笑え!」
なんて素晴らしい言葉なのでしょう。
アイルランドのベルファストという街で宗教の違いによる争い。
それまで、仲良く近所つきあいをしていた住民が翻弄されて、
子どもたちまで、そこに巻き込まれていく。
そんな中でも日々の暮らしを大切にしながら、
前を向いて生きていく家族の在り方、絆、愛…。
おじいちゃんの笑いを含んだ導きも優しい。
そして、若い家族の未来へと背中を押す
おばあちゃんの姿に、じんわりと温かい涙が流れました。
パの家族を守る強さ、
マの生まれた場所を思う気持ちから、
子どもたちの未来を考えた決断への心の動きを現した
脚本も素晴らしかったし、
家族での映画鑑賞でのカラー使い、カメラアングル、
そして、何より、ヴァン・モリソンの音楽が、モノクロにマッチして、最高でした。
本当に愛に溢れた作品でした。
補足
最近、海外ではモノクロが流行っているのかしら?
立て続けに三本観た中で、
この作品が一番しっくりと、敢えてモノクロ映画を観ているという意識なく楽しめました。
モノクロでも、色味のセンスって大切。
とにかく、バディ少年が、可愛い🎵
アイルランドの歴史云々、知らなくても大丈夫
有り難うグランマと、静かに言いたい
音楽も映画もテレビドラマもコミクスも、オモチャも懐かしいけれど盛りすぎ。回想が全然ついていけない。ラクウェル・ウェルチ! ジョン・ウェイン、サンダー・バード…
◉右も左も対立ばかり
プロテスタントとカトリックの対立と、プロテスタントの中の急進派と穏健派の対立があって、更にベルファストの存在するアイルランドとイングランドの反目がある。
だがしかし、そうした剣呑な周囲に振り回されてしまう家族の話ではなく、圧力を受けながらも頑張る一家の話。
◉軽く傷つきながら生きていけ
パパは渋い渋い顔でバスに乗り、ママは美脚をバタバタさせて騒いで、兄は黙って俯き、バディは真剣な眼差しで人や街を見つめる。で、グランパとグランマは家族全てのことを呑み込んだ上で、表面は面白く可笑しく暮らしている。
人生は軽く傷ついたり胸を張ったりしなきゃ生きていけないんだから、あまり深く考えすぎないで行動してみろと、孫に悟すグランパ。ストッキングのパチ物を作ったグランマは、可憐だったんでしょうね!
孫を挟んで二人が並んで座ったシーンは、熱くはなくても、本当に温かでした。
◉長く生きていりゃ
でも、長く生きていくうちには、嫌でも悲しいことがたくさん起こる。笑ってる子供が、いつも心まで笑ってる訳じゃない。
それでも、この場所でまた立ち上がって生きていくしかない。何か気の利いた飾り言葉でも付けたいけれど、それだけのシンプルセンテンス。イングランドへ住まいを移そうと言うパパとて、止む無くそう思うだけだ。
グランパは亡くなりグランマを残して、家族はイングランドへ。それでも、バディの彼女が、うん待ってると小さく言った時は、泣けましたね。
グランマの、さぁ皆行きなさいの言葉には本当に力づけられました。有り難う、おばあちゃん。
一家の季節は、大半が春でした。
とんでもない9才
全278件中、61~80件目を表示