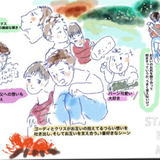コーダ あいのうたのレビュー・感想・評価
全170件中、81~100件目を表示
聾唖の苦悩と希望を描く傑作
特質すべき点は多々あるが、多くは語らない。
子を持つ父親である自分が、一番胸に響き、泣いてしまったシーンについて。
終盤。
歌の発表会で、主人公のルビーが、大勢の観客と聾唖の家族が見守る中、その歌声を披露するシーン。
歌い始め、その美声にうっとりした瞬間、突然、映画の全ての音がシャットダウンする。
耳が痛くなる程の静寂。
ルビーの美声に酔いしれる観客の映像とは裏腹に、不気味なほど不釣り合いな「沈黙」だ。
ここで映画を観ている我々は、ハッと思い知らされる。
そうだ、聾唖の家族の世界では、常にこの「沈黙の世界」なのだ。
結局我々映画の観客も、「分かったつもり」でこの作品を観ていなに過ぎない。
声も歌も音楽も聴こえていた前半は、聾唖者の気持ちなど分かりえなかったのである。
父親は娘の歌声に感動する人々の表情をじっと見る。
皆、娘の歌声に涙している。間接的にしか分からないその歌声に、父親の表情は暗い。
誰より娘を愛している筈の自分は、その声が聴こえないのだ。
その日の夜、父親はルビーに「自分の為に歌ってくれ」と言う。
そして歌うルビーの頬を、喉を指で触り、聴こえない娘の声を感じようとする。
最も愛する子供の声を聴けない絶望と悲しみを、まるで今初めて思い知ったかの様に。
聞こえる筈のない声を必死に聴こうとするその父親の気持ちに、自分は涙を禁じ得なかった。
誰も悪くないストーリー
外野からみれば、マサチューセッツの漁村に生きる彼らの世界は美しいと思ってしまう。
それは外野だからで、実際の彼らは、魚の臭いをまとっていたり、生活もぎりぎりで、余裕なんてとてもない。リアルは生々しいはずだ。
この家族だって、外からみれば、ただ温かいだけのストーリー。でもリアルはもっと生々しく、愛だけでは割り切れない現実がある。家族を愛していても、家族が困るとわかっていても、自分の才能をのばして違う環境で羽ばたきたいって望みは抱いたっていいはず。そして家族はそれを手放しで応援してやりたいけれど、現実は手放しとは言えない。
演奏会で歌がきこえないからと手話で会話する両親。その後で、彼らの世界を体感させられることで、彼らの感覚にちょっとだけ近寄れる、あくまでちょっとだけ。
よくある優しいストーリー。ちょっと切なく、ちょっと温かい。
久々号泣した
まず主役のルビーちゃんの歌声の沁みること!
漁業という異色の組み合わせも面白い。
そして手話で語られる言葉と感情の幅広さと深さ。どこまでリアルかわからないが驚かされる。
そして聾唖の家族の逞しさよ。
父母兄と全員聾で、かつ家族に健聴者もいるからこそ仕事も成り立ち、家族の中では怯えることなく、遠慮することなく、明るく生きてこれたということなのか。きっと日本ではこんなに前向きにいられる環境はあまりないのでは。。と思った。かといって周りも優しい訳ではなく、ひどいイジメや中傷に晒される。なのに強く生きている。
うるさい兄の頼もしさ。後半の怒りの台詞が心に響く。かわいそうと色眼鏡をかけてみていなかったかと省みる。助けているつもりが本当に彼の頑張りの横槍になっていたのかと。
コンサートのシーンの演出は予期していたものの、感情移入して涙が止まらなかった。なのに静寂の中泣けない鼻噛めない辛さ。。合わない手拍子を見るステージ上の娘の気持ちはどんなだろう。
映画としてもとてもテンポ良かった。膝に乗せた荷物を後で床に置こうと思ったままひきこまれて気づいたら終わってた。手話シーンが多く、字幕を見るのに忙しかったのもあるか。
実際日常の手話は伝えたいことをもっと端的に伝わるよう表現しているのだと思う。けど、愛の言葉や卑猥な言葉、怒りや複雑な感情まで映画のように手話で表現できるとしたら、本当に大事な手段。今はテクノロジーも寄与するとしても、もっと健聴者にも浸透するようにできないかと思う。
大好きな映画になりました。
映画館のロビーで予告が流れていて気になっていました。
公開期間中に観にいけず、映画館で観ることを諦めていましたが、アカデミー賞後に上映を再開する劇場があり今日行ってきました。
予告みて泣きそうになっていたので一応ハンカチを持っていきましたが、持っていって正解でした◎
ルビーがオーディションで「青春の光と影」を手話をつけて歌う場面が本当に良かったです。
学校の合唱クラブの発表会で、お父さんが周りの人の表情や様子を見て娘の歌の素晴らしさを感じているのも良かったです。
愛は家族と歌声の中に
祝!本年度アカデミー賞作品賞受賞!
本公開は1月21日だったけど(ちなみに私の誕生日)、隣町ではロングラン上映しており、オスカー受賞した事もあって、ミーハーながら観に行ってきた。
公開時からの評判の良さは聞いており、勿論気になっていた作品だったので、絶好のタイミング。
にしても、本作のオスカー作品賞は驚きだった。当初は本命でも何でもなかった。
だって、作品賞を狙うのに絶対候補を落としてはならない監督賞や編集賞にノミネートされず。ノミネートされたのはたったの3部門(作品・助演男優・脚色)。おまけにフランス映画のリメイク。
なのに、徐々にダークホースになってきて、オスカー直前の組合賞を受賞してからは本命視に。その勢いのままオスカーもかっさらっていっちゃった感じ。
まあオスカーでは度々ある番狂わせとは言え、如何にこの作品が愛されたかという事だろう。
実際作品を見て、納得。
今回の作品賞ノミネート作で、(まだ全部は見てないが見た中では)、一際インパクトあったのは『パワー・オブ・ザ・ドッグ』。個人的に推していた。
紛れもなく傑作で2021年公開作の中でもBEST級だが、見る人を選ぶ。支持する人は支持するが、支持しない人からは拒絶される。それほど異質な作品。
2018年の『ROMA/ローマ』vs『グリーンブック』と似ている。実際、“2021年の『グリーンブック』”とも形容された。
誰からも愛される作風。よほどのひねくれ者か感動やハートフルが嫌い、はたまた全く映画を観ない人でもない限り、本作を嫌いになる人はそう居ないだろう。
“聾唖”を題材にしている以外、非常に普遍的な作品。砕いて言えば、ベタで王道。
耳が聴こえない家族(両親・兄)と、唯一耳の聴こえる娘ルビー。
ずっと周囲との“通訳”として家族を支えている。家業の漁も手伝う。実に孝行娘なのだが…、
学校では孤立。“コーダ”であるが故に。“コーダ”とは、耳の聴こえない親の下に産まれた子供を指すという。
歌う事が好き。合唱クラブに入る。動機は片想いの男子が入ったからなんだけど…。
顧問から歌の才能を認められる。コンサートに向けての個人レッスンと音大への薦め。
家族の事を思って留まるか、開けた才能に向かって進むか。
少女の葛藤、青春。
夢。
家族愛…。
話的にも題材的にも特別目新しさは無い。
が、それを実に巧く語っていく。
まるで、素敵な歌が心にスッと入っていくかのように、心地よく。
2時間があっという間。もっとこの素敵な歌声に浸っていたかった。
ルビーはまだまだ10代なのに、苦労や悩みが絶えない女の子だ。
荷が重いほど、色々なものを背負っている。
自分の事、漁業の事、家族の事…。
家族が大事。何より家族の事を思っている。
だから心配。私が居なかったら周囲とコミュニケーションが取れない。
漁以外何も出来ない。唯一出来る仕事。聾唖者の上に無職なんて、酷。
漁業組合でトラブル。金だけ搾り取っていく国の寄生虫に頼らず、自分たちで独立。尽力。
だけど、自分にもやりたい事がある。歌いたい。
どれが一番大事?…なんて優劣付けられない。どれも大事。
だから、悩む。悩む。悩む。
その姿に我々も一緒になって悩み、共感し、“エール!”を送りたくなる事必至!
母にとって娘はまだ“ベイビー”。が、父は“昔から大人”。
親の手を借りないと何も出来なかったら、“ベイビー”と呼ばれて致し方ないだろう。が、ルビーは真逆。寧ろ一人で、あれこれこなしている。
“ベイビー”なのは家族の方かもしれない。
娘が居ないと何も出来ない。周囲とのコミュニケーション、漁で娘不在時の通訳の手配など。
何もかも娘任せ。頼りっきり。
ルビー本人は家族を支えなければならない責任や役割を自覚しているだろうが、束縛や依存は双方にとっても良くない。
ルビーにも自分自身の人生や夢を追う自由がある。
本作は聾唖者であっても健常者と変わらぬ生き方(漁業で生計を立てる)やユニークさ(いんきんたむしになろうともSEXしたい!)を描きつつ、全肯定ではない。
ルビーが同行しなかったある漁で、沿岸警備船からの無線に気付かず、免停。
この時の無線は注意勧告だったが、もし急な嵐の接近とか、命に関わる報せの無線だったら…?
聾唖者だから無線に気付かないのは無理もないが、だからこそ尚更彼らにとっては生き辛い。
酷な言い方かもしれないが、最低限の準備や手配は自分たちでしなければならない。
いざって時、社会は助けてくれない。貧困層の障害者家族の事など殊更。
言葉で訴えが伝わらぬなら、行動で示す。例えそれが大荒れの海原への船出であっても。
まさに“ルビーの輝き”。エミリア・ジョーンズの等身大の魅力と好演。
手話と歌を学びに学び、取得。通常ならどちらかだけでも大変なのに、その二つを器用にこなす。
クライマックスは歌と手話を同時に。圧巻のパフォーマンス。映画史に残った名歌唱シーンと言っても過言ではない。
周りも実にいい。俳優組合賞のアンサンブル・キャスト賞受賞は、こりゃ当然。
『愛は静けさの中に』以来の当たり役で魅せてくれたマーリー・マトリン。ちょっと心配性でちょっとウザい母親を、いるいると思わせる。
気軽に手話で貶す呼び合いしながらも、度々本当に衝突する兄。妹は特に両親から頼られ、これでも“兄”という立場上うっすらジェラシー。それは同時に、妹を足枷から解放してやりたいという陰ながらの思いやりもある。
顧問の“ミスターV”も良かった。指導はかなり風変わりで型破り。しかし、“見る目”と“聞く耳”は確かで、指導者としての才能の引き出しは確か。ルビーにとっても夢へ進むきっかけを与えてくれた恩師。(やりようによってはルビーとミスターVだけでも、教え子と恩師の一本の作品が出来そうなくらい)
そして、本作の“大黒柱”は言うまでもない。
トロイ・コッツァー。
誰もが彼に魅了される。
誰もが彼に笑わせられ、目頭熱くさせられる。
名演。熱演。体現。見る者の心を揺さぶる、助演の鏡。
ちょっとのお下品さ(いや、ちょっとどころではないかな…?)や不器用さは憎めず、チャーミング。
“海の男”としての逞しさ、荒々しさ。漁師たちと組合が集まった話し合いの場で、いつもなら耳が聴こえない故発言などしなかったが、溜まりに溜まり兼ねて発言。その内に込めた“言葉”に、皆賛同。それほど漁師として漢として、熱いのだ。
滲み出る家族への優しさ、愛…。
特筆すべきシーンがあった。クライマックスのルビーの歌唱シーンもいいけど、個人的に本作のハイライトだと思っている。
娘も出演するコンサートを鑑賞。コンサートの途中、無音になる。我々観客も父親と同じになった視点の演出で、
自分は耳が聴こえないから娘の歌声も聴こえない。が、周りの観客は娘の歌声を聴いて感動している。娘がどれほど素晴らしい歌の才能を持っているか…この無音になったシーンで実に分かる。
それを目の当たりにした父。支えられていた立場から、これをきっかけに娘を支え、夢へ応援。
名演も役回りもシーンも、全てが美味しい。
アカデミー助演男優賞は、『パワー・オブ・ザ・ドッグ』の“実は真の主人公”だったコディ・スミット=マクフィーを推していたが、こうして見てしまうと、コッツァーに一票投じたくなるのも分かる。と言うか、両人とも素晴らしくて決め切れないほど。2015年の『クリード』シルヴェスター・スタローンvs『ブリッジ・オブ・スパイ』マーク・ライランスに匹敵する頂上決戦であった。
コッツァー自身も聾唖者。彼が役者を志したのは、『愛は静けさの中に』のマーリー・マトリンを見て。そのマトリンと本作で夫婦役。
もう何て言ったらいいのだろう。数奇な運命、奇跡、巡り巡って至った必然…。
それはきっと、本当にある映画の不思議な力他ならない。
俊英女性監督シアン・ヘダーの温もり溢れた演出、優しい眼差し。
オリジナルは酪農らしいが(オリジナルの『エール!』はまだ未見)、漁業に変更。監督が海辺の町で育ったらしく、自身の思いを美しい海辺の町の風景に込めて。
コッツァーやマトリンら実際に聾唖者をキャスティングしたこだわり。昨年度の『サウンド・オブ・メタル 聞こえるということ』共々、今後の聾唖を題材にした作品へ多大な影響を与え続ける事になるだろう。
それは同時に、障害者だからと言って不可能な事はない、何にでも挑戦出来、活躍の場が与えられ、自由に羽ばたけるメッセージが込められている。
オチも分かり切っている。分かっていても、いい。
やがて子供は巣立つ。それが大人になった子供というものだ。
家族はそれを見送る。それが家族というものだ。
「行け」…父親が唯一発した一言がまた泣かせる。
支えて、支え合って。
例え離れようとも心はいつも繋がっている。
家族は変わらず一緒。
家族ももう自分たちだけのフィールドに留まらず、きっとやっていける。
愛娘も自分の夢をさらに目指していける。
そんな勇気に励まされて。
そんな愛に包まれて。触れて。
そんな家族の下に産まれて。
この上ない幸せ。
素敵なうたをありがとう。
音をみせる凄い映画
家族愛や歌の上手な主人公…きっと感動するだろうと思い見に行った。しかしそんな簡単な映画ではなくて『音』について考えさせられた作品だった!
背中かゾクっとして金縛りにあった様な感覚を映画館で味わったのは初めて。ある一瞬数秒だが体感した無音の耐え難い感覚はこれからも残るだろう。
ゼログラビティの時とは反対。
あの時は息が出来るとか緑が綺麗だとか嬉しい感覚が後から来たが今回は広い映画館で初めて味わう孤独で海の中にいるような静けさ。主人公の明るい家族たちとも対照的な孤独。こんな無音な中で生活をしている人たちが実際にいるのだと言う現実を思い知らされた。
観て本当に良かった!
一人で観に行くのがベスト。良い映画だった
主人公の家族がとても下品で最初最後まで見れるだろうか?って思いながら見てました。
知人とそういったシーンを一緒に見るのが苦手なので一人で行ってよかった。
ある種下品なそのやり取りも慣れてきて、最終的にとても感動しました。
父親の生き方には全然共感できないけど
耳が聞こえないが故に我が子の歌がステージで周囲を感動させているのに
他者の様子からでしか、それを感じ取ることが出来ない。
見てて切なくなったし、すごいシーンだなって思いました。
その後の野外で歌うシーンで少しでも我が子の歌を感じ取ろうとする父と
その父のために歌うシーンがドストレートに突き刺さりました。
泣いた泣きましたよみっともないくらい泣いた。一人できてよかったよ。
僕が見た時はエンドロールで誰ひとり立たなかったですね。
リメイクなのを知らないくらい不勉強な僕ですが、
すごくいい映画だったと思いました。
特殊性から考える普遍性
「耳の聞こえない両親のもとで育った子ども」というのは、あまりない環境だと思う。そういった環境に名前があることも、この映画を見るまで知らなかった。映画には、こう言った自身の知らないことを教えてもらえるという良い面がある。
しかし、この映画が素晴らしいのはそこだけではないように思う。この映画の中に描かれていたのは、伝える手段を持たない相手に、どうやって伝えるかという普遍的な「相互理解」だったのではないか。「歌うときどんな気分だ?」と聞かれたとき、彼女は「気持ち」という抽象的な概念を伝える「言葉」を持たない。そのとき彼女がたどたどしく表現した「言葉」がかくも美しく、感動的だったのは、苦しみながら紡ぎ出すように生み出されたものだったからだ。娘の歌を「聞く」ために、すがるように喉元に手を伸ばす父があんなにも悲しく美しかったのは、決して叶うことのないものを理解したいという渇望があったからだ。自分の気持ちや家族という、一番わかっていると思い込んでいるものに対して、わかり合いたいという人間の本質が描かれている素晴らしい映画だった。
I've looked at life from both sides now
I really don't know life at all
私は耳の聞こえない世界を本質的に知ることはできない。それでもその世界を理解したいと思う。私は何も知らない。それでも想いを伝えたい、想いを理解したいという気持ちは普遍的なものだ。この映画は決して自分と違う境遇の人間の話ではなく、私の話だ。アカデミー作品賞、伊達ではない。
う〜〜〜〜ん😓
今朝、朝イチで観てきました
昨晩観たオリジナルのフランス映画「エール!」と脚本、演出まで完全コピー😅
舞台と言語、歌曲がフランスから米国に変換
キャラクター設定もほぼそのままで、酪農家から漁師に家業を変えただけ
30分くらいからソックリさん疑惑がモヤモヤしだしてラストシーンまでキッチリコピー
音楽も全曲知ってるエモくない曲で旨味なし、エスプリが程よく効いた、よく出来た本家を堪能した後じゃ感動しないよね😕
これがアカデミー作品賞って?ドライブ・マイ・カーの方がずっと上質だ
カジュアルな印象でした!!
重苦しい雰囲気が好きという訳では無いですが、特に序盤は下ネタも多く全体的にカジュアルな印象でした。アカデミー作品賞か?と言われれば何か違うと思いますし、ジョン・カーニー作品(「シング・ストリート」、「はじまりのうた」等)やピッチ・パーフェクトの類似作だと思います。苛立ちを怒鳴り声や騒音で表すのは好みではありませんでしたが、一般的な日本人と違って親子共に思っている事をストレートに伝えるのは良かったです。しかし、ストーリーの肝は終盤の決断部分だと思いますが、お父さんからも特に言葉が無く、雰囲気で終わってしまって消化不良でした。合唱部なのに皆R&B歌手並みの上手さで主人公だけ際立っていたという訳では無いですし、彼氏と水に飛び込むシーンは3回も要らないと思います。特にオリジナル版を観てみようとは思えませんでした。
邦題の大事さ❗️ジュニアさんありがとう🙏
ずっと気にはなっていたのに、中々劇場に足が向かなかった作品。たまたま「にけつッ‼︎」という地上波のバラエティ番組を観ていたら、千原ジュニアさんが洋画の邦題の付け方が変だ!という回でこの作品も話題にだしてました。それを機に、劇場公開中に絶対に観に行くぞという気になり観に行きました。結果は大成功❣️
原作は「Coda」のみで邦題では「あいのうた」がつきますが、この作品でいうとこれ以上にない絶妙な表現の邦題だと思う。
主人公の高校生ルビーが家族のなかで、唯一の健聴者。家族の仕事、生活に幼い頃から通訳として欠かせない存在。差別も受けながらも、歌が好きで家族思いの本当に心の強い良い子に成長していく。そんな時に学校の合唱サークルで顧問の先生に歌の才能を見出される。この先生役の演技がまた良いんです❣️しかし、ルビー以外の家族3人はろうあ者でもちろん歌を聴くことが出来ません。歌うことと家業の板挟みになるルビー。諦めて家業に専念する道を選ぼうとするが、家族が徐々に彼女の歌の才能に気付き始める。合唱部のコンサート。1分間くらいの無音のシーンがこの作品のなかでの最高インパクト。ろうあ者の家族がこんなふうに無音で我が娘の歌を聴いてるのかと思うと切なくなった。それでも、家族はまわりの反応を見て娘の歌の才能を確信する。兄の言葉「家族の犠牲になるんじゃない」というセリフが頭に残る。ラスト、家族全員で向かった音大のオーディション。合唱部の顧問の先生のピアノ伴奏で歌うルビー。途中から家族に向けて手話付で堂々と歌う姿、家族の笑顔😃泣けましたよ本当に!ろうあ者を演じた3人は本当に凄い!手話も含めて相当な難易度な役を見事に演じました。最高に愛があふれる家族を表現するのに「あいのうた」の邦題はなくてはならない。今後は邦題を少し気にして映画を観ていきたい。最後にルビーの彼氏役が音大に落ちたのは、良い落ちでした。🤣
身障者を扱ってる映画とか、そんなの関係ない!最高の青春映画✨
とにかくルビーがいい!大好き!全力で応援したくなる。彼女が船の上で歌いながら漁をするファーストシーンから彼女の歌声、立ち振る舞いに魅了されました。
コンサートの無音の時間、あれは絶対映画館で味わってほしい。あんな体験初めて。
そして出てくる人みんな大好きになる。赤いほっぺのボーイフレンドもヤリマンな親友もクセ強すぎな先生もクソ兄貴もルビーに依存しまくってるけどルビーのことを愛して離したくないママもパパもみんな大好きー!!
A love song. 予告編通り感動できます
もう予告を観た時点で泣けるファミリー映画っぽいなっと思ってたのですが、本当にドストレートな泣けるファミリー映画でした。いやー、良かったです。
主演のエミリア・ジョーンズは海外ドラマの「ロック&キー」を観てて上手い女の子だなぁっと思っていたのですが、本作でもお見事でしたね。手話の表現もバッチリだし、思春期の将来に悩める若者を体現しています。甘酸っぱい恋の始まりとか青春だなぁ。
でも、あの両親は破天荒過ぎて自分の親だったら嫌だなっと思ってしまいました。観てる分には楽しいですけどね。特にあの親父‼️娘は思春期っちゅーねん‼️ちったぁ気を使えや‼️まぁ、何だかんだ言っても喧嘩してても深い繋がりのある家族は観てて良いもんなんですけどね。親父の為に歌ってあげたり。ルビーはホントいい娘さんや😢
そして、V先生。厳しいながらもちゃんとルビーの事を見ててくれて。試験の時に伴奏を買って出ただけじゃなくルビーのフォローもしっかりしてくれる。正しく教師の鏡ですね。
デュエットシーンで無音になる演出には何だかグッと来ました。耳が聞こえないとああいう状態なんだなっと印象に残るシーンでした。んで、試験の時に手話交えながら歌うシーンもジーンときます。演出が上手いですね。
しかし、こういう作品こそアカデミー賞取って欲しいもんですよね。批評家の方にはストレート過ぎるのかもしれませんが、何年経って観ても、どんな世代が観ても共感できる良い作品だと思います。
家族愛を感じたい人に観てほしい
家族の中でひとり健聴者だからこそ、耳の聞こえない家族から頼りにされてきた事もあるだろうけれど、それ以上に家族が仲良くユーモアたっぷりで、愛情深く育てられたからこそ、家族が大好きで、自分の夢より家族のサポートを選択したのかな。
責任感が強く、自分の夢をあきらめる決心をする主人公の気持ちを考えると切ない。
母親が、娘を反抗期だといって、親が耳が聞こえないから(当てつけに)合唱を始めたんだと喧嘩をふっかけるシーン、今まで耳の聞こえない両親+兄の通訳者となり、家業を支えてきた主人公の気持ちを考えると腹立たしく感じた。
と同時に、母親の気持ちを考えてみると、耳が聞こえないハンデを娘がサポートしてきてくれて、そのサポートが減ったり、なくなってしまうかもしれない不安、子供が自分の手の中から離れてしまう寂しさなんかがあったのだろうか。
子供のやりたいことや自立を応援したい気持ちと、これからの自分達の仕事や生活、将来の不安と入り混じった複雑な親の気持ちも分かる。
ハンデがあり、生計を立てるにも誰かのサポートが必要で、そんな状況で、私だったら、素直に子供の夢を応援してあげられるだろうか。
最終的にお互いを愛しているからこそ、認め合い、親も子供も自立していく。
主人公の歌のデュエットの相手の家族はそれほど仲が良さそうではない描写もあり、対比となってより家族愛について考える事ができた。
人生を両側から見てきた
ふだん、SFとファンタジー以外はあまり観ないのだが、「すごく良い」とすすめられて観たところ、すごく良かった! 映画で涙を流したのはだいぶ久しぶりだ。
CODAというのは、Children of Deaf Adultsのことで、聾唖者の親を持つ健聴者の子供のこと。主人公は聾唖者の家庭に生まれた唯一の健聴者で、家族の通訳として幼いころから家族を助けてきた。
障害者や多様性がテーマの映画だが、障害者が主人公なのではなく、健常者が主人公であることがこの映画のポイントで、とても重要な問題提起がされていると思った。それは、障害者や介護が必要な者などの家庭における、健常者の問題だ。
これは最近、ヤングケアラーや、障害者のきょうだいの問題として注目されるようになってきた。
障害者には社会的な支援があるのが当然である、という認識はずいぶん浸透したが、実際にはその理想通りには全くなっていない。その理想と現実のギャップの犠牲になるのが、障害者と直接接する立場にいる者だ。
そういった者は、障害者をサポートするのが当然という、本人にとっては理不尽な「常識」を受け入れざるを得なくて、自分自身の人生を選択する権利を奪われている場合も多いだろう。
障害者の家庭に生まれた主人公は家族を愛しながらも、家族の中では逆にマイノリティであり、ある種の孤独を抱えていたり、家族の犠牲になることを当然のように強いられることもある。
聾唖者の描き方もリアリティがある。障害者を理想的な性格の天使のように描く映画もあるが、この映画では人間としての障害者を描いている。障害を持っているがゆえに一人前の人間として扱われないことに強い苛立ちをもっており、過剰なプライドを持ち、そのために合理的な判断ができなかったり、社会との軋轢を生んでいたりする場面がある。
理想的な性格どころか、粗野で下品、反社会的な面もある。しかし、それを「障害者のくせにけしからん」と思う人がいるとすれば、それは「障害者は清く正しく慎ましく、できるだけ社会に迷惑をかけないように生きねばならないのだ」というひどく傲慢な差別思想を差別と自覚せずもっているということだ。
この映画が本当に優れていると思うのは、「歌」ということを軸にして、さまざまな角度から聾唖者と健聴者とのコンフリクト(対立・軋轢)を描いている、ということだ。
印象的なシーンがいくつもあるが、そのほとんどは「歌」に関係する。物語の背景で示されたさまざまな不調和(もやもや)が「フリ」となり、「オチ」として歌が関係するシーンが出てくる。
先生から、「歌うとはどんな感じか?」と問われたとき、主人公は言葉では表現できなかったが、「手話的には」表現することができた。適当にその場をつくろう言葉を言ってもよさそうなものだが、それを言えなかったことから、主人公の「言葉」に対する誠実さを感じることができる。そして、主人公はその特殊な家庭環境によって備えた特殊な感性をもっている、ということを示したシーンだと思う。
主人公が発表会で歌を披露しているとき、突然主人公の父親主観のシーンに切り替わり、場面から音が消えていく…。鳥肌が立つほど素晴らしい表現方法だと思った。
このシーンになる直前、我々は健聴者の視点から映画を観ている。父親の歌に興味を持たない態度、娘の発表会に似つかわしくない無礼な態度に、少し腹を立てさえする。しかし、場面から音が消えていくとき、我々は聾者がどんな風に世界を見ているのか、少しだけ想像できるようになる。音は聞こえないが、人々の喜ぶ顔、感動する顔を見て、娘の歌声がどんなに素晴らしいか、知る。そして、歓び、誇りに思うと同時に、寂しさ、悲しさも感じる。そんな素晴らしい歌声を、私は聴くことはできないのだ、という。音が聞こえる、聞こえない、ということが、2人を断絶してしまっている、2人は違う世界に住んでいるのだ、ということを。
そしてこの問題提起のあと、この問題に対する回答もやはり歌だ。喉に直接手を当て、振動で歌を感じることや、手話をしながら歌を歌うことなど。
ぼくはこの映画を観るまで、手話をしながら歌を歌うこと(手話歌)など、意味がないのではないか、と内心思っていた。正直言えば、健聴者の自己満足ではないか、とさえ思っていた。でも、考え方が浅かったなあと思う。
歌とは、単に「音」なのではない。歌う表情や、身振り手振り、歌い手のすべてが歌なのだ。木々が揺れる様子でそこに激しい風が吹いているのが分かるように、歌う姿から、その音を想像することができる。それは心に奏でられる想像の歌であるがゆえに、もしかしたらリアルな音よりもより心に響くものになる可能性すらある。
また、この映画では聾唖者の「孤独」が多く描かれている。手話歌は、聾唖者と健聴者が同じ歌(表現)について感動を共有できることに価値があるのだと思う。もちろん、同じ体験をしたわけではないが、それはつきつめれば健聴者どうしであっても同様だと思う。
映画に出てくる、「青春の光と影(Both sides now)」という謎めいた歌詞の歌。「人生を両側から見てきた」というフレーズがくり返し出てくる。これは、主人公が聾唖者の視点と健聴者の視点の両側から人生を見てきた、ということを象徴しているのだと思うけど、もっといろいろな意味を含んでいるんじゃないか、と思ったので、歌詞を探してみた。
I've looked at life from both sides now
From win and lose
And still somehow
It's life's illusions I recall
I really don't know life at all
この歌詞が意味するのは、「人生の様々な出来事」、この映画のテーマ的には、「障害」「家族」「環境」「愛情」といったものに対して、ときに「良かった(win)」と思ったり、ときに「悪かった(lose)」と思ったりするものだけど、いろいろなことが過ぎて、ふり返ってみると、何が良くて何が悪かったのかなんて、よく分からないものだ、人生とは玄妙なものよ…。そんな感じの歌なんじゃないかと思った。
主人公はCODAだけど、だから不幸というわけではない。家族は不自由に生きているからこそ、お互いに切実に助け合う必要があり、その中で深い愛情が醸成されてきた、という面もある。また、主人公の特異な歌声と感性は、CODAでなかったら身につかなかったかもしれない。
自分の環境であるとか、自分の人生について考えるとき、こういう考え方ってすごく重要だなあ、と思う。「足りないものを数えるより、持ってるものを数えろよ」みたいな話ではあるが、「自分に才能が無い」とか、「環境が悪い」と考えることは無意味というか…
一見「悪い」ことだと思えるようなこと(例えば障害とか)でも、それが良いことの原因になるようなことだってある。何が良いことだとか、何が悪いことだとか、固定されているわけじゃない。人生はそんな単純なものじゃない。
フィクションが描く鮮やかさと限界
コーダである主人公の彼女の物語としては、感動的。
上映中、何度も涙した。
終映直後の快感のあとに残ったのは、主人公の周りにいたひとびとの存在…
主人公の父は、母は、兄は、恋人は、一体どんな葛藤を抱えていたのだろう?
主人公の葛藤は、コーダの少女の生きざまが見事に描かれていたように思う。
一方で、主人公の夢を送り出す、周りのひとびとの葛藤については解像度が粗く、一見めでたしめでたしのようだが、モヤモヤが残る。
性生活を主人公である娘にオープンな両親、マリファナを吸う父、娘の都合を鑑みずに何度も手話通訳を頼む母、キレやすい兄。
学校のクラスメイトたちの主人公へのいじめ紛いないじり、疲れ切っている彼女の居眠りへの教師の嫌味、学校全体の彼女への差別的な空気、家庭環境が良いとは言えない恋人(ここは気になったが、あまり描かれていない)。
ろう者であるとか障碍の以前に、全体的に難ありな環境下にいる主人公。
そんな状況の中、主人公だけが清潔に描かれる。
家族の通訳を生まれてからずっと担い続け、家業の漁もし、自分の学校生活や私生活の多くを犠牲にして、ろう者である家族のために尽くす娘。
そんな悲惨な状況にある彼女には、歌の才能がある。
障碍を才能で乗りこえるパターンの物語をみると、いつもなんだかな〜という気持ちになってしまう。
全170件中、81~100件目を表示